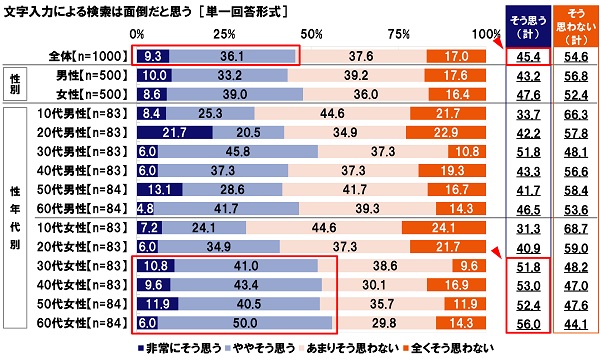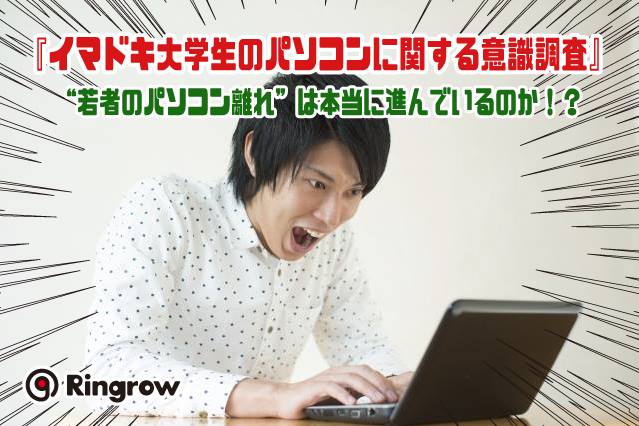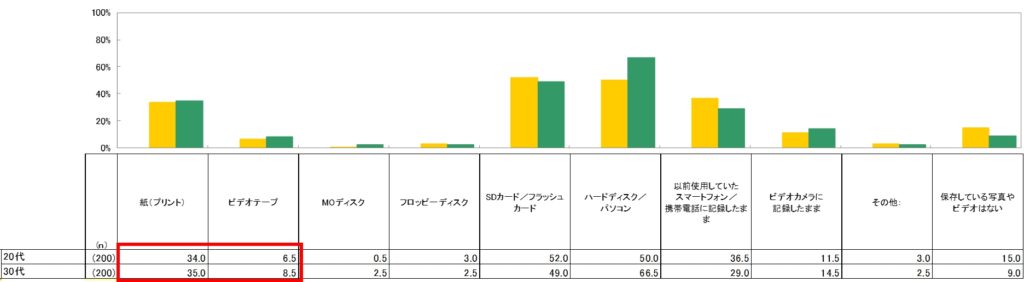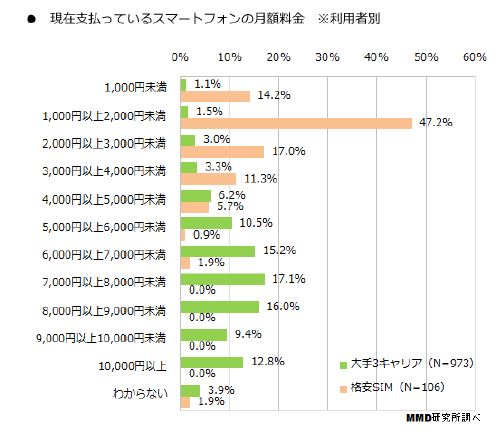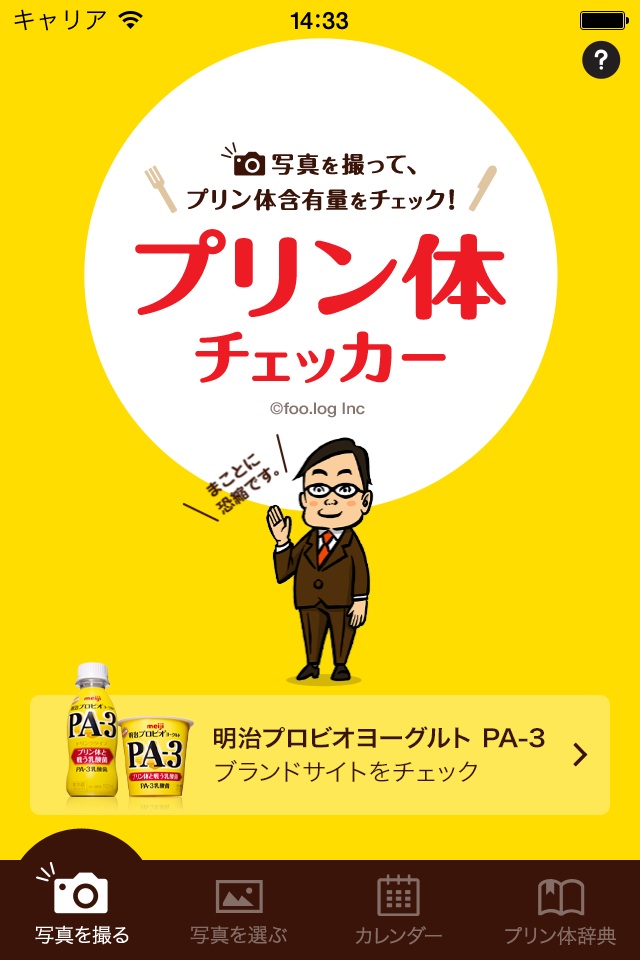朝起きて最初に見る活字がSNS、という人は少なくない。SNSの利用に関するアンケート調査(マイボイスコム・東京)によると、現在SNSに登録している人の割合は57.7%、そのうちの74.4%がLINEだった。 10,929件の回答をまとめた結果。SNSの登録者は若年層でその比率が高く、10・20代で8〜9割、30代で7割、50代以上では5割。過去調査に比べて増加傾向だ。一番多く使われているのはLINE。次点がFacebookで53.8%、Twitterは44.7%だった。過去調査との比較では、LINEは増えているが、Facebook、mixiは減少傾向だ。 利用頻度をみると、毎日という人が7割弱。スマホで、という人がやはり最も多く75.5%、ノートパソコンやデスクトップパソコンでという人は2〜3割にとどまっている。特に、LINEやInstagramを主に利用する人では、スマホでという人が9割に上った。 SNSは、自宅でくつろいでいるときや、暇なときに使うという人が4〜5割。電車やバスなど公共交通機関の車中、夜寝る前、仕事や学校の休憩時間や待ち時間なども20%台で、「空いた時間にSNS」という生活スタイルがすっかり定着しているようだ。