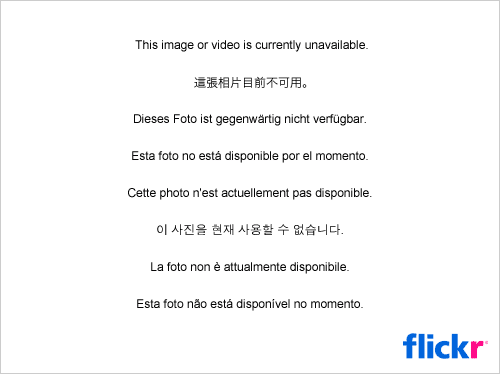[となりのテレ金ちゃん−テレビ金沢]2016年6月15日放送の「仰天コロンブス」のコーナーで、金沢のめった汁が紹介されていました。豚汁(kimishowotaさん撮影、flickrより)全国的には「豚汁」と言われることが多いのですが、石川県民は「めった汁」と言う人が圧倒的です。名前の由来には諸説あり金沢市の二水高校の保護者会では、おそろいの「めった汁」Tシャツを作っており、生徒がゴミ拾いなどで汗を流したあとに、大鍋でつくったものを振舞うという慣習があります。めった汁は、人が集まった時の振る舞い料理、大鍋でみんなで食べるという風習があります。防災士の資格を持つ金沢市の主婦も「めった汁は具をいっぱい入れる。災害時にはおにぎりなどの配給はあるが、具や水分などをとれるめった汁は炊き出しに向いている」と定期的に主婦仲間とめった汁をつくって、もしもの時の訓練をしているそうです。「めった汁」と言われる由来は、「具をめっためたに切る」という説や、石川県の農業スタイルとして地産地消が多く、収穫した野菜を消費する方法として「やたらめったら具を入れた」という説などがあるそうです。また石川が生んだ文豪徳田秋声が明治44年に発表した「黴」という作品にも「滅多汁」という言葉が登場しています。昔から石川県では、イベント時だけでなく家庭でも愛されてきた思い出深いおかずなのですね。(ライター:りえ160)