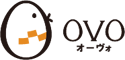(OVO オーヴォより)

今年は例年より早くインフルエンザの流行が見られる一方、ノロウイルスの患者数も増えており、今シーズンはダブルで流行する可能性も出てきた。子どもが急な激しい下痢やおう吐に襲われ、親を慌てさせるのが、ノロウイルスなどの感染性胃腸炎だ。重い下痢やおう吐の症状は長くは続かないものの、それによって起こる脱水症状にきちんと対処しないと重症化し、深刻な状態になることもある。教えて!「かくれ脱水」委員会の委員を務める済生会横浜市東部病院の十河剛医師(小児肝臓消化器科)は「小児は脱水症状を起こして重症化することがあるが、点滴が必要になるのは数%で、ほとんどは自宅で治療が可能」と指摘する。
ノロウイルスは感染したら翌日には発症、おう吐はせいぜい1〜2日
ノロウイルスに感染すると、12〜24時間で発症する。ノロウイルスによる感染性胃腸炎の場合、おう吐なら1〜2日、長くてもせいぜい3〜4日で治る。下痢も普通は1〜3日で治まり、長くても1〜2週間程度で元に戻る。
「感染、発症しても慌てないことが大切。下痢やおう吐は、ウイルスを体外に排出しようとする体の反応なので、それ自体を無理に止める必要はない。深刻な脱水症状を招かないようにきちんと水分を補給する必要がある。家庭でできる脱水対策をちゃんと知っておくとよい」と十河医師。
電解質を含む吸収の速い経口補水液を、「吐いても少しずつ飲む」のがポイント
下痢便やおう吐で体外に排出される体液には、多量のナトリウムやカリウムといった電解質が含まれている。水分補給をする場合、電解質を含まない真水だけを飲むことは低ナトリウム血症など病気をかえって招く可能性があり危険という。ポイントは電解質を含み、さらに吸収スピードを速めるために適度なブドウ糖も配合した経口補水液などを摂取して水分補給をすることだ。経口補水液を飲めない小児にはゼリータイプを活用するとよい。吐いても少しずつ飲ませることが症状の深刻化を防ぐ。
中程度の脱水症状まで家庭で対処可能、病院に行くレベルは
中程度の脱水症状については、経口補水液を用いて家庭での対処も可能という。具体的には①口の中が乾いてネバネバしてくる②尿の量が減ってくる③(幼児の場合)泣いても涙が出にくくなっている―などのサインがみられる場合は、脱水症状が中程度まで進んでいる可能性がある。
一方、病院に行った方がよいレベルではどういう症状が出現するのだろうか。十河医師は「尿が出なくなる。目が落ちくぼむ。脈や呼吸が速くなっている。反応が鈍くなる。神経が過敏になっている、などの症状が見られる場合は中程度以上に脱水が進んでいると考えられる。おかしいと思ったら主治医や近くの病院に相談してほしい」と見分け方を説明する。
子どもにできるノロ対策は
突然の下痢やおう吐は、親だけでなく子どももパニックに陥れる。そんなときどうすればよいのか。11月下旬、十河医師は川崎市の伸こう福祉会の保育園「キディ百合丘・川崎」を訪れ、園児を相手にノロウイルスの対処法を分かりやすく解説した。同園は日ごろからノロウイルスの対策に力を入れてきたという。
十河医師が指摘したのは、発症したときの経口補水液の摂取法だ。おう吐や下痢などで塩分が体外に排出し失われるので、それを補給する必要がある。この日はペットボトルとゼリータイプの経口補水液「オーエスワン」が用意され、園児は実際に飲み方を練習した。
次いでおう吐の処理をどうするか。感染力が強いノロウイルスが含まれているので、職員などにすぐに知らせる。子どもは絶対に触ってもいけないし、飛散している恐れもあるので近づいたりしてはいけない。おう吐をしたときの行動の訓練も実施、さらに処理法も学習した。
また、ノロウイルスに感染しないためには日ごろから石けんを使って手を丁寧に洗う習慣をつける必要もある。園児に手洗いの様子を実演して見せた。
「幼稚園や保育園でノロウイルスの処理を間違うと集団感染を起こしてしまう。子どもたちがノロウイルスの対処法を少しでも知っていれば、混乱を起こさないし、集団感染を防ぐことができる」と十河医師は話している。
十河医師らが委員を務める教えて!「かくれ脱水」委員会のホームページでは、ノロウイルスに感染したときの脱水への対処法などを紹介している。
http://www.kakuredassui.jp/