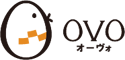(OVO オーヴォより)

正直、便利だけど、改良してほしいのが電子書籍。情報を引っかけたらすぐにダウンロードして読めるし、本棚があふれる心配もなし。出張や休暇先に、100冊だって持って行ける。だが、便利さと使いやすさは別物。しおり機能でどこまで読んだかはもちろん分かるし、マーカーもつけられるけれど、「68%読んだ」という数字が“体感”としてピンとこない。いちいちマークしておかないど「3章のあの辺に、あの文章があったんだけど…」という振り返り行為がかなり難しい。「34%のところにあの文章があった」という記憶の仕方はしていないからだ。
それでも、年々拡大する国内の電子書籍市場。2014年には1,000億規模を超え、低迷している出版業界でもネットサービスとの融合が進んでいる。トレンド総研(東京)の調査によると、「紙の書籍だけを読む」人はまだ圧倒的に多く77%。「電子書籍だけを読む」と回答したのはわずか7%だが、「紙・電子書籍のどちらでも読む」人が16%いる。デバイスとして最も多かったのは「スマートフォン」。
電子書籍を読む理由は、「無料で閲覧・入手可能な本があるから」(53%)、「読みたいと思ったときにすぐに読めるから」(51%)が上位。また、「本を保管するスペースがとられないから」(50%)、「持ち歩きに便利だから」(49%)など、やはり紙の本にはない長所が理由になっている。
本を選ぶ際に参考にしているのは、「書店でのPOPなど書店員による情報」(33%)、「オンライン書店などでのユーザーのレビュー」(29%)が僅差でトップ2に。商品ジャーナリスト・北村 森氏は、本と読者との接点について「“キュレーション型”書店などは分かりやすい例だが、本はキュレーションと親和性が高いコンテンツ。そもそも“キュレーター”という言葉は、図書館や美術館の“学芸員”、コンテンツを選ぶプロ。書店は独自の視点で本を並べているわけで、元来“キュレーション型”であり、消費者は書店員によって並べられた本や店頭POPなど、キュレーションがされた情報を信用して本を選んでいる」とし、「情報接点の変化や、情報発信方法の多様化を背景として、いかに自分自身にとって価値ある情報であるかどうかが求められる動きは、さらに加速していくと考えられる」と話している。