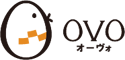(OVO オーヴォより)

海や川に設けられた護岸や堤防などの防災コンクリートブロック―。災害に備えた頼もしい存在だが、周囲の景観と不釣り合いな無骨な姿ゆえ、「環境破壊」の“負”のイメージが独り歩きしている。
このイメージを変える困難な課題に挑戦する企業が「防災と環境の両立」を掲げる日建工学(東京)。コンブやワカメらの「藻類」が定着させて魚を引き寄せる「環境活性コンクリート」を開発するなど、環境に優しい防災ブロックの普及を目指している。
主力商品は、堤防の前面や海・川床などに置いて災害時に荒れ狂う水の勢いをそぐ様々な形状のブロック群。業界では「消波根固(しょうはねがため)ブロック」と呼ばれている。いずれも需要は公共事業にほぼ限られ、官公庁の財政事情に大きく左右される商品だ。
それだけに、環境へのマイナスイメージをなくすことが社の最大の課題。行本卓生社長は「ブロックはどうしても景観の中で異質なものとして捉えられがち。環境にネガティブなイメージをもたれやすい。このイメージを変えなければいけない」と固く決意している。
この強固な思いが、ブロックの中にアミノ酸を混ぜた防災ブロック「環境活性コンクリート」を誕生させた。
アミノ酸は十数年の長期にわたって少しずつコンクリートからしみ出し、それを栄養素とする藻類が通常の5〜10倍の速さで成長、コンクリートを覆っていく。そこに藻を餌とするアワビやサザエなどが集い、魚も寄ってくる。
つまり海や川に置かれた「環境活性コンクリート」が、生き物の生息環境を「創造」する新たな食物連鎖の起点となる。環境破壊の「虚像」を環境創造の「実像」が覆す。これまでのイメージを180度変え得るブロックだ。
行本社長は「人間と生き物の両方の視点を大切にしたい。海や川の生き物も人間と同じく、環境に関するステークホルダー(利害関係者)だ。環境保護と防災は必ず表裏一体でなければならない」と事業理念を明確に語る。
もう一つの大きな課題は、今後の国内需要の縮小を見越しての海外展開。
「いまは東日本大震災の復興需要があるが、近い将来当然、国内需要はしぼんでいく」と危機感を募らせる。
ベトナムで大型案件を受注するなど、すでにアジア進出の足場は築いているが、社会基盤がまだまだ未整備のアジア全体を思えば、海外進出はこれから本番を迎える。行本社長は「まだまだよちよち歩きの状態。これからどんどん海外に事業を広げていきたい」と意気込んでいる。
日建工学が展開する高品質の防災ブロックがアジアの雄大な自然を維持しつつ、災害から人々の命を守る―。それは単なる技術の輸出にとどまらず、古来より自然と共生してきた日本人の「文明観」を伝えることでもある。同社がアジアで果たすべき役割は決して小さくない。