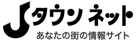(Jタウンネットより)
「わかやま妖怪研究会」というフェイスブックがある。妖しの刻へようこそ、というサブタイトルが付いている。そこには、こんな前文が記されている。
妖怪や不思議に出くわしてしまった!、その存在を感じた、怖かった!、神秘の地である和歌山で、そんな思いをした人は少なくないはず。妖怪に出遭ってみたい人もいることでしょう。このサイトは、そんな妖怪ファンのためのサイトです。和歌山で妖怪や不思議に出遭った場所や、その時の状況などを書き込んで下さい。皆さんから集まった情報をもとに、どこに、どんな妖怪や不思議がいそうか?を整理して公開していきます。
なんとも妖しい気配を漂わせたフェイスブックではないか。
その2014年7月27日には、「わかやま妖怪マップの試作(まだまだ途上)を一般公開しました。」と書き込まれている。わかやま妖怪マップとは、いったい何か?
インターネット上の地図サービス「グーグルマップ」は紀伊半島、どうやら和歌山県のエリアを示しているようだ。その上に、赤・青・緑に色分けされたピンがびっしりと刺されている。これが全て妖怪との遭遇情報があったポイントらしい。
緑は山の妖怪、黄色は人里の妖怪、水色は水辺の妖怪、青は海の妖怪、赤は動き回るので位置が特定できない、辺りそこらじゅうにいる妖怪、とのこと。
和歌山県にはこれほどにも妖怪が潜んでいるのか?
この妖怪マップの企画責任者であり、「わかやま妖怪研究会」を主宰するのは、和歌山大学システム工学部環境システム学科教授の中島敦司さん。「人間と自然とのつきあいについて考えてみよう」というのが、この企画のきっかけだった。和歌山の妖怪について、中島さんに聞いてみた。
「ダル」という妖怪は、空腹の旅人に取りつくと言われている。和歌山出身の博物学者・生物学者・民俗学者である巨人・南方熊楠が紹介した。妖怪マップには次のような解説が書き込まれている。
地蔵峠や水呑峠でダルに憑かれることがある。ダルに憑かれると,急激に腹が減って動けなくなる。飯を食べると治る。飯がないときは,手のひらや紙などに米と 3回書いてなめるといい。弁当を持っていったら,全部食べないで米を3粒残しておくという。ダルに憑かれると「こっちに来い」と招かれている感じがしたと いう。文献:國學院大學民俗学研究会 民俗採訪 通巻昭和51年度号,129-214(1977年)
他にも、熊野を巡礼する旅人の路銀を強奪するという「一つだたら」や、熊野の山中に出没しては人畜を害する「一つ目」といった妖怪がいるそうだ。
また河童の伝承、遭遇の報告の数が非常に多い。夏は水の中、冬は陸に上がって行動するため、赤いピンとなっているのだという。
「人間が自然と共生する中で線引きが必要な場面に、妖怪が登場することが多い」と、中島さんは語る。自然の中で人間がどのように暮らしてきたかを理解することで、自然との関わり方を考え直すきっかけとなるかもしれない。
さてあなたが和歌山で妖怪に遭遇したら、どうするか? 「わかやま妖怪研究会」フェイスブックからコメントを寄せるか、妖怪マップの解説内の中島教授のメールアドレス宛にメールすること。「妖怪マップ」はあなたの協力を待っている。