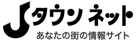(Jタウンネットより)

どっしりとした姿が印象的な下仁田葱
群馬県甘楽郡下仁田町は、古くからネギ栽培・こんにゃく栽培に特化した地域です。
逆に言うと青果の名産品はこの2点しかないので、それだけに並々ならぬ努力を続けてきたのです。
この地での下仁田葱の会の発足は、それまでの効率重視の栽培により、消費者の評価が低下してきたことに危機感を覚えたのがきっかけでした。
「下仁田葱の会」は伝統の味を守る為、品種維持、昔ながらの栽培にこだわります。
根本には、土着の品種であり伝統的な栽培が本来の美味しさを引き出すという考えがあります。その変わらない味こそをブランドとして残すという強い意志が原動力なのです。
これは「下仁田ネギは下仁田へおけ※」という古い言葉に繋がるところです。
※下仁田葱を下仁田町以外で育てると、栽培方法・環境などの要因で生育バランスが変わり、歯触りから味まで変わってしまうという意味。

下仁田生まれ下仁田育ちのネギ
自家採種で維持される下仁田葱
下仁田葱の会は種を自家採取して、品種維持に努めています。
しかし、葱の交配上では従来の品種は劣勢の様子で、簡単に多品種が混じり、形状を含め味わいが変わってしまうそうです。
分かりにくいかもしれませんが、下図の赤枠が形状の変わった下仁田葱です。

赤枠内のネギの葉は、すらっとしており異質
手前の畝の葉の様子と比べると明らか、通常はどっしりとした葉の形状が、赤枠のネギは細くすらっと伸びています。
これは性質が変化した証。会の生産者はこれらを確認次第に、抜いて淘汰していきます。
品種維持のためとは言え、自ら生産量を減らす作業を行うほど真剣な取り組みということです。
会の下仁田葱の畑では14〜15か月の栽培期間中に、伝統の栽培にのっとって2度の植え替えを実施します。1度目は間引きを含む植え替えで、2度目は品種維持とネギの性質の為です。
7月に行う2度目の植え替えは、伝統的な栽培の方法にのっとったものです。
取材した堀口さんによると7月頃、下仁田葱の根は徐々に生え変わるとのこと。
品種的な要因なのか、繰り返す伝統栽培の結果なのかははっきりしません。
けれども昔からそのように栽培されており、今も品種維持のために会員の畑では続けています。会の方全員が栽培方法を徹底しており、違反者は会を除名されるほど厳しい決まりなのです。

下仁田葱の会の堀口さん
出荷期間は霜が降りる12月から1月限定
寒さを感じて引き締まり、甘さがのったものでなければ下仁田葱と呼ばない。
下仁田葱の会では、もっとも味の良い時期にしか出荷しません。
「当たり前のことを当たり前にしているだけ」今回お会いした堀口さんは昔ながらの美味しさを広めることに真摯に向き合っている一人です。

豚バラ肉と炒めると脂がネギの甘みを際立てる
取材した時はちょっと早かったのですが、特別に抜いて味見をさせて頂きました。
生でかじると、かなりの辛い!しかし炒めて火を通すと抜群の甘みが引き出されます。
白い部分と青い部分の味わい、食感の違いがまた下仁田葱の魅力だと納得です。
霜が降りる寒い季節しか味わえない特別なネギ、存分に楽しみたいものですね。

http://www.umai-mon.com