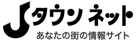(Jタウンネットより)
[Jステーション-広島HOMEテレビ]2015年8月11日放送で、広島市に言い伝えられるお化け伝説を紹介していました。
広島市郷土資料館では、2010年から毎年この時期にお化けに関する展示をしています。2015年の展示を企画した、広島市郷土資料館学芸員の正連山恵さんが、広島市内にいる妖怪についての問いに答えてくださいました。
人間の肝を引き抜いて食べると言われている妖怪「猿猴」
江戸時代、「猿猴」が住む川として、川や橋には「猿猴川」、「猿猴橋」とその名がつけられ、今なお人々が行き来う町の中にその名を残しています。この猿猴は河童のような妖怪で、人間の肝を引き抜いて食べるといわれていたんだとか。
500匹の部下を引き連れる妖怪「おさん狐」
江波地区に住んでいたと言われる妖怪「おさん狐」は、80歳くらいの狐で、500匹の部下を引き連れている立派な妖怪です。
町の人たちにも愛され、その愛情の表れとして江波車庫前には「おさん狐」の像も立てられています。妖怪とはいいつつも、神様のような尊敬される存在として、その名が残されています。
人々を守る妖怪「牛田の天狗」
東区牛田本町にある総合福祉施設では、牛田地区にまつわるお化けの紙芝居が行われていました。子どもたちが食い入るように見ていたのは、牛田に住む天狗のお話です。
この紙芝居は、牛田の歴史と文化を活かして、街作りに取り組む地域の人々によって作られました。
お話によると、牛田の天狗は大の酒好きで、二葉山の1番大きな松に住んでいたそうです。風を起こして町の人々の田畑を守ったり、生活を潤していたといいます。
また、天狗の住んでいた松の下には石の仏様があり、子孫繁栄のシンボルとして、多くの女性が拝みに来たといいます。実は、この石の仏様、30〜40年前にグラウンドを作るために土を掘り返したところ、実際に出てきたのだそうです。
身近に伝承されるお化けの存在を、町の活性化の為に活かす活動も行われているとのこと。実際にいるとはなかなか考え辛いですが、身近なものに伝承されているのは、それにまつわる話を聞くだけでも面白いですね。(ライター:haruhana)