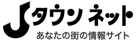(Jタウンネットより)
[ちちんぷいぷい – 毎日放送] 2015年7月17日放送で、「ため池ソーラー」について取り上げていました。
日本の再生可能エネルギーの代表格はやはり太陽光発電ですよね。太陽光発電のメリットは、日射量さえ確保できれば設置場所を選ばないことや、メンテナンスが比較的楽なこと、災害時に電力を使用できることなどがあります。
大阪府も大阪市と共同で「おおさかエネルギー地産地消推進プラン」を策定し、再生可能エネルギーの普及拡大に取り組んでいます。主には、府や市が保有している施設の屋根や土地を利用しての太陽光発電が挙げられます。大阪府立砂川厚生福祉センターの屋根の上に設置したり、ソフトバンク泉大津ソーラーパークを作ったりがその一例です。
ですが大阪も限られた土地しかなく、パネルを置く場所がなくなってきました。そこで大阪府が考えた秘策が、”ある場所”を使った発電です。
水上太陽光発電のメリットとは
大阪府が目を付けたのが、「ため池を使った太陽光発電」です。大阪府はため池が全国で4番目に多く、1万1000か所あります。そのうちのおよそ800か所が水面太陽光発電ができる立地場所なんだそうです。
大阪府初のため池ソーラーとなるのは、岸和田市の傍示池(ほうじいけ)です。傍示池は農業用水確保のために人工的に造られた貯水池で、水は高台の池にポンプで送られパイプラインを通って周辺の田畑に供給されています。
傍示池ではフロート(浮き)にソーラーパネルを取り付け、それを水面に浮かべるという方法が取られました。年間発電量は115万キロワットで、一般家庭のおよそ320世帯分に相当すると見込まれています。
太陽光は暑い時期時は発電効率が落ちるのですが、水上の方が周辺の温度が低いので発電量の低下を抑えることになると期待されています。また、池を管理する事業主は関西電力に電気を売電し、その収益を池を管理する土地改良区に賃料として支払い、その賃料は池の維持管理に使われることで、農空間の保全にも役立ちます。
また、ため池では水面に水草が生えてそれが腐り水質悪化につながることもあるのですが、ソーラーパネルで日光が遮られることによって水草の発生を抑えられるかもとの期待もあるのです。(ライター:ツカダ)