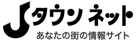(Jタウンネットより)
[ちちんぷいぷい – 毎日放送] 2015年5月20日放送で、「淡路島の歴史的出土品」について取り上げていました。
4月8日、兵庫県南あわじ市の砂利工場で作業を行っていた西田さんがショベルカーで砂山をすくった瞬間、中から何かが姿を現しました。それを見た西田さん・・・、「あ!教科書で見たやつや!」。
これが、数十年に一度、第一級の大発見になろうとは、当の西田さんもこのときはまだ気づいてはいなかったのです。
すくいあげた塊を掘りだしてみると現われたのは、全長30センチほどの金属の物体2個。それは”銅鐸”だったのです。南あわじ市の教育委員会が調べたところ、さらに5個が見つかりました。銅鐸は弥生時代のもので、合計7個も同時に見つかるのは極めて珍しいことだといいます。
見つかった銅鐸はどれも保存状態が良く、「舌(ぜつ)」と呼ばれる銅鐸を鳴らす振り子もついていて、とても貴重な発見となりました。
これまでにも銅鐸が多く見つかっている淡路島
実は兵庫県は全国で最も多く銅鐸が出土していて、今回のものを含めると68点におよびます。そのうち淡路島で見つかった銅鐸は21点を占めています。
淡路島は「古事記」にも出てくるように、最初に生まれた島とされていて、聖なる場所と考えられていたそうです。そのため淡路島では神さまを祀ることが非常に盛んで、その結果銅鐸がよく使用されていたのでは?とみられています。
今回銅鐸が発見された砂山の砂は、市内の海岸付近から工場に運ばれたものだとのことで、今後市教委などは、出土場所を特定してさらなる調査をする予定です。
実は、考古学者の間では前々から「淡路島には何かある!」と言われていて、今回の発見で「やっぱりそうだった!」と色めき立っているそう。こうして注目を浴びた淡路島、今後も研究が進んで日本の歴史をくつがえすような大発見があるかも?!楽しみですね!(ライター:ツカダ)