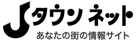(Jタウンネットより)
[となりのテレ金ちゃん−テレビ金沢]2015年4月6日放送の「旅のおまけマップ」のコーナーでひがし茶屋街のそばにある寿経寺について紹介していました。
北陸新幹線開業後、休日にもなると石畳が見えないくらい大勢の観光客でにぎわいをみせるひがし茶屋街は江戸時代、金沢随一の花街でした。
今回の寄り道ポイントは、ひがし茶屋街のそばにある「寿経寺」です。ひっそりと佇んでいる寿経寺は浄土宗のお寺で、代々尼さんによって守られてきたそうです。
庶民のいのちを救ったのは7人の有志の決断
通りに面したところには7体のお地蔵と石碑があり、7人の名前が彫られています。
この7人は江戸時代、お殿様に「お米をくれ」と訴えて処刑されてしまった人たちなんだそうです。
今から約150年前、飢饉が起こり、お米の値段が跳ね上がったことで、庶民は食べることができず、ひもじい思いをしていました。
追い詰められた人たちは意を決して、当時立ち入り禁止だった卯辰山に登り、約1.7キロ先の金沢城に向かって「米くれまいやー」と叫んだそうです。
悲痛な叫びは13代藩主・前田斉泰の耳にも届いたようです。
翌日さっそく藩の米蔵からお救い米が出され、人々は救われました。
庶民を救った功労者たちへの思いを地蔵に…
お米はもらえたものの、お上への直訴は御法度でした。
首謀者の7人は捕らえられ処刑されてしまったということです。
寿経寺の石碑には7人の名前が刻まれ、7体のお地蔵が祀られているのです。
よくみると7体の顔のつくりが違い、稲を抱くような姿から、犠牲になった7人への賞賛と感謝の気持ちが伝わってきます。
ひがし茶屋街のメーンストリートは多くの観光客で賑わいをみせていますが、少し離れた寿経寺のあたりは落ち着いた雰囲気を残しています。
華やかさの傍らにある悲しい歴史を伝える一面を感じながら散策してみるのはいかがでしょうか。(ライター:ファンキー金沢)