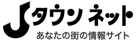(Jタウンネットより)
[となりのテレ金ちゃん−テレビ金沢]2015年4月7日放送の「教えて!小倉さん」のコーナーで姫路城のについて紹介していました。
5年に及ぶ大改修を終え、一般公開された世界遺産・姫路城。
輝くような真っ白な漆喰の壁は金沢の左官職人が参加して支えてきたということです。
日本建築を支える左官の技に注目を!
日本建築の良さは壁に現れるということで、そこに注目して評価することが大事なんだそうです。
「壁は家の顔」といわれ、壁は面積的に一番大きく、左官仕事は大工の出来より大事だという意味だそうです。
さらに「一壁、二障子、三柱」という言葉があり、新築の家に招かれたときは、まず壁から褒めるといいという意味です。
柱や天井板も自慢したいところかも知れませんが、壁にお金を掛けた家というのは特別に良いということなんです。
それだけに壁を作るのは高い技術や複雑な手順が必要とされるのです。
手順を追いますと、まずは竹と縄を組んで下地を作り、その上から土を塗る。乾いたらまた土を塗り重ねる。
そのあと漆喰を何種類もの「鏝(こて)」を使って整え、最後になまこ壁や鏝絵などの装飾をするのです。
金沢の左官職人は「鏝は武士の刀と同じ」と言っており、誇りを持って技を継承してきたと言います。
建築工法は時代とともに変化し、土壁はパネルになり、障子や建具は既成品のドアになり、柱や天井板はプリント合板になっていき、多くの職人が消えていきました。
仕事が消えれば技も消えていくといい、伝統の技はいったん消えたら復活は難しいと言います。
今回大改修を終えた姫路城の素晴らしさの裏には、伝統を継承してきた石川の左官職人たちの誇りがあったのですね。(ライター:ファンキー金沢)