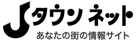(Jタウンネットより)
[となりのテレ金ちゃん−テレビ金沢]2015年3月19日放送の「教えて!小倉さん」のコーナーで石川にあった最古の国道について紹介していました。
2000年、津幡町の加茂遺跡から平安時代の「ぼう示札(ぼうは片ヘンに旁)」というお触書が出土しました。このぼう示札には、農民に対して「早寝早起き」や「ぜいたく禁止」などの命令が書かれ、当時の制度を示す貴重な資料です。
発掘されたぼう示札には「国の道のそばにビキし、これを進め路頭にぼう示し」、つまり「国道のわきに立てて示せ」と書いてあるそうです。
江戸時代まで国が作って管理する道路は「官道」と呼ばれ、現在の「国道」と言い方になったのは明治以降とされてきました。
ところがこのぼう示札の解析で平安時代から「国道」があったことが分かったというのです。
「国と国をつなぐ道」という意味合いが強かった「国道」という表記が確認された日本最古の例だそうです。
北陸新幹線のルートの起源は大名行列に!
加茂遺跡がある場所は、奈良時代の北陸道が加賀から越中に向かう分岐点に近く、河北潟も入り組み、陸路と海路を交差する重要地点だったとさせます。
大名行列が通った北国街道も鉄道の北陸本線も、国道8号や北陸自動車道もこの付近を通るルートで、北陸新幹線のルートも近く、道路が作りやすい場所は昔も今も変わらないということです。
昔の人が歩いた道の上に私たちも道路を造り、電車のレールを引いているのですね。
将来国宝指定の価値があるとされる「ぼう示札」が発掘された津幡町では博物館を作る方針を立てているそうです。(ライター:ファンキー金沢)