
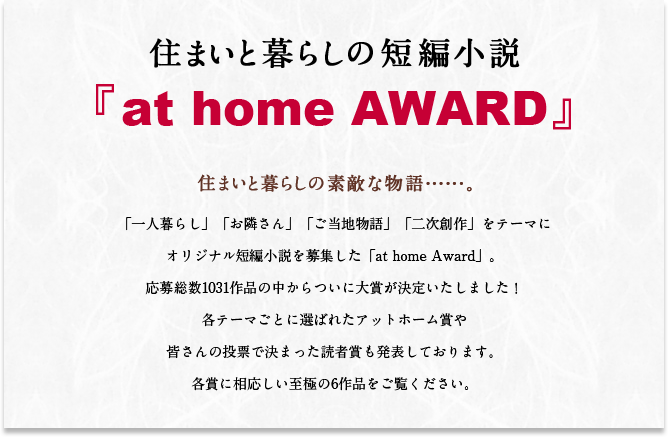
恋人の愛佳は完璧に整えられた部屋で、猫の骨と暮らしている。ある日、愛佳はおれに一つの頼み事をした。虫がジージーと鳴く夏の夜、おれは骨を持って愛佳の実家に忍び込み、愛佳も骨を携えておれを待っていた。
大学入学と同時に両親もとい母からの強権的支配から脱した私は新天地京都に独立国家を建国した。自由と幸福に満ちあふれたユートピアでの日々をエンジョイする私にある日届いた一通のメールは、お国を揺るがす地獄の衝撃だった。
内見で一目惚れした物件に無事入居し、一人暮らしと大学生活をスタートさせた夏江。彼女の心を射止めたのは、1960年代に誕生した日本独自の浴室機構「ユニットバス」だった。
数学界の難問『ミレニアム問題』が解かれ、まだ行われてもいないギャンブルの結果が提示され、何もない空間から突如、アタッシュケースが現れる。人間のしわざと思えない、一連の出来事は何を意味するのか。そんな中、ある男が映像を録画しはじめる。
「はい、これで開きました」作業の手を止めた鍵屋は母に金庫を開けるように促す。母は緊張した面持ちで金庫に手をかけた。「結局ガラクタばかりだったわねぇ」現金なこと言う母だが、私も少しだけ期待していた分あまり人のことも言えない。
大学時代に一人暮らしをしていたことを思い出す。当時チャットアプリだけで話をする友達未満の関係の安藤渚がいた。その彼女がある日、部屋交換をしようと言い出した。お互いの部屋を一日だけ交換して過ごそうと言うのだ。それを承諾した俺は緊張しながら彼女の部屋へと向かう。
彼は不動産屋に勤めていた。客に何枚も間取り図を見せ、気に入れば案内する。なかなか便利ですよとか、掘り出しものなので早めに決断した方がいいですよ等と言いながら、彼自身は部屋にほとんど興味がなかった。その不動産屋は主に単身者向け物件を扱っていて、中には女性限定の物件も少なくなかった。
「一人暮らしの栞は、大好きだったかつての恋人柿沼を<風待トンネル>を抜けた束の間、思い出す。同僚の月島さんとの日常と向こう側にひそんでいるもうひとつの世界への憧れと。街を雪一色に染めていたその年の冬。めったに降らない雪が降り積もってゆく。そんなある日、一枚のポストカードが迷い込む。
さらば、実家。これからはセンスのいいおしゃれな部屋で暮らすのだ。誰だって家を出る時にはそう思ったはずだ。しかし、現実は厳しい。魔法使いに杖を一振りしてもらうか、匠にでも来てもらわない限りその夢は叶いそうにない。そんなあたしの前に、そっくりそのまま部屋を譲るという人が現れて……。
部屋をアイテムで着飾るゲーム『クリエイト・ルーム』。スーパーレア以上の景品は、実際に現物が届くシステムだ。部屋がダサいことを理由に彼女に別れを告げられた笹塚ヒロキは、彼女とよりを戻すべくオシャレな部屋を目指して課金に勤しんだ。そして、ついに念願の部屋を手に入れたが……。
結婚三十年目の陽一と亜希子の夫婦。亜希子が新しい仕事のためにベトナムに旅立ち、日本とハノイ、それぞれの一人暮らしが、突然に始まる。着実に積み上げてきた人生の中でのちょっとした停滞と変化。五十歳を超えて彷徨う二人の探し物はいったい何?そして見つかるのか?
団塊の世代の多くが退職を迎え、会社から家庭へと生活の場を変えた。その一人である福田が、自分なりの考えと行動で新しい生活を作って行く。呆け防止のために始めた図書館利用で知り合いとなった同年輩の人達との交流を通して終活へ向けた夫婦関係や生き方を改めて考えさせられる。
四十代の私はかつて父と母と妹と暮らしていた。普通に生きてきたはずなのに、ぽつりぽつりと一人暮らしが始まった。はじめは戸惑い、さびしいとも感じたけれど、今では楽しい。
私が親元を離れて一人暮らしをはじめたきっかけは、おなじ会社につとめる先輩デザイナーの聡里さんの影響が大きかったのはまちがいない。聡里さんは私がいまの『スタジオB-Y』に入社したとき顔をあわせたわけだが、全身からオーラがまばゆいまでに輝いていて、同性からみても魅力抜群の女性だった。
蝉の鳴く季節、「僕」は一人暮らしをする女性の部屋に招かれ、一緒に夕餉を食べる。そこで、毎日忘れものの話をした。女性と話すうちに、「僕」は大切なものを思い出すのだ。
隣に越してきた女が予言者だった。私はその予言者の女のことを、ノストラダム子と名付け、親しみを込めてダム子と呼ぶことにした。ダム子の予言は本当によく当たる。恐ろしいくらいによく当たる。ダム子の予言によって世界は彩られ、そして破滅を迎える。そんなダム子に私は徐々に惹かれていく。
身近な誰かと別れる時、わたしの足の指は何処かに消えて、そしていつの間にか生えてくる。右足の薬指がなくなったある朝、隣人が引っ越して行きわたしは恋人に振られ、新しく越してきた爽やかな青年は右手の小指が欠けていた。
由利子は大学の近くで一人暮らしをしている。仲の良い友達はおらず、いつも一人で過ごしている。一人の時間は好きだが、ある日隣人の弾くギターの音を心地良く思い、自分の寂しさに気付く。二人は壁越しに互いを意識するようになり、学園祭の夜、距離を縮める。
ある日、インド舞踊家の魅惑的な女性が隣室に引っ越してきた。僕達はバルコニーで顔を合わせると、舞踊の所作で挨拶を交わす。僕は何回か彼女の公演に足を運んで親しくなったが、彼女は舞踊修行でインドに行くためまた引っ越していった。僕の脳裏には彼女の魅惑的な姿が残る。
女として自分に自信がない鈴子。そんな彼女へ宛名も差出人も不明の妙な手紙が届くようになる。最初は隣の部屋に住む女の子へ宛てた手紙が間違えて入ってきたのではと思うが、しかしどうやらそれは鈴子へ宛てた手紙のよう。ストーカーか、悪戯か、それとも恋人の策略か。手紙の差出人は一体誰だろう。
大学近くの安アパートで一人暮らしをしつつ作家を目指す“僕”は,敬愛する小説家である山田國夫大先生の賞に応募するものの,落選.心折れて気分転換に公園に行ったところ,何とそこには山田先生本人がいた.一生の運を使い果たしたのではないかと,僕は舞い上がる.
今年で本厄を向かえた先輩にことごとく降りかかる厄。犬も歩けば棒に当たるではないが、厄が歩けば棒にも当たるしこけるし、公共料金だって払えなくなるもので、先輩の厄には恐れ入ってしまう。自分の厄年を迎えるときには必ず厄払いはしようと思う。
自由な母と二人暮らしだった三角菜奈(ミスミナナ)は、大学進学を期に一人暮らしを始める。生活費や家賃の為にバイトに明け暮れ、節約しながら生活している。ある日、同じ大学の「田中さん」が隣に住んでいる事を知る。自分とは違う感性や考えを持つ田中さんに、興味を持ちつつ暮らしていたが・・。
夫の耳から、いつの間にか耳毛が消えていた。自分で処理したとは思えず、私は浮気を疑った。夫を問いつめると、情けない声で「耳かきのお店」で切ってもらったのだという。私は夫を脅して、「耳かきのお店」とやらに乗り込むのであった。
アパートで独り暮らしをする拓三(23)の隣人は、拓三が不在の時にベランダから部屋に入り込み自炊したりベッドで眠ることが当たり前になっている。隣人は若くて魅力的な少し年上の女性だ。拓三が大人になるために、彼女はいろいろなことを教えてくれることになる。
争い事の嫌いな佐藤浩は幼い時分よりずっと、自分を出さず他人に合わせて生きてきた。そんな浩も目出度く大学を卒業して、春から社会人となる。彼は実家を出て通勤するのに便利な賃貸マンションへと引越した。引越しの片づけの途中、空になったダンボール箱を、彼は何気に頭からかぶってみた。すると?
お隣は母子家庭。ママは登下校するランドセルの少年を怒鳴りつけるのが日常だ。「わたし」は少年がかわいそうだと思いながらも、若いママが気になっている。ある夕方、ドーナツ屋の列に並んでいる親子の姿を見つける。「わたし」は思わず同じ列に並んでしまう。
娘と二人暮らしの母親。甘えん坊でわがままな娘に手を焼きながら毎日を過ごしている。そんなある日、二人は家の中で小人を見つける。娘は小人の世話をし始め、次第に自立心を高め、そして母親のありがたみに気づいていくが・・・?
「ちゃんとしっかり喋れんのかいなぁ」バイト先でいつもお世話になっている人の呆れる顔。もう何度見たことだろうか。「……すみません」「いや、ちゃんとな、落ち着いて言えばいいねんか。そんなに焦らんでもな。」僕は俯く。「…はい、分かりました」「返事しぃな!」僕は前を向いて、笑顔をつくる。
闇は人を不安にさせる。突然のマンションの停電、ぼくらは一丸となって一刻も早い電気の復旧のためにあれこれ考えるのだが、ぼくはふとある考えに捕らわれる。この人たちは本当にこのマンションの住人なのか? もしそうでなければ、その目的は? 誰が嘘をついている?考えるとわからなくなってきて……。
転勤で鳥取県は鳥取市にやってきた二十九歳の『私』は、お盆休みだというのに実家にも帰らず、この街の夏の風物詩『しゃんしゃん祭り』にやってきていた。そこで、一緒に来ていた友人と別行動をしていると、一人の浴衣の似合う『少女』と出会う。
台東区上野桜木一丁目。かつては恋人と暮らしていた、小さな家に、いまはひとりで住んでいる。当たり前の幸せは当たり前のように手に入ると思っていたけれど。絵を描いてどうにか暮らせるようになった僕の、下町での小さな暮らしは……。
大学入学と同時に、南の町でひとり暮らしを始めた「私」。関東から南西に900キロ離れたその地は、細くて硬いラーメンと、熱い強風が町に溢れる地方都市だった。そして町の浜辺にある野球場では、とある弱小チームが快進撃を続けている。
大学院に進学した為に仲間より一歩遅れて卒業したクマは、彼らの多くが住まう広島市を就職先に選んだ。引越祝いの飲み会で、クマは大学時代を過ごした思い出の地「西条」を出て「市内」で大人になった仲間たちにもう一度出会う。彼らが教えてくれる広島市の夜は、驚きと光と酒で満たされていた。
岩手県の大槌町からは鯨山が見える。クジラに関する伝説が残るこの山は、その山容から、三陸沖を航海する船の羅針盤としての役割を果たしてきた。彼女はその町で生まれ、育ち、そして震災にあった。藤沢市のぼくの通う中学校に転入してきた彼女の夢は、生物学者になってクジラを研究することだった。
20年足らずの人生で少なくない男と関係を持ってきた彼女は、その関係が終わるごとにその男を、いつもの場所、時刻で待ってみるのだった。彼女が最後の男を渋谷で待つ。かつての男たちの記憶とともに、自分が本当は何を待っていて何をしようとしているのかも知らず。
神田神保町の路地裏。夫婦で営んでいるイタリア食堂へ、風変りなお客が訪れた。つわりで動けないバリスタの妻に代わって、おそるおそるコーヒーを淹れ、彼の話に耳を傾けるうちに、私は奇妙な体験をすることになる・・・。
「自分」はどういう人間なのかがよく分からない高校生の『僕』は、長くて退屈な夏休みを迎える。何かをしよう。そう思った彼はある日ロードバイクを買うことを決意するが・・・。
五十三歳になる彼女は、非人間的で惨めな自分自身の人生に疲れていた。職場を早期退職したことをきっかけに、縁もゆかりもない帯広市へ引っ越す。穏やかで厳しい帯広の自然に触れるうち、彼女は人間らしい生き方を取り戻して、新しい人生を歩み始めた。
愛知県西尾張地方に暮らす青井家の主人竜男は、自分ではそれほど食にこだわりを見せやしない方だと思っている。青井家の味噌汁は赤、白、合わせ、と日によって違う。この地方八丁味噌に代表される赤味噌が人気である。ある朝、八丁味噌を使った赤出しを口にして竜男は思わず言葉する。やっぱ赤だがね。
道夫のうちでは、毎年、お盆の十三日の夕方、まだ暮れきらないたそがれ時になりますと、先祖迎えの迎え火を焚きます。家の戸口の前に、ホウロクという素焼きの土器を地面に置いて、その上で、折ったオガラを燃やすのです。この火を目印にしてご先祖さまが帰ってくるといわれています。
会社の倒産により人生に破れ、大橋隆信は妻を残し、昔憧れた菜穂子の故郷・青森を訪ねた。吹雪の中で飛び込んだ小料理店の女将との会話で、大橋は昭和の世界に迷い込んだこと、女将の娘が早逝した菜穂子であることを知る。最終の青函連絡船で再会した菜穂子の言葉に、大橋は救われていくのだった。
流れるように生きていく不安を胸に秘めながらも、流れるように金沢に辿り着いた女性の追憶が、最初と最後の「薄紫色の着物」を介して一つの円い輪になっていく……。そんなふうに連鎖していく記憶の物語です。
最初に人間に恋したマーメイド以来、わたしも恋をしたいと想うマーメイドはいたことはいたけれど、ああいう最期を遂げてしまったことに対する恐怖心が彼女たちに二の足を踏ませていた。そんななか、人間に恋した3番目のマーメイドがいた。
今日は二〇一四年の七月十二日、大阪は晴れている土曜日で、ラモーンズの初代ドラマー、トミー・ラモーンが死んだのはきのう十一日の金曜日、ニューヨーク。阪急・十三駅近くのアパートに帰って、俺、はやくラモーンズが聞きたい。
風呂場や洗面所、家中の排水溝をパテで塞ぎ、窓枠もテープで目張りする。そして家中の蛇口を全開にひねる。今夜中には二階まで水は溜まるだろう。そう、今日から私はこの小さな家で、人魚と暮らすのだから。わがままで、すこし悲しい人魚の願いと、水浸しの暮らしの結末は……。
それは、突然の、来訪だった。うさぎと月、の、看板が、目印。その店の、前に。黒塗りの、車が、止まった。降り立った、紳士。仕立ての良い。三つ揃えの、スーツ。白い、ワイシャツ。絹の、ネクタイ。銀縁の、メガネ。ステッキ。紳士の、カタログから。
祖母の遺したシェアハウスの管理人兼住人として暮らす紅子。大学生の雪絵と太郎、留学生のグレーテ、専門学生のヒナキと過ごすルームシェアの日々に、ある夜新たな住人がやってくる。
野地沙麗子(のぢされいこ)。彼女のせいで最近の私は憂鬱だ。一人暮らしの部屋探し、おまけにお金に糸目はつけないときた。だが、その要望が「自分の髪を垂らしても問題ない物件に住みたい」という、わけのわからないもので…。