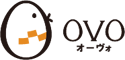(OVO オーヴォより)

8月5日のリオデジャネイロ・オリンピック開会式。会場だったマラカナン競技場のフィールドに、いくつものビルがにょきにょきと伸びたり縮んだりする映像が表れ、出演者がそのビルの屋上を本当に跳び移るかのような、スリリングな場面が展開された。出演者は平らな地上で演技しているだけだが、まるで空中を移動するように見えたのはプロジェクションマッピングと呼ばれる技術のお蔭。あらゆる建物や壁面をスクリーンにするこの投写技術は、今やイベントや催しに欠かせない演出になった。
世界中の人が注目するオリンピックの開閉会式で、プロジェクションマッピングの機器納入と操作を担当したのがパナソニック株式会社(以下パナソニック)。マラカナン競技場に約110台のプロジェクターを持ち込み、世界からスタッフを集め、演出家の厳しい要求に応え、寸分の狂いもなく映像を映しだし祭典に彩りをそえた。
パナソニックは前回のロンドン大会にもこの技術で開閉会式に加わったが、今回、特にこだわったのが「影を消すこと」だった。マッピングでは1方向から投写すれば、人物に当たると反対側に影ができて真っ黒になる。2方向だと色は薄くなるが完全ではない。そこで挑んだのが4方向からの投写だ。4方向からのそれぞれの画像が、時間や位置にずれがないよう綿密にプログラムを組んで投写する。冒頭に紹介した場面では、影に影響されず足元の映像はくっきり映しだされ、その上を人物が動いているようなリアルなシーンになった。
テレビで見ていては何の疑問も持たないこうした技術。それこそ何十回にも及ぶ試行錯誤とリハーサルの上に成り立っている。英国、フランス、ブラジル、日本など、約30人からなる投写チームを率いたのがパナソニックのビジュアルシステム事業部の山本淳さんと大丸(おおまる)惠史さんこの仕事はチームビルディングから始まったという。経験者を集め、言葉も習慣も違う中で意思の疎通を図っていく。次に演出家の意向をくんで画像を作り上げ、不意の出来事に備えてバックアップ策を練る。仕事の内容は、日々の組織運営に腐心する管理職のそれだ。2人とも50代。何より大事だったのは、オリンピックのセレモニーで絶対に失敗は許されないという使命感と責任感だった。
同時に、企業戦士はしたたかでもある。財政難の大会組織委員会の要望により、開閉会式の経費が大幅に削られたことが、少ない予算で最大の効果を上げるという課題のクリアにもつながったという。そして、今回はランプのプロジェクターが中心だったが、密かにレーザーの新製品も試した。ランプは切れやすく維持も難しい。しかし、レーザーは寿命が長い上に切れないという安心感がある。2020年の東京オリンピックをにらんだ時、レーザーの効果は絶対に試しておきたいことだった。
この2人に先立ち、2年前にブラジルに赴任し、機器の納入にあたったのがパナソニック・ブラジル社の金山睦さん。過去のオリンピックでは最大という陸上競技場の面積135平方メートルの大型LED電光掲示盤2画面をはじめ、各会場、選手村などに計72画面を納め、設置した。記者席などのテレビは1万5千台を越えた。前回のロンドン大会も経験済みとはいえ、こちらも約10カ国の出身者からなるチームを率いての作業だった。ブラジル国内だけでは無理で、世界各地から機器を調達した。しかし、製品、パーツの品番ごとに税率が違うなど手続きが複雑であったり、準備期間中に税制が変わったりしたことなど、その都度、勉強して事に当たったという。設置してからも電源の供給不足など、インフラの弱さに悩まされたそうだ。
裏方とはいえ、オリンピックという大舞台を経験し、自社の映像音響機器に自信を深めた3人は奇しくも同じビジネスモデルを描いていた。より小型になりながら繊細な画像、迫力ある音声を伝える自社の機器を、最大限に生かせるのがエンターテインメント業界だということを。一緒に苦労した仲間が世界に戻った時、その素晴らしさを伝えてくれると信じている。