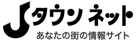(Jタウンネットより)
いったい誰が、どんな基準で決めたのかは分からないが、日本には「昭和四大方言」なるものが存在しているらしい。選ばれているのは、仙台の「ジャス」、鹿児島の「ラーフル」、名古屋の「ケッタマシン」、福井の「ジャミジャミ」だ。
なんだか言葉のインパクトだけで選んでいるような気もするが、いわれてみれば確かに「方言感」も「昭和感」も強そうではある。とにかく、それぞれの言葉について詳しく見ていこう。
昭和四大方言、その意味と由来を解説
まずは、仙台の「ジャス」から。
昭和30年(1950年)代から宮城県内で使われているという「ジャス」は、運動着のジャージを指す方言。その中でもとくに学校指定の運動着を呼ぶときに使われることが多いという。その起源は、地元企業が「ジャージスーツ」を略してジャスと呼んだことがはじまり、という説が有力だそうだ。
続いて、鹿児島の「ラーフル」。
鹿児島県全域、そのほか宮崎県や愛媛県の一部でも使われるという「ラーフル」は、黒板けしの正式名称なのだとか。由来はオランダ語の「rafel(ボロ布)」だといわれており、戦前までは西日本全域で使われていたという。しかし、その後鹿児島など一部の地域を除いて「黒板消し」が使われるように変化したそうだ。その後、昭和40年代ごろに方言研究家などに「ラーフル」が注目され、「鹿児島県人は黒板消しをラーフルと呼ぶ」ということが全国的に広まったらしい。
次は、名古屋の「ケッタマシン」。
名古屋を中心に東海地方の広い範囲で使われる「ケッタマシン」は、自転車を指す方言。略称の「ケッタ」や、派生形の「ケッタリング」などそのバリエーションは多い。言葉の由来は、「蹴ったくりマシーン」というのが通説。鳥山明さんの「Dr.スランプ」(連載は昭和50年代)に登場したことで、全国的な知名度が急上昇したようだ。
最後は、福井の「ジャミジャミ」。
福井県のほか、富山や岐阜など中部地方の北西地域で使われる「ジャミジャミ」は、テレビの砂嵐を表す方言。「ジャミジャミになってる」などと使われる。もともとは、「目が疲れてしょぼしょぼしたり、かすんで見えたりする様子」を指す言葉だったが、昭和に入りテレビが普及した後に、画面の砂嵐状態を指す際にも使われるようになったという。
ここまで紹介してきた昭和四大方言のなかには、平成となった現在では使う地元民が徐々に減ってきている言葉もあるようで、ネットでは「地元民だけど知らなかった…」といった声もいくつか見られた。そう考えると、選ばれた基準はさておき、昭和という時代を代表する方言であることは確かといえそうだ。