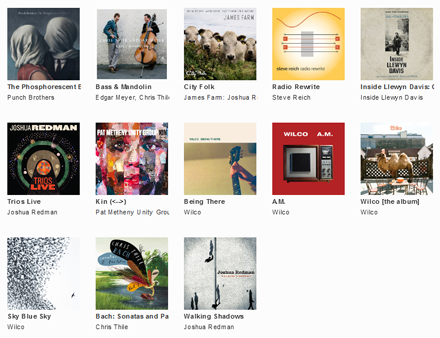ジョージ・ハリスンは反原発の立場であったことで知られている。 1981年に発表された「セイブ・ザ・ワールド」(世界を救え)という曲で、ジョージは宇宙開発、熱帯雨林伐採、捕鯨、原子力などの問題をとりあげて歌っている。 「世界を救わなきゃならない。また誰かが悪用しようとしている。今見る限りでは、この惑星は略奪されている。ぼくらは酷使してきた。世界を救わなきゃ」 「軍事産業家はぼくらに(核物質である)プルトニウムを売りつける。今じゃ自家製の水爆をママと台所で作れる時代だ。核エネルギーは何よりもカネがかかる。ガンや死や破壊や欲望のための理知のない馬鹿者たちの答え(が核エネルギー)」 「ぼくらは、この惑星を地獄に貶めようという邪悪な少数の者たちに左右されている」 79年に米国で起きたスリーマイル島原発事故が念頭にあったのだろう。しかし、86年のチェルノブイリ原発事故や2011年の福島第一原発事故のことを考えるとジョージの考えがかなり「先」をいっていたことがわかるのである。 ザ・ビートルズ・クラブ編の「ジョージ・ハリスン全仕事」(プロデュース・センター)によると、ジョージは80年3月末に妻オリビアとともに、ロンドンで行われた国際環境団体「フレンズ・オブ・ジ・アース」の反核デモ行進に参加した。 そのジョージだが、90年代に入ると癌におかされ、闘病生活を余儀なくされる。 2001年には彼の代表作『オール・シングス・マスト・パス』のリマスター盤を発表。インナースリーブには彼自慢の庭園が次第に原子力発電所らしき建物、高層ビル、高速道路やジェット機などに囲まれていくさまをあしらい彼一流の皮肉を利かせた。 死の間際まで彼が制作にたずさわり、死後約1年経った2002年11月に発表されたアルバム『BRAINWASHED(ブレインウォッシュド)』は、まさに彼の遺言である。 タイトル曲では、現代社会あるいは物質社会に暮らす人々が、子供時代から学校で洗脳され、大人になってからも日経平均株価やフィナンシャル・タイムス(FT)指数といった株価指数やワシントンやボンなどの権力者たちやメディアやコンピューターや携帯電話などに洗脳され続けているとし、その救いを神に求めている。 ジョージは「隠遁生活」を送りながら、癌と闘いつつ、振り絞るようにして紡ぎだしたラストメッセージが『BRAINWASHED』である。救いを神に求めているのが彼らしいが、そうせざるをえないほどにわれわれを取り巻く状況に対して悲観的になっていたのかもしれない。 日本では福島第一原発事故のあと、ロックグループRCサクセションのアルバム『カバーズ』がチャートを駆け上がった。このアルバムには「ラブ・ミー・テンダー」と「サマータイム・ブルース」という2曲の反原発ソングが含まれている。前者では、「放射能はいらねえ、牛乳を飲みてえ。何言ってんだ、税金(カネ)かえせ」と忌野清志郎は歌い、後者でも日本では根拠なく原発は安全だといわれているとして批判的な姿勢を示した。 88年のこのアルバムの発売をめぐってはひと悶着あった。その2年前のチェルノブイリ原発事故の影響が取りざたされ、日本でも草の根の反原発運動が動き出していた時期のことである。RCサクセションの所属レコード会社である東芝EMIは、親会社の東芝が原発を手掛けていることなどにかんがみ、発売を拒否したのだ。結局は別のレコード会社から発売されたものの、原発をめぐる「タブー」があることを世に知らしめた「事件」だった。 経済評論家の内橋克人氏は早くから原発をめぐる問題を指摘してきた一人だ。著書「原発への警鐘」(講談社文庫)の帯には「日本列島“原発基地化”の実態と危険を暴く」とあった。内橋氏は原発をめぐっては、政府、自民党、電力業界、電力ユーザーである産業界、原発の立地自治体などが複雑な利権でがんじがらめになってしまっていることを指摘するとともに、ひとたび事故が起きたら取り返しがつかない危険性があるとしていた。 その内橋氏がのちに批判をすることとなる市場原理主義的な経済政策を標ぼうし、推し進めた小泉純一郎元首相がいま脱原発を唱えていることは意外にも思える。 しかし小泉氏は本気のようだ。同氏は細川護煕元首相とともに、2014年5月に、原発ゼロに向けて自然エネルギーの普及を目指す一般社団法人「自然エネルギー推進会議」を発足させた。小泉氏は、襟を正すためか、東京電力のトップら財界主導による民間シンクタンク「国際公共政策研究センター」の顧問を辞任した。 小泉氏は脱原発を求める根拠として、放射性廃棄物の最終処分場の選定が難しい点をあげ、原発にかけてきた費用を代替エネルギーに回した方がよいと述べている。 安倍晋三首相率いる政府・与党は、福島第一原発事故当時の民主党政権が掲げた「原発ゼロ」方針と決別し、再稼働への動きを進めている。 核を作らず、持たず、持ち込ませないという「非核三原則」を表向きは掲げる日本政府だが、核兵器5千発分に相当する44トンのプルトニウムを内外に保有したままである。 今では、プルトニウムがママではなく、テロリストに渡る危険もあるのにである。 (文・桑原亘之介)