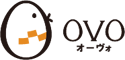(OVO オーヴォより)

学校法人城西大学は、創立50周年を記念して、国際シンポジウム「TEXTURES of SOUND」(音のテクスチャ)を1月13日・14日に紀尾井町キャンパスで開催した。城西大学・城西国際大学では、日頃から「世界の中の日本」という講義を行っており、今回のシンポジウムは50周年を迎えるにあたっての集大成として企画した。美術、音楽、文学などの分野における日本文化の代表的研究者を国内外から招き、「前近代の日本におけるオーラリティ、パフォーマンス、視覚芸術」というテーマで、さまざまな角度から興味深い研究が発表された。
開催に先立って、城西大学の水田宗子(みずた・のりこ)理事長は、「日本文化をもう一度考え直し、新たな日本研究の視点を開拓していきたい。非常に先端的なテーマを新しい文化の課題として取り上げることによって、人文科学全体の勉強の仕方、あり方について示唆が得られるようなシンポジウムにしたい。世界の日本文化研究者の新しい成果を聞いていただきたい」とあいさつした。
今回のシンポジウムで焦点が当てられたのは、日本古典の中のオーラリティ(声の文化)や音楽の果たす役割。それを考察することによって日本文化の研究にどれほどの変革をもたらすことができるのか、それを学術的に見きわめることがこのシンポジウムの目的。
さまざまな日本古典を例に挙げ、オーラリティを、記述されたテキストや絵画・造形といったビジュアルオブジェクトの対立物ではなく、織物の糸のように集合体に織り込まれた構成要素であると見なすところから、主題は「音のテクスチャ」と名付けられた。
この音のテクスチャを紐解くかのように、コロンビア大学ハルオ・シラネ教授が基調講演「共同的記憶の形成における声、身体、音楽:中世日本の説話のメディア再考」を行い、「御伽草子」や「平家物語」をはじめとする日本の中世文学における複合芸術の重要な問題点を指摘した。
そのほか、ハーバード大学ユージン・ワン教授、メリッサ・マコーミック教授、シカゴ大学アシュトン・ラザラス助教授、宮城学院女子大学 大内典教授、城西国際大学 岡田美也子准教授、ハイデルベルグ大学ユディット・アロカイ教授、ロンドン大学タイモン・スクリーチ教授らが登壇。個々の論文をもとに、近代以前の音とイメージの接点、声や文字化されたテキスト(歌集や楽譜など)の接点や音響的側面を探求した内容などが発表され、日本文化が世界でどのように享受されているかや、日本文化研究の新たな道が浮き彫りとなった。また講演に関連して、川嶋信子さんによる琵琶演奏も行われ、音のテクスチャとして肌で感じられる内容のシンポジウムとなった。