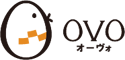(OVO オーヴォより)

昔読んだ、池澤夏樹の「真昼のプリニウス」という小説を思い出す。女性火山学者と男性が、何度も交わす長い手紙のやりとり。男女の仲がどう進むというわけではないのだが、そのやりとりのペースが緩やかで、相手に投げかける言葉が丁寧に選択されていて心地よい。手紙、というツールをはさんで、ゆるやかにめぐる人と人の思い。
飲み物というのも、間違いなくそんなツールだ。味や香りも大事だけれど、何より、その場所の空気をうまく回していく道具として、いろんな場面で不可欠な代物になっている。アラタ(井浦新)が働くレコード屋さんでの再会から、アユミ(伊藤歩)が留学して帰国するまで、6本のショートストーリーで描いてきたチルドカップコーヒーのマウントレーニア。お互いの距離は少しずつ縮まっているのだろうけれど、“劇的”な展開はない。二人の手に何気なくあるマウントレーニアは、いつもまるで、選び抜いた末に言い出せないまま捨てた言葉をごまかす、照れ隠しのように控えめだ。だが手元のカップを眺めたり、ストローをさし直したり、カップに描かれた絵を見るフリをしながらやり過ごす時間の大切さ、それがなかったら、うまく切り抜けられないかもしれない、隠れた主役でもある。
その第2章が始まった。アラタの家の引っ越しの手伝いに来たアユミが、手に2つのカップを持って上階で作業するアラタを見上げる。おそらくこのシリーズで初めて、彼女が「マウントレーニア!」という言葉を発した瞬間だ。明快に発音されたその商品名だが、CMっぽさはなく、やはりストーリーの重要な立て役者。アユミがその後小声でしめくくった後半の言葉は「…と私、どっちが好き?」なのだ。
仕事をしながら、車窓を飛んでいく風景を眺めながら、会議でプレゼンを聞きながら、そして大切な誰かとの時間を過ごしながら。のどが渇いていなくても、手にしていることで何かが滑らかに進んでいく一杯の飲み物。このまま、落ち着いた結末が永遠にやってこなくても構わないと思わせる心地よさが、このシリーズにはある。
でも実は、「聞こえないよ!」と答えていたアラタは、部屋でくつろいでいるときに、アユミの質問が聞こえていたと告白する。「ホントはね、聞こえた。・・・ふふっ」といたずらっぽく笑うアラタ。その言葉にキュンとする女子も多そうだ。
この緩やかな時間が流れるストーリー、やっぱりなんかいい。