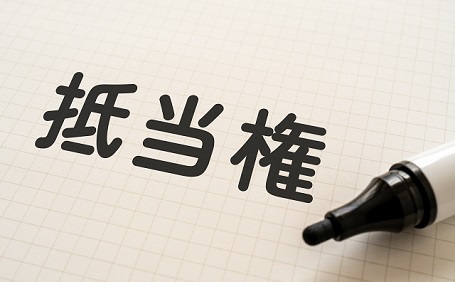土地を売却する際の必要書類は?費用も含めてまとめて紹介

本記事では、土地を売却する際の必要書類と費用を紹介します。さらに、確定申告に必要な書類と手続き、土地の売却で気を付けたいことを解説。記事を読むことで、土地を売却するにあたって必要な準備を網羅的に把握できるようになるでしょう。
記事の目次
土地を売却する際の必要書類

土地の売却にあたって必要な書類を以下にまとめました。
- 本人確認書類
- 住民票
- 印鑑証明書
- 登記済権利証(権利証)または登記識別情報通知書
- 固定資産評価証明書
- 固定資産税・都市計画税納税通知書の写し
- 確定測量図(確定実測図)
- 筆界確認書・越境物の覚書
- 抵当権抹消登記用書類
- 共有名義・相続物件の同意書
- 代理権委任状
それぞれ詳しく見ていきましょう。
本人確認書類
本人確認書類は売主が本人であることを示す書類です。具体的には、売買契約時と引き渡し時、登記手続きを依頼する司法書士への本人確認のタイミングで提示します。普段から携帯している運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証を使うため、基本的にあらためて取得する必要はありません。
住民票
住民票は、司法書士が登記申請をおこなう際の添付書類になります。市区町村役場や、コンビニの証明書交付サービスにより即日で入手可能であり、発行手数料は300円~400円程度。また、登記名義人の登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合には、戸籍の附票等の住所の変遷がわかる書類も必要になります。
印鑑証明書
印鑑証明書は、実印であることを証明する書類です。買主への所有権移転登記の際に、売買契約書へ押印した実印が本物であることを示すために提出します。用意するタイミングが重要で、3カ月以内に発行したものでなければならないため、できれば引き渡し予定日の直前がおすすめです。市区町村役場で取得でき、発行費用は300円~400円程度です。
登記済権利証(権利証)または登記識別情報通知書
「登記済権利証(権利証)」、または「登記識別情報通知書」は、土地の持ち主を示すもので、土地の所有者(売主)しか所有していないもっとも重要な書類です。ただし、2005年3月7日より改正不動産登記法が施行され、登記済権利証(権利証)が廃止。登記識別情報通知書になりました。そのため、改正以前に登記した不動産は登記済権利証(権利証)、以降は12桁の英数字が記載された登記識別情報通知書が交付されます。土地を所有した時点で、すでに保有している書類であるため、売却の際に取得費用はかかりません。
固定資産評価証明書
「固定資産評価証明書」は、その名のとおり、土地の固定資産税評価額が記載された証明書です。登録免許税や、譲渡所得税の計算に使用します。発行から年度が変わると使用不可となるため、売買契約を結ぶ年度の証明書を用意しましょう。市区町村の資産税課で発行でき、取得費用は300円です。
固定資産税・都市計画税納税通知書の写し
「固定資産税・都市計画税納税通知書」は、毎年4~6月頃に郵送される納税通知書で、固定資産税精算金を計算するために必要です。「固定資産税精算金」とは、引渡日以降の固定資産税・都市計画税の負担を実質的に買主へ移転するために買主が売主へ支払う精算金のこと。さらに売主が納税していた期間の未納税額がないかを買主が確認するためにも使用されます。また、納税通知書の再発行はできないため、届いた通知書は大切に保管してください。
確定測量図(確定実測図)
「確定測量図(確定実測図)」は、隣地所有者の立ち会いのもと、境界杭を設置し、面積を実測した図面です。土地売却時の測量は法的義務でなく、確定測量図も法的には必要な書類ではありませんが、面積の差異や境界トラブルを防ぐために、測量をして、確定測量図を取得しておくと安心でしょう。作成の際は土地家屋調査士に依頼して報酬を支払う必要があり、完成には数週間、場合によっては数カ月かかることもあります。
筆界確認書・越境物の覚書
「筆界確認書」・「越境物の覚書」は、自身が所有している土地の境界の確定を、隣地所有者と確認する書類です。筆界確認書は、隣接する土地の境界線について双方の所有者が合意した旨を記した書面のこと。また越境物の覚書とは、屋根の一部やブロック塀など、越境物問題の解決に関する内容が記された合意書を指します。前述でご紹介した確定測量図(確定実測図)の作成時にまとめて作成する場合が多い書類で、確定測量図(確定実測図)があれば問題ないですが、この2つがあると売却の手続きをスムーズに進めやすくなります。
抵当権抹消登記用書類
「抵当権」とは、住宅ローンの担保として一戸建てやマンションを設定した場合に住宅ローンを融資した金融機関が有する権利のこと。抵当権のある土地は、必ず抹消登記をしてから売却するため、抵当権抹消登記用の書類が必要です。また、抵当権抹消の手続きは司法書士に依頼するのが一般的なため、司法書士報酬がかかります。
共有名義・相続物件の同意書
「共有名義・相続物件の同意書」は、共有名義の不動産においてすべての権利者が売却に同意していることを示す書類です。売却する土地が単独名義ではなく、共有名義の場合は、合意のうえでの売却であることを示すために必須となります。共有名義人とのトラブルを防ぐためにも、用意しておきましょう。同意書は司法書士に依頼して作成するのが一般的なため、司法書士報酬がかかります。
代理権委任状
「代理権委任状」は、売主本人が売買契約や残代金決済などの手続きを代理人に一任するために作成する書類です。売主が遠方に住んでいる場合や、高齢や入院で動けない場合は、代理権委任状を用意することで、代理人に契約行為を任せることができます。不動産会社がひな形を用意して売主本人が作成することが一般的であるため、費用は原則としてかかりません。
土地売却に必要な費用
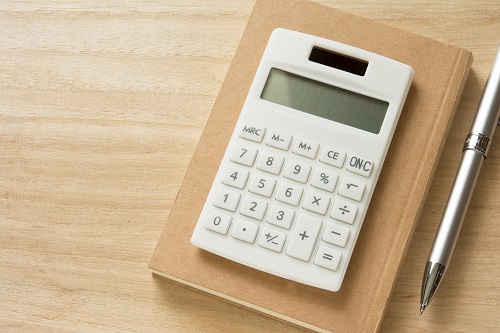
土地売却に必要な費用は以下のとおりです。
仲介手数料
仲介手数料は、土地売却の仲介を請け負う不動産会社へ支払う成功報酬です。
売買金額が400万円を超える場合の上限は宅建業法で次のように決まっています。
売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税
例えば、3,000万円で不動産が売れた場合の仲介手数料の上限は「96万円+消費税」です。基本的には売買契約が成立しなければ、仲介手数料の支払い義務はありません。
印紙税
印紙税は、売買契約書に収入印紙を貼って納める税金です。契約金額によって印紙税額も段階的に変わります。
軽減措置の適用の有無によっても税額が変化し、2027年3月31日までは軽減措置が適用されます。契約金額に応じた軽減措置適用時の印紙税の税額を以下にまとめました。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 10万円超~50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超~100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超~500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 1万円 | 1万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 1万円 | 3万円 |
| 1億円超~5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円超~10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円超~50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円超 | 60万円 | 48万円 |
出典:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」
収入印紙は契約書原本1通につき1枚貼付し、売主・買主でそれぞれ作成します。不動産売却にかかる印紙税は折半が一般的ですが、売主と買主の間で合意が取れた場合はその限りではありません。
登録免許税
登録免許税は、所有権移転登記の際に納める国税です。土地の売却時の税額を求める計算式は次のとおりです。
課税標準(固定資産税評価額)× 1.5%(軽減税率)
2027年3月31日まで軽減税率の1.5%が適用され、通常は税率2.0%です。
評価額が1,500万円であれば、登録免許税は22万5,000円です。さらに抵当権抹消登記がある場合は、登録免許税は土地一つあたり1,000円かかります。
司法書士報酬
登記申請を司法書士に任せる場合、手数料がかかります。土地の売却で考えられる登記申請は、所有権移転登記と抵当権抹消登記があります。報酬の金額は依頼する司法書士によって異なりますが、数万円~十数万円が相場になるでしょう。
測量費・筆界確認費用
測量費・筆界確認費用は、境界を確定するための確定測量図の作成を、土地家屋調査士に依頼する費用です。費用は数十万円程度になることが多く、隣接地権者や越境物の数が増えるほど高くなりやすいでしょう。
筆界確認書・越境覚書も同時に依頼することで、土地の売却時に必要な書類を同じタイミングで集められます。
建物の解体費用
すでに建物が建っている土地を更地で売却する場合には建物の解体費用が発生します。木造住宅であれば1坪あたり3万1,000円~4万4,000円が目安であり、例えば30坪の建物であれば、解体費用は90万〜132万円ほど。
鉄骨造・鉄筋コンクリート造の住宅の場合は処分費がかさむため、解体費用は増加します。また、アスベストの除去作業が発生した場合は、別途費用が加算される場合があるため、注意が必要です。
固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日時点の所有者に税金が課される仕組みになっています。土地を売却したタイミングが2月であっても、翌年になるまでの期間分の税金を売主が納める必要があります。
そのため、売主は翌年の1月1日まで固定資産税・都市計画税を全額納める必要がありますが、決済日以降の期間分の税額は、日割り精算して買主から受け取ることが一般的です。
譲渡所得税・住民税
譲渡所得税・住民税は、土地の売却益に対して課される税金です。所有期間で以下のように税率が変化します。
また、2013年1月1日~2037年12月31日までは、東日本大震災の復興財源に充てるための「復興特別所得税」が通常の所得税に上乗せして加算されます。
| 短期譲渡所得 | 長期譲渡所得 | |
|---|---|---|
| 所得税率 | 30% | 15% |
| 住民税率 | 9% | 5% |
| 復興特別所得税率 | 0.63% | 0.315% |
| 合計 | 39.63% | 20.315% |
土地の売却で得た利益から、取得費と諸経費を差し引いた課税対象金額が1,000万円の場合、短期譲渡所得では396万3,000円の税金が課されます。一方で、所有期間が5年を超え、長期譲渡所得で税額を計算する場合は、203万3,150円に減少し、税負担が軽減される仕組みです。
譲渡所得税・住民税をはじめ、土地の売却で支払う税金は控除制度の利用で節税できることがあります。納税額を安くするなら、税理士報酬が別途かかりますが、税理士に相談しましょう。
土地売却後の確定申告の必要書類と手順

土地の売却で利益を得たあとには、譲渡所得税・住民税を納めるために確定申告が必要です。確定申告で必要な書類を以下にまとめました。
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 確定申告書 (第一表・第二表) |
納税者全員が提出する基本の申告書 |
| 確定申告書第三表 (分離課税用) |
不動産の譲渡所得の税金を申告する書類 |
| 譲渡所得の内訳書 (土地・建物用) |
譲渡所得の内訳を細かく記載し計算根拠を示す書類 |
| 売買契約書のコピー | 取得価額と売却価額を証明する書類 |
| 登記事項証明書 (全部事項証明書) |
所有者・地番・面積などを確認できる登記簿謄本 |
| 領収書一式 | 仲介手数料・測量費・解体費などの経費を計上する際に必要な書類 |
| マイナンバー確認書類 | e-Taxで申告する際にマイナンバーを確認するために必要な書類 |
ここからは上記の書類を揃えたことを前提に、確定申告の手順を解説します。
STEP1.譲渡所得金額を計算する
譲渡所得金額は、「譲渡収入 -(取得費 + 譲渡費用)」で計算できます。それぞれの金額と確定させるために参考にする資料を以下にまとめました。
| 項目 | 内容 | 参考にする書類 |
|---|---|---|
| 譲渡収入 | 土地の売却代金 | 売買契約書 |
| 取得費 | 購入代金と購入時の諸経費 | 売買契約書・領収書 |
| 譲渡費用 | 仲介手数料・測量費・ 解体費などの経費 |
領収書 |
取得費は、購入当時の売買契約書・領収書から客観的に証明する必要があります。証明できない場合は、取得費不明となり、売却代金の5%で計上します。仲介手数料などの土地の売却にかかった経費である譲渡費用は、領収書から合計を計算しましょう。
具体的な例を挙げて、実際に計算をしました。
- 譲渡収入:4,000万円
- 取得費:3,000万円
- 譲渡費用:200万円
4,000 万円 -(3,000 万円 + 200 万円)= 800万円
以上の計算から、譲渡所得金額は800万円と計算できました。譲渡所得金額を求められれば、土地の所有期間に応じた税率を適用して税額を計算できます。この例の場合、長期譲渡所得の場合に納める税金は162万5,200円です。
STEP2.申告書類を作成する
確定申告書の作成は大きく分けて、手書きとe-Taxを利用して作成する方法があります。手書きの場合は国税庁サイトまたは税務署窓口で各申告書類を入手します。適切な数値を記載し、売買契約書のコピーと領収書などの必要書類を添付しましょう。
e-Taxは画面の指示に従うだけで、確定申告書(第一表〜第三表)、譲渡所得の内訳書(土地・建物用)を自動で作成できるため、別途書類を用意する必要がありません。必要な添付書類はPDFなどのイメージデータにします。
STEP3.確定申告書を提出する
土地を売却して譲渡益が発生した場合は原則として確定申告が必要です。確定申告書は、原則として土地を売却した翌年の2月16日〜3月15日に提出します。提出方法は手書きとe-Taxで異なるため、確認しておきましょう。手書きの場合は税務署受付で直接提出できる窓口持参と、郵送による提出も受け付けています。e-Taxの場合は、提出にマイナンバーが必要であり、オンラインで電子送信して完了します。
申告書を提出して納税額が確定したら、譲渡所得税を確定申告期間内に納めましょう。専用の納付書を使用して、税務署の会計窓口か金融機関で納付できますが、クレジットカード納付やコンビニ納付にも対応しています。住民税は6月以降に正式に確定され、納める仕組みです。
土地売却の必要書類で気を付けること

最後に、土地の売却における必要書類で気を付けることを2つ解説します。
登記識別情報は再発行できない
登記識別情報は、12桁の英数字で所有権を証明する書面です。法務省の運用上、いかなる理由でも再発行は認められていません。紛失した状態で売却当日を迎えると、決済がストップします。ただし、紛失した場合でも以下の救済策があります。
- 事前通知制度
- 資格者代理人による本人確認
- 公証人による本人確認
事前通知は、法務局が本人宛に郵送で照会をおこなう方式であり、追加費用は不要です。受け取るまでに1~2週間かかるため、紛失に気付いたタイミングで前もって手続きを始めるようにしましょう。資格者代理人による本人確認は、司法書士が本人確認情報を作成して登記に添付する方法です。
迅速に対応しなければならない場合は、公証人による本人確認を利用しましょう。公証役場で委任状などに署名・押印して認証を受ける手続きであり、即日で完了します。登記済権利証・登記識別情報通知書を紛失したことに気付いた場合は、できる限り早く対応するようにしてください。
印鑑証明書は発行から3カ月以内に取得する
土地の売却に関する書類はできる限り前もって用意することが推奨されます。しかし、一部の書類は用意するタイミングが重要になることも。所有権移転登記を申請する際に添付する印鑑証明書は、作成後3カ月以内のものに限ると定められています。
所有権移転登記の申請に対して余裕をもって用意することに変わりありませんが、3カ月以上前に用意しないようにしましょう。万が一、発行後に売却が先延ばしされて期限切れになる場合も考えて、引き渡し予定日の1~2週間前に用意することをおすすめします。
まとめ
土地を売りに出す際には、さまざまな書類が必要になります。本人確認書類などの用意しやすい書類から、土地家屋調査士に依頼して作成する確定測量図などの専門的な書類も必要です。書類によってはタイミングに気を付けて、余裕をもって用意するようにしましょう。
土地を売却したあとの利益に対する税金を納めるためには、確定申告が必要になります。土地の売却にあたって必要な書類を用意するタイミングで、確定申告に使う書類を集めておくと効率的です。必要に応じて専門家と連携して、土地を売却する準備を進めましょう。
注文住宅を建てる

執筆者
長谷川 賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ