家の解体費用の相場は?安く抑えるコツや払えない場合の対処法を徹底解説
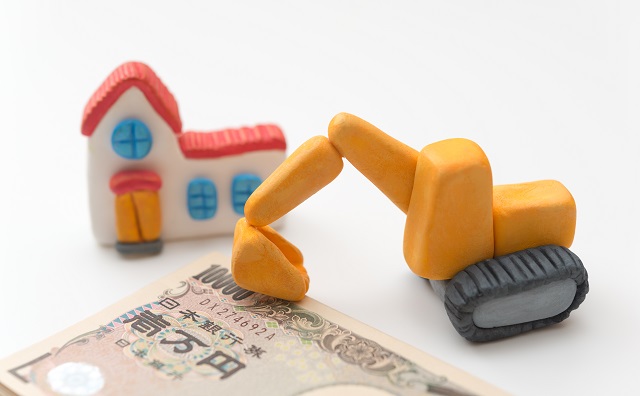
この記事では、解体費用の相場や解体費用を安く抑えるコツを紹介します。また解体工事の基本的な流れや解体費用が払えない時の対処法、注意点も詳しく解説します。家の解体を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
記事の目次
家の解体費用は何で決まる?

家の解体費用は、解体する手間と処分しなければならない廃材の量によって異なります。解体するのが難しい構造ほど手間が余分にかかるため、その分解体費用も高くなります。また廃材の量が多ければ、処分費もかさみます。
この章では、家の解体費用が決まる主な要因を5つ紹介します。
構造・使用建材
1つ目が構造・使用建材です。家が堅固な構造であるほど解体に時間や労力がかかります。解体や廃材の搬出に、特別な重機が必要になることも。その場合、人件費や重機の運搬費(回送費)がコストに跳ね返るため、解体費用も高くなるでしょう。
なお、木造の家よりも鉄骨造のほうが高くなり、鉄筋コンクリート造はさらに高くなる傾向があります。また、木造であっても使用している建材や工法によっては余分に手間と処分費がかかることがあるため、見積もり時にしっかり調査してもらうようにしましょう。
立地条件
前面道路の幅員や隣家との距離など、立地条件が解体費用に影響することもあります。
家の前面道路が広ければ大きい工事車両が使用でき、廃棄物の搬出などを効率よくおこなうことが可能です。解体作業のしやすい条件が揃うと、少人数で作業ができ、工期も短くなるので、解体費用を抑えられるでしょう。
一方、住宅密集地などにより使える重機が限定される場合、手作業が増えるので作業効率は悪くなります。旗竿地や狭小地、傾斜地なども、解体費用は高くなる傾向にあります。
広さ・階数
建物の床面積が広ければ、解体作業と廃棄物の処分費が増えるため、解体費用はふくらみます。また階数もコストに影響します。例えば3階建ての家の場合、アーム付きの重機を使って解体することがあります。その際、重機の運搬費(回送費)がかかるので、2階建てよりも3階建てのほうが、解体費用は高くなりやすいでしょう。
では平屋の場合、コストは安くなるのでしょうか。高さがないことで解体作業はしやすくなるかもしれません。しかし、平屋は解体に手間のかかる基礎部分が大きくなるため、2階建ての同じ床面積の家と比べると、平屋のほうが高くなることがあります。また、屋根の面積が広い分、処分費も増します。
築年数
建物の築年数が、解体費用に影響することもあります。
現在、「アスベスト含有建材」は発がん性があることから製造や使用が禁止されています。ところが、昔は住宅用の建材として広く使われていました。アスベストを含有する建材が使われた建物を解体する際、14日前までに都道府県に届け出する必要があります。解体時にはアスベスト繊維の飛散を防止する作業基準を遵守しなければなりません。
アスベスト含有建材が使われた家の解体には、建物の解体費用とは別に、アスベスト除去費用がかかります。処理する面積や個別の条件によって費用は異なるため、詳しくは解体専門の会社に相談しましょう。アスベストの除去費用の相場は、このあとの章で紹介します。
廃棄する建材の量
廃棄する建材の量が多ければ多いほど処分費は増えるため、解体費用も高くなります。例えば床面積が同じ家でも、構造部分が多い家は一般的な建物に比べて割高になる可能性があります。床面積だけでは解体費用を計れないこともあるので注意しましょう。
家の解体にかかる費用と相場
家の解体費用は、本体工事費や廃材の処分費、仮設工事費、諸経費などから構成されます。また、重機を使う場合は重機回送費、ガードマンを配置する必要がある場合は現場管理費が高くなることもあります。
ここでは、構造別に床面積30坪と50坪の場合の解体費用の相場を紹介します。
| 30坪 | 50坪 | |
|---|---|---|
| 木造住宅 | 120~150万円 | 200~250万円 |
| 鉄骨造住宅 | 180~210万円 | 300~350万円 |
| RC(鉄筋コンクリート)住宅 | 210~240万円 | 350~400万円 |
上記の表はあくまでも一般的な相場です。実際の解体費用は、解体会社に見積もりを依頼するようにしましょう。
解体工事以外にかかる費用
家を解体して更地にする場合、建物の解体費用や廃材の処分費以外にも付帯工事が発生し、別途費用がかかることがあります。またアスベストが含有する建材を使用していれば、除去費用も必要です。この章では、解体工事費以外にかかる費用を紹介します。
付帯工事費
家を解体して更地にすると、通常庭木やブロック塀、ガレージなども解体することになります。これらの解体費用が見積書に「付帯工事費」として上乗せされます。家に庭やガレージなどがある場合は、一般的な相場を把握して、費用がかかることを想定しておきましょう。
・庭木の撤去(抜根)

更地にする場合は、庭木の根の部分も撤去(抜根)する必要があります。庭木の伐採のみを依頼すると、根の部分が残ってしまうため注意しましょう。
庭木の抜根はその幹回りや高さによって異なりますが、3~5mで幹回りが30~50cm程度であれば、15,000~25,000円が相場です。小さな庭木であれば、1本5,000~10,000円程度でしょう。
・ブロック塀の解体
ブロック塀は、重機で解体できれば人件費が抑えられるため比較的安く解体できます。手作業でしか解体できない場合は、手間がかかるため割高になります。ブロック塀の種類や地域によっても異なりますが4,000円/平方メートル~10,000円/平方メートルが相場です。
・ガレージの解体
ガレージの解体はその構造によって、かかる費用も異なります。木造やトタン、カスケードガレージ(雪国仕様の車庫)は15,000~20,000円/坪、鉄骨造は20,000~40,000円/坪、RC造は60,000~80,000円/坪が一般的な相場です。
・浄化槽の撤去処分
浄化槽の撤去処分にかかる費用は、浄化槽のサイズにもよりますが、30,000~70,000円が相場です。ただし解体が難しい浄化槽や、材質がコンクリート製の浄化槽は100,000円前後かかることもあります。
アスベスト調査・除去費用
アスベストが含まれた建材を使用した家の解体では、解体費以外にアスベスト除去費用がかかります。
国土交通省が公表している、2007年1月~2007年12月までの施工実績から算出した除去単価は以下のとおりです。
| アスベスト処理面積 | 除去費用 |
|---|---|
| 300平方メートル以下 | 2.0万円/平方メートル ~8.5万円平方メートル |
|
300平方メートル ~1,000平方メートル |
1.5万円/平方メートル ~4.5万円平方メートル |
| 1,000平方メートル以上 | 1.0万円/平方メートル ~3.0万円/平方メートル |
(出典:国土交通省ホームページ「アスベスト対策Q&A」)
整地工事費

かならずしも必要な工事ではありませんが、ガラやゴミ、パイプを取り除いて転圧機や重機などで地面を平らにする場合は、「整地工事費」がかかります。大きなコンクリートガラや土地に傾斜がない場合は300~600円/平方メートル程度、一緒に除草や植栽などを撤去する場合は2,000~8,000円/平方メートル程度が相場です。
諸経費
解体費とは別に「諸経費」として現場管理費や書類作成日、損害保険料などがかかることもあります。相場は解体費用の5〜10%であることが多く、工事の規模によって変動します。見積もり時に高いと感じた場合は、その内訳を確認してみましょう。
家の解体費用を抑えるコツ
家の解体費用は構造や面積によって異なりますが、なるべく安く抑えたいですよね。この章では、家の解体費を抑えるコツを4つ紹介します。
複数の解体会社に見積もりを取る
解体の見積もりは複数社に依頼し、比較するようにしましょう。依頼先によっては、見積もりが大きく異なることもあります。また解体後の土地を売却する予定の場合は、不動産会社に相談してみるのもよいでしょう。
安い時期に工事をおこなう
解体会社にも繁忙期があります。解体を急がないのであれば、忙しくない時期を解体会社に確認し、シーズンオフや費用の安い日程で依頼するとよいでしょう。
自分でできることは事前にやっておく
自分でできることは事前にやっておきましょう。例えば庭木は自ら伐採して、処分もしておくことで解体費用以外の支出を抑えられます。また家財道具も一緒に解体してもらいたいと思うかもしれませんが、家財道具の解体・処分にも費用がかかるため、自治体の回収日や粗大ごみの回収を利用して、ゴミを減らしておくと、解体費用を抑えることができます。
補助金制度があれば活用する
自治体によっては古い建物や空き家の解体費用に対して、補助金制度を用意していることがあります。まずは自治体の窓口やホームページで、ご自身が対象になるか確認してみましょう。
解体費用が払えない場合の対処法

解体費用は100万円単位でかかり、構造によっては高額になることも。この章では解体費用が払えない場合の対処法を4つ紹介します。
解体ローンを活用する
手持ちの資金で解体費用を捻出するのが難しい方は、「解体ローン」の活用を検討しましょう。金融機関によって「空き家解体ローン」や「空き家解体・有効活用ローン」などさまざまな商品があります。住宅ローンに比べて金利は高くなりますが、基本的に無担保で借り入れできることが多いです。金融機関によっては解体工事費用だけでなく、解体後の駐車場の造成工事費用などにも利用できるものもあるので、複数の金融機関の商品を比べ、借り入れを相談してみましょう。
解体せずに売却する
建物付き土地として、解体せずに売却することも可能です。土地として売却するにあたり、かならずしも更地にする必要はありません。また、買い手が見つからなさそうな物件でも、不動産会社に売却するという方法もあるので、まずは不動産会社に相談してみましょう。
解体を前提に売る(更地渡し)
売買契約後、引渡しまでに更地にして引き渡すことを条件にして売却する(更地渡し)という方法もあります。売買代金を解体費用に充てられるため、解体費用よりも高く売れた場合は手持ちの資金を減らさずに済みます。一般的には建物付き土地よりも更地のほうが売れやすい傾向があるため、更地渡しとすることにはメリットがあります。
賃貸に出す
建物の状態が比較的よく、賃貸物件として貸し出せる場合は、売却ではなく賃貸に出すことも検討してみるとよいでしょう。入居者が決まれば、月々家賃収入を得られます。ただし維持管理するための費用や、貸し出すためにリフォームが必要になることもあるので注意しましょう。
家の解体工事の基本的な流れ

家の解体にかかる日数は、構造や面積によって異なりますが、おおむね1週間から20日程度です。この章では解体会社へ見積もりを依頼して、整地工事するまでの一般的な流れを紹介します。
見積もり・解体会社との契約
まずは複数社に見積もり依頼し、比較検討をします。見積もりの内訳や価格設定、解体会社の担当者との相性を考慮して、納得できる1社と契約します。費用の安さだけで解体会社を選ばないことがポイントです。
事前準備
次に、解体工事がはじまる前にライフラインの停止や解約をし、近隣への挨拶をしておきます。また、なるべく家財を処分しておきましょう。
アスベスト調査・除去工事
家を解体する前には、アスベスト調査をおこなうことが義務付けられています。現地での目視や分析調査によってアスベスト含有建材の使用が判明した場合は、工事の14日前までに都道府県知事へ届け出たうえでアスベスト除去工事をおこなう必要があります。また作業内容の掲示や、プラスチックシートによる解体現場の隔離をしなければなりません。
解体工事
解体工事をする前に足場や防音パネルを設置し、近隣へ迷惑がかからないように養生をします。初めから重機を使うのではなく、瓦やガラスなどは手作業で撤去します。その後重機を使って構造部分を解体し、廃材を搬出していきます。どうしてもガラスの破片や細かいガラが残ってしまうため、最後は手作業で清掃してきれいな状態にします。
整地工事
建物の解体が終わった「更地」の状態では、砂利などが残り、凸凹もある状態です。この状態から重機や転圧機などで地面を平らにすることを整地工事といいます。更地の状態のままでも問題ありませんが、土地の売却や活用を検討している場合は、整地工事の実施をおすすめします。土地をきれいにすることで、売却活動や建て替え工事を円滑に進めやすくなります。
家を解体する時の注意点

家を解体する場合、注意すべきことがあります。代表的な3つのポイントを紹介します。
更地にすると再建築不可になる可能性がある
更地にすると「再建築不可」になってしまわないか、注意が必要です。建築物の最低基準を定めた建築基準法の43条では、接道義務を果たしていない物件は、更地にすると、新しく建築物を建てられないと定められています。接道義務とは、建築物の敷地は原則として道路に2m以上接しなければならない決まりです。
そのため、もし接道義務を満たしていない場合に家を取り壊してしまったら、再度建築ができなくなります。建物を残しておくことで、リフォームや改修をして活用することも可能なので、解体をして再建築不可にならないか、事前に役所で確認しておくとよいでしょう。
更地にすると固定資産税が高くなる
更地にすると固定資産税が高くなります。住宅用地の特例措置により、住宅1戸につき200平方メートルまでの部分が、固定資産税は1/6(200平方メートル超の部分は1/3)、都市計画税は1/3(200平方メートル超の部分ま2/3)に軽減されます。住宅を解体することで特例措置が適用されず、税負担が増えるため注意が必要です。
なお1月1日(賦課期日)の所有者に対して課税されるため、解体する場合は賦課期日を考慮してスケジュールを立てるようにしましょう。
解体後は建物滅失登記をおこなう必要がある
建物を解体したら1カ月以内に建物の滅失登記をしなければなりません。怠った場合は10万円の過料を科せられます。自ら申請をすれば、費用は数千円程度で済みます。難しい場合は土地家屋調査士に相談しましょう。依頼先にもよりますが、5万円前後が手続き費用の相場です。
家の解体に関するよくある質問
家を解体するメリットは?
家を解体するメリットは、維持管理をする手間や費用がかからなくなることです。売却する場合は、一般的に売れやすくなります。また、空き家のまま放置しておくと不法侵入や放火の危険、老朽化した建物なら倒壊リスクがありますが、解体することで犯罪やトラブルを未然に防止できます。
家を解体するデメリットは?
家を解体するデメリットは、解体費用がかかることです。また、賦課期日のタイミングによっては、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、土地に対する固定資産税と都市計画税も高くなります。
接道義務を果たしていない物件の場合は、再建築できなくなってしまいます。
家を自分で解体してもいい?
家を自分で解体しても構いませんが、避けたほうがよいでしょう。建物の解体する際は、アスベストの調査が義務付けられています。また解体による騒音や土ほこりにより、近隣トラブルになる可能性も。したがって自分でおこなうのではなく、解体会社に依頼することをおすすめします。
まとめ
建物を解体することで、一般的には売却しやすくなります。しかし解体費用は高額であるため、デメリットも十分把握したうえで、解体するかを決定しましょう。また建物の状態や条件によっては、建物付きのまま売却するほうがよいこともあります。まずは不動産会社に査定を依頼し、解体すべきかの相談をしてみましょう。
不動産会社へ査定を依頼する場合は、一度の入力で複数社に依頼ができる「一括査定」が便利です。ぜひ活用してみてくださいね。
物件を探す







