空き家の解体費用に補助金が出る?制度やもらう条件を徹底解説!

対策の一つとして、解体費用の補助金制度が設けられました。制度の詳細は自治体によって異なりますが、基本的な考えは変わらないため、記事を読んでポイントを押さえておきましょう。
記事の目次
なぜ空き家の解体費用に補助金が出る?

総務省の「住宅・土地統計調査」によると、総住宅数に占める空き家の割合は13.6%(2018年)。少子高齢化が進み、空き家が年々増えているといいます。国も法律を制定するなどして、空き家対策が本格化していますが、そもそも空き家が多いとどのような問題があるのでしょうか。
空き家によって引き起こされる問題
誰も住んでいない家は劣化が早く進みます。放置された空き家が引き起こす問題は、大きく3つあります。
- 保安面で危険な状態になる
- 衛生面で有害な状態になる
- 景観を悪化させる
劣化が進むと、屋根・外壁の落下や家屋の倒壊などの恐れがあります。また、ネズミや野良猫などが繁殖したり、ゴミの不法投棄で衛生面が悪化したりする可能性があります。さらに、雑草が生い茂るなどして景観の悪化を招くことも。これらは、周辺の生活環境に大きな影響を与えるでしょう。他にも、近隣の不動産の資産価値を下げ、放火や不審者の出入りなど、地域の防犯性を低下させると指摘されています。
空き家対策特別措置法の制定
先述した空き家による問題を受け、2015年に「空き家対策特別措置法」が制定されました。これは、空き家が放置されることで引き起こる問題から、地域住民の生命、身体や財産の保護、生活環境の保全を図るものです。同時に、空き家の活用を促進するための基本方針も定められました。さらに、空き家のなかでも特に問題があるとみなされた場合には、「特定空き家」と認定されることも決められました。
空き家特別対策措置法は今年の6月に改正され、「特定空き家」に対しては、12月から所有者に代わって市区町村長が空き家の管理・処分されることが認められます。空き家を適切に管理・活用するための一つとして、空き家の解体費用の補助金制度が設けられたのです。
空き家解体によるメリット・デメリット

空き家が引き起こす問題を見てきましたが、解体すると具体的にどういったメリット・デメリットがあるのでしょうか。それぞれ詳しく見ていきましょう。
空き家を解体するメリット
空き家を解体するメリットは大きく3つあります。以下で一つずつ解説していきます。
トラブルの原因がなくなる
空き家を解体すれば、トラブルそのものがなくなります。国が空き家対策に力を入れている理由の一つとして、空き家が引き起こす問題がありました。空き家を放置していると、倒壊の危険性があります。もし倒壊して通行人にケガをさせてしまった場合には、損害賠償に問われる可能性もあります。また、倒壊だけでなく、放火されたり、犯罪者の住処となったりする恐れもあります。そういったトラブルの原因そのものをなくせることは、メリットでしょう。
土地を有効活用できる
空き家を解体すると、更地になった土地を有効活用できます。例えば、駐車場にしたり、アパートを建てたりなど、経営することもできるでしょう。また、売却する場合にも、空き家を解体したほうが売れやすく、地価も上がります。なぜなら、買主は解体費用がかかるところをなるべく避けたいと考えるためです。自分で使うか、売却するか、どちらにしても空き家を解体したほうがスムーズでしょう。
管理コストを削減できる
空き家を解体すると、管理コストを削減できます。誰も住んでいないからといって、お金がまったくかからないわけではありません。例えば、固定資産税や火災保険料、補修費用などがかかります。もし遠方に住んでいて、外部に依頼する場合にはその費用も必要となります。また、かかるのはお金だけではありません。自分が管理をする場合には、掃除をしたり、庭の手入れをしたりなどの手間もかかります。空き家を解体すると、そういった管理コストや手間が省けるでしょう。
空き家を解体するデメリット
空き家を解体するデメリットは大きく2つあります。以下で一つずつ解説していきます。
解体費用が発生する
空き家を解体するデメリットとして、解体費用が発生することが挙げられます。詳しくは後述しますが、解体費用は建物の構造や規模、立地などによって異なります。また、残置物がある場合には、処分費用も必要となります。空き家の解体を検討する際には、解体費用と管理コストを比較するようにしましょう。
固定資産税の特例措置が受けられなくなる
空き家を解体すると、固定資産税の特例措置が受けられなくなります。固定資産税の特例措置とは、小規模用宅地であれば固定資産税額が1/6、一般用住宅地であれば1/3まで減額されるというものです。空き家を解体すると、住宅用地でなく非住宅用地とみなされるため、特例が受けられなくなり固定資産税が上がります。そのため、固定資産税を含めた管理コストと解体費用を比較し、解体するかを検討しましょう。
空き家の解体費用の相場
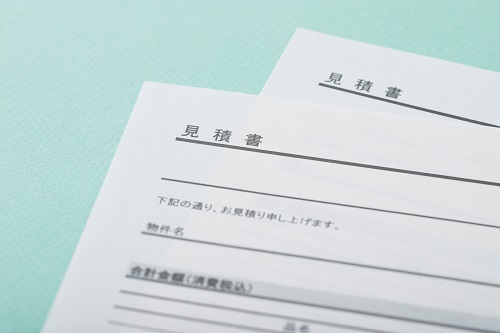
実際に空き家を解体するとなると、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。先述したように、建物の構造によっても相場は変わります。具体的には下記のとおりです。
| 構造 | 坪あたりの相場 |
|---|---|
| 木造 | 3〜5万円/坪 |
| 鉄骨造 | 5〜7万円/坪 |
| RC(鉄筋コンクリート)造 | 6〜8万円/坪 |
30〜50坪の解体費用の相場をまとめてみました。
| 30坪 | 40坪 | 50坪 | |
|---|---|---|---|
| 木造 | 90〜150万円 | 120〜200万円 | 150〜250万円 |
| 鉄骨造 | 150〜210万円 | 200〜280万円 | 250〜350万円 |
| RC(鉄筋コンクリート)造 | 180〜240万円 | 240〜320万円 | 300〜400万円 |
当然ですが、広いほど費用がかかります。また、道路が狭かったり、住宅が密集していたりすると、解体費用は高くなります。他にも、庭に木が植えてあったり、特殊な工事が必要になったりすると、別に費用がかかります。建物の状況や立地によっても変わるため、解体業者に見積もりを依頼しましょう。
空き家解体費用に関する補助金

先述したように、空き家の解体費用は、建物の構造や広さ、立地などによっても異なります。一番安い木造でも、30坪の場合は90〜150万円と、それなりに費用がかかります。本章では、どれくらい補助があるのか、補助金の制度を解説していきます。また、自治体によって名称は違うため、詳細は市区町村に問い合わせましょう。
老朽危険家屋解体撤去補助金
老朽危険家屋解体撤去補助金は、老朽化や倒壊の危険性が高い空き家を解体するための補助金です。もらえる金額は解体費用の20〜50%程度となっています。補助金をもらうためには、事前に申請し、自治体に空き家の状態を確認してもらう必要があります。
具体例として、長野県長野市の「長野市老朽危険空き家解体事業補助金」を見てみましょう。補助金額は所得金額によって異なっており、下記のとおりとなっています。
| 所得金額 | 補助金額 |
|---|---|
| 200万円以下 | 工事費用の60%以内
※120万円または国が定める標準的な費用から計算する額の少ない額が限度額
|
| 200万円超 | 工事費用の50%以内
※100万円または国が定める標準的な費用から計算する額の少ない額が限度額
|
あらかじめ予算が決められているため、申請すれば誰でも受けられるわけではありません。制度を活用したい場合には、自治体に事前に相談しておきましょう。
都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金
都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金は、都市の景観を守るために、周辺の環境に悪影響を及ぼす可能性のある空き家の解体費用を補助する制度です。あくまで都市の景観を守るため、工事後に景観形成基準を満たしている必要があります。先ほどの制度と同様、解体費用の20〜50%が補助されます。
例えば、福岡県福岡市の「都市景観形成建築物等保全補助金」を見てみましょう。
| 区分 | 補助対象 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 修理 | 都市景観形成建築物などの修理 | 50%以内 | 450万円 |
| 修景 | 上記以外の建築物などの修景 | 50%以内 | 300万円 |
| 設計費 など |
測量、調査および設計・監理に要する費用 | 50%以内 | 75万円 |
| その他市長が必要と認める経費 | 特にその建築物などの規模が大きく、著しく修景に要する費用が見込まれるもので、 敷地面積が300平方メートル以上、かつ、建物の階数 が4階以上の建築物などとする。 | 50%以内 | 200万円 |
歴史的な街並みを守るため、補助対象が細かく分けられており、限度額も大きくなっています。また、工事して終わりではなく、完成後の写真や報告書の提出も求められます。
建て替え建設費補助金
建て替え建設費補助金は、家を解体して一定の基準を満たす住宅を建築する際に、その費用の一部を補助する制度です。解体費用だけでなく、新しく建て替える住宅の建設費用の一部も補助される点は、大きなメリットでしょう。具体例として、大阪府大阪市の「大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度」を見てみましょう。建て替え前の住宅については、「昭和56年5月31日以前に建てられたもの」という要件しかありません。しかし、建て替え後の要件は、住宅の面積が50平方メートルであること、省エネ基準に適合していることなど、細かく定められています。
このように、制度の名称や内容などは、自治体によって大きく異なります。自分が住んでいる自治体の制度はどうなっているか、確認してみましょう。また、事前に相談が必要となる場合が多いため、詳細は各自治体に問い合わせましょう。
解体費用の補助金をもらうための条件

解体費用の補助金制度は、自治体によって異なりますが、共通している条件があります。ここでは、一般的にみられる条件を解説していきます。補助金がもらえる条件は、物件、申請者、工事の3つに区分されます。詳しくみていきましょう。
<物件の条件>
- 一定期間、空き家であること
- 対象の市町村・区域にあること
<申請者の条件>
- 空き家の所有者であること
- 市税の滞納がないこと
<工事の条件>
- 空き家の全部を解体すること
- 対象の市町村内の会社・事業者登録名簿に登録されている会社に依頼すること
期間は自治体によって異なりますが、空き家であることが条件となります。また、各自治体の制度であるため、対象となる空き家が自治体内にあることも求められます。申請者の条件としては、税金を滞納していないことが挙げられます。補助金は税金で賄われているため、滞納している場合は受給できません。工事会社は対象地域内にある、もしくは事業者登録名簿に登録されている会社である必要があります。
ここでは、あくまで基本的なものを取り上げているため、各自治体によっても条件が異なります。詳細は各自治体に問い合わせてみましょう。
空き家解体費用の補助金に関する注意点

空き家の解体費用の補助金に関して、気をつけなければならない点があります。それぞれ詳しくみていきましょう。
工事を着手する前に申請する
補助金をもらうためには、工事を着手する前に申請する必要があります。簡単に手続きの流れを確認しておきましょう。一般的に、どの自治体でも関係窓口に事前相談をしなければなりません。相談したあと、自治体の方が空き家の状態を確認するなどして、制度を適用するか判断します。制度が適用できると判断された時に、補助金の申請をおこない着工となります。着工後に申請はできないため、注意しましょう。
審査に時間がかかる
補助金の制度が適用されるか、審査に時間がかかることも覚えておきましょう。自治体によっては、いつまでに工事を完了させなければならないか、決まっているところもあります。例えば、先ほど例にも挙げた福岡県福岡市の場合は、2023年の12月に制度を適用するか確定し、2024年2月に補助金の交付額を決定するとしています。補助金を受給したい場合には、スケジュールを確認し、早めに手続きをしておきましょう。
自治体ごとに対象物件が異なる
空き家解体費用の補助金は、自治体ごとに対象物件が異なります。例えば、同じ老朽化した空き家を解体する補助金制度でも、先ほど例に挙げた長野県長野市と、兵庫県神戸市では次のようになっています。
| 長野県長野市 |
|---|
| ・市内に所在している ・1年以上使用されていない ・「戸建住宅」「1/2以上が住宅である併用住宅」「長屋建住宅」のいずれかに該当する
・事前調査において「老朽危険空き家」として市長が認めたものである
|
| 兵庫県神戸市 |
|
・1981(昭和56)年5月以前に着工された家屋
<空き家の場合> ・家屋に一部腐朽・破損があること
<居住している、または一部腐朽・破損のない空き家の場合> ・幅員2m未満の道路のみに接する土地の上に建つ家屋、または面積60平方メートル未満の土地の上に建つ家屋
|
自治体によって、要件が異なるのがわかります。自分が所有する空き家が対象となるか、よく確認しましょう。
工事完了後に補助金を受け取れる
解体費用の補助金を受け取れるのは、工事完了後であることも留意しておきましょう。補助金を受け取るためには、工事が完了したことを報告し、場合によっては自治体の検査を受ける必要があります。解体費用の補助金制度は、空き家の解体を目的としたものであるため、不正に利用されることのないよう、厳しくチェックされます。解体費用を自分で全額負担する必要があるため、資金計画を立てておきましょう。
まとめ
今回は、空き家の解体費用における補助金制度について解説しました。自治体によって、名称や内容、受給できる条件は異なり申請期間や工事期間なども決められている場合があります。自分が住んでいる自治体の制度はどうなっているか、よく確認しましょう。また、補助金を受ける時には気をつけなければならない点があります。受給できるのは工事が完了した後のため、事前に資金計画を立て、計画的に進めましょう。
物件を探す

執筆者
民辻伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ




