不動産は生前贈与した方が良い?贈与と相続のメリット・デメリットと注意点をわかりやすく解説

記事の目次
そもそも生前贈与とは?
一般的に生前贈与(せいぜんぞうよ)とは、相続対策として生前に自己の財産を特定の相手へ無償で譲渡することです。これは、「遺産の前渡し」ともいわれています。贈与は契約の一種ですので、自分の意思だけでは成立しません。贈与する側(贈与者)と受け取る側(受贈者)との意思の合致があることで成立します。
贈与の方法には、口頭による贈与と書面による贈与があります。口頭による贈与とは、いわゆる口約束のことです。一方、贈与契約書を作成することを書面による贈与といいます。口頭による贈与の場合、相手に財産を渡すまではいつでも撤回ができますが、書面による贈与の場合には撤回ができないという違いがあります。
生前贈与は贈与税の対象となり、贈与する財産の価額が大きいほど税率が高くなります。ただし、一定の条件を満たしていれば税負担を軽減できる特例もあります。そのため、節税対策として生前贈与が利用されることがあります。
不動産の生前贈与とは?
不動産の生前贈与とは、所有している不動産を特定の相手に無償で譲渡することです。不動産の贈与契約においては、引渡しが完了すれば贈与契約の履行が完了するため、不動産登記は必ずしも必要ではありません。しかし、第三者とのトラブルを防止するため、通常は贈与を原因とした所有権移転登記をします。
不動産の生前贈与がおこなわれるのは、以下のようなケースが考えられます。
<不動産の生前贈与がおこなわれるケース>
- 贈与税の特例を使って相続対策をしたい
- 相続人間の争いを未然に防ぎたい
- 老後の面倒を見てもらう代わりに子どもに自宅を譲りたい
- 先祖代々の田んぼや畑を跡継ぎに継いでほしい
- 生前贈与により共有関係を解消して将来的な売却に備えたい
不動産の生前贈与にかかる税金には、贈与税以外に不動産取得税と登録免許税があります。また、不動産を取得した受贈者は、財産を取得した日以降の固定資産税を納めることになります。
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、贈与を受けたときに生じる税金の支払いを相続時まで先延ばしできる制度です。先延ばしにした税金は、相続時にまとめて精算します。この相続時精算課税制度を使えば、生前贈与を受ける際に2,500万円分までは贈与税を支払う必要がありません。なお、2,500万円を超えた部分については一律20%の贈与税が課税されます。
相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた後、贈与者が亡くなって相続が発生したとしましょう。本制度を利用して贈与を受けた財産は、相続財産に加算されて相続税の計算対象となります。そして計算の結果、相続税が発生する場合はすでに支払った贈与税を控除して、残りの金額を納めることになります。もし、すでに支払った贈与税が相続税の額より多額であれば、還付を受けることができます。
相続時精算課税制度を利用するためには、贈与者が60歳以上の父母または祖父母、受贈者が18歳以上の子や孫などであることが条件となります。相続時精算課税制度は暦年課税制度との選択制となっており、相続時精算課税制度を選択すると申告が必要となり、その後に撤回することはできません。一度選択すると暦年課税には戻れないので、どちらを選ぶかは慎重な判断が必要です。ただし、令和5年度の税制改正で、相続時精算課税制度を利用した贈与の場合も基礎控除として110万円が控除されることになりました。
不動産を生前贈与するメリット

不動産の生前贈与には注意すべき点が多々あります。不動産の生前贈与をする前にメリット・デメリットをしっかり理解しておかないと、「こんなはずじゃなかった」と後悔することにもなりかねません。まずは不動産の生前贈与について、メリットから順番に見ていきましょう。
贈与したい相手に好きなタイミングで渡せる
財産をあげたい相手がいる場合、意思能力がはっきりしている元気なうちであれば、好きなタイミングで贈与をすることができます。また、相続人はもちろん、相続人ではない孫やお世話になった施設など、自分で選んだ相手に贈与をすることが可能です。
もし生前贈与もせず遺言書も残さず亡くなってしまうと、相続財産は法定相続人の共有になるか、法定相続人の協議によって取得者を決めることになります。贈与したい相手がいる場合は、できるだけ早めに生前贈与を検討しましょう。
短期間で財産を渡せる
一般的な不動産の贈与の場合、当事者の合意のみによって成立するため、短時間で物件を引渡してもらうことが可能です。もし生前贈与をせずに亡くなってしまうと、相続手続きが必要になります。相続手続きは相続人が多数になったり、相続関係が複雑だったりする場合もあり、時間がかかる可能性があるでしょう。また、遺産分割協議がスムーズに進まないことも考えられます。
自筆証書遺言を書いていたとしても、自宅に保管していた場合には家庭裁判所の検認が必要です。書類の準備から手続きまで、場合によっては相当な時間がかかります。煩わしい相続手続きを経ることなく、スムーズに財産を引渡すことができるというのも生前贈与のメリットです。
相続税が軽減できる
不動産を生前贈与することで、相続税の負担を軽減できる可能性があります。不動産を贈与した場合の贈与税の計算は、贈与を受けた時点での時価でおこなわれます。相続税の計算も、贈与税と税率は違いますが相続時の時価に基づいておこなわれます。
計算のベースとなる不動産の時価が高ければ高いほど、その分だけ税額も高くなります。そのため、将来大幅な値上がりが確実な不動産の場合、時価が低いうちに贈与をしておくことで節税対策につながると考えられるでしょう。
認知症対策になる
認知症になって意思能力がないと診断されてしまうと、自由に財産を処分できなくなります。認知症の方が不動産を処分するためには、成年後見人を申立てて裁判所の許可を得なければなりません。しかし、裁判所は単純に被後見人の財産を減らすような行為は認めない傾向にあります。将来的に認知症になるかはわからなくても、意思能力がはっきりしているうちに不動産の生前贈与をおこなうことが、認知症対策のひとつになります。
不動産を生前贈与するデメリット
不動産の生前贈与においては、デメリットもあります。特に税金に関して注意すべき点が多いので、デメリットを理解し納得したうえで、生前贈与するかを判断するようにしましょう。以下に、不動産の生前贈与について気を付けておきたいデメリットをまとめました。
贈与税がかかる場合、相続税よりも高額になる

まず贈与をした場合の贈与税ですが、暦年贈与の場合、110万円の基礎控除を超えると最低でも10%の贈与税がかかります。
一方、相続税には「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」の基礎控除があります。例えば相続人が配偶者と子ども二人の場合、4,800万円まで基礎控除を受けることが可能です。相続財産が基礎控除内で収まる場合、相続税の支払いはありません。相続財産の基礎控除を考慮すると、生前贈与の方が税負担は大きくなる可能性があります。
不動産取得税がかかる
不動産を贈与した場合、贈与税のほかに不動産取得税がかかります。不動産取得税とは贈与を受けた方が支払う税金で、課税されるのは1回のみです。税額は市区町村の固定資産評価額に対して、以下の税率をかけた額となります。なお、土地は特例により評価額を2分の1にして計算します。
| 土地 | 家屋 | |
|---|---|---|
| 住宅 | 住宅以外 | |
| 3% | 3% | 4% |
※条件により軽減の特例有り
例えば、1,000万円の土地の贈与を受けた場合、納める税額は15万円(1,000万×2分の1×3%)となります。一方、相続で不動産を取得した場合には、不動産取得税はかかりません。
小規模宅地等の特例が適用されない
相続が発生し、相続税の計算に必要な不動産評価の算定をする際、土地の評価を低くできる小規模宅地等の特例という制度が設けられています。この制度は相続税が高額になった場合に、自宅の敷地などを売却せざるをえなくなることを回避するための制度です。一定の条件を満たせば、居住用宅地の場合は評価額が最大80%減額されます。ただし、この小規模宅地等の特例は、相続税の計算時に使われる特例です。そのため、贈与時には適用されません。
所有権移転登記の登録免許税が高額になる
不動産を生前贈与で取得する場合でも、相続で取得する場合でも、不動産の名義変更のための所有権移転登記には登録免許税がかかります。登録免許税の税率は贈与と相続で異なっており、贈与税は評価額に対して2%、相続税は0.4%の登録免許税がかかります。これは、土地・家屋どちらも同じ税率です。
例えば、1,000万円の不動産を贈与した場合には登録免許税は20万円になりますが、相続の場合は4万円です。
<例>
1,000万円の不動産の所有権移転をする場合の登録免許税
| 不動産の評価額 | 贈与税 | 相続税 |
|---|---|---|
| 1,000万円 | 20万円 | 4万円 |
贈与登記の場合、相続登記と比較すると5倍の金額です。残念ながら軽減の特例もありません。生前贈与のデメリットとして、登録免許税が高額になるということを覚えておきましょう。
不動産は生前贈与と相続どっちがお得?
それでは、なるべく余計な税金を払わずに不動産を配偶者や子どもに残すためには、生前贈与と相続、実際どちらがお得なのでしょうか。その答えは、個々の事情によって異なります。相続財産全体の価額、内容、適用できる特例の有無など人それぞれ条件が違ううえ、生前贈与をする本人の希望もさまざまです。結論は一概には言えませんが、デメリットを理解したうえで、生前贈与が向いているか相続が向いているかを考えるべきでしょう。
生前贈与が向いているケース
必ずしも節税対策になるとは限りませんが、生前贈与が向いているのは、次のようなケースが考えられます。
将来価値が確実に上がる土地
贈与税、相続税はどちらも取得したときの時価で計算します。そのため、不動産の価値が将来確実に値上がりする場合には、生前贈与が向いていると考えられます。
例えば、今は3,000万円の土地が相続時には5,000万円になっていた場合、課税価格が2,000万円も違うことになります。早めに贈与すれば、値上がりする前の低い価格をもとに税金を納めることができます。そのため、値上がり後に相続が発生して高額な相続税を払うよりも、税負担が軽くなる可能性があります。
賃貸マンションなどの収益物件
自分が亡くなったときに子どものためにできるだけ残してあげたいという気持ちから、賃貸マンション・アパートなどの家賃収入を早い時期から蓄えて財産を築いていると、相続税が多額になる可能性があります。このような場合には生前に収益物件を贈与し、家賃収入を子どもが直接受け取れるようにすることも相続対策の一つです。収益物件の贈与を受けた時には贈与税がかかりますが、毎月入る家賃収入には贈与税は課税されません。
また、生前贈与をすると、固定資産税の支払いは新たに不動産を取得した受贈者が負担します。そのため、贈与した側は固定資産税の負担から逃れることができます。
婚姻期間が20年以上の夫婦
婚姻期間20年以上の夫婦の一方が、もう一方に居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための金銭を贈与する場合、贈与税の課税価格から2,000万円を限度に控除できる贈与税の配偶者控除という特例があります。これは、「おしどり贈与」とも呼ばれているものです。
この特例を使うことで、贈与税の支払を軽減することができます。また、贈与税の配偶者控除は、暦年課税の110万円の控除を併用することが可能です。
認知症対策としての生前贈与
認知症と診断されてしまうと意思能力がないと見なされ、所有する不動産を自分の意思で自由に処分することができなくなってしまいます。また、認知症と診断されたあとに遺言書を書いたとしても、有効性を認められなくなってしまうので注意しましょう。このように、認知症になってしまうと行動を制限されますので、贈与をしたい相手がいる場合は、元気なうちに生前贈与をすることが認知症対策として有効です。
土地の共有者となっている場合
不動産の共有者となっていて、その不動産を将来的に売却する場合、共有者全員が売主になる必要があります。もし共有者が亡くなった場合、相続手続きが終わるまで不動産の処分ができません。そのため、すぐには売却できなくなってしまいます。また、遺産分割協議が難航すれば、売却がさらに難しくなります。
共有者が認知症になってしまった場合も、同様に不動産の売却ができなくなってしまいます。このような状況になりそうな共有者がいる場合には、事前に生前贈与をして共有関係を解消しておくことで、スムーズな不動産の処分ができると考えられます。
相続が向いているケース
反対に、相続が向いているのは次のようなケースが考えられます。
相続税が発生しない財産
生前贈与は相続税対策としておこなわれる場合が多いので、そもそも相続税が発生するような財産がなければ、相続税対策としての生前贈与は不要です。ただし、相続税が発生しないケースでも、将来自分の面倒を見てもらう特定の相続人にあらかじめ財産を贈与したいなどの生前贈与のニーズがあります。この場合、相続時精算課税制度を使うことで贈与税の負担を軽減することができます。
また、相続時精算課税制度を使って贈与した財産を含む相続財産が、基礎控除内で収まれば、相続税がかからないので当事者の負担なく生前贈与をすることが可能です。
子どもや配偶者がいない人
贈与税の配偶者控除や教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に対する非課税制度など、贈与税は配偶者もしくは子・孫に対する贈与に対して税額が軽減される仕組みとなっています。そのため、子どもや配偶者がいない方は特例を使っての生前贈与はできず、メリットを享受できません。
被相続人に子どもや配偶者がなく、両親も他界している場合、相続人は兄弟姉妹もしくは甥姪(せいてつ)となります。もし、疎遠な兄弟姉妹に相続財産を渡すより、自分の面倒を見てくれる近しい人に財産を残したいという場合には、生前贈与の活用を検討してもよいでしょう。
認知症を発症している人
前述のとおり、認知症を発症してしまい意思能力がないと診断されると、自分自身で財産の処分ができなくなってしまいます。たとえ子どもが「認知症になる前から親は自分に自宅を贈与すると言っていた」と主張しても、一旦親が認知症と診断されてしまえば子どもに自宅を贈与することはできません。この場合、相続が向いているというより、相続を待つしかないといわざるをえません。ただし、本人が望んだとおりの遺産分割ができるか否かはまた別となります。
もう長くないことが確実な人
相続開始3年前までに贈与した財産は、相続財産に含めるというルールがあります。ただし、2023年(令和5年度)の税制改正で、相続財産に加算される期間が7年前までに伸長されました。
例えば、生前贈与をして贈与税を支払った後、5年後に亡くなったとしましょう。この場合、生前贈与をした分の財産が相続財産に加算されてしまいます。そして、すでに支払った贈与税は控除されますが、控除しきれなかった税額については還付されません。
生前贈与をしても相続財産に加算されてしまう可能性がある場合は、相続を前提に遺言書を遺すことも選択肢の一つです。
不動産の生前贈与と相続、どのケースにおいてもリスクがあるため、どちらがいいか自分で判断することはとても難しいものです。個々の事情によって選択肢が異なりますので、具体的な検討については税理士などの専門家に相談するようにしましょう。
不動産を生前贈与する手続き・流れ
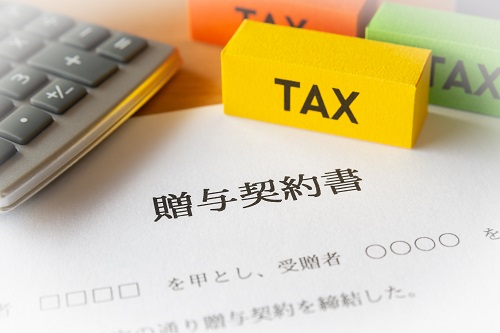
ここからは、不動産を生前贈与するための手続きおよび流れについてご説明します。まずは実際に不動産を生前贈与するイメージを掴んでみましょう。流れとしては、大きくわけて3つあります。
- STEP 1贈与契約書の作成
- STEP 2名義変更登記
- STEP 3贈与税の申告
贈与契約書の作成
贈与契約は口頭でも成立しますが、取引の安全のため贈与契約書を作成します。贈与契約書は、贈与による所有権移転登記において添付書類としても提出します。贈与契約書に記載する内容は次の項目です。
- 贈与者および受贈者の住所・氏名・押印
- 贈与者が贈与し、受贈者が受諾した旨
- 引渡しの日
- 所有権移転登記手続きの負担
- 公租公課等の負担
- 物件の表示
贈与契約書は2部作成し、それぞれ署名・押印・割り印をし、200円の印紙を貼付します。受贈者は認印でも構いませんが、贈与者の押印は実印である必要があります。贈与契約書を登記書類に添付する場合には、1部のみ提出すれば問題ありません。
名義変更登記(所有権移転登記)
贈与契約書が整ったら、名義変更のための所有権移転登記をします。法務局に提出する書類は、贈与契約書の他、以下の書類が必要です。
- 登記申請書
- 物件の権利証もしくは登記識別情報
- 贈与者の印鑑証明書
- 受贈者の住民票
- 評価証明書
- 委任状(代理人が申請する場合)
登記申請する前に、必ず全部事項証明書を取得して現在の権利関係を確認しましょう。もし、贈与者が登記簿上の住所から転居しているなど登記簿に記載の住所と相違がある場合には、所有権移転登記の前に住所変更登記をする必要があります。
登記申請時には登録免許税を支払います。すでにご説明したとおり、登録免許税の税率は土地、建物どちらも固定資産評価額の0.2%です。
贈与税の申告
贈与税の申告は、贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までの間におこないます。相続時精算課税制度を選択する場合は、申告期間内に選択届出書を提出して申告します。
生前贈与の際にかかる税金・計算方法

不動産を生前贈与するうえで必ず把握しておきたいのが、贈与時にかかる税金です。生前贈与の際にかかる税金は不動産取得税、登録免許税、贈与税の3つです。それぞれの税金の内容と計算方法を見ていきましょう。
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 贈与税
不動産取得税
不動産取得税については記事の前半でも触れましたが、不動産を取得した際に1回限り課される税金です。不動産の贈与の場合は、受贈者が不動産取得税を支払います。不動産取得税の本則の税率は以下のとおりです。
| 土地 | 家屋 | |
|---|---|---|
| 住宅 | 住宅以外 | |
| 3% | 3% | 4% |
不動産取得税の計算は、固定資産税評価額に法定の税率をかける方法で算出します。土地については特例があり、宅地の場合、評価額を2分の1にして計算します。居住用不動産を贈与によって取得した場合、一定の条件を満たせばさらに軽減を受けられる可能性があります。
不動産取得税の軽減手続を受けるためには、基本的に自分で申告が必要です。ただし、自治体によっては申告しなくても軽減の特例を適用してくれる場合もあります。生前贈与を検討している場合は、お住まいの自治体でどう対応しているのか、事前に都道府県税事務所に確認しておくとよいでしょう。
なお、不動産取得税は不動産の取得が有償か無償かを問わず課税されますが、相続で取得した場合には課税されません。
登録免許税
登録免許税は、登記申請の時点で支払いが必要になる税金です。不動産を取得した場合、登記をしなければ第三者に権利を主張できません。そのため、不動産の贈与を受けた場合には、不動産の名義を変更するための登記を申請することになります。
登録免許税の算出に必要なのが、固定資産税評価証明書です。役所の資産税課など、資産税を扱う部署で発行してもらえます。また、毎年4月に届く固定資産税納付通知書からも評価額を確認することが可能です。
不動産の贈与による所有権移転登記の登録免許税は、土地と家屋のどちらも0.2%です。例えば、土地と建物合わせて固定資産評価額が1,000万円だった場合、支払う登録免許税は20万円になります。
登記申請を司法書士に依頼する場合には、登録免許税の計算、納付も含めすべて任せることができます。不動産の生前贈与をしたいけれど何から手を付けてよいかわからない場合は、司法書士に相談するとスムーズに手続きが進められるでしょう。
贈与税
110万円以上の贈与を受けた場合、贈与税の申告が必要です。贈与税の申告は贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までの間におこないます。親から18歳以上の子、孫への生前贈与は特例贈与財産となり、一般の税率より低い特例税率が適用されます。例えば親から子へ1,000万円を贈与した場合、贈与税は177万円となります。
<例:1,000万円の特例贈与財産の贈与税>
基礎控除後の課税価格 1,000万-110万=890万円
贈与税額 890万円×30%-90万円=177万円
<贈与税の税率>
| 基礎控除後の 課税価格 |
一般贈与財産 | 特例贈与財産 (特例税率) |
||
|---|---|---|---|---|
| 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
| 200万円以下 | 10% | – | 10% | – |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 | ||
| 600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 | ||
贈与税の計算や申告方法が難しいという場合には、税理士に相談してみましょう。また、生前贈与をおこなう前に贈与税の納付額について、事前に税理士に相談してみることもおすすめです。
生前贈与をする際の注意点
これまでの内容をもとに、生前贈与をする際の注意点をまとめました。不動産の生前贈与は、必ずしもメリットばかりとはいえません。注意点をしっかりと理解して、生前贈与の検討をするようにしましょう。
生前贈与は、贈与者が元気なうちに
これまでお伝えしてきたとおり、認知症になって意思能力がないと診断されてしまうと、贈与を含め契約行為自体ができなくなってしまいます。また、病気や加齢で贈与契約書にサインができなくなってしまえば、有効性が問題となり後々トラブルが生じかねません。そのため、生前贈与は贈与者が元気なうちにするようにしましょう。
相続開始前3年以内の贈与に注意
相続が発生した時、相続開始前3年以内におこなわれた生前贈与は相続財産に加算されるという制度があります。2024年1月1日からは、生前贈与加算の対象が相続開始前7年以内の贈与までと税制改正されました。生前贈与して間もなく亡くなった場合、相続対策として生前贈与したつもりでも、相続財産に加算されてしまいうことになりますので注意が必要です。
分割贈与にはリスクがある
暦年贈与の場合、毎年110万までは基礎控除を受けることができます。そのため、毎年110万円ずつ贈与すれば、贈与税はかからないのではないかと思われるかもしれません。しかし、まとまった額をあえて毎年110万円ずつに分けて贈与した場合、その合計額に贈与税がかかる可能性があります。
また、子ども名義の口座を作って毎年基礎控除内の金額を贈与するのも危険です。子どもが知らない間に子どもの口座に入金を続けていた場合、名義預金と見なされて贈与税がかかってしまう恐れがあります。
登録免許税の税率に注意
不動産の生前贈与をする場合、登記申請をするために登録免許税を支払います。繰り返しになってしまいますが、贈与登記の税率は土地・建物両方とも評価額に対して2%です。相続登記の税率は0.4%なので、比較すると税率が5倍も違います。これは、マイホームを購入する際の登録免許税よりも高い税率です。登録免許税は登記する場合は必ずかかってきますし、後払いや分割払いができないので注意しましょう。
必ず贈与契約書を作成する
贈与は口頭でも成立しますが、口頭での贈与の場合、引渡しをしていない部分についてはいつでも撤回ができます。つまり、口約束で贈与を受けたとしても、財産を必ずもらえるとは限らないのです。言った・言わないのトラブルを避けるためには、たとえ親子間であっても贈与契約書を作成することをおすすめします。
生前贈与された不動産でも控除を受けることができる?

居住用の不動産を売却して譲渡益が発生した場合、条件を満たせば3,000万円が控除される特例があります。贈与で取得した不動産を譲渡した場合についても、この居住用財産の3,000万円控除の特例が受けることが可能です。ただし、細かい条件がありその全部を満たす必要があります。主な条件は次のとおりです。
<居住用財産の3,000万円控除の主な条件>
- 自らが住んでいた家屋を売却するか、家屋とともにその敷地や借地権を売却すること
- すでに転居している場合は、住まなくなった日から3年目の年末までの売却であること
- 家屋を取り壊した場合には、次の2つの要件すべてに当てはまること
ア)敷地の譲渡契約を家屋の取壊しから1年以内に締結し、かつ住まなくなった日から3年目の年末までに売却することイ)家屋の取壊しから売却までの期間、敷地を利用していないこと
- 売却した年の前年及び前々年に居住用財産の3,000万円控除もしくはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰り越し控除の特例の適用を受けていないこと
- 売却した年、その前年、および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと
- 売手と買手が親子や夫婦など特別な関係ではないこと
なお、居住用財産の3,000万円控除を受けるためには、譲渡益が3,000万円未満で譲渡所得税が発生しない場合でも確定申告をする必要があります。
この記事のまとめ
不動産を生前贈与するかどうかは、税金対策以外の角度から検討することも大切です。不動産を生前贈与する理由は、税金対策だけではないからです。生前贈与をするということは、生きている間に自分の思いを形にすることでもあります。
最後に、生前贈与を検討するにあたって意識しておきたい内容をまとめました。
不動産は生前贈与と相続どっちがお得?
不動産の生前贈与と相続、どちらがお得かはそれぞれの事情によって異なります。生前贈与と相続について、双方のメリットとデメリットを理解して検討するようにしましょう。
不動産の生前贈与が向いているケースは?
不動産の生前贈与が向いているのは、相続財産が基礎控除内で収まるケース、将来不動産の価格が大きく値上がりする可能性が高いケースなどです。また、特例により贈与税の軽減が受けられる場合にも、不動産の生前贈与が向いているといえます。
生前贈与する際の注意点は?
2024年1月1日から、生前贈与加算の対象が相続開始前7年以内の贈与までと税制改正されました。生前贈与して間もなく亡くなった場合、相続対策として生前贈与したつもりでも、相続財産に加算されてしまいうことになりますので注意が必要です。
いかがでしたか?相続対策のために不動産の生前贈与をしようと思っていても、実は生前贈与をせずに相続財産として相続時に相続した方がよい場合もあるかもしれません。特定の相続人に不動産を贈与させたい場合には、遺言書に遺すことも手段の一つです。また、認知症対策としては家族信託することも考えられます。
相続対策にはさまざまな選択肢があります。不動産の生前贈与に悩んだら一つの方法にこだわらず、広い視点で考えることを心がけてみてください。どうしても困ったときは、専門家に相談しましょう。
物件を探す




