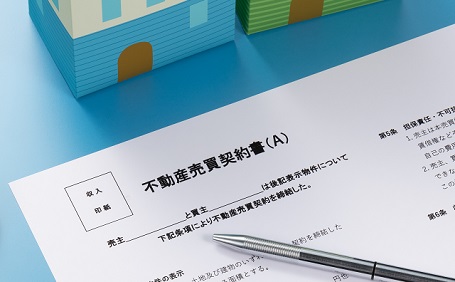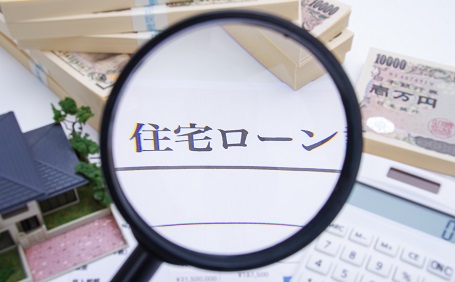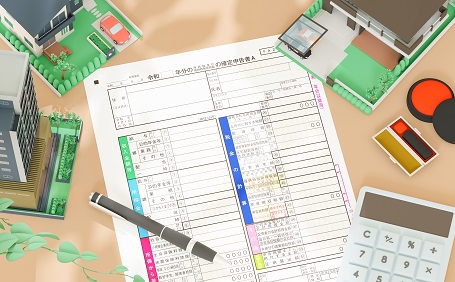【早見表付き】不動産売却の仲介手数料はいくら?計算方法や支払うタイミングを解説!

仲介手数料は、売却時にかかる諸費用のなかでも大きな割合を占めます。そのため、「仲介手数料はどれくらいかかるの?」「費用を抑えることはできるのか?」など、さまざまな疑問や悩みを持たれる方も少なくありません。
この記事では、売却時の仲介手数料を網羅的に解説します。正しい計算方法や準備するタイミングのほか、値引き交渉の方法・注意点を理解したうえで販売活動を進めましょう。
ぜひ最後までご一読ください。
記事の目次
不動産売却の仲介手数料とは?

土地や建物を売却する時に、不動産会社へ支払う仲介手数料はなぜ必要なのでしょうか。その意味や一般的に含まれるものを解説します。
不動産会社の売却活動に対する成功報酬
仲介手数料は、売却を依頼した不動産会社に、売買契約が成立した際に支払う成功報酬です。
不動産会社は、物件調査のうえ価格査定をおこない、売主と売り出し価格を決めます。その後、レインズや不動産ポータルサイトなどで、広く買主を募集し、契約条件の調整や交渉をおこないます。
これらの業務を通じて売買契約が成立した時に支払う報酬が、仲介手数料です。
各種手続きのサポート費用も含む
仲介手数料は、売買契約成立に対する報酬ですが、不動産取引は契約が成立して終わりではありません。
売買契約の締結から決済・引渡しまでには一定の期間を要し、その間の司法書士の手配や決済書類の作成などのサポート費用も仲介手数料に含まれます。
また、なかには仲介手数料の範囲内で、ホームステージングやハウスクリーニングがおこなわれることもあります。こうしたサービスや利用条件を比較して選ぶとよいでしょう。
なお、仲介手数料には、法律上上限が定められており、原則としてその範囲を超えて請求できません。(宅地建物取引業法第46条)
ただし、売却時の状況や依頼内容によって、遠方の物件を扱う際の交通費や宿泊費、特別な広告費などが発生する場合があります。
また、2024年7月の法改正で、空き家問題の解消を目的として、仲介業務以外のコンサルティング業務に対する報酬が認められました。
例えば、土地の境界確定やリフォーム提案、相続手続きのサポートなどです。これらの業務は別契約として報酬を受け取ることが可能です。
出典:国土交通省「「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」改正」
不動産売却の仲介手数料を計算する方法

不動産売却の仲介手数料の計算方法を解説します。
仲介手数料には上限がある
| 売却価格 | 仲介手数料の上限 |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 売却価格の5%+消費税 |
| 200万円を超えて400万円以下の部分 | 売却価格の4%+消費税 |
| 400万円を超える部分 | 売却価格の3%+消費税 |
前章でもお伝えしましたが、上表のとおり不動産会社が受け取れる仲介手数料は、売却価格帯に応じて上限金額が定められているため、それを超えて請求できません(宅地建物取引業法46条)。
出典:e-GOV 法令検索「宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)」
仲介手数料の計算方法(速算式)
仲介手数料は売却価格帯に応じて上限額が設定されており、複数の計算式があるためやや複雑に感じるかもしれません。
そこで、契約金額に応じた速算式があります。
| 契約金額(税抜) | 速算式 |
|---|---|
| 400万円超 | 契約金額×3%+6万円+税 |
| 200万円超~400万円以下 | 契約金額×4%+2万円+税 |
| 200万円以下 | 契約金額×5%+税 |
例えば、売買価格が4,000万円の場合、以下のようになります。
4,000万円×3%+6万円=126万円(税別)
消費税(10%)がかかるため138万6,000円(税込)となります。
800万円以下の不動産売買仲介手数料は30万円に引き上げ
2024年(令和6年)6月の改正により、物件価格が800万円以下の場合、仲介手数料の上限が30万円(税抜)に引き上げられました。
この改正には、地方を中心に増え続ける低価格の空き家流通を促進し、不動産会社が価格の低い取引にも積極的に取り組みやすくする目的があります。
その前の2017年改正では、400万円以下の場合、18万円(税抜)を上限とされていましたが、今回の改正で、対象となる物件と上限額が拡大しました。ただし、不動産会社は、事前に報酬額を依頼者に説明し、合意を得る必要があります。
出典:国土交通省「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」
仲介手数料の早見表

下表は、売買代金に応じた仲介手数料(上限)をまとめたものです。
| 売買金額 | 仲介手数料(税込) |
|---|---|
| 800万円以下 ※特例適用時 | 33万円 |
| 1,000万円 | 39.6万円 |
| 2,000万円 | 72.6万円 |
| 3,000万円 | 105.6万円 |
| 4,000万円 | 138.6万円 |
| 5,000万円 | 171.6万円 |
| 6,000万円 | 204.6万円 |
| 7,000万円 | 237.6万円 |
| 8,000万円 | 270.6万円 |
| 9,000万円 | 303.6万円 |
| 1億円 | 336.6万円 |
売却時の費用によって最終的に受け取れる金額は変わります。仲介手数料もしっかりと資金計画に入れておきましょう。
不動産売却の仲介手数料を支払うタイミング

不動産売却の仲介手数料は、売買契約時に半金、残りを決済・引渡し時に支払うのが一般的です。
これは、売買契約の成立後も、司法書士の手配や引渡し準備、清算書の作成など、不動産会社による業務が発生するためです。ただし、仲介手数料は、売買契約成立に対する報酬のため、契約時に全額を請求されても違法ではありません。
支払い時期の取り決めは不動産会社によって異なる場合があります。売却を依頼する際の媒介契約書で仲介手数料を準備するタイミングと金額をしっかりと確認しましょう。
不動産売却の仲介手数料を値引き交渉する際の注意点

上限が定められている仲介手数料ですが、不動産会社によって値引き交渉が可能な場合もあります。
ただし、安易な交渉は、販売活動の質やスピードに影響するおそれがあります。ここでは、仲介手数料を値引き交渉する際のリスクや交渉を控えたほうがよいケースを解説します。
値引き交渉が売却活用に与えるリスク
仲介手数料の値引き交渉をした時の売却活動への影響も理解しておくべきでしょう。
不動産会社の担当者は複数の物件を同時に担当しています。そのなかで、手数料が低い物件は、販売活動の優先順位が下がったり、広告費を抑えられたりするおそれがあります。
また、手数料が低い分できるだけ早く成約させたいと考え、買主からの値下げ交渉に応じるよう勧められる可能性が高まるかもしれません。
値引き交渉しないほうがよいケース
次のようなケースでは、仲介手数料の値引き交渉をしないほうがよいでしょう。
- 再建築不可や旧耐震基準のマンション
- 雨漏れなどの欠陥がある物件や事故物件
- 売り出し価格が低い物件不動産
- 相場より高値で売却したい物件
これらは、売却の難易度が高く、成約までに手間と時間がかかります。そのうえ手数料まで下がると、担当者のモチベーションが下がり、販売活動に影響しかねません。
また、複数の不動産会社に同時に依頼できる一般媒介契約の場合、他社が成約すれば報酬が得られません。
そのため、他の専任媒介契約、あるいは専属専任媒介契約と比べて、値引き交渉は難しいでしょう。
不動産の仲介手数料以外にかかる費用

ここでは不動産を売却した時に、仲介手数料以外にかかる費用を解説します。
印紙税
印紙税は、売買契約書などの課税文書を作成する際に課される税金です。
契約金額ごとにかかる税額は次のとおりです(軽減税率は2027年3月31日まで適用)。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 50万円超え100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超え500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超え1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超え5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超え1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
なお、2022年5月の宅地建物取引業法の改正により、電子契約で売買契約書を作成した場合、印紙税は必要ありません。
譲渡所得税
不動産を売却して譲渡所得(利益)が出た場合、譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税の計算式は、次のとおりです。
・譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率
譲渡所得は、売却金額から不動産を取得するためにかかった費用(取得費)や売却にかかった費用(譲渡費用)を控除して計算します。
・譲渡所得 = 売却収入 -(取得費+譲渡費用)
また、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除などの特例を活用することで、非課税となるケースも少なくありません。
出典:国税庁「No.1440譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
国税庁「No.3302マイホームを売ったときの特例」
抵当権抹消登録免許税
住宅ローンが残っている不動産を売却する場合、金融機関が設定した抵当権を抹消するための登録免許税が必要です。
登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。土地と建物を1度で申請する場合、2,000円となります。
司法書士手数料
抵当権抹消登記の手続きを司法書士に依頼する場合、1万~3万円程度の手数料が必要です。
住所変更登記や不動産の所有者がすでに亡くなっている場合は費用が増えます。なお、抵当権抹消登記は、自分でおこなえば登録免許税や書類の取得費以外にはかかりません。
ただし、法務局へ申請する際の登記申請書の作成から必要書類(登記原因情報や登記済証、抵当権抹消の委任状など)の準備を、自分でおこなう必要があります。
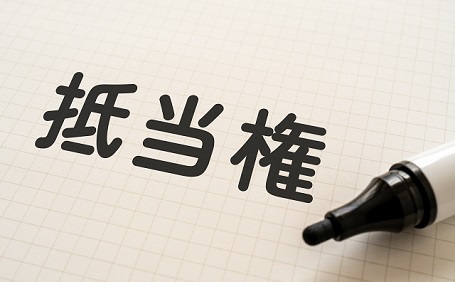
- 抵当権抹消の手続きを自分でやるには?手続きの流れや必要書類を解説
- 住宅ローンの完済時には、抵当権抹消手続きをおこなう必要があります。住宅ローンを完済しても、不動産に設定された抵当権の登記は
続きを読む

住宅ローン一括返済のための費用
住宅ローンの残債がある物件を売却する場合、金融機関に対して一括返済のための手数料がかかります。
手数料の目安は、金融機関によって異なり、インターネットで手続きする場合は1万~3万円、窓口で手続きする場合は4万~5万円程度です。
リフォーム・ハウスクリーニング費用
売却する際にリフォームやハウスクリーニングをする場合、その費用がかかります。
見栄えを良くしたり、不具合箇所を修繕したりすることで、早期売却や高値での売却につながるケースもありますが、費用対効果を慎重に判断することが大切です。
建物解体費用
土地上の建物を解体し、更地にして売却する場合、建物の解体費用がかかります。
構造別の解体費用の目安は以下のとおりです。
| 構造 | 解体費用 (坪単価) |
30坪の解体費用 |
|---|---|---|
| 木造 | 3万円~5万円 | 90万円~150万円 |
| 鉄骨造 | 3万円~7万円 | 90万円~210万円 |
| 鉄筋コンクリート造 | 4万円~8万円 | 120万円~240万円 |
解体費用は、作業環境(敷地の広さや前面道路幅など)や残置物の量、築年数によって変動します。
引越し費用
新居への引越し費用も、しっかり見積もっておくことが必要です。引越し料金は、移動距離や荷物量のほか、オプション作業(エアコンの取り外しや不用品の処理など)によって変わります。
なるべく費用を抑えるには、複数社での相見積もりや、繁忙期(3月~4月)を避けることが有効です。
引越しするまでの仮住まい費用
住み替えで今住んでいる家を先に売却しなければならない場合、一時的な仮住まいの費用がかかることがあります。
仮住まいが必要な場合、現在の自宅から仮住まい、仮住まいから新居へと、引越し費用が2度かかる点に注意が必要です。
不動産売却の仲介手数料でよくある質問
最後に、仲介手数料に関してよく寄せられる質問をご紹介します。
不動産売却の仲介手数料は誰が払う?
売却を依頼した不動産会社へは、売主が支払います。一方、物件探しを依頼した買主は、購入側の不動産会社に仲介手数料を支払います。
同じ不動産会社が売主と買主双方の仲介をおこなう「両手仲介」の場合、その1社が双方から手数料を受け取る形になります。
仲介手数料がかからないケースは?
売却にかかる仲介手数料がかからないケースは、自己発見取引(※)が成立する場合を除き、基本的にないと考えてよいでしょう。
手数料がかからない不動産会社があっても、物件の紹介先が仲介手数料を確実にもらえる不動産買取会社に限定されるおそれがあります。
(※)自己発見取引とは、売主自身が買主を見つけ、個人間で直接取引すること
規定の仲介手数料よりも高くなるケースは?
原則として、規定の仲介手数料より高く請求されることはありません。ただし、遠方への出張費や特別な広告費など、依頼者が同意した追加業務が発生する場合は、仲介手数料とは別に請求されることがあります。
仲介手数料が安い不動産会社のほうがいい?
必ずしも仲介手数料が安い不動産会社がいいとはいえません。なぜなら、仲介手数料が安い分、広告や販売活動の範囲が制限されることがあるためです。
仲介手数料が安くても、それ以上に売却価格が下がっては本末転倒です。必ず、販売方法を確認し、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。
仲介手数料は値引きできる?
法律上、仲介手数料の上限は決められていますが下限はありません。そのため、値引交渉は可能です。
ただし、物件の状況などを見て判断しないと、販売活動の優先度が下がるおそれがあります。
不動産売却の仲介手数料を解説しました。
仲介手数料は、不動産売却時の諸費用に占める割合も高く、できるだけ節約したいと思われるでしょう。
とはいえ不動産の売却でもっとも大切なことは、より高く、確実に売却することです。
物件の売れやすさやかけられる期間、住宅ローン残債の有無など、売却時の状況はさまざまです。そのため、売却時の状況を踏まえ、最適な売り出し価格や販売方法を提案してくれる不動産会社を選ぶことが大切になります。
仲介手数料だけでなく、不動産会社の販売方法や安心して任せられる担当者であるかなど総合的に判断して不動産会社を選びましょう。
物件を探す