
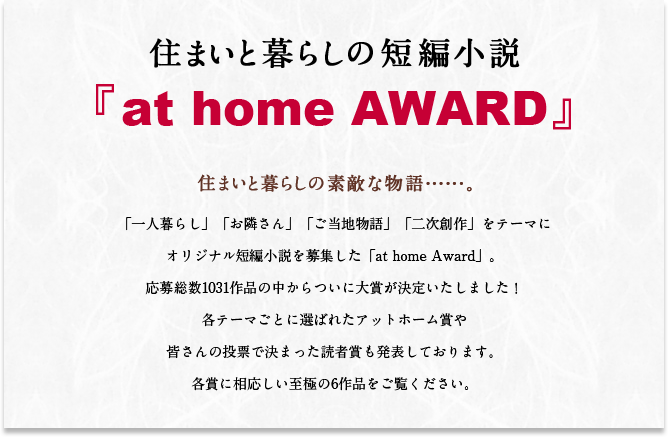
転勤で鳥取県は鳥取市にやってきた二十九歳の『私』は、お盆休みだというのに実家にも帰らず、この街の夏の風物詩『しゃんしゃん祭り』にやってきていた。そこで、一緒に来ていた友人と別行動をしていると、一人の浴衣の似合う『少女』と出会う。
台東区上野桜木一丁目。かつては恋人と暮らしていた、小さな家に、いまはひとりで住んでいる。当たり前の幸せは当たり前のように手に入ると思っていたけれど。絵を描いてどうにか暮らせるようになった僕の、下町での小さな暮らしは……。
大学入学と同時に、南の町でひとり暮らしを始めた「私」。関東から南西に900キロ離れたその地は、細くて硬いラーメンと、熱い強風が町に溢れる地方都市だった。そして町の浜辺にある野球場では、とある弱小チームが快進撃を続けている。
大学院に進学した為に仲間より一歩遅れて卒業したクマは、彼らの多くが住まう広島市を就職先に選んだ。引越祝いの飲み会で、クマは大学時代を過ごした思い出の地「西条」を出て「市内」で大人になった仲間たちにもう一度出会う。彼らが教えてくれる広島市の夜は、驚きと光と酒で満たされていた。
岩手県の大槌町からは鯨山が見える。クジラに関する伝説が残るこの山は、その山容から、三陸沖を航海する船の羅針盤としての役割を果たしてきた。彼女はその町で生まれ、育ち、そして震災にあった。藤沢市のぼくの通う中学校に転入してきた彼女の夢は、生物学者になってクジラを研究することだった。
20年足らずの人生で少なくない男と関係を持ってきた彼女は、その関係が終わるごとにその男を、いつもの場所、時刻で待ってみるのだった。彼女が最後の男を渋谷で待つ。かつての男たちの記憶とともに、自分が本当は何を待っていて何をしようとしているのかも知らず。
神田神保町の路地裏。夫婦で営んでいるイタリア食堂へ、風変りなお客が訪れた。つわりで動けないバリスタの妻に代わって、おそるおそるコーヒーを淹れ、彼の話に耳を傾けるうちに、私は奇妙な体験をすることになる・・・。
「自分」はどういう人間なのかがよく分からない高校生の『僕』は、長くて退屈な夏休みを迎える。何かをしよう。そう思った彼はある日ロードバイクを買うことを決意するが・・・。
五十三歳になる彼女は、非人間的で惨めな自分自身の人生に疲れていた。職場を早期退職したことをきっかけに、縁もゆかりもない帯広市へ引っ越す。穏やかで厳しい帯広の自然に触れるうち、彼女は人間らしい生き方を取り戻して、新しい人生を歩み始めた。
愛知県西尾張地方に暮らす青井家の主人竜男は、自分ではそれほど食にこだわりを見せやしない方だと思っている。青井家の味噌汁は赤、白、合わせ、と日によって違う。この地方八丁味噌に代表される赤味噌が人気である。ある朝、八丁味噌を使った赤出しを口にして竜男は思わず言葉する。やっぱ赤だがね。
道夫のうちでは、毎年、お盆の十三日の夕方、まだ暮れきらないたそがれ時になりますと、先祖迎えの迎え火を焚きます。家の戸口の前に、ホウロクという素焼きの土器を地面に置いて、その上で、折ったオガラを燃やすのです。この火を目印にしてご先祖さまが帰ってくるといわれています。
会社の倒産により人生に破れ、大橋隆信は妻を残し、昔憧れた菜穂子の故郷・青森を訪ねた。吹雪の中で飛び込んだ小料理店の女将との会話で、大橋は昭和の世界に迷い込んだこと、女将の娘が早逝した菜穂子であることを知る。最終の青函連絡船で再会した菜穂子の言葉に、大橋は救われていくのだった。
流れるように生きていく不安を胸に秘めながらも、流れるように金沢に辿り着いた女性の追憶が、最初と最後の「薄紫色の着物」を介して一つの円い輪になっていく……。そんなふうに連鎖していく記憶の物語です。