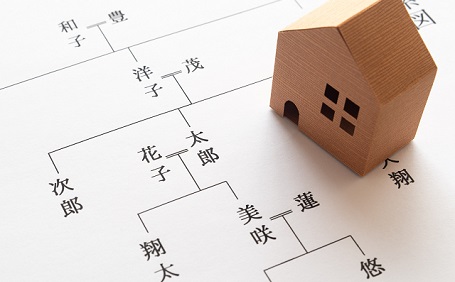実家の売却で後悔する理由は?後悔しないためのポイントを徹底解説!

この記事では、実家の売却で後悔する理由と後悔しないためのポイントを解説します。さらに実家を売却するメリットと売却する以外の選択肢を紹介。記事を読むことで、実家を本当に売却するべきかを含めて、後悔しない選択を取れるようになるでしょう。
記事の目次
実家の売却で後悔する理由

実家の売却で後悔する理由をそれぞれ詳しく見ていきましょう。
愛着のある実家を失う喪失感がある
実家は、幼少期からの思い出や家族の歴史を刻んだ場所です。家のすべての部屋が記憶と結びついていることでしょう。よって、実家を売却すると自分の居場所を失ったと感じる場合があります。手放した瞬間に急激な喪失感に襲われてしまうかもしれません。心の整理をつけずに、まとまったお金が得られることを理由に軽い気持ちで売却してしまうと、後悔は大きくなるでしょう。
親や家族に罪悪感がある
実家を売る決断は、親や兄弟など他の家族の思いを背負う重い決断です。特に高齢の親が築いてきた家を手放すことは、自らが親の努力や歴史を否定してしまうような罪悪感をともなうかもしれません。
家族間で売却について十分に共有できなかった
家族間で売却について十分に共有できない状態で実家を売却すると、トラブルに発展する危険性もあります。家族と十分に話し合いをしないまま実家の売却を進めると、意見が尊重されなかった不信感から対立が生じやすくなります。結果的に、家族の仲が悪化して後悔することになるかもしれません。また、実家が共有名義の不動産の場合は、相続人全員の合意を得られず、売買契約が無効になるケースもあります。
大切な家を納得のいく価格で売れなかった
実家は思い入れのある大切な家であるからこそ、納得のいく価格で売れなかったことに後悔をするケースがあります。具体的には、相場に沿った価格で売却できていても、自身の価値基準から納得ができなかった場合と、相場よりも低い価格で売却してしまった場合が考えられます。後者の場合は、「売却活動で他にもできることがあったのではないか」という思いから後悔しやすいでしょう。
十分な時間を取ることができなかった
実家の売却スケジュールを把握していないと時間が足りなくなるケースも。また、大切なものに向き合う時間が十分にとれないと、後から悔やむことになるかもしれません。
売却にかかる費用を理解していなかった
実家の売却には、さまざまな費用・税金がかかります。具体的には、売却を仲介する不動産会社に支払う仲介手数料、売却益にかかる譲渡所得税・住民税が挙げられます。費用を過少に見積もってしまうと、予想よりも手元に残る金額が減少して、想定よりもお金が残らなかった後悔を招くことになります。
空き家の状態で長期間放置してしまった
相続の発生から売却を決めるまでの間に、実家を空き家状態で放置すると、建物の老朽化が進行して建物の価値が下がる可能性があります。実家を売却する決断をあと回しにしてしまった場合や、売却活動をしていたとしても売り手を見つけられずに売却期間が延びた場合に考えられるリスクです。
実家に限らず、家は人が住んでいなければ劣化の進行が早くなるため、長期間人が住んでいない状況が続くことを避ける必要があります。誰も住まない状況が続く場合は早急に手を打たなければ、売却するにしても住むにしても後悔することになるかもしれません。
実家の売却で後悔しないためのポイント

実家の売却で後悔しないためのポイントをそれぞれ詳しく見ていきましょう。
家族・親族と十分に話し合う
実家の売却で後悔しないためには、家族・親族全員で売却について十分に話し合うことが重要です。合意したあとに意見を変えられることを防ぐために、家族会議の内容は議事録やメールなど証拠に残る形で残しておくと安心です。特に実家が共有名義の不動産の場合は、全員の同意と委任状がなければ売買契約を進められません。
売却を決めたなら、いつまでに売るか、売却に必要な資金や売却後の利益をどのように分配するかを含めて共有すればトラブルを避けられるでしょう。家族・親族全員が納得するまで十分に話し合うことで心に整理がつき、実家の売却で後悔することを防げます。
相続から売却の流れを理解する
受け継いだ実家を売却する場合は、相続登記の手続きから始まります。被相続人の名義のままでは売却できないため、相続登記をおこない自分の名義に変更しましょう。売却しない場合も、相続登記は義務化されているため、未登録のまま放置すると過料が科されることから注意しましょう。売却の流れは、以下のとおりです。
- STEP 1実家の価格を査定する
- STEP 2不動産会社と媒介契約を結ぶ
- STEP 3不動産会社と売却活動を開始する
- STEP 4購入希望者と交渉して売買契約を結ぶ
- STEP 5決済と引き渡しをおこなう
各段階で登記済権利証・住民票・印鑑証明書などの必要書類を求められることがあるため、あらかじめ準備しておきましょう。相続から売却の流れを理解すれば、スケジュールにあわせて行動できるため、形見分けに十分な時間を取ることができなかったなどの後悔を避けることができます。
市場調査と相場を把握する
実家を適正な価格で売却するには、十分な市場調査をおこない、相場を把握することが重要です。複数の不動産会社に査定を依頼して実家の相場を把握しましょう。
実家は本人にとって特別な思い入れと価値があるため、相場よりも高い価格で売却したいと考えるかもしれません。しかし、相場より高過ぎる価格では買い手が見つからないため客観的な視点を持って判断することが大切です。より正確な価格を知るためには、インターネット上で受けられる一括査定を受けた後、そのなかから数社に絞り込み、訪問査定を受けましょう。
不動産情報サイト アットホームには、「不動産一括査定依頼サービス」があります。複数の会社に同時に査定を依頼できるため、ぜひご活用ください。
不動産会社を入念に選定する
実家売却の成功は、選ぶ不動産会社によって結果が大きく変わることがあります。そのため、一つの不動産会社のみに相談することなく、複数の不動産会社に相談して念入りに選定するようにしましょう。不動産会社選びでは販売実績や口コミ・評判など、複数の要素を総合的に判断して選択します。
不動産会社と結ぶ媒介契約には、複数の不動産会社に依頼できる一般媒介契約と、一社のみと契約する専任媒介契約があります。専任媒介契約では一社のみと契約しますが、契約した不動産会社の積極的な売却活動を期待できるため、買い手が見つかりやすいことがメリットです。実家は築年数が古く、買い手が見つかりにくい場合が多いことから、積極的な売却活動を期待しにくい一般媒介契約では、売却に時間がかかることも。
契約後も定期的に売却活動の報告を求めるなら、活動報告が義務付けられている専任媒介契約がおすすめです。媒介契約の種類を含めて検討し、売却活動を仲介する不動産会社を選択しましょう。
不動産の売却にかかる費用・税金を把握する
不動産の売却にかかる費用・税金は以下のとおりです。
| 費用 | 内容 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う仲介業務の手数料 |
| 解体費用 | 建物を更地にして売却する際の解体工事費 |
| 測量費用 | 売却時の境界確定測量や地積測量にかかる費用 |
| 印紙税 | 売買契約書に貼付する収入印紙の税金 |
| 登録免許税 | 登記にかかる税金 |
| 司法書士報酬 | 登記手続きの代行手数料 |
| 譲渡所得税・ 住民税 |
売却益(譲渡所得)に対して課される所得税・住民税 |
仲介手数料の他にも、実家の状態によって費用がかかることも。実家の建物部分に価値がない場合は、建物を更地にして売却するために解体費用がかかります。また、境界が明確でない場合は境界を確定させるために測量費用が必要です。
売買契約書を作成する際には収入印紙を貼る必要があり、契約金額に応じた印紙税を支払う必要があります。相続登記などの登記手続きが必要になった際には、登録免許税が発生。また、登記手続きを専門家に代行する場合は、代行手数料である司法書士報酬がかかります。
譲渡所得税・住民税は、売却益に対して課される税金です。課税の基準となる譲渡所得を求める際には、かかった他の費用を差し引いて計算できる仕組みのため、領収書などの費用を証明できる書類を必ず保管しておきましょう。
片付け・掃除の時間を十分に取る
実家の売却前に片付け・掃除の時間を十分に取りましょう。実家での思い出に十分な時間を取ることで後悔を減らせるだけでなく、成約率の上昇にもつながります。
また、築年数が古く汚い状態の実家は、買い手が見つかりにくい傾向にあります。売却期間が延びるだけでなく、最終的な売却価格にも影響をおよぼすかもしれません。特にキッチン・お風呂などの水回りの設備は汚れが蓄積されやすいため、買い手に悪印象を与えないためにも、重点的に掃除するべきでしょう。必要があれば、ハウスクリーニングを活用する選択肢もあります。
内覧時の印象をできる限りよくするために、片付け・掃除の時間を十分に取るようにしましょう。
利用できる節税制度を活用する
実家を売却して利益を得ると、譲渡所得税・住民税がかかります。税金が発生すると手元に残る金額が減少しますが、節税制度を利用すると支払う税金が少なくなる場合や、税金がかからないこともあります。
例えば、居住用財産3,000万円控除を利用すれば、実家の売却益が3,000万円まで非課税に。実家を相続後に売却するなら、被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例を利用すれば、最高3,000万円の控除を受けられます。
売却益を最大限大きくするためにも制度の活用がおすすめです。制度によっては適用要件と申告手続きが複雑な場合も多いため、税理士などの専門家に相談すると安心でしょう。
実家を売却するメリット

実家の売却は後悔するケースもありますが、売却を検討するうえで重要な実家を売却するメリットを以下にまとめました。
空き家の所有による維持費がなくなる
実家に住むことなく、空き家の状態で所有を続けると、固定資産税や都市計画税などの税金が毎年発生します。空き家は人の手で管理しなければ劣化するため、定期的な点検と修繕が必要です。累積すると年間で数十万円から百万円単位の費用になるため、大きな負担になってしまう場合もあります。
一方で、売却すれば、空き家の所有による維持費が一切なくなります。将来的に自身や親族が住む予定がなければ、金銭的な負担を考えると売却するメリットは大きいでしょう。
まとまったお金を確保できる
実家を売却すると、多額の現金を一度に手に入れられます。売却で得た資金は実家に住む家族の次の住まいにも利用可能です。
すでに実家が空き家だった場合は、まとまった資金を得て他の費用にあてられることも大きなメリットでしょう。
また、築年数が上昇するほど建物の資産価値は下落してしまうため、実家を売却する場合は可能な限り早く決断するほうが、より高値で売却できる可能性が高まります。家族・親族で十分に話し合い、売却が決定したらできるだけ早めの行動がおすすめです。
実家を売却する以外の選択肢

もちろん、売却以外の選択肢もあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
そのまま実家に住む・管理をする
実家を売らずにそのまま住み続けるか、管理し続けられる場合は売却する必要はないでしょう。遠方から管理するなら、不動産管理会社に管理を委託できます。
築年数が古い場合は、修繕によるコストがかかることもあります。コストが発生するデメリットはありますが、思い入れの深い実家を手放さずに済むメリットは大きいでしょう。
リフォーム・リノベーションをおこなう
実家がすでに老朽化しており、実際に住むにあたって安全性・快適性が損なわれているケースもあるでしょう。この場合、リフォーム・リノベーションをおこなって住み続ける選択肢もあります。断熱性能や耐震性能の補強、キッチン・浴室の交換をおこなえば、実家を住みやすい状態に変えられます。
リフォーム・リノベーションの内容によっては、多額の費用がかかることもあります。しかし、受け継いだ家と土地を守り続けられる方法であるため、現在の状態で住み続けることが難しい場合は検討してみましょう。
賃貸に出す
実家を賃貸に出せば、手放さずに済むうえに毎月家賃収入を得られます。人が住み続けることになるため、空き家として放置するリスクもなくなるでしょう。不動産管理会社に委託すれば、入居者募集や家賃回収、修繕手配を代行してもらえるため、経営にかかる手間を大きく減らせます。
将来的に住むことを計画している場合は、契約期間を定める定期借家契約の利用が有効です。また、リフォーム・リノベーションをおこなって資産価値を高めれば、より賃料を得やすくなるでしょう。入居者を募集しやすい魅力的な条件を持っている実家であるなら、賃貸に出すことも検討できます。
まとめ
実家を売却する際には、さまざまな要素をあらかじめ整理して、家族・親族全員が納得できる計画を立てることが重要です。後悔をしないために、入念な準備が大切です。
リフォーム・リノベーション、賃貸に出すなど、売却以外の選択肢もあるため、より後悔の少ない選択をしましょう。
物件を探す
注文住宅を建てる

執筆者
長谷川 賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ