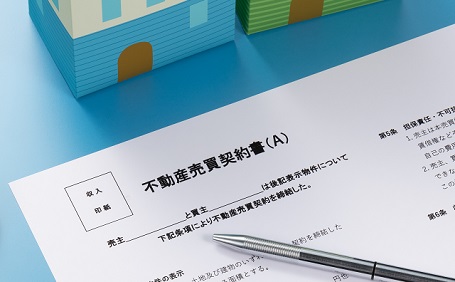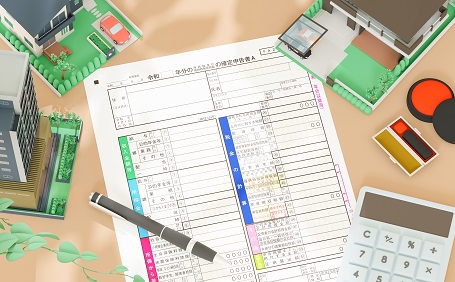不動産の売却益には税金がかかる?計算方法の解説やシミュレーションも!
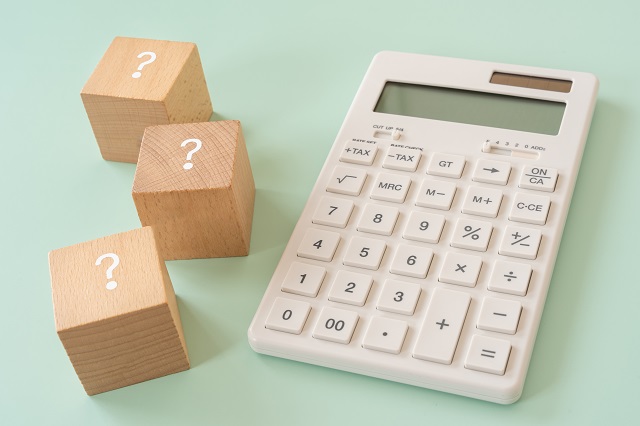
記事の目次
不動産の売却益には税金がかかる

不動産を売却して得た利益には、税金がかかります。土地や建物をはじめ、株式、ゴルフの会員権など、資産を譲渡(売却)することによって得た所得を「譲渡所得」といい、これに対して「譲渡所得税」という税金がかかります。譲渡所得税以外にも、不動産の売却時にかかる税金はさまざまです。それぞれ詳しくみていきましょう。
印紙税
印紙税とは、お金のやり取りをする取引にともなって作成する契約書や領収書に課税される税金のことです。不動産の売却では、売買契約書に必要となります。契約書1通につき1枚必要で、売主と買主がそれぞれ作成し、売主が保管するための契約書1通分を負担します。売買金額によって税額が異なり、具体的には下記のとおりです。
| 不動産譲渡契約書 | 本来の 印紙税 |
軽減後の印紙税 (2024年3月31日に作成されるもの) |
|---|---|---|
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円超10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円超50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円超 | 60万円 | 48万円 |
なお、2023年12月時点では軽減措置が取られており、本来の税額よりも少なくなっています。
登録免許税
登録免許税とは、不動産の名義を変更する際に納める税金です。何がきっかけで名義を変更するかによって、税率が変わります。不動産を売買する際には、固定資産税評価額に対して2%となっており、買主が負担するのが一般的です。しかし、売主が買主にお願いして買ってもらう場合などは、売主が負担することもあります。
また、不動産の売却代金で住宅ローンを完済し、抵当権を抹消する場合は、抵当権抹消の登録免許税が必要となることを理解しておきましょう。不動産1つにつき1,000円で、土地と建物に抵当権が設定されている場合にはそれぞれ必要となり、2,000円になります。
譲渡所得税
先述したように、不動産を売却して得た利益には、譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税は分離課税となり、給与所得などの他の所得と区分されて課税されます。税率は、所有期間によって異なります。詳しくは後述します。
譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税は、自分で計算して求めることが可能です。本章では、具体的な計算方法を解説します。
譲渡所得を求める
まずは譲渡所得を求めましょう。譲渡所得を求める式は次のとおりです。
譲渡所得=収入価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
-
収入価格
不動産を売った時の価格です。売買契約書に記載されているため、確認してみましょう。 -
取得費
不動産を購入した際にかかった費用のことです。不動産の購入代金や仲介手数料、登録免許税、不動産取得税などが該当します。もし、取得費が売却価格の5%に満たない時や取得費がわからない場合は、売却価格の5%を取得費とすることができます。取得費が多いほど、譲渡所得が下がるため、結果として税金が抑えられます。領収書などがないか、探してみましょう。 -
譲渡費用
不動産を売却した際にかかった費用のことです。例えば、売却時の仲介手数料や印紙税、取り壊しの費用が該当します。こちらも多いほど、税金が抑えられるため、書類を確認してみましょう。
特別控除額を引く
一定の要件に当てはまる場合には、特別控除が受けられます。控除には「差し引く」という意味があり、控除額を譲渡所得から引くことができます。ご自身のケースに、受けられる控除がないか確認しましょう。どのような控除があるのか、後述します。
所有期間に応じた税率をかける
譲渡所得を求めたら、売却した不動産の所有期間に応じた税率をかけます。所有期間によって税率が異なり、具体的には下記のとおりです。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 復興特別 所得税 |
|---|---|---|---|
| 5年以下 | 30% | 9% | 0.63% |
| 5年超 | 15% | 5% | 0.315% |
※復興特別所得税は2037年12月31日までに生ずる所得について、所得税と合わせて徴収されます。
表を見ると、所有期間が長いほど、税負担が軽くなるのがわかります。
譲渡所得税を計算する時のポイント

譲渡所得税を計算するにあたって、気をつけなければならないポイントがあります。一つひとつ押さえておきましょう。
取得費の求め方
譲渡所得を求める際に必要となる取得費ですが、種類によって扱いが異なります。
例えば、土地は購入価格をそのまま取得費とすることができますが、建物はできません。それは、建物は時間が経つにつれて価値が下がると考えられるからです。このように、経年劣化が生じるような資産の取得費を、資産の使用可能期間に応じて分けて必要経費にすることを減価償却といいます。そのため、建物は購入価格から減価償却費を引く必要があります。具体的な計算式は次のとおりです。
建物購入代金など取得に要した費用×90%×償却率×経過年数
償却率は、木造や鉄骨などの建物が何でできているかによって変わります。詳細は国税庁のホームページを確認しましょう。
譲渡所得税の税率は所有期間で変わる
先述したように、譲渡所得税の税率は不動産の所有期間で変わります。この所有期間は、不動産を売却した年の1月1日現在の期間に基づいて計算する点に注意しましょう。例えば、2018年5月1日に不動産を購入し、2023年5月1日に売却した場合。購入した日と売却した日を見ると5年経っていることになります。しかし、売却した年(2023年)の1月1日時点では4年しか経っていないため、5年以下の税率で計算します。たった数カ月でも税率に大きな差が出るため、急ぎでないなら5年経つのを待ってから売却するという方法も一つです。
最新の情報を取得する
不動産の売却に限らず、税金に関する情報はアンテナを張り、最新情報を確認するようにしましょう。例えば、先ほど解説した印紙税の軽減措置も、もともとは2022年(令和4年)3月31日までのものでしたが、2024年(令和6年)3月31日までに延長されました。このように、知らぬ間に変わっていることが多々あります。国税庁のホームページなどで、最新の情報をチェックするようにしましょう。
譲渡所得税の計算シミュレーション

実際に譲渡所得税がどれくらいかかるのか、気になるところでしょう。本章では具体的な例を挙げて計算してみます。
2,000万円で買った土地を3,000万円で売却したケース
所有期間:8年
譲渡費用:100万円
まず譲渡所得から求めていきましょう。先述した式に当てはめて計算すると、次のようになります。
3,000万円-(2,000万円+100万円)=900万円
譲渡所得を求めたら、所有期間に応じた税率をかけます。このケースは8年のため、次のとおりです。
900万円×20.315%=182万8,350円
譲渡所得税では100円以下を切り捨てるため、182万8,300円となります。
土地1,000万、建物2,500万で買った不動産を5,000万円で売却したケース
所有期間:15年
取得費:土地20万円、建物50万円
譲渡費用:100万円
建物があるため、減価償却しなければなりません。木造だったと仮定し、減価償却費を計算してみましょう。
(2,500万円+50万円)×90%×0.031×15=1,067万1,750円
次に譲渡所得を計算していきます。
5,000万円-(3,500万円+70万円-1,067万1,750円-100万円)=2,597万1,750円
譲渡所得税率をかけてみましょう。
2,597万1,750円×20.315%=527万6,161円
100円以下切り捨てのため527万6,100円となります。
もし控除の適用が受けられるなら、求めた譲渡所得から控除額を引けるため、場合によっては譲渡所得税が0円になる可能性もあります。損をしないために、適用できる控除がないか確認しましょう。
譲渡所得税を抑えられる特別控除

不動産を売却した際には、特別控除を受けることで税金を抑えられます。本章では、具体的にどういった特別控除があるのかを解説します。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
売却した不動産の所有期間に関係なく、譲渡所得から3,000万円を差し引くことができます。しかし、差し引いたあとの譲渡所得が0円になった場合でも、確定申告が必要となるため、忘れず申告しましょう。また、配偶者や両親、子どもへの売却は適用されません。他にも、居住しなくなった日から3年経ったあとの12月31日までに売却をしている必要があります。他にも要件があるため、ご自身が当てはまるか、国税庁のホームページで確認しましょう。
マイホームを売ったときの軽減税率の特例
所有期間10年超の不動産を売却し、一定の要件に該当する場合には、通常よりも低い税率で計算できます。
具体的な税率は下記のとおりです。
| 譲渡所得 金額 |
税額 |
|---|---|
| 6,000万円以下 | 譲渡所得金額×10% |
| 6,000万円超 | (譲渡所得金額ー6,000万円)×15%+600万円 |
所有期間10年超の税率は20.315%と説明しましたが、要件に当てはまれば、税率が半分近く下がります。国税庁のホームページでは簡単なシミュレーションができるため、ぜひ利用してみましょう。
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
「両親が亡くなったため、相続した家を売った」などの場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できます。ただし、大きく次の3つが要件として挙げられます。
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋であること
- マンションなど区分所有建物でないこと
- 相続開始まで被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
他にも細かな要件があるため、確認しておきましょう。
参考:国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
特定の居住用財産の買換えの特例
特定のマイホームを売却し、新しくマイホームを買い換えた時は、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます。
例えば、2,000万円で購入したマイホームを6,000万円で売却し、5,000万円のマイホームを新しく買ったとしましょう。本来ならば4,000万円(6,000万円-2,000円)が譲渡益として課税対象になります。しかし、この特例を適用すると、売却した年には課税されず、新しく買った5,000万円のマイホームを売却する際に、この4,000万円をプラスして課税対象となります。
非課税になるわけではなく、繰り延べる点に注意しましょう。
損失が発生した時に利用できる特例

譲渡所得を計算して、マイナスになることもあるでしょう。マイナスになったら、何もしなくていいのではないかと思うかもしれませんが、他の所得と損益通算ができるため、総所得が減り、結果として税負担を軽くできます。利用できる特別控除は2つあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
マイホームを売却し、新しくマイホームを買い換えた際に、譲渡損失が発生した場合は、その年の他の所得から譲渡損失分を控除できます。また、控除しきれなかった譲渡損失は、翌3年以後に繰り越すことも可能です。
ただし、この特例の適用を受けるためには、その年の合計所得が3,000万円以下でなければなりません。また、新しく購入したマイホームの床面積が50平方メートル以上である必要があります。他にも細かな要件があるため、確認しておきましょう。
参考:国税庁 No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
住宅ローンが残っているマイホームを売却して、売却価格が住宅ローンの残高よりも下回り、損失が出た場合に特例が受けられる可能性があります。先ほどと同様、譲渡損失分を他の所得から損益通算でき、控除しきれなかった場合は、翌3年以後まで繰り越せます。
どちらの特例にしても、適用を受ける際には、確定申告をしなければなりません。また、繰越控除を受けるためには、毎年続けて申告する必要があるため、忘れないようにしましょう。
参考:国税庁 No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
不動産の売却益に対する税金はいつ払う?

これまで、不動産の売却益に対する税金「譲渡所得税」について説明してきました。本章では、譲渡所得税をいつ、どのように納めればいいのかを解説します。
確定申告で申告・納税する
不動産を売却して譲渡所得が発生した場合、「譲渡所得税」を確定申告で申告・納税する必要があります。確定申告は、1月1日〜12月31日までに発生した所得に応じて、所得税を計算し、精算するものです。所得税を納めすぎていた場合は払い戻され(還付)、不足していた場合は納付する必要があります。確定申告の時期は、毎年2月15日〜3月15日となっており、同時期に申告だけでなく、納税も済ませなければなりません。申告先は住所地を管轄する税務署です。終盤になると混み合うため、なるべく早めに済ませておきましょう。
確定申告に必要な書類
特例によっても必要となる書類は変わりますが、基本的に必要となる書類は下記のとおりです。
| 種類 | 入手方法 |
|---|---|
| 確定申告書第一表 | 税務署 国税庁ホームページ |
| 確定申告書第三表 (分離課税用) | |
| 譲渡所得の内訳書 (確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】 | |
| 購入時の売買契約書のコピー | 自分で用意 |
| 購入時の手数料・税金の領収書のコピー | |
| 売却時の売買契約書のコピー | |
| 売却時の手数料・税金の領収書のコピー | |
| 土地・建物の登記事項証明書 | 法務局 |
| 本人確認書類 (免許証やマイナンバーカード等) | 自分で用意 |
国税庁のホームページからダウンロードできるものもありますが、自分で用意しなければならないものもあります。申告書を書くにあたって必要になるものも多いため、事前に探しておきましょう。また、特例を受けるために、別途必要となる書類もあります。特例ごとに必要となる書類は、こちらで確認できます。わからない場合は、税務署や税理士に問い合わせましょう。
まとめ
本記事では、不動産の売却益に対する税金について解説しました。売却益が発生した時は、譲渡所得税を納める必要があります。各ケースによって、受けられる控除も異なるため、受けられるものはないか確認しましょう。専門知識が必要になる部分も多いため、税務署や税理士の力を借りるのも一つです。知識や経験が豊富なため、的確なアドバイスを受けられるでしょう。
物件を探す

執筆者
民辻伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ