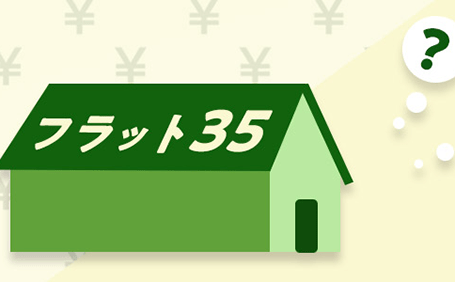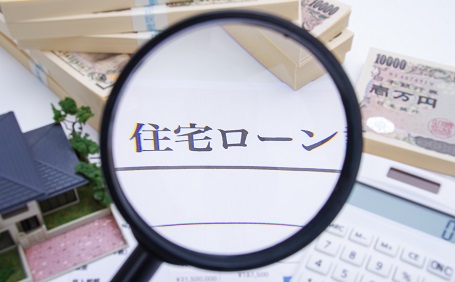住宅ローンで余ったお金はどうしたらいい?自由に使えるの?

今回は、住宅ローンで余ったお金の対処法を解説します。また、お金が余る理由やメリット・デメリットもご紹介するため、これから住宅ローンを組む方はぜひご参考ください。
記事の目次
住宅ローンでお金が余るオーバーローンとは?
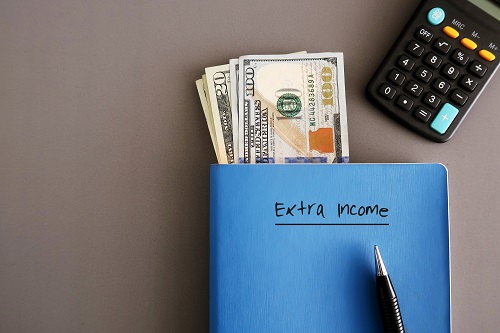
オーバーローンとは、住宅を購入する際に購入価格以上のお金を借り入れることです。例えば、3,000万円の住宅ローンを組み、購入価格が2,800万円だった場合、200万円が余ることになります。200万円あれば、家具や家電もひととおり揃えることができるでしょう。しかし、お金を余らせる目的で、あらかじめ多く借り入れることは禁止されています。
住宅ローンで借り入れたお金が余る理由

なぜ住宅ローンで借り入れたお金が余るのでしょうか。それは工事費用や登記費用が変動するからです。どのような費用が変動するのか、具体的に以下で詳しく説明いたします。
地盤改良工事費用
地盤改良工事とは、住宅の安全性を確保するために、地盤が弱い場合におこなう工事です。一般的に、地盤改良工事には数十万円から数百万円の費用がかかります。そのため、地盤改良工事予算を含めて住宅ローンを借り入れることがあります。しかし、地盤調査は土地の購入後、建て替えの場合には、既存建物の解体後でなければできません。調査の結果、地盤改良工事が不要だった場合、その分の予算が余ることになります。
外構工事費用
外構工事とは、駐車場や庭、門扉(もんぴ)を設置する工事です。外構工事にも費用がかかるため、住宅ローンを利用して借り入れることになります。しかし、家に間取りの変更や仕様変更があった場合、それらが優先されるため、外構工事の予算が余ってしまうことがあります。
登記費用
登記費用とは、不動産所有者の住所や氏名などを帳簿に記載する際に発生する手数料のことです。登記を司法書士に依頼する際は、司法書士への報酬も含みます。登記手数料は、計算式で求めることができます。しかし、司法書士への報酬は、事務所により異なるため、予算よりも低く抑えられる可能性があります。
資金使途で3種類に分けられる住宅ローン

住宅ローンは、購入や建築に必要な資金を借り入れるためのローンです。一般的に、資金使途で大きく3種類分けられます。
住宅ローンの種類を知ることで、ニーズや条件に合ったものを適切に選ぶことができます。それぞれどういうものなのかを詳しく見ていきましょう。
物件の購入資金や請負金額のみに使えるローン
1つ目は、自分が住む新築住宅の購入や建築、増改築の資金を借り入れる時に使えるローンです。住宅を購入する際には、不動産所得税や登記費用などがかかります。しかし、このローンではそういった費用に使うことはできません。自分で資金を用意するか、新たにローンを組む必要があります。金融機関によって、名称が異なるため、何に使うことができるローンなのかを確認しましょう。
諸費用の一部に使えるローン
2つ目は、住宅の購入代金だけでなく、購入する際にかかる諸費用にも使うことができるローンです。例えば、関西みらい銀行では、下記の費用に使える諸費用ローンが用意されています。
- 不動産仲介手数料
- 保証料
- 火災保険料
- 登記費用
- 住宅諸費用ローン
- 引越し費用
また、最初から住宅ローンに諸費用を組み込まれているものもあります。例えば、auじぶん銀行では、資金使途に購入資金や新築資金にともなう諸費用が組み込まれています。借り入れることができる諸費用として、下記が挙げられています。
- 印紙税
- 登録免許税
- 司法書士・土地家屋調査士の手数料
- 借入れの際に発生する事務手数料
- 火災保険料
- 地震保険料
- 不動産仲介手数料
- 引越し費用
諸費用の一部にも使えるローンを利用することで、諸費用を自分で用意する必要がなくなります。ただし、繰返しになりますが、何に使えるのかは金融機関によって異なります。事前に確認するようにしましょう。
フラット35
フラット35は、住宅金融支援機構が提供する住宅ローンです。特徴として、長期間にわたって固定金利が適用される点が挙げられます。借り入れることのできる費用も明記されており、書類で金額を確認できれば住宅ローンに組み込むことができます。
例えば、住宅を建設する場合は次のとおりです。
| 対象となる住宅の費用 | 確認書類 |
|---|---|
| ① 外構工事の費用 | 請負契約書、売買契約書、注文書・注文請書 |
| ② 設計費用、工事監理費用 | |
| ③ 敷地の測量、境界確定、整地、造成、地盤(地質)調査、地盤改良、擁壁の築造のための費用 | |
| ④ 敷地内の既存家屋などの取壊し、除却の費用 | |
| ⑤ 住宅への据付工事を伴う家具を購入する費用 | |
| ⑥ 住宅の屋根、外壁、住宅用カーポートに固定して設置される太陽光発電設備の設置費用 | |
| ⑦ 住宅の敷地に水道管、下水道管を引くための費用(水道負担金など)、浄化槽設置費用 | [自身で請求先に直接支払う場合] 申請書、請求書、領収書 [事業者がお支払いを代行する場合] 請負契約書、売買契約書、注文書・注文請書 |
| ⑧ 太陽光発電設備の工事費負担金 | |
| ⑨ 建築確認、中間検査、完了検査の申請費用 | |
| ⑩ 建築確認などに関連する各種申請費用※1 | |
| ⑪ 適合証明検査費用 | |
| ⑫ 住宅性能評価関係費用 | |
| ⑬ 長期優良住宅の認定関係費用※2 | |
| ⑭ 認定低炭素住宅の認定関係費用※3 | |
| ⑮ 建築物省エネ法に基づく評価、認定に係る費用 | |
| ⑯ 土地購入に係る仲介手数料※4 | 契約書、請求書、領収書 |
| ⑰ 融資手数料 | 取扱金融機関で算出した書類 |
| ⑱ 金銭消費貸借契約証書に貼付する印紙代(お客さまの負担分) | |
| ⑲ 請負契約書、売買契約書に貼付した印紙代(お客さまの負担分) | 請負契約書、売買契約書 |
| ⑳ 火災保険料(積立型火災保険商品※5に係るものを除きます。)、地震保険料 | 保険会社が発行した見積書 |
| ㉑ 登記費用(司法書士報酬、土地家屋調査士報酬) | 司法書士、土地家屋調査士が発行した見積書 |
| ㉒ 登記費用(登録免許税) | |
| ㉓ つなぎローンに係る費用(金利、融資手数料など) | 取扱金融機関で算出した書類など |
(出典:住宅金融支援機構「【フラット35】借入対象費用の追加について」)
※1:各種申請費用とは、以下の費用を指します
| ⑴ 浄化槽申請手数料 | ⑵ 土地区画整理法第76条申請手数料 | ⑶ 市街化調整区域申請手数料 |
| ⑷ 都市計画法第53条建築許可申請手数料 | ⑸ 建築基準法第88条工作物申請手数料 | ⑹ 風致地区申請手数料 |
| ⑺ 中高層申請手数料 | ⑻ 狭あい道路申請手数料 | ⑼ 文化財保護法第93条申請手数料 |
| ⑽ 都市計画法第29条開発許可申請手数料 | ⑾ 農地転用申請手数料 (行政書士報酬等の手続費用を含む) |
⑿ ホームエレベーター申請手数料 |
| ⒀ 水路占用許可申請手数料 | ⒁ 沿道掘削申請手数料 | ⒂ 建築基準法第43条第1項ただし書道路申請手数料 |
| ⒃ 宅地造成等規制法第8条許可申請手数料 | ⒄ 河川占用許可申請手数料 | ⒅ 急傾斜崩壊危険区域申請手数料 |
| ⒆ 構造計算適合性判定手数料 |
金額を証明できる書類が必要なため、なくさないように大切に保管しましょう。
オーバーローンのデメリット

購入価格以上の借り入れをおこなうオーバーローンですが、デメリットはあるのでしょうか。デメリットを知ると、返済能力やライフプランに合わせた適切な借入額を設定することができます。具体的なデメリットは次の3つです。
毎月の返済額が増える
本来必要な額以上の借入が発生するため、結果として返済額が増えてしまいます。毎月の返済額が増えることはもちろん、総返済額も増えることになります。無理のない返済計画が立てられているか、シミュレーションをしましょう。
売却しても住宅ローンの返済が続く可能性がある
オーバーローンのデメリットは、住宅ローンの返済途中で売却することになった場合、売却しても返済が続く可能性があることです。購入価格以上のお金を借り入れているため、売却しても、住宅ローンの完済ができないケースがあります。
住宅の売却価格が借り入れた金額を下回ると、差額を自己資金で補てんする必要が出てきます。返済途中での住宅売却のリスクを十分に理解したうえで、借り入れる金額を慎重に検討しましょう。
金利が高くなる傾向がある
金融機関によって異なりますが、購入価格以上に借り入れをすると、金利が高くなる傾向があります。
例えば、先ほど例に挙げた関西みらい銀行の諸費用ローンの金利は年4.675%です。住宅ローンの変動金利(店頭表示金利は)年2.675%のため、2%も高くなっています。
また、自己資金が少なく、借り入れる割合が高い場合も金利が高くなる可能性があります。住宅金融支援機構のフラット35では、次のように明記されています。
融資率が9割を超える場合は、融資率が9割以下の場合と比較して、ご返済の確実性などをより慎重に審査させていただくとともに、お借入額全体の金利を一定程度高く設定させていただきます(お借入金利は、取扱金融機関によって異なります)。
(出典:住宅金融支援機構【フラット35】)
オーバーローンになる時は金利が高くなることを見越したうえで、返済額がいくらになるのか、返済計画に無理がないかを確認しましょう。
オーバーローンのメリット

オーバーローンは購入価格以上の借り入れをするため、返済が増えますが、メリットが3つあります。
メリット・デメリットを把握し、適切な借入額を決めましょう。以下で一つずつ詳しく解説していきます。
自己資金が少なくても住宅を購入できる
メリットの1つ目は、自己資金が少なくても住宅を購入できる点です。金融機関によっては、頭金や諸費用を住宅ローンに組み込むことができるため、自己資金なしで住宅を購入できます。
「今ある貯金を減らしたくない」「気に入った物件があったから今すぐ買いたい」などの場合には検討してもいいでしょう。ただし、先述したように、返済額が増えるため、無理のない返済計画を立てることが大前提です。住宅ローンの返済で生活が苦しくならないよう、事前にシミュレーションをしましょう。
諸費用を低い金利で借りられる
登記費用や仲介手数料などの諸費用を低い金利で融資してもらえる点もメリットです。例えばauじぶん銀行の場合、住宅ローンに諸費用が組み込まれており、金利は下記のとおりです。
| 当初期間引下げ プラン |
全期間引下げ プラン |
保証付金利 プラン |
|---|---|---|
| 1.710% (固定30年) |
0.319% (変動) |
0.615%〜1.150% (変動) |
(出典:auじぶん銀行「金利・手数料一覧」)
先ほど挙げた関西みらい銀行の諸費用ローンと比較しても、3%近く低いことがわかります。このように、住宅ローンと同じ金利で諸費用を借り入れることができる金融機関があります。ただし、諸費用は別で金利設定をしている金融機関もあるため、事前によく確認するようにしましょう。
住宅ローン控除を受けられる
オーバーローンで借り入れることの3つ目のメリットは、住宅ローン控除を受けられる点です。オーバーローンの場合、返済額や利子が増えるため、その分控除の対象となる金額が増えます。しかし、控除の詳細や条件は制度の改定によって変わることがあります。アンテナを張り、最新情報を把握するようにしましょう。
これまでに説明してきたメリット・デメリットを把握し、適切な借入額を決め、無理のない返済をおこなうことが重要です。
住宅ローンで余ったお金を違うことに使うとどうなる?

「住宅ローンの余ったお金で車を買った」「新居に必要な家具や家電を買った」など耳にしたことがあるかもしれません。もし、住宅ローンで余ったお金を違うことに使った場合、どうなるのでしょうか?
一括返済を求められる可能性がある
住宅ローンで余ったお金を違うことに使う場合、金融機関から一括返済を求められる可能性があります。それは、契約条件や貸付目的に違反したとみなされるからです。住宅ローンの商品説明書や契約書には、資金使途が明記されています。借り入れることのできる費用は何か、よく確認しましょう。
契約や金利優遇が解除される可能性がある
住宅ローンで余ったお金を違うことに使うと、違約金の請求、契約や金利優遇が解除される可能性があります。例えば、琉球銀行の住宅ローン契約書には次のように記載されています。
借主が契約書の借入要項で定めた借入金の使途以外の使途に使用した場合は、銀行が
その事実を知って借主に違反の是正を求めてから 1 カ月以内に解消されない場合には、
当該時点からその時点の「りゅうぎんアパ-トロ-ン」の基準金利まで金利引上げされ
ることに異議申立しないことを確認します。
(出典:りゅうぎん住宅ローン契約書「金銭消費貸借契約書」 )
資金使途以外に使った場合の対応は、金融機関によって異なります。住宅ローン規約をよく読みましょう。
住宅ローンで余ったお金はどうしたらいい?

住宅ローンで余ったお金を資金使途以外に使うと、一括返済が求められたり、優遇金利が解除されたりすることがわかりました。では余った時はどうしたらいいのでしょうか。本章では具体的な対応を見ていきましょう。
金融機関に確認する
住宅ローンでお金が余った時は、金融機関に確認することをおすすめします。金融機関は、資金トレースといわれる、借り入れたお金がきちんと使われているか確認する手続きをおこないます。もし余ったことがわかれば、余ったお金をどうしたのか確認されることになります。できるだけ早く連絡しましょう。
繰上げ返済を求められる可能性がある
住宅ローンのお金が余った時には、繰上げ返済を求められる可能性もあります。金融機関や余った金額によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
なかには悪徳業者も存在し、「住宅ローンで車を買える」「家具を買える」など説明することもあるようです。しかし、これらは契約違反にあたります。業者の言葉を鵜呑みにするのではなく、事前に規約をよく確認し、違法な契約を結ばないようにしましょう。住宅ローンが余った時には、金融機関に相談し、指示を仰ぎましょう。
まとめ
住宅ローンで余ったお金を自由に使うことはできません。住宅ローンでは、何にお金を使えるかが決められています。決められたこと以外のことに使うと、一括返済を求められたり、優遇金利が解除されたりと負担が増えることになります。必ず金融機関にどうすればいいかを確認するようにしましょう。住宅ローンには諸費用に使えるものもありますが、金利が高くなる傾向にあります。事前によく確認し、シミュレーションをしたうえで、返済計画を立てましょう。
物件を探す

執筆者
民辻伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ