住宅ローンの名義人である夫が死亡したら?連帯保証人の妻には返済が残る?

本記事では住宅ローンを組む際に、妻を連帯保証人にするメリットやデメリット、夫が死亡した際に妻に返済が残るケースを解説します。
記事の目次
連帯保証人とは?保証人や連帯債務との違いを解説

まず、連帯保証人の定義から解説します。
似た言葉に「保証人」と「連帯債務」があるため、一つずつ詳しく見ていきましょう。
連帯保証人とは
連帯保証人とは、債務者が債務の履行をしなかった際に、債務を代わりに履行する責任を負う人のことです。住宅ローンの連帯保証人は、契約者が返済義務を果たさなかった際に、代わりに返済する責任を負います。
連帯保証人になるには、信用力や経済的な安定性が求められることが一般的です。
契約者の返済能力が不安定な際や信用力が低いと、金融機関への返済が滞るリスクが高くなり、融資を受けられない可能性が高くなりますが、連帯保証人をつけることで金融機関から融資を受けられる可能性が高くなります。
ただし、連帯保証人になることは重要な責任をともないます。
契約者が返済不能になると、連帯保証人は代わりに住宅ローンの返済をしなければならないため、慎重に判断し、リスクを理解したうえで連帯保証人になる必要があるでしょう。
保証人とは
保証人とは、債務者が債務の履行をしなかった際に、債務を代わりに履行する責任を負う人である点は、連帯保証人と共通しています。
連帯保証人と異なる点としては、以下の3点です。
| 連帯保証人 | 保証人 | |
|---|---|---|
| 貸金業者から返済の請求をされた時 | まず住宅ローンの契約者に請求することを主張できない | まず住宅ローンの契約者に請求することを主張できる |
| 契約者に返済義務があるにも関わらず返済をしなかった時 | 住宅ローンの契約者に対する強制執行を主張できない | 住宅ローンの契約者に対する強制執行を主張できる |
| 保証人が複数いる時 | 保証人が複数人いても全額負担する必要がある | 保証人の頭数で割った金額を負担すればよい |
これらの点から保証人が連帯保証人よりも比較的軽い責任となることがわかります。
連帯債務
連帯債務とは、二人の収入を合算して住宅ローンを組むことで、それぞれが主債務者と連帯債務者になります。
連帯債務で住宅ローンを組む際には、主債務者と連帯債務者が同等の債務を負うことになるため、主債務者が返済できなくなると連帯債務者に返済義務が発生します。
一方で、主債務者の年収だけでは希望の融資額まで到達できなくても、収入のある配偶者が連帯債務者となることで、融資額が増え希望の物件を購入できる可能性が高くなるでしょう。
配偶者以外にも連帯債務者になれる可能性がありますが、金融機関によって基準が異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
一例として、住宅金融支援機構のフラット35では以下の人が連帯債務者になれると定めています。
- 申し込みご本人の親、子、配偶者等
- 申し込み時の年齢が70歳未満の方
- 申し込みご本人と同居される方
引用:フラット35「収入合算」
また、連帯債務で住宅ローンを組むと、連帯債務者も主債務者と同様の住宅ローン控除を受けることができます。
住宅ローンを組む際に妻が連帯保証人になる4つのメリット

住宅ローンを組む際に妻が連帯保証人になるメリットは、以下の4つです。
- 審査に比較的通りやすくなる
- 低金利での融資が受けられる
- 融資限度額が増える
- 返済のリスクが分散される
それでは4つのメリットについて、順番に見ていきましょう。
審査に通りやすくなる
一つ目のメリットは、審査に通りやすくなることです。
住宅ローンの審査では、金融機関が夫(契約者)の返済能力を評価するため、返済能力が不十分だと判断されると、審査が通過しづらくなる可能性があります。
しかし、妻が連帯保証人になれば、夫の信用力が増し住宅ローン審査に影響を与えることがあります。
先に説明したとおり連帯保証人は、契約者が返済できなくなった際に債務を保証する役割を果たすため、連帯保証人の信用力が高ければ金融機関からの評価も高くなるでしょう。
ただし、夫が住宅ローンの返済ができなくなったら、連帯保証人である妻が債務を引き受けなければなりません。連帯保証人になる責任とリスクを把握したうえで判断しましょう。
低金利での融資が受けられる
二つ目のメリットは、低金利での融資が受けられることです。
金融機関は、融資をおこなう際に貸し手としてリスクを考慮する必要があり、借り手の返済が滞ると貸付金を回収できなくなります。
貸付金を回収できないリスクを軽減するために、金融機関は借り手の信用力を評価し、返済能力の高い人には低金利で融資をおこなうことがあります。
妻が連帯保証人になることで、金融機関は審査の際に夫と妻二人分の信用力を考慮することになるため、好条件で融資を受けられる可能性が高くなるでしょう。
つまり、連帯保証人となる妻の信用力が高ければ高いほど、金融機関はより安全で返済が確実な融資先として評価し、低金利を提示することがあります。
住宅ローンを組む際に妻を連帯保証人にすることで、夫が一人で契約するよりも低金利で借りられる可能性がある点は、メリットといえるでしょう。
連帯保証人がいることによって、借り手はより低い金利で住宅ローンを組むことができる可能性が高まります。
融資限度額が増える
三つ目のメリットは、融資限度額が増えることです。
融資限度額は、借り手が借りることができる最大の金額を指し、借り手の返済能力などから金融機関ごとに金額が定められています。連帯保証人となる妻の信用力が高ければ、金融機関は返済のリスクが低いと判断し、より高額な融資を受けることができる可能性も。
融資限度額の増加幅は、夫と妻の収入や資産状況から総合的に判断されますが、金融機関の規定に基づいて決定されるため、連帯保証人がいても大幅な増枠が見込めないこともある点には注意しましょう。
返済のリスクが分散される
四つ目のメリットは、返済のリスクが分散されることです。
連帯保証人は、借り手が返済できなくなった際に債務を引き受ける立場であるため、夫が返済不能になったら妻は残りの住宅ローンの返済をしなければなりません。
妻が連帯保証人になることで、返済のリスクが夫一人に集中することを回避できます。
金融機関は、妻が連帯保証人になることでリスクの分散ができると考え、融資がより安全なものとして審査することがあります。
金融機関にとってリスクを軽減できるからこそ、先述した低金利や融資限度額の増枠など、好条件で融資を受けられる可能性が高くなるでしょう。
住宅ローンを組む際に妻が連帯保証人になる4つのデメリット
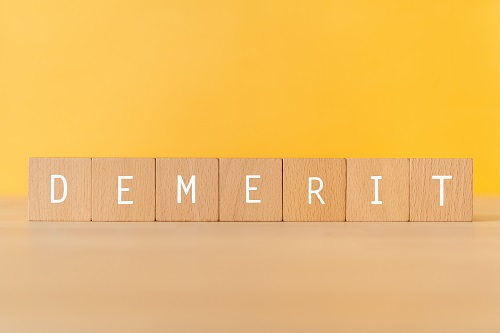
ここまで住宅ローンを組む際に妻が連帯保証人になる場合のメリットについて紹介してきましたが、一方でデメリットもあります。懸念されるデメリットは以下の4つです。
- 責任とリスクを負うことになる
- 支払いができないと信用情報に傷がつく
- 自身の借入を制限することになる
- 債務者との関係が悪化する可能性がある
それぞれのデメリットについて順番に見ていきましょう。
責任とリスクを負うことになる
一つ目のデメリットは、責任とリスクを負うことです。
妻が連帯保証人になることで、夫が住宅ローンの返済を滞らせたり、完済できない状況になったりしたら、連帯保証人である妻は夫に代わって返済をしなければなりません。
夫が返済不能になると、金融機関は連帯保証人である妻に対して返済を要求します。
先述したとおり、連帯保証人は基本的に主張する権利がないため、金融機関から要求されたら支払いに応じなければなりません。
つまり、連帯保証人になることは住宅ローンの契約者の返済能力に関わらず、責任とリスクを負うことになるため、ご自身の経済的な状況やリスクを慎重に考える必要があるでしょう。
支払いができないと信用情報に傷がつく
二つ目のデメリットは、支払いできないと信用情報に傷がつくことです。
住宅ローンの連帯保証人として署名することは、契約者の債務を保証することを意味します。
住宅ローンの契約者である夫が返済不能になると、妻が返済をする必要があり、返済ができないと妻自身の信用情報に傷がつくことになります。
妻自身の信用情報に傷がつけば、クレジットカードの発行ができなくなったり、利用中のクレジットカードにも制限がかかったりするため、生活に影響が出る可能性もあるでしょう。
自身の借入を制限することになる
三つ目のデメリットは、自身の借入を制限することです。
連帯保証人になることで、保証した債務は負債として判断され、信用情報に記録されます。
信用情報に負債として登録されれば、妻自身が別のローンを組む際に制限がかかることになるでしょう。
例えば、連帯保証人として保証した住宅ローンの借入額が大きいと、妻名義で自動車ローンを組む際に制限がされたり、住宅ローンの追加借入が制限されたりします。
連帯保証人になる際は、保証する住宅ローンの借入額やご自身への影響を理解しておきましょう。
債務者との関係が悪化する可能性がある
四つ目のデメリットは、債務者との関係が悪化する可能性があることです。
夫名義の住宅ローンで妻が連帯保証人になることで、夫が返済不能になった際は妻が返済を負担することになります。
連帯保証人となった妻は、金融機関から返済を要求されたら基本的には断ることができないため、夫が返済不能の状況にあることに対する不満や衝突が生じる可能性があります。
お金の問題は感情的な問題と結びつくことがあるため、夫婦関係に関わる可能性もあるでしょう。
夫婦間で連帯保証人となる際は、連帯保証人として署名をする前に必ず話し合いをおこない、双方で合意してから将来的なトラブルになるリスクを軽減しましょう。
夫が死亡した際にも妻に住宅ローンが残る3つの理由

夫が死亡した際に妻に住宅ローンが残るケースがあります。理由は、以下の3つです。
- 夫が団体信用生命保険に加入していなかった
- 契約違反をして団体信用生命保険の適用外になった
- 住宅ローンを滞納している
順番に詳しく見ていきましょう。
夫が団体信用生命保険に加入していなかった
一つ目の理由は、夫が団体信用生命保険(団信)に加入していなかったケースです。
団体信用生命保険とは、住宅ローンの契約者が死亡や高度障害などの予期せぬ事態により、返済が困難になった場合に保険金を支払うことで、残りの住宅ローンを完済する保険制度のことです。
民間の金融機関で住宅ローンを組む際には、基本的には団体信用生命保険への加入が義務付けられていますが、すべての金融機関で加入が必須ではありません。
住宅ローンの契約者本人の意思で任意で加入を決める金融機関もあるため、加入せずに住宅ローンを契約することができます。
団体信用生命保険に加入していれば、契約者が死亡した場合に妻に返済の義務は発生しませんが、加入していないことで住宅ローンの残債はすべて妻が引き受けることになります。
契約違反をして団体信用生命保険の適用外になった
二つ目の理由は、契約違反をして団体信用生命保険の適用外になったケースです。
団体信用生命保険はあくまで生命保険の一種であるため、自殺や告知内容に偽りがあると保険の適用外となります。
先述したとおり、団体信用生命保険が適用されないと、夫が死亡した際は残された妻が住宅ローンの返済を続けなければなりません。
団体信用生命保険に加入する際は、適用となる条件をしっかりと確認しておくことが大切です。
住宅ローンを滞納している
三つ目の理由は、住宅ローンを滞納している場合。
住宅ローンを組む際に団体信用生命保険に加入していても、保険が適用されないケースがあります。
団体信用生命保険の保険料の支払いは、住宅ローンの返済から充当されるのが一般的です。
住宅ローンの返済を滞納すると、団体信用生命保険の保険料も未払いの状態となります。
生命保険は、失効から3年以内など定められた期間内に保険料や利息を払い込むことで、復活することもあるため、過去に住宅ローンの返済を滞納していないか確認しておきましょう。
ただし、復活するための条件は金融機関によって異なるため、事前に確認しておくのがおすすめです。
団体信用生命保険(団信)については、こちらの記事も合わせてご覧ください。
住宅ローンの名義人である夫が死亡した際に妻が取るべき対策とは

住宅ローンの名義人である夫が死亡した際、団体信用生命保険の保証対象であれば、妻に負担がかかることはありません。
しかし、団体信用生命保険の対象外となると、妻が住宅ローンの残債を返済する必要があるため、対策を取る必要があります。
住宅ローンの借り換えを検討する
一つ目の対策は、住宅ローンの借り換えを検討しましょう。
住宅ローンの契約名義人である夫が死亡すると、妻が残債を返済することになりますが、妻が返済できれば問題ありません。
しかし、夫の収入がなくなるため、生活費の支払いをしながら返済をすることが困難となるケースも多いでしょう。
そこで住宅ローンの借り換えをすることで、低金利にできる可能性があり、返済の負担を軽減できます。
また、借入をしている金融機関に相談すると、返済期間の延長をして月々の返済額を減らすことができる場合もあります。まずは、借入をしている金融機関に相談し、難しければ他の金融機関に相談してみるのがおすすめです。
住宅を売却する
二つ目の対策は、住宅を売却することです。
住宅ローンの契約名義人である夫が死亡した場合、収入源が減り、妻一人では返済が難しくなることもあります。
借入をしている金融機関や、他の金融機関に住宅ローンの借り換えをおこない、返済額の負担を軽減できない際は、住宅の売却を視野に入れましょう。
ただし、住宅を売却した資金で住宅ローンを完済できないと、住む家がなくなってしまうだけではなく、返済も残ることになります。
売却を検討する際は、まず複数の不動産会社に売却査定を依頼し、売却の時期なども相談するとよいでしょう。
まとめ
住宅ローンの契約名義人である夫が死亡すると、3つのケースでは妻が残債を返済する必要があります。妻が残債を負担することになる際は、住宅ローンの借り換えや、住宅の売却を検討しましょう。
妻を連帯保証人にすることで多くのメリットを得られるものの、慎重に判断しないとリスクを負うことになります。
ご自身で判断できない場合は、金融機関に相談するのがおすすめです。
物件を探す

執筆者
民辻伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ






