住宅ローンを利用して中古マンションは購入できる?借り入れの条件や必要経費と控除制度を解説

そこで本記事では、中古マンションの購入時に住宅ローンが利用できるか、融資の条件や住宅ローン控除についても解説します。中古マンションを購入する時に住宅ローンを利用したいと思っている方は必見です。
記事の目次
中古マンション購入時に住宅ローンを利用する時のルールは?

中古マンションの購入でも住宅ローンは利用可能です。新築物件を購入する時と変わらない点もありますが、条件が厳しくなる点もあります。本章では、中古マンション購入時に住宅ローンを利用する時のルールを解説します。
リフォーム費用や諸費用も借り入れできる
中古マンション購入時には、リフォーム費用や諸費用を住宅ローンに組み込める場合もあります。リフォーム費用に加え、物件取得にともなう諸費用とされるのは、不動産取得税や仲介手数料、登記費用、火災保険料、修繕積立金、上下水道料金などです。築年数が経過した中古マンションを購入する場合、購入後すぐに内装や設備のリフォームが必要になる場合が少なくありません。リフォーム費用を住宅ローンに組み込むと、費用負担が軽減できて便利です。
ただし、すべての金融機関が諸費用の融資を提供しているわけではなく、条件は金融機関ごとに異なります。金融機関によっては借り入れできる費用の範囲が異なるため、仲介手数料は含まれても、上下水道料金や管理費などは含まれないかもしれません。物件の購入前に金融機関に相談し、どの範囲まで住宅ローンに組み込めるかを確認しておくとよいでしょう。
手付金の借り入れはできない
中古マンションの購入では多くの場合、手付金の借り入れができない点が住宅ローン融資の条件になります。手付金は、売買契約時に買主が売主に対して支払う保証金で、契約成立を確約する役割です。手付金は契約が成立すると、買主が契約を解除しても原則として返還されないため、自己資金から支払わなければなりません。手付金に必要な額は、物件の価格や契約内容によって異なりますが、一般的に購入価格の5~10%が必要とされるケースが多くなっています。
築年数によって返済期間と借入金額が制限される
中古マンションは購入時点ですでに築年数が数年経っているため、返済期間や借入金額に制限が設けられます。
返済期間の制限
一般的に住宅ローンは最長35年の返済期間で設定されますが、中古マンションでは築年数が影響し、35年未満の返済期間になることも。例えば、築30年の中古マンションを購入する場合、耐用年数の47年から築年数の30年を引いた残りの17年が返済可能期間として設定される場合があります。
ではなぜこのようになるのでしょうか。ローンの返済期間が短くなるのは、物件の法定対応年数を加味するためです。法定耐用年数とは、建物が経年劣化などを考慮し、使用可能とみなされる年数を示しています。マンションの構造が鉄骨鉄筋コンクリート造の場合、法定耐用年数は47年。金融機関にもよりますが、法定耐用年数の残年数を超える返済期間は認められません。築年数が古い物件ほど、ローンの返済期間が短くなる可能性が高い点を念頭に置いて契約に臨みましょう。
借入金額が制限される
中古マンションの住宅ローンは、借入金額も制限されます。中古物件は築年数が経過しているため、資産価値が新築に比べて低く見積もられる傾向があり、金融機関が物件の担保価値を厳しく評価するためです。その結果、購入金額全額の融資が受けられず、自己資金の投入が必要になるかもしれません。
金融機関が住宅ローンの担保にするマンションは、万が一返済が滞った際、競売にかけて融資金を回収するための資産と位置付けられます。しかし、築年数が古い中古マンションの場合、競売による売却価格が低くなりがちです。その場合、融資金を回収しきれないかもしれません。特に、築年数が進んでいる場合はそのリスクが高まるため、金融機関側も慎重に評価します。このようなリスクを軽減するため、金融機関は中古マンションの融資額に上限を設ける場合が多いです。そのため、中古マンションの購入時は、事前に物件の担保評価額を確認し、金融機関からの融資額がどの程度になるかを見極めておくようにしましょう。
住宅ローン審査に通りにくい中古マンションとは?
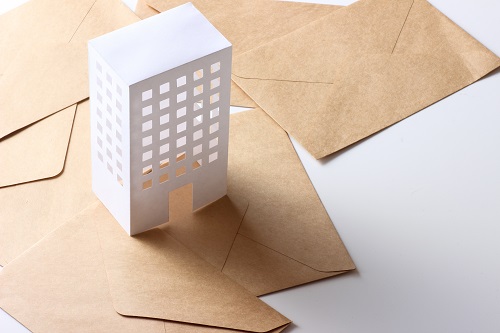
中古マンションも住宅ローンを利用できますが、融資実行には審査が必要になります。物件の状況によっては、審査に通らないかもしれません。では、それはどのような物件なのか、本章では審査に通りにくい物件の特徴を紹介します。
旧耐震基準の物件
旧耐震基準の物件は、住宅ローンの審査に通りにくいでしょう。日本の耐震基準は1981年6月に大幅に見直されましたが、それ以前に建築された物件は旧耐震基準に基づいており、現行基準に比べて耐震性が低いとみられます。
具体的には、1981年6月以降に建てられた物件は新耐震基準を満たしており、一定の地震に耐えられる設計がなされています。一方、旧耐震基準の物件は耐震性の面で劣るとされ、金融機関の担保評価が低くなることが。
金融機関にとって、担保価値は融資のリスクを判断する重要な基準です。住宅ローンを組む際、担保価値が低い物件は貸し倒れリスクが高いと判断され、審査が厳しくなる可能性があります。そのため、旧耐震基準の物件は地震などの自然災害によって損害を受けやすいとみなされることが多く、金融機関も融資に慎重にならざるをえません。
さらに、金融機関によっては旧耐震基準の物件への融資額を制限したり、担保としての評価を下げたりする場合もあります。特にマンションの場合、将来的な資産価値の下落リスクが懸念され、住宅ローンの審査でも不利となる可能性が高いです。旧耐震基準の物件に対する住宅ローンの審査が厳しいのは、こうした担保価値とリスク管理の観点によるものであり、購入を検討する際にはこの点に留意しましょう。
再建築不可の物件
再建築不可物件も、住宅ローンの審査に通りにくい中古マンションの特徴です。再建築不可物件とは、現存する建物を解体して更地にすると、新たな建築物を建設できない物件を指します。これは都市計画区域や準都市計画区域内に適用される建築基準法の「接道義務」からきており、建物を建てるためには、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。つまり、この接道義務を満たしていない土地に建つ建物は、一度取り壊すと、以後建物の建設ができなくなります。
このような再建築不可物件は、物件を解体した場合に新たに建築ができないため、売却や転用の際の自由度が制限される点がネックです。そのような物件は、金融機関に融資のリスクが高いと判断され、住宅ローンの審査に通りにくくなってしまうでしょう。たとえローンの審査に通過しても、融資額が減額される可能性が高まります。また、再建築不可物件は、耐震性や設備の古さが問題となる場合も多く、購入後のメンテナンスやリフォームが必要になりやすい点も資産価値が低下する原因です。住宅ローンの利用を考えるなら、基本的にはこのような物件は避けるべきでしょう。
借地権付きの物件
購入する中古マンションが借地権付きの場合、住宅ローンが利用できない可能性が高いでしょう。借地権付き物件とは、地代を支払いながら地主から借りた土地に建てられた建物を指し、土地は自己所有ではなく第三者の所有になります。所有者が第三者となると、自己所有の土地に比べて担保評価が低くなるのは避けられません。また住宅ローンを借りる際には、地主からの許可が原則として必要で、自己判断できなくなります。
借地権付き物件は一般的に価格が安く、自己資金で手が届くと購入される方もいらっしゃるでしょう。一方で、住宅ローンを利用する場合には、特別な条件が設けられる傾向にあります。
金融機関の多くは、担保としての評価が不安定とみなし、借地権付きの物件を住宅ローンの対象外にする場合が多くなります。こうした条件を踏まえ、借地権付きの物件に興味がある場合は、事前に金融機関に相談し、住宅ローンが利用可能かを確認するようにしましょう。
中古マンション購入で住宅ローンを利用する際に必要な費用

中古マンション購入で住宅ローンを利用する際に、必要な費用の主なものを紹介します。なお、「保証料・保証事務取扱手数料」「団体信用生命保険料」は、不要な金融機関もあります。また、「事務取扱手数料」は、金融機関が自由に設定できる手数料です。住宅ローンの契約前にいくらなのか確認しておきましょう。
事務手数料
事務手数料は契約者が支払う費用のひとつで、住宅ローンを利用する場合に、金融機関がおこなう事務作業への対価です。具体的には、契約書の作成や書類の確認、登記手続きにかかる手数料など。事務手数料の金額は金融機関によって異なり、数万円程度で設定されます。
特に、ペアローンを選択する場合は、夫婦それぞれが負担する可能性があるため留意しましょう。なおペアローンとは、住宅ローンの契約者を夫婦それぞれとする方法で、共働きの家庭にとっては収入合算により借入金額が増えるメリットがあります。しかし、それぞれに手続きが発生し、その分手数料も2倍です。事務手数料の金額の設定は金融機関により異なり、一律で数万円の場合もあれば、融資額に対して1%〜2%程度になる場合もあります。
事務手数料は一度支払ったら返金されない費用であり、ローン契約で必須になるため、購入予定の金融機関に事前に確認しておくようにしましょう。
仲介手数料
仲介手数料は、物件の購入を仲介してくれる不動産会社に支払う報酬で、宅地建物取引業法に基づいて、手数料の上限が定められています。この手数料は、物件価格に応じて計算されるため、購入価格が高ければその分金額も大きくなる点に留意しましょう。
例えば、購入価格が400万円を超える物件の場合、仲介手数料は「購入価格×3%+6万円+消費税」で計算されます。例えば、購入金額が3,000万円の場合、仲介手数料は次のように計算されます。
3,000万円×3%=90万円
90万円+6万円=96万円(税抜)
消費税を加えると、最終的な仲介手数料は105万6,000円になります。
仲介手数料は上限額が決まっていますが、必ずしも上限いっぱいまで支払う必要はありません。不動産会社との交渉により、手数料の一部を値引いてもらうことも可能です。そのため、契約前に仲介会社としっかりと話し合い、支払う金額を協議できます。物件の価格帯や不動産市場の状況によって、交渉が有利に進む可能性もあるでしょう。仲介手数料は一度支払ったら返金されないため、事前にしっかりと計算し、予算に組み込んでおかなければなりません。物件購入の際は、仲介手数料を含めた全体の費用を考慮して、慎重に進めるようにしましょう。
保証料
保証料は、万が一、住宅ローンの返済ができなくなった場合に備えて、保証会社に支払う費用です。もし契約者がローンの返済を滞納した場合、保証会社は代わりに金融機関に残債を支払います。金融機関からみると、保証会社のおかげで返済が滞るリスクを負わずに済みます。ただ、保証会社が代わりに返済をおこなった場合でも、契約者はその分を保証会社に返済しなければなりません。保証料は、ローンの借入金額や返済期間によって異なりますが、一般的には融資額の一定割合です。保証料の他、保証事務手数料が発生する場合もありますが、手数料の額は一般的に数万円程度で、住宅ローンの契約時に一度支払います。
なお、ネット銀行で住宅ローンを組む場合は、保証会社を利用しないのが通例で、その場合は保証料は必要ありません。ネット銀行では、保証会社を介さずに他の方法でリスクを管理しているためです。保証料をカットする視点では、ネット銀行も選択肢になるでしょう。
団体信用生命保険料
団体信用生命保険(以降、団信)は、住宅ローンの契約者が返済途中で死亡または高度障害状態になった場合に、残りのローンが保険金で相殺される仕組みです。この保険に加入すれば、万が一契約者が返済できない状態になった際、遺族がローンを返済する必要がなくなります。
通常、基本的な団体信用生命保険料は金融機関が負担するため、契約者自身が追加で支払う必要はありません。しかし、団信にはさまざまな特約が用意されており、死亡や高度障害に加え、病気による入院や手術の保障を充実させる場合などには、保険料を上乗せします。その分、金利が0.1%〜0.3%程度上乗せされるのが一般的です。
団信は、住宅ローンの契約時に必須な場合が多いため、その内容はローン契約前に十分に理解しておくようにしましょう。特約をつけるか、金利の変動を考慮して保険内容を選ぶ点が大切です。
火災保険料
火災保険は、火災や雷、風災、さらには水災など、自然災害による損害から建物や家財を守るための保険です。万が一、これらの災害が発生した場合、保険に加入していれば、損害額に応じて保険金が支払われます。そのため、購入したマンションやそのなかにある家具・家電に対する補償を受けられるでしょう。多くの金融機関では、住宅ローンを契約する際に火災保険への加入を求められます。ローンの融資を受けるための条件で、保険の加入が必須となるため、火災保険料の支払いが必要です。
この保険料の金額は、購入する物件の建物構造や所在地、保険の補償内容、保険会社によって異なる点に注意しましょう。例えば、マンションの階数や地域によって火災のリスクは異なるため、それに応じた保険料が設定されています。
また、火災保険には基本的な補償内容に加えて、オプションで風水害や盗難などに対する補償を追加できます。ただし、補償内容を充実させると保険料が高くなる点に注意しましょう。
火災保険料は、通常は一括で支払うか、年単位で更新する形式が多いです。住宅ローンを組む際は、火災保険料を含めた総額を計算し、予算に合わせて契約内容を決めましょう。
印紙税
印紙税は、契約書に収入印紙を貼って納める税金です。住宅ローンを組む際、金融機関と金銭消費貸借契約書を交わす必要がありますが、この契約書に対して印紙税が課せられます。印紙税額を準備する場合には、借入金額が大きくなるほど高くなる点に注意しましょう。例えば借入金額が3,000万円の場合、印紙税は2万円です。金額が大きくなると、印紙税も増額されるため、購入者は事前に予算に組み込んでおきましょう。
また、最近では電子契約が普及しており、金融機関によって紙ではなく電子形式で契約書を交わせるようになりました。電子契約が導入されている場合、契約書に対して印紙税は不要なので、物理的な収入印紙を貼る必要がなく、手続きは簡素化できるでしょう。ただし、すべての金融機関が電子契約を導入しているわけではないため注意が必要です。
さらに、契約者が複数いるペアローンなどの場合は、契約書が別々に作成されるため、契約書ごとに印紙税が必要になります。印紙税の額は、国税庁のホームページで最新の税率を確認できるので、契約時にはその情報をもとに必要な額を準備しておきましょう。
抵当権設定登記の登録免許税・司法書士報酬
住宅ローンを利用してマンションを購入する場合、金融機関はそのローンの担保として購入した不動産に抵当権を設定します。この抵当権設定登記には「登録免許税」が課せられ、税金を支払わなければなりません。2027年3月31日までは、抵当権設定登記にかかる登録免許税が軽減されており、一定の要件を満たす場合、税率が「借入金額×0.1%」に設定されています。
これに対して、通常は「借入金額×0.4%」の税率が適用されるため、現行の制度では税額の軽減が大きい点がわかるでしょう。例えば、住宅ローンの借入金額が3,000万円の場合、軽減後の登録免許税は3万円です。一方、通常の税率では12万円となり、9万円もの差額があります。
一方、抵当権設定登記の手続きを司法書士に依頼する場合は、別途司法書士報酬が必要になります。司法書士は登記手続きを代行し、必要な書類の作成や提出をおこないますが、報酬額は司法書士によって異なり、一般的には数万円程度です。司法書士に依頼すると、手続きはスムーズに進み、確実に登記を完了させられるでしょう。
このように、抵当権設定登記には登録免許税と司法書士への報酬の2つの費用がかかります。これらの費用を事前に把握し、購入計画に組み込む点が大切です。
必要に応じて用意する費用
中古マンションを購入する際、物件の価格や手続き関連費用以外にも、必要になる費用があります。その一つはリフォーム費用です。中古物件は、新築と比べて設備や内装が古くなっている場合が多いため、購入後にリフォームをおこなうかもしれません。リフォームは、キッチンやバスルームの改装、壁紙や床材の張り替え、設備の交換などです。
リフォームの内容や規模によって費用は大きく異なりますが、一般的に数十万円から数百万円程度の予算が必要になるケースがあります。部分的な修繕や塗装だけであれば比較的安価で済みますが、間取り変更や設備の交換をともなう大規模なリフォームとなると、かなりの費用がかかるかもしれません。また、リフォームは単に見た目をよくするだけでなく、居住性や快適さを向上させるためにおこなうケースも。そのため、購入前にどの程度のリフォームが必要かを見積もり、必要な費用を予算に組み込んでおくようにしましょう。
中古マンション購入時の住宅ローン控除

中古マンションの購入にあたって住宅ローンを利用する場合、一定の条件を満たせば「住宅ローン控除」を受けられます。住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んでマイホームを購入した方が、所定の条件を満たすと、年末の住宅ローン残高に応じて所得税などを控除できる制度です。ただし、新築と中古マンションの適用条件は同じではありません。特に中古物件には独自の要件があるため、購入前に詳細を確認しておくようにしましょう。
住宅ローン控除が適用される条件
住宅ローン控除を利用するためには、主に以下の条件を満たしている必要があります。
- 購入する住宅が自ら居住するもの
- 床面積が50平方メートル以上
- 住宅ローンの返済期間が10年以上
- 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下(※)
なおこれらの条件は、新築物件と同様ですが、2021年度からは一部の条件が緩和されています。具体的には、40平方メートル以上50平方メートル未満の物件でも、合計所得金額が1,000万円以下であれば控除対象となります。
中古マンション特有の条件
中古マンションの場合、上記の基本条件に加えて、さらにいくつかの要件が課せられています。
- 建物の築年数
- 物件を購入してから6カ月以内に居住を始め、控除を受ける年の12月31日まで居住している
1つ目の築年数は、1982年(昭和57年)1月1日以後に建築されたものが対象になります。この要件は耐震性などの観点から定められています。建物が耐震基準に適合しているかの確認は、中古マンション購入の際に欠かせません。加えて、住宅ローン控除の適用には、物件を購入してから6カ月以内に居住を開始し、その後も毎年12月31日まで継続して居住している点も求められます。これは居住実態を確かめ、控除を適用する正当性を保証するためです。
住宅ローン控除が使えないケース
住宅ローン控除適用には条件があります。例えば、以下のケースでは控除対象外です。
- 住宅ローンの返済期間が10年未満
- 居住用として使用する床面積が全体の1/2未満の場合
また、1982年1月1日以前に建築されていたり新耐震基準に適合していない物件も控除が適用されないため、事前の確認が必須です。中古マンションの購入を検討する際には、こうした住宅ローン控除の条件を把握しておくと、住宅購入にかかる税金負担を軽減できる可能性があります。
住宅ローンを利用した中古マンションの購入に関するよくある質問
住宅ローンを利用した中古マンションの購入に関するよくある質問をまとめました。
中古マンション購入時に住宅ローンを利用する時のルールは?
中古マンション購入時に住宅ローンを利用する際には、リフォームや諸費用も一部借り入れが可能です。しかし、手付金の借り入れはできず、自己資金で支払わなければならない点に注意しましょう。また、築年数に応じて返済期間と借入金額に制限がかかります。さらに、築年数が古い物件ほど法定耐用年数が短くなるため、返済期間が短縮され、融資可能額も減少しがちです。金融機関は資産価値の低下リスクを考慮するため、担保評価額を事前に確認し、資金計画を立てるようにしましょう。
住宅ローン審査に通りにくい中古マンションとは?
住宅ローン審査に通りにくい中古マンションは、旧耐震基準で建てられた物件、再建築不可の物件、借地権付き物件です。それぞれが審査に通りにくい理由は、旧耐震基準の物件は耐震性が低く担保評価が下がりやすいためです。再建築不可物件は資産価値が制限され、借地権付き物件は所有権の制約から融資が難しい点です。これらは金融機関がリスクと判断するため審査に通りにくいと考え、あらかじめ購入前に住宅ローン利用ができるかを確認するようにしましょう。
中古マンション購入時に住宅ローンを利用する際の費用は?
中古マンションの購入時に住宅ローンを利用する際には、事務手数料や仲介手数料、保証料、団体信用生命保険料、火災保険料、印紙税、そして抵当権設定登記の登録免許税や司法書士報酬などの費用が必要です。さらに物件の状態により、リフォーム費用も考慮する必要があります。これらの費用は金融機関や物件価格により変動し、一部は不要な場合もあるため、事前に確認し、予算に組み込むようにしましょう。
中古マンション購入時の住宅ローン控除は?
中古マンション購入時の住宅ローン控除は、所定の条件を満たすことで適用されます。基本条件は、住宅が自ら居住するもので、床面積が50平方メートル以上、ローン返済期間が10年以上、所得が2,000万円以下などです。また中古物件特有の条件として、購入後6カ月以内に居住を開始し、毎年12月31日まで継続して住む必要がある点に留意しましょう。条件を満たせば税負担を軽減できる可能性があるため、築年数や耐震性の確認が重要です。
まとめ
本記事では、中古マンション購入時の住宅ローン利用の主要なポイントを解説しました。具体的には、ローンを組む際の手付金や返済期間・借入金額の制約、審査に通りにくい物件の特徴、ローンに関連する諸費用、控除制度の条件などを挙げています。
住宅ローンを利用する前にこのような情報を知っておくと、購入計画がよりスムーズになり、無理のない予算組みや税負担の軽減ができるようになります。住宅ローン審査を有利に進め、希望の中古マンションを現実的な資金計画で取得しましょう。
物件を探す

執筆者
長谷川 賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ











