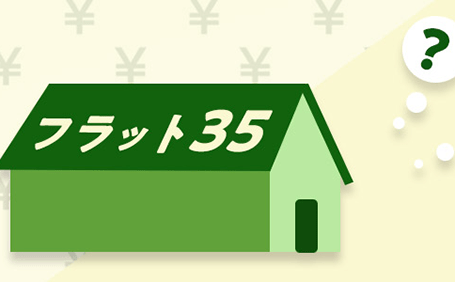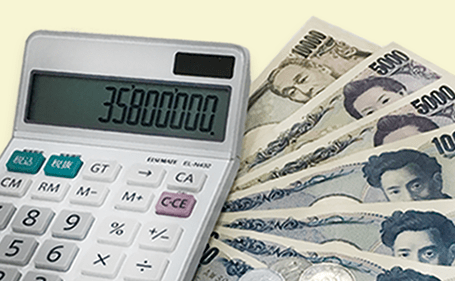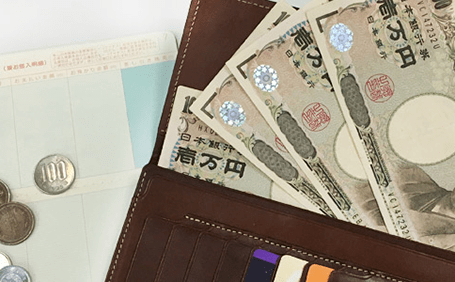住宅ローンはどこで借りる?どの金融機関を利用するか決めるためのポイントを解説

今回は、住宅ローンをどこで借りるかを決めるためのポイントを解説します。
記事の目次
金融機関別の特徴を知る

まずは、金融機関ごとにどういった特徴があるのかを見ていきましょう。今回取り上げるのは、下記の4つです。
- 都市銀行
- 地方銀行・信用金庫
- ネット銀行
- 住宅ローン専門の金融機関
上記の特徴を簡単にまとめたものが次の表です。
| 都市銀行 | 地方銀行・信用金庫 | ネット銀行 | 住宅ローン専門の金融機関 | |
|---|---|---|---|---|
| 金利 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ローンの商品数 | ◎ | △ | △ | 〇 |
| 審査の通過しやすさ | △ | ◎ | 〇 | 〇 |
| アクセス | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
ここからは、もう少し詳しく見ていきます。それぞれの違いを知り、住宅ローンの借り入れの際にご自身に合った金融機関を選びましょう。
都市銀行
都市銀行は全国に幅広いネットワークを持つ大手銀行です。例えば、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行などが挙げられます。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・融資額が大きい ・来店しやすい ・住宅ローン商品の種類が豊富 |
・住宅ローン審査が厳しい ・地方に店舗が少ない |
都市銀行は大手金融機関であるため、安心して住宅ローンを借りることができます。また、住宅ローン商品の種類が豊富で、自分のライフスタイルに合った商品を選べる点も魅力です。しかし、審査が厳しい傾向にあるため、事前に準備をしたうえで審査を受けるようにしましょう。
地方銀行・信用金庫
地方銀行と信用金庫は、その地域に根差し、経済や住民のニーズに合わせたサービスを提供しています。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・窓口で相談しやすい ・住宅ローン審査が柔軟で、借入がしやすい
・金利が都市銀行に比べて低い傾向がある
・もともと取引があった場合は、金利の優遇が受けられる可能性がある
|
・特定の地域にしか支店を展開していないため、来店しにくいことがある
・住宅ローン商品の種類が少ない
|
地方銀行と信用金庫は、地域とのつながりが深い点が特徴です。もともと、お勤めの企業や個人で取引をしていた場合には、優遇金利が適用される可能性があります。また、都市銀行と比べ、住宅ローン審査が柔軟で借入がしやすい点も魅力でしょう。
しかし、その地域に住んでいる人でないと利用しづらい点がデメリットです。地方銀行や信用金庫とすでに取引がある場合は、検討するといいでしょう。
ネット銀行
ネット銀行は、インターネットを通じて金融サービスを提供する銀行のことです。口座開設をはじめ、残高照会、振込、支払いなどさまざまな取引がインターネット上でおこなえます。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・金利が低い ・諸費用が安い ・手続きが簡単 ・24時間365日取引可能 |
・対面での相談ができない ・取扱商品が少ない |
実店舗がないため、人件費が削減されていることから、金利が低い傾向にあります。しかし、対面で相談できない点はデメリットです。対面であれば相談の場で書類の不備に気付くことができても、ネット銀行では銀行に届いてからでないと気付けません。特に住宅ローンは重要な書類が多いため、不備があると修正に時間がかかってしまいます。
なかなか時間が取れず、対面での相談が難しい方やスピーディに住宅ローンの借入を進めたい方に向いているでしょう。
住宅ローン専門の金融機関
住宅ローンのみを扱う金融機関があることをご存知ですか?抵当や抵当権を意味する「モーゲージ(Mortgage)」からモーゲージバンクと呼ばれます。
全期間固定金利の住宅ローン「フラット35」の約9割をこのモーゲージバンクが取り扱っています。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・全国対応している ・金利が低い ・専門的なアドバイスとサポートが受けられる
|
・借り手の条件が決まっている ・住宅の条件が決まっている |
住宅ローン専門の金融機関は、住宅ローンを専門に取り扱っていることもあり、的確なアドバイスとサポートが受けられる点が魅力です。特に住宅は大きな買い物で、高額なローンを組むことから不安も大きいでしょう。専門知識と経験の豊富さが、不安を解消してくれます。
ただし、取り扱われることが多いのはフラット35となります。フラット35は借り手だけでなく、ローンを組むことができる住宅の条件が決まっているため、購入する物件が条件を満たすか、事前に確認しましょう。
金利のタイプで決める

住宅ローンをどこで借りるかを決めるポイントの一つに、金利のタイプがあります。
大きく分けて、借入期間中の金利が変動する「変動金利」と、金利が固定されている「固定金利」の2種類があります。
なお、国土交通省の「令和4年度民間住宅ローンの実態に関する調査結果報告書(PDF)」によると新規貸出額における金利タイプ別の割合は、令和3年度末時点で変動金利が76.2%と割合がもっとも高くなっています。順に固定金利期間選択で13.5%、全期間固定金利が3.4%となっています。
住宅ローンを契約している方の半分以上が選んでいる変動金利ですが、固定金利と比べ、どういう違いがあるのかを詳しく見ていきましょう。
変動金利
変動金利は、市場の変動に応じて住宅ローンの金利が変化します。通常は4月と10月の半年ごとに金利が見直されます。
| メリット | デメリット |
|---|---|
・他の金利タイプに比べて金利が低い |
・金利が上昇するリスクがある ・返済計画が立てにくい |
変動金利は固定金利と比べ、金利が低いことが多いです。また、金利が下がった場合は、毎月の返済額が安くなるというメリットもあります。
しかし、金利が上がるリスクがあり、毎月の返済額が増える可能性もあります。金利が変動するため、返済計画が立てにくい面もデメリットです。
変動金利の住宅ローンを利用する場合には、ご自身の家計や将来の金利動向を慎重に考慮し、リスクを把握したうえで選択しましょう。
固定金利
固定金利は、住宅ローンの金利が契約期間中、一定しています。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・返済計画が立てやすい ・金利の上昇による返済額の増加リスクがない
|
・変動金利と比べて金利が高い |
固定金利の住宅ローンは、金利が固定されているため、返済額も一定です。そのため、返済計画を立てやすく、家計管理もしやすくなります。また、市場の金利が上がっても、住宅ローンの返済額には影響がありません。将来の金利上昇に対する不安をなくせる点は魅力です。
しかし、金利が高めに設定されていることが多いため、注意しておきましょう。
さらに、固定金利には次の2種類に分けられます。
- 全期間固定金利
- 固定期間選択型金利
ここからはそれぞれを詳しく見ていきましょう。
全期間固定金利
全期間固定金利とは、住宅ローン返済期間全体に渡って金利が固定されているタイプです。つまり、契約を結んだ時点から返済期間が終わるまでの間、常に金利が一定となります。そのため、金利の変動リスクを完全に回避でき、返済が安定します。
しかし、金利の安定性を保つ代わりに、金利自体が高く設定されている傾向があります。変動金利と比べ、総返済額が増える可能性があることを理解しておきましょう。
固定期間選択型金利
固定期間選択型金利とは、住宅ローンの契約期間を一定期間で区切り、その期間内の金利を固定するものです。一般的に、2年〜10年程度の期間で金利を固定することができます。国土交通省の「令和4年度民間住宅ローンの実態に関する調査結果報告書(PDF)」によると、10年を選んでいる方が47.3%と一番多くなっており、次に3年で29.3%、2年が12.8%の割合となっています。少しでも長く安定して返済を続けたいと考えている方が多いようです。
金利が固定されている間は、決まった額で返済を続けることができるため、家計支出が明確になります。固定金利期間が終わったあと、変動金利を選択することも可能です。金利が下がった場合には、毎月の返済額が安くなるというメリットもあります。
しかし、金利を選択する際には、優遇の幅が狭くなることがあります。デメリットも考慮したうえで、判断しましょう。
返済方法で決める

住宅ローンをどこで借りるかを決める際に、返済方法を考慮して決めることもできます。本章では一般的な返済方法を解説します。
- 元利均等返済か元金均等返済か
- 毎月払いのみかボーナス払いを併用するか
それぞれどのように考えたらいいのかを見ていきましょう。
元利均等返済か元金均等返済か
まず、元利均等返済と元金均等返済は、それぞれがどういう返済方法かを知っておきましょう。
「元利均等返済」とは、借入金額に対して元金と利息を均等に分割して返済する方法です。毎月の返済額は一定となります。ただし、返済期間が長くなるほど、総返済額は増えます。
次に、「元金均等返済は」、元金を毎月一定額返済し、利息は住宅ローンの残高に応じて変化します。返済当初は利息の割合が高くなり、返済額が増えます。しかし、返済が進み元金が少なくなると返済額も減っていきます。
返済計画を立てやすくして、家計管理をしやすくしたい方は元利均等返済がおすすめです。一方、とにかく総返済額を抑えたい方は、元金均等返済がいいでしょう。
毎月払いのみかボーナス払いを併用するか
毎月払いとは、毎月コンスタントに住宅ローンを返済していく方法です。一方、ボーナス払い併用とは、毎月の返済額に加えて、年2回のボーナス時期に追加で返済をおこなう方法です。
毎月払いのみとボーナス払いを併用した時の違いを、シミュレーションして見てみましょう。
借入額3,000万円
返済期間 35年(元利均等返済)
金利1.5%(固定金利)
ボーナス分で1,000万円
| 毎月払いのみ | ボーナス払い併用 | |
|---|---|---|
| 月々の返済額 | 9万1,855円 | 6万1,236円 |
| ボーナス月の 返済額 |
なし | 18万4,146円 |
| 総返済額 | 3,857万9,007円 | 3,860万9,544円 |
ボーナス払いを併用すると、毎月の返済額を抑えられるのがわかります。しかし、ボーナス払いは、本来毎月払うべき額をボーナス月に先延ばししているため、利息の負担が増えることになります。結果として、総返済額は多くなることを理解しておきましょう。
また、ボーナスが減ったり、なくなったりした時、払えなくなる可能性があるというリスクがあります。住宅ローンは、安定して返せることが重要です。リスクを把握したうえで、どうするかを決めましょう。
団体信用生命保険の保障内容で決める

住宅ローンを決める際のポイントとして、団体信用生命保険の保障内容を考慮するのも一つです。団体信用生命保険とは、借り手が死亡した場合や高度障害状態になった場合、保険金が住宅ローンを契約した金融機関に支払われ、家族や相続人が残りの住宅ローンを返済するための資金に充てることができます。
団体信用生命保険は、各金融機関によって内容が異なる場合があります。また、先ほど説明した借り手が死亡、高度障害状態になった場合だけでなく、がん保障が付いたものや3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)を保障するものなど、特約の種類も多くあります。さらに、特約をつけることで、金利が年0〜0.3%程度上乗せされることが一般的です。なお、一度契約すると、内容の変更ができないため、事前にしっかり検討するようにしましょう。
手数料の安さで決める

手数料の安さも、住宅ローンを借りる際のポイントとなります。住宅ローンの手数料には、次のようなものがあります。
-
事務手数料
住宅ローンの手続きをする際に発生する費用 -
ローン保証料
借り手が住宅ローンを返済できなくなった際に保証会社に立て替えてもらうための費用
事務手数料は定額の場合と、借入金額に対し2.2%(税込)と定率の場合があります。
例えば、定率の場合で3,000万円を借り入れた時の事務手数料は次のとおりです。
3,000万円×2.20%=66万円
大きな金額になることがわかります。
また、保証料は借り入れ金額や返済年数によって変わりますが、借り入れ金額の0%〜2.0%程度です。例えば、先ほどと同様、3,000万円を借り入れた場合の保証料は次のとおりです。
3,000万円×2.0%=60万円
事務手数料が定率の場合、保証料は不要となっています。手数料は金融機関によって違うため、複数を比較し、検討することが大切です。
総返済額だけでなく、手数料を加味してシミュレーションしましょう。
まとめ
住宅ローンと一言でいっても、金融機関をはじめ、金利や返済方法など、考えなければならないポイントは多くあります。住宅ローンは契約したら終わりではありません。返済が終わるまで、金融機関とは長く付き合うことになります。総合的に判断し、どこで借りるかを決めるようにしましょう。
なお、金融機関を選ぶ際、Web上で借りたい金額や自分の属性などの情報を入力すると複数の住宅ローンを提案してくれ、比較できるサービス「モゲチェック」を活用すると便利です。金利や総返済額はもちろん、各種手数料や団信の内容などもまとめて確認できます。プロのアドバイザーに相談することも可能なので、住宅ローンをどこで借りるか迷っている方は、一度利用してみてはいかがでしょうか。
物件を探す

執筆者
長谷川賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ