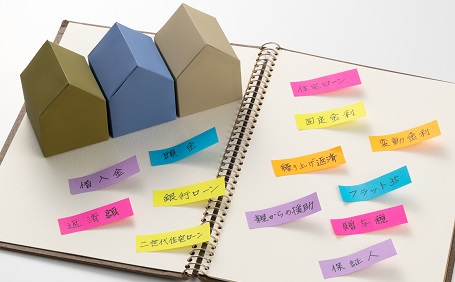中古住宅の購入でも住宅ローンは組める?控除は受けられる?

今回は、中古住宅でも住宅ローンが借りられるのか、控除が受けられるのかをわかりやすく解説します。不安や疑問を解消し、中古住宅の購入に向けて一歩を踏み出しましょう。
記事の目次
住宅ローンは中古住宅でも借りられる?

結論からいうと、中古住宅を購入する場合でも住宅ローンを借りることができます。
例えば、auじぶん銀行の「住宅ローン商品詳細説明書」資金使途の欄には次のような記載があります。
ご自身またはご家族(※1)がお住まいになるための以下の資金
-
戸建・マンション(中古物件含む)の購入資金
※1:ご家族とは、配偶者、配偶者以外の扶養されるご家族、およびご自身または配偶者のご両親に限ります。
また、一般社団法人不動産流通経営協会が公表した「中古住宅購入における住宅ローン利用等実態調査」によると、中古住宅を購入した人のうち、68.2%が購入時に住宅ローンを利用しています。
このように、中古住宅を購入する際、住宅ローンを借りることは可能であり、実際に借りている方も多くいます。
しかし、中古住宅を購入すると一口にいっても、2つのパターンがあります。次から詳しく説明していきます。
リフォーム済み物件を購入する
1つ目は、すでにリフォームされた中古物件を購入するパターンです。新築よりも安く購入できるうえ、内装や設備も新品のため、候補にあげる方もいるでしょう。支払い方法は新築物件と同様、住宅ローンを借り入れ、売主に一括で支払います。そのあと、借入金を金融機関に返済していきます。
なお、リフォーム済みでも断熱材が入ってなかったり、床下が腐っていたりなど、見えない箇所の工事が必要になる場合があります。購入前には建築士などにチェックしてもらうようにしましょう。
中古物件を購入してリフォームする
2つ目は、中古物件を購入してからリフォームする場合です。
この場合、住宅ローンを利用して支払いをおこなう方法として、次の3パターンに分かれます。
- 住宅ローンのみを利用する
- 住宅ローンとリフォームローンを併用する
- リフォーム一体型ローンを利用する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
住宅ローンのみを利用する
物件の購入費を住宅ローンでまかない、リフォーム費用は手持ち資金で払う方法です。リフォーム費用が少ない、もしくは手持ち資金に余裕がある場合はこの方法になるでしょう。
住宅ローンとリフォームローンを併用する
物件の購入費を住宅ローンでまかない、リフォーム費用はリフォームローンで払う方法です。住宅ローンは低金利ですが、リフォームローンは金利が高めであることが多いです。事前にシミュレーションをし、合計の返済額がいくらになるのかをよく確認しましょう。
リフォーム一体型ローンを利用する
リフォーム一体型ローンとは、物件の購入費とリフォーム費用をまとめて借り入れできるローンのことです。一つにまとめられているため、併用する時と違い、住宅ローンと同じように低金利で借りることができます。
リフォームローンとリフォーム一体型ローンの違いや、リフォーム一体型ローンのメリット・デメリットについては、以下の記事で詳しく説明しています。ぜひ参考にしてみてくださいね。
中古住宅で住宅ローンを借り入れる時の注意点

中古住宅を購入する際にも、住宅ローンを利用できます。しかし、中古であることから、新築とは異なるさまざまな制限や条件があります。本章では、具体的な注意点を4つ解説します。
- 借入金額が制限される可能性がある
- 返済期間が制限される可能性がある
- 住宅ローンの審査に通らない可能性がある
- 住宅ローン控除が受けられない可能性がある
それぞれ詳しく見ていきましょう。
借入金額が制限される可能性がある
住宅ローンを利用して中古住宅を購入する際の注意点の1つ目は、借入金額が制限される可能性があることです。
住宅ローンの審査では、物件の価値も重視されています。もし契約者がローンの返済をできなくなった場合、金融機関は住宅を売却してローンの残債を回収します。つまり、物件が担保となっているため、新築住宅と比べ、築年数や状態が劣る中古住宅は物件の価値は低くなります。金融機関は中古住宅のリスクを高く判断し、借入金額を制限する場合があります。
返済期間が制限される可能性がある
中古住宅の購入で住宅ローンを組む際、返済期間が制限される可能性があります。
建物には「法定耐用年数」が定められており、木造や合成樹脂造の場合は22年、木骨モルタル造では20年となっています。法定耐用年数を過ぎると、不動産としての価値がほぼなくなるため、金融機関は住宅ローンの完済が間に合うよう、返済期間を制限します。具体的には「法定耐用年数―現在の築年数」とするところが多いです。返済期間が短くなれば、その分、毎月の返済額が高めになります。中古住宅を購入する際には、築年数にも目を向けるとよいでしょう。しかし、金融機関によっては、法定耐用年数を超えた返済期間を設定できる場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
住宅ローンの審査に通らない可能性がある
中古住宅の状態によって、住宅ローンの審査に通らない可能性があることも理解しておきましょう。具体的に通らない可能性があるのは、次の3つにあてはまる物件です。
- 旧耐震基準の物件
- 再建築不可物件
- 借地権がついている物件
それぞれどのような物件なのか解説します。
旧耐震基準の物件
まずは旧耐震基準の物件です。
旧耐震基準とは、1981年5月31日以前に適用されていた、地震に対する耐久構造の基準です。建築基準法が改正され、1981年6月1日からは新耐震基準が適用されています。
多くの金融機関では、住宅ローンを借り入れることのできる条件の1つに、物件が現行の建築基準法に適合していることを挙げています。例えば、auじぶん銀行では、住宅ローンの借入対象となる物件について「建築基準法、およびその他の法令に適合している物件に限ります。」と規定しています。しかし、金融機関によって判断が異なるため、旧耐震基準の物件がすべて借入不可能となるわけではありません。複数の金融機関に相談してみるとよいでしょう。
再建築不可物件
再建築不可物件とは、建物を建て替えることができない土地のことです。
建築基準法では、「接道義務」が定められており、建築物の敷地は、幅が4m以上ある道路に2m以上接していなければなりません。この義務を果たしていない土地が再建築不可物件にあたります。土地評価が低くなることから、住宅ローンの担保として不十分とみなされ、審査に通らない可能性があります。
借地権がついている物件
住宅ローンの審査に通らない可能性がある物件として、借地権がついている物件も挙げられます。
借地権がついている物件とは、他人が持っている土地を借りて、そのうえに住宅を建てている物件のことです。土地を借りる権利を担保にすることは可能ですが、土地そのものを担保とする場合と比べ、価値が下がります。
また、土地の所有者と住宅の所有者は別であるため、使用状況が悪かったり、契約違反をした場合には、借地権が解除されるかもしれません。この時、抵当権にも影響が出てくることから、金融機関は「リスクが高い」と判断し、審査が通らない可能性があります。
このように、中古住宅を購入する際には、資産価値を見極めることが大切です。不動産会社や専門家のアドバイスを活用し、適切な物件選びをおこないましょう。
住宅ローン控除が受けられない可能性がある
住宅ローンを組んで中古住宅を購入しても、住宅ローン控除が受けられない可能性があります。詳しくは後述しますが、控除を受けるためには、耐震基準や所定の条件を満たす必要があります。しかし、2022年の税制改正により、耐火住宅築25年以内、非耐火住宅築20年以内という築年数の要件が撤廃され、新耐震基準を満たした住宅であれば、適用されることになりました。住宅ローン控除が受けられないからと中古住宅の購入を諦めていた方にも、チャンスが広がったといえるでしょう。
中古住宅で住宅ローン審査が通らなかった時の対処法

中古住宅を購入する際、物件の担保価値が低いことから住宅ローン審査が通らない可能性があります。本章では、もし通らなかった時の対処法を2つ解説します。
- 他の金融機関の住宅ローンを検討する
- より条件がいい中古住宅を検討する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
他の金融機関の住宅ローンを検討する
住宅ローンの審査が通らなかった場合、他の金融機関も検討してみましょう。金融機関によって、審査基準や借り入れ条件は異なります。事前審査は複数申し込むことができるため、最初から一つに絞るのではなく、選択肢を広げてみるとよいでしょう。複数の金融機関を比較検討することで、より最適な住宅ローンを見つけられる可能性もあります。
より条件がいい中古住宅を検討する
住宅ローンの審査に通らなかった場合、買いたかった物件は諦めて、より条件がいい物件を探し直すのもひとつの手です。
住宅ローンの審査では、借り手の信用情報をはじめ、返済能力や担保となる物件の価値も評価されます。いい条件が揃った中古住宅は市場価値が高く、万が一の場合も売却しやすいことから、金融機関の貸し倒れリスクが軽減されるため、審査が通る可能性があります。中古住宅を購入する際は、価格に目が行きがちですが、担保としての価値を知ることも大切です。信頼できる不動産会社のアドバイスを受けながら、物件探しましょう。
中古住宅で住宅ローン控除を受けるにはどうしたらいい?

住宅ローンを組んで中古住宅を購入する際、住宅ローン控除が受けられるのか、気になる方もいるでしょう。一般社団法人不動産流通経営協会が発行した「中古住宅購入における住宅ローン利用等実態調査」によると、築年数の要件を満たしていないことから住宅ローン控除を利用しなかった人のうち69.8%が、そもそも要件を満たすための行動を取っていないことがわかっています。
築年数を満たしていないからと住宅ローンの控除適用を諦めるのではなく、不動産会社に相談するなどして書類の取得を検討してみましょう。
中古住宅で住宅ローン控除を受ける要件
まず、どういう要件であれば住宅ローン控除を受けられるのかを確認しましょう。
- 取得した日から6カ月以内に住んでいること
- 控除を適用する年の12月31日まで続いて住んでいること
- 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
- 住宅の床面積が50平方メートル以上、かつ床面積2分の1以上を居住用にしていること
- 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
- 譲渡所得の特例の適用を受けていないこと
- 次のいずれかに該当すること
(1)昭和57年1月1日以後に建築されたものであること
(2)昭和56年12月31日以前に建築されたもので、耐震基準を満たす場合
(3)昭和56年12月31日以前に建築されたもので、耐震基準を満たさない場合
上述した要件を満たしていなければ、住宅ローン控除を受けることができません。中古住宅を購入する際は、要件に当てはまるか、よく確認しましょう。
中古住宅で住宅ローン控除を受けるために必要な書類
旧耐震基準で建てられた中古住宅であっても、必要な書類を準備する、もしくは保険に加入すれば住宅ローン控除を受けられる可能性があります。
昭和56年12月31日以前に建築された物件の場合は、以下のいずれかの書類の提出が必要です。
- 耐震基準適合証明書
- 建設住宅性能評価書
- 既存住宅売買瑕疵(かし)担保責任保険契約に係る付保証明書
それぞれの書類について、どのようなものなのかを解説します。
耐震基準適合証明書
耐震基準適合証明書とは、建物が新耐震基準を満たしていることを証明する書類です。
耐震基準適合証明書は、建築士事務所に所属する建築士や指定確認検査機関などに依頼し、耐震診断を受け、基準を満たしていれば証明書を発行してもらうことができます。すでに不動産会社とやり取りしている場合は、相談してみましょう。
なお、住宅ローンの控除を受けるには、調査してから2年以内の証明書が必要ですのでご注意ください。
具体的な証明書発行の流れや取得にかかる期間・費用などについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてくださいね。
建設住宅性能評価書
建設住宅性能評価書とは、国の基準に基づいて第三者(登録住宅性能評価期間)が既存(中古)住宅を評価した書類のことです。1〜5等級で評価され、1〜3等級であれば、住宅ローン控除が適用されます。こちらも耐震基準適合証明書と同様、調査してから2年以内のものに限られます。
既存住宅売買瑕疵(かし)担保責任保険契約に係る付保証明書
既存住宅売買瑕疵(かし)担保責任保険契約に係る付保証明書とは、既存住宅売買瑕疵(かし)保険などに加入していることを証明する書類です。
既存住宅売買瑕疵(かし)保険とは、中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度で、専門の建築士による検査に合格することが加入条件となっています。
瑕疵(かし)とは、欠陥があることを指し、物理的な欠陥だけでなく、法律的な欠陥も含みます。もし購入後に瑕疵が見つかった場合には、補修を求めることができ、補修に必要な資金は保険によってまかなうことができます。
付保証明書(ふほしょうめいしょ)は、既存住宅売買瑕疵保険に加入している中古住宅が引き渡される際に売主から渡されるのが一般的ですが、検査を行った検査会社から買主に直接交付されることもあります。万が一、付保証明書を紛失した場合は、再発行をすることも可能です。
ただし、物件を取得した日の前2年以内に締結した保険の付保証明書でなければなりません。
中古住宅の住宅ローン控除額はいくら?
住宅ローンの控除では、実際にどれくらいの控除を受けられるのか、気になる方もいるでしょう。
ここ数年、控除額の計算方法や控除期間は頻繁に変わっています。住宅を取得した日によって変わるため、確認しておきましょう。下表は2019(令和元)年10月1日から2025(令和7)年12月31日までの控除期間と、控除額の計算法をまとめたものです。
| 住宅取得日 | 控除期間 | 各年の控除額の計算(控除限度額) |
|---|---|---|
| 2019(令和元)年 10月1日から 2019(令和元)年 12月31日まで |
13年 | [住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合] 【1~10年目】 年末残高等×1% (40万円) 【11~13年目】 次のいずれか少ない額が控除限度額 ①年末残高等〔上限4,000万円〕×1% ②(住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限4,000万円〕×2%÷3 ※この場合の「住宅取得等対価の額」は、補助金および住宅取得等資金の贈与の額を控除しないで計算した金額 |
| 2020(令和2)年 1月1日から 2020(令和2)年 12月31日まで |
10年 | [上記以外の場合] 1~10年目 年末残高等×1% (40万円) ※住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円 |
| 2021(令和3)年 1月1日から 2021(令和3)年 12月31日まで |
10年 | 1~10年目 年末残高等×1% (40万円) ※住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円 |
| 2022(令和4)年 1月1日から 2022(令和4)年 12月31日まで |
13年 | [住宅の取得等が特別特例取得または特例特別特例取得に該当する場合] 【1~10年目】 年末残高等×1% (40万円) 【11~13年目】 次のいずれか少ない額が控除限度額 ① 年末残高等〔上限4,000万円〕×1% ②(住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限4,000万円〕×2%÷3 ※「住宅取得等対価の額」は、補助金および住宅取得等資金の贈与の額を控除しないで計算した金額 |
| 2022(令和4)年 1月1日から 2025(令和7)年 12月31日まで |
10年 | [認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、特定エネルギー消費性能向上住宅またはエネルギー消費性能向上住宅に該当する場合] 年末残高等〔上限3,000万円〕×0.7% [上記以外(一般住宅)の場合] 年末残高等〔上限2,000万円〕×0.7% |
近年は、環境に配慮した住宅を優遇する傾向があるようです。また、令和7年12月31日以降、変わる可能性もあります。中古住宅を購入し、住宅ローン控除の適用を受けたい場合は、アンテナを張り、常に情報収集をしておきましょう。
まとめ
今回は、中古住宅購入時における住宅ローンと住宅ローン控除について解説しました。中古住宅でも住宅ローンを借り入れることはできますが、新築と違って担保価値が下がることから、借り入れ金額や返済期間が制限される可能性があります。物件価格だけに注目するのではなく、担保価値としての価値も確認するとよいでしょう。
また、中古住宅でも要件を満たせば、住宅ローン控除が適用されます。築年数が要件を満たしていなくても、書類を準備したり、必要な保険に加入すれば、適用される可能性があります。要件を満たす方法がないか、不動産会社など専門家に相談してみましょう。
物件を探す

執筆者
民辻伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ