リースバックのトラブル事例!避けるための5つのポイントを解説

本記事では、リースバックの仕組みとデメリットを踏まえたうえで、具体的なトラブル事例を紹介します。トラブルを避けるためのポイントも解説するため、現在抱えている不動産の問題に対して、本当にリースバックを契約すべきかわかるようになるでしょう。
記事の目次
リースバックの仕組み
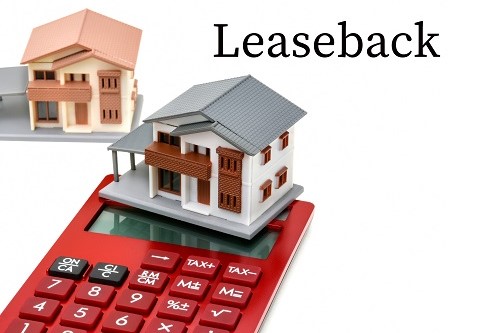
リースバックは住んでいる物件を一度売却し、その後売却した物件を賃貸借契約で借りることで、売却しても同じ物件に住み続けられる仕組みです。売却時にまとまった資金を得ながら、住み慣れた自宅に引き続き住むことが可能になります。
リースバックを利用するには、サービスを提供する不動産会社に査定を依頼します。査定結果を踏まえて、不動産会社と売買契約・賃貸借契約の2種類の契約を締結。売却代金を受け取り、家賃を支払い続けることで、売却した物件に住み続けられます。
また、買い戻し特約がつくリースバックもあります。一定期間内であれば物件の買い戻しが可能になる特約です。まとまった資金が必要であることを理由に一度自宅を売却して、資金に余裕ができたタイミングで、自宅を買い戻すこともできるでしょう。
他にも、固定資産税は物件を購入した買主(不動産会社)が支払うため、固定資産税の支払いがなくなります。住宅ローンを組んでいる場合は、売却代金で一括返済すれば、毎月のローンの返済も発生しません。
リースバックは自宅を売却してお金を得られるため、まとまった資金がどうしても必要な場合に、資金調達の手段の一つになるでしょう。
リースバックのデメリット

リースバックの仕組みを踏まえたうえで、デメリットを3つ紹介します。詳しく見ていきましょう。
売却価格が市場価格より低くなりやすい
リースバックの売却価格は、通常の仲介売却で得られる市場価格よりも割安になりやすいです。一般的には、市場価格の60%~80%程度の売却価格になるため、リースバックで物件を高く売ることは難しいでしょう。
家賃(リース料)が発生する
売却した住宅は他者の所有物になるため、住み続けるには家賃(リース料)を支払わなければなりません。固定資産税の支払い、住宅ローンの返済はなくなりますが、代わりに家賃が発生します。リースバックで家賃を設定する際には、必要経費に固定資産税の負担を含めた金額を設定される可能性もあります。
固定資産税そのものの支払いはなくても、額面が家賃に反映されてしまえば、固定資産税相当の負担がないとはいえないかもしれません。結果的にリースバック前よりも負担が増えてしまう可能性があるため、固定資産税の負担を和らげる目的の場合は、リースバックの利用は適切でない可能性があります。
賃貸期間には制限がある
リースバック契約では定期賃貸借契約が多く採用されており、契約期間は2~3年程度に定められることが一般的です。期間満了後に更新が保証されない場合があり、更新拒否となれば退去を求められることも。
契約期限までしか住み続けることが保証されていないため、長期的に今の自宅に住み続けたい場合にも適切ではない契約です。ただし、買い戻し特約を行使して、再び物件を取得できれば、住み続けることができます。
リースバックのトラブル事例

リースバックを利用すると、契約者にとって不都合な事態に陥ることがあります。具体的なトラブル事例をまとめました。
家賃の急激な値上げにより支払い不能になった
「支払い不能な水準まで家賃を引き上げられた」「家賃は上げないと言ったのに約束が守られなかった」などが、家賃の支払いに関連する具体的なトラブルです。
リースバックで自宅を買い取った会社から、契約更新時に予想以上の家賃引き上げ請求が届き、支払い不能に陥る事例が報告されています。リースバックの家賃は買主側が投資回収を重視して、周辺相場よりも高く設定する場合があります。元々高い家賃を値上げされれば、支払い不能に陥るリスクは高いでしょう。
仮に契約時に家賃は上げないと口約束しても、賃貸借契約書に内容が盛り込まれていない場合、家賃の引き上げは正当化されます。支払い不能になれば、自宅に住み続けることができなくなり、退去しなければならなくなるかもしれません。
契約更新拒否により退去を要求された
リースバックでは定期賃貸借契約が採用されることが多く、契約期間満了時に更新は保証されません。更新を拒否されれば、退去を迫られる事態が生じます。
買主側は「当初の想定利回りが維持できない」「別の運用方針が決まった」などの理由で、現在の契約更新にメリットがないと判断すれば、契約の更新を拒否することが可能です。更新可否の条件を曖昧なまま契約を締結してしまうと、発生しやすいトラブルです。
契約に則って退去を要求されると、新しい居住先を探さなければなりません。現在の住居で暮らし続ける目的でリースバックを利用するのであれば、特に気を付ける必要がある事例です。
買い戻し特約が不十分で行使できなかった
リースバック契約では、将来的に買い戻しができる買い戻し特約を設けられますが、契約書の条件が不十分である場合は行使できない事例があります。行使できないケースは、買い戻し価格の額面・算出方法を明確に定めておらず、買い戻し特約が法的に有効な契約と認められない場合が挙げられるでしょう。
買い戻し特約が有効でない場合は、不動産の市場価格の上昇分を反映した高額な請求になることも。買い戻し特約により、有利に買い戻しできるはずが、相場に沿った高額な価格での買い戻しとなり、資金不足に陥ります。
買い戻し特約を行使して、物件を買い戻す前提でリースバックを契約する場合は、法的に認められる形で契約書に詳細を記さなければ、特約が無効になることがあります。
勝手に売却されて居住継続が困難になった
リースバックのサービスを提供する不動産会社が資金繰り悪化により、物件を第三者に転売した場合、新しい所有者から賃貸借契約の更新を拒否され、居住継続が困難になる事例もあります。譲渡後も契約を維持する旨を契約書に盛り込まなければ、転売後の居住者の権利は守られません。
リースバックのサービスを提供する不動産会社が物件を第三者に転売することは、契約で禁止されていなければ法的に問題ありません。家賃収入を継続して得たあとは、売却益を得る方針でリースバックを結んでいる物件を第三者に提供することは十分に考えられます。
売却した不動産は必ずしも買主である不動産会社が保有を続けるわけではありません。このようなトラブルを防ぐためにも不動産会社が物件を手放す可能性を含めて契約内容を考えましょう。
リースバックを提供する会社が倒産した
リースバックを提供する会社が、経営破綻するリスクもあります。リースバックを提供する不動産会社は小規模の会社も多いため、倒産する可能性は十分に考えられるでしょう。
家賃の支払い中にリースバックを提供する会社が倒産すれば、新しい物件の所有者と契約の再締結にいたるまでの過程で、トラブルに発展する可能性があります。このようなリスクを避けるためにも、契約する前に不動産会社の規模や経営状況を確認し、信頼できる会社かを見極めることが大切です。
売却価格が相場より著しく低い
リースバックのデメリットには、売却価格が相場よりも低くなりやすいことが挙げられます。しかし、一般的なリースバックでは市場価格の60%~80%程度の売却価格になることが多いため市場価格の50%以下の価格であれば、リースバックによる売却であっても非常に低い水準の売却といえるでしょう。悪質な不動産会社の査定に騙され、市場価格の半分以下で物件を売却してしまうケースが考えられます。
1つの不動産会社の査定で契約を決めると、著しく低い売却価格を提示されたとしても気付けません。複数の不動産会社に査定を依頼して比較し、相場を把握した状態でリースバックをおこないましょう。
高額な修繕費を負担させられた
リースバック契約で修繕費の負担範囲を明確に定めずに契約すると、本来であれば不動産会社が負担するはずの修繕費まで負担させられる事例があります。場合によっては、高額な修繕費を負担させられる可能性もあるでしょう。
リースバックでは売却後も元所有者が住み続ける契約であることから、設備の不具合を発見することが難しくなります。よって、不動産会社はリスクを避けるために、特約で元所有者に修繕費を負担させる契約を結ぶケースもあります。契約の際には、負担する費用の内容を確認しましょう。
相続人とのトラブルに発展した
ここまでリースバックを提供する不動産会社とのトラブル事例を紹介しました。しかし、リースバックにより所有権を無断で移転すれば、相続人とのトラブルに発展する事例もあります。
リースバックの利用には、推定相続人の同意は不要です。しかし、配偶者・子どもなどの推定相続人に相談せずに物件を売却すれば、親族間の関係が悪化する可能性があります。
特に同居している家族に対しては、現在の物件に住み続けられるとしても、リースバックを利用する前に相談するようにしましょう。
リースバックのトラブルを避けるためのポイント

リースバックのトラブルを避けるためのポイントをまとめました。詳しく見ていきましょう。
複数の会社を比較して信頼できる相談先を見つける
リースバックを提供する不動産会社には、大手企業から中小企業までさまざまな事業者が存在します。それぞれ売却価格や家賃設定が異なり、サポート対応の質にも差があるため、複数の会社を比較して信頼できる相談先を見つけることが重要です。
リースバックの売却価格の相場は、不動産の市場価格と異なるため、一社の見積もりでは相場が妥当であるかを判断できず、不当に低い価格に設定されることも。家賃設定でも不当に高い家賃を設定されないために、複数の会社を比較して選ぶ必要があります。
契約書の内容を専門家と確認する
リースバックは、契約書の条項のとおりにおこなわれます。仮に口約束をしていたとしても、契約書に内容が盛り込まれていなければ無効です。契約を締結したあとに「契約書を読んでいなかった」という主張は通りません。
自分にとって不利な条項を見逃して契約してしまうことが、リースバックの多くのトラブルに共通します。リースバックに限らず、不動産において契約を締結する際は、契約書の内容が絶対であることを理解しておきましょう。
よって、契約書の不利な条項を見逃さないために、弁護士などの専門家と契約書の内容を確認することをおすすめします。第三者の専門家が契約書をチェックすれば、公平でない契約を結ぶことを防ぎやすくなるでしょう。
家賃負担を事前にシミュレーションする
リースバック後の家賃は、周辺相場より割高になることも多いため、事前に家賃負担をシミュレーションしておきましょう。割高な家賃を毎月負担できなければ、リースバックで同じ物件に住み続けられません。また、リースバックは売却価格をもとに家賃を計算する仕組みです。
家賃 = 売却価格 × 利回り ÷ 12
例えば、売却価格が1,000万円で、不動産会社がリースバックで10%の利回りを期待していると仮定します。計算式に当てはめると「1,000万円 × 10% ÷ 12 = 約8万3,333円」になります。
想定利回りは不動産会社の方針によって変動しますが、売却価格が高いほど、家賃負担も増加しやすくなります。また、計算した家賃に加えて必要経費も上乗せされるため、計算結果と比較すると、実際に設定される家賃は高くなりやすいことを留意しておきましょう。
自宅の売却価格の相場を把握する
自宅の売却価格の相場を把握すれば、適切なリースバックをしやすくなるでしょう。一般的には市場価格の60%~80%程度の売却価格になることか多いです。
売却価格の相場を把握していれば、極端に低い価格、または高い価格を提示されても不審であることに気付けるでしょう。相場を自分で把握しなければ、各不動産会社が提示する売却価格が適正であるかを判断できません。
国土交通省の「不動産情報ライブラリ」で公的な価格を調べ、インターネット上で提供される物件の一括査定を活用すれば、自宅の売却価格の相場を把握できます。
家族・相続人全員と合意してから契約する
リースバックは所有権が第三者に移転するため、同居家族・推定相続人に影響が生じます。そのため、関係者がいる場合は、事前にリースバックを利用する理由、売却によって得る資金の使い道などの十分な説明をおこない、全員と合意してから契約するようにしましょう。
推定相続人の場合は、所有権を移転すれば相続できる財産が減るため、理解を得る必要があるでしょう。
リースバックは自分以外にも影響が出る可能性があるため、契約前に関係者全員との合意は必須です。
まとめ
リースバックは自宅を売却して資金を確保しながら、住み慣れた自宅に住み続けられる点が魅力です。しかし、契約内容をよく確認しなければ、トラブルに巻き込まれる可能性があります。
家賃が高額になり、思うように資金を確保できないケースから、最悪の場合は自宅から退去させられることも。リースバックを利用して後悔しないためには、専門知識を持っている人を交えて、契約書の内容を十分に確認することが重要です。
物件を探す
注文住宅を建てる

執筆者
長谷川 賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ





