古家付き土地の売却のメリット・デメリットは?高く・早く売却するコツを徹底解説!

本記事では、古家付き土地をそのまま売るメリット・デメリットや、解体する場合のポイント、売却前に知っておくべき注意点をわかりやすく解説します。土地の売却で後悔しないために、ぜひ参考にしてください。
記事の目次
古家付き土地とは

「古家付き土地」という言葉は、不動産業界では昔から使われている表現方法の一つです。築年数がかなり経過し、住まいとしての価値がほとんどなくなった古い家を、そのままの状態で土地と一緒に販売する手法です。例えば、相続によって引き継いだ築数十年の実家や、大幅なリフォームが必要な木造住宅などが挙げられます。
このような物件を「古い建物がまだ残っています」などの形で紹介することで、「土地を探している人」に向けて訴求しやすくなる点が特徴。建物そのものに価値はないと明言すれば、物件の本質が土地にあると印象づけられ、土地の購入を検討している層へのアピールが可能になります。
「古い家を売る」と聞くとネガティブな印象を持たれがちですが、「土地+おまけの建物」として提示することで、かえって購入希望者にとって魅力的に映ることがあります。古家をあえて残して「古家付き土地」として販売することにより、土地の存在感を引き立て、売却活動を有利に進められます。
古家付き土地として売却するメリット

ここからは、「古家付きの状態で土地を売却すること」によって得られる、具体的なメリットを詳しく見ていきましょう。
固定資産税の軽減措置を維持できる
土地の上に住宅があると、「住宅用地の特例」により固定資産税や都市計画税が軽減される仕組みを利用できます。この特例を活かせば、売却活動中の間も税金の負担を抑えることが可能です。固定資産税は、以下の計算式で算出されます。
固定資産税=課税標準額×1.4%
都市計画税=課税標準額×0.3%(標準税率)
この課税標準額には、住宅用地であれば以下のような軽減係数が適用されます。
| 区分 | 内容 | 固定 資産税の係数 |
都市 計画税の係数 |
|---|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 1戸につき200平方メートル までの部分 |
1/6 | 1/3 (東京23区は1/2) |
| 一般住宅用地 | 小規模住宅用地以外の部分 | 1/3 | 2/3 |
住宅が残っていれば土地に対する課税標準額が下がり、税額も軽減されます。たとえ空き家であっても、建物が存在する限りこの特例は適用可能です。古家付きのまま売却活動をおこなえば、売却までの間の税金負担を抑えられる点が魅力です。
3,000万円の特別控除を使える期間が長くなる
不動産を売却して利益が出た場合、「譲渡所得」として所得税・住民税・復興特別所得税がかかることになります。この譲渡所得は以下の計算式で求められます。
譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用
ただし、売却する建物が「マイホーム」だった場合、3,000万円までの譲渡所得を控除できる「3,000万円特別控除」が適用できる可能性があります。控除を適用した場合の譲渡所得は、以下の計算式で求められます。
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)-3,000万円
上記の計算結果がマイナスであれば課税対象にはなりません。特例を適用するには「居住用財産」としての条件を満たす必要があり、下記のいずれかに該当すれば適用されます。
居住用財産の対象条件
- 1. 実際に住んでいる家や、その敷地を売却する場合
- 2. すでに転居しているが、転居後3年以内(かつ12月31日まで)に売却する場合
- 3. 災害で家が滅失し、その日から3年以内に敷地を売却する場合
- 4. 転居後に家屋を解体し、解体後1年以内に売買契約、かつ、転居後3年後までに売却する場合(貸付や事業利用は不可)
古家が空き家であっても、転居後3年以内に売却すれば、特例を適用できる可能性があります。一方で、家を取り壊してしまうと、1年以内に売買契約をしなければこの控除が使えなくなってしまいます。
そのため、古家を残して売却したほうが、3,000万円特別控除を長く活用でき、結果的に税制面でも有利に働きます。急いで売却する必要がないため、適正価格で売るチャンスも広がるでしょう。
解体費用を負担しなくて済む
古家を解体して更地にしてから売る場合、その解体費用は売主の負担となります。木造住宅であれば、一般的な解体費用は1坪あたりおおよそ3万1,000円~4万4,000円が相場です。仮に、延べ床面積30坪の木造2階建て住宅を解体する場合、トータルの費用は90万円〜130万円程度になると考えられます。これは決して小さな金額ではありません。
一方、古家を解体せずにそのまま売却すれば、これらの解体費用をかけずに済みます。売主にとっては余計な出費を避けられる点が大きな魅力です。
土地が広く見える
少し意外に思われるかもしれませんが、古家付きのままのほうが、土地を広く感じられる視覚的な効果も期待できます。更地は何もないため、かえって狭く感じることも。古家があることで、土地との比較対象が生まれ、敷地の広さを感じ取りやすくなります。購入希望者が実際にその場に立った時、敷地の奥行きや広さのイメージがつきやすくなる点がメリットの一つ。
ただし、このメリットは副次的なものにすぎません。古家が残っていると不動産としての見た目の印象が悪くなることもあり、状態によってはマイナスに働くこともあります。とはいえ、古家付き土地でも、実際に高値で売れた事例も存在します。物件の立地や需要次第では、古家があることが必ずしもネックになるとは限りません。
古家付き土地を売却する際に注意すべきデメリット

ここでは、古家が建ったままの状態で土地を売却する場合に考えられるデメリットをご紹介します。
売れにくくなる可能性がある
古家付き土地として売却すると、買い手が見つかりにくくなる可能性があります。購入を検討する多くの方は、更地の状態を希望することが多いためです。古家が残った状態での売却の場合、購入者側が建物の解体費用を負担しなければならず、その費用は住宅ローンの対象外となります。したがって、注文住宅を新たに建てる予定の方にとっては、150万円程度の解体費用を自己資金で用意しなければなりません。
しかし、家を建てたいと思っている方でも、そのようなまとまった資金をすぐに準備できるケースは少数派です。仮に資金があっても、通常はその予算を新築の建物本体に回したいと考える方が多いでしょう。
結果として、古家付きの土地を買いたい個人の購入希望者は減ってしまい、不動産会社による戸建て分譲や転売を目的とした買い手に限られてしまいます。この状況では、売却先の選択肢が狭まり、売却に時間がかかってしまう恐れがあります。
迅速に売却を進めたいと考えているのであれば、事前に建物を解体し、更地にしてから売り出すほうがスムーズです。
古民家に魅力を感じる層に届きにくい
古家付き土地として売り出すと、建物そのものに価値を見出してくれる層にアピールしづらくなるデメリットもあります。近年は古民家ブームが到来しており、古い建物をリノベーションして住むスタイルが注目を集めています。そのため、築年数が40年以上の建物であっても、「古民家」として打ち出せば需要が見込めるケースも少なくありません。
なかには、「これは古民家なのか?」と思えるような建物までが古民家として市場に出ていることもあります。古民家専門の不動産会社が存在していることからも、ニーズが一定数あることがわかります。このような買い手は、建物を壊すつもりがないため、古い建物に価値を感じて購入してくれる可能性があり、結果として高値での売却も期待できるでしょう。
その一方で、「土地」としての価値ばかりを強調し過ぎてしまうと、このような建物を好む層の関心を引けず、せっかくの売却機会を逃してしまうかもしれません。つまり、古家付き土地として販売する際には、「古い家にも価値がある」と考える層を意識しなければ、思わぬ機会損失につながる恐れがあります。
売却価格が下がりやすい
古家付きの土地は、解体費用を購入者が負担する前提のもとで取引されることが多いため、どうしてもその分だけ売却価格は抑えられてしまいます。例えば、買主が不動産会社の場合、単に建物を解体するだけでなく、開発や分譲のために敷地内に道路やインフラを整備する必要も出てくるため、さらに仕入れ価格を下げる傾向があります。
一見すると、「解体費用をかけずに済むのだから、古家付きのままのほうが得なのでは?」と思うかもしれませんが、実際には売却価格が低くなるため、必ずしも経済的に有利とはいえません。ただし、売主側から見れば、「自分で解体費用を負担しなくて済む」「解体業者を探して工事を依頼する手間がかからない」などの意味での利便性はあります。
しかしその便利さの裏には、もともと売主が負担すべきだった解体のコストと手間を買主に押し付けた背景があり、その分が価格に反映されてしまいます。最終的に、更地で売却したほうが高値で売れる可能性が高いため、経済的な面で有利に進めたい場合は、事前に解体しておくとよいかもしれません。
古家付き土地の価格に見られるタイプ

古家付き土地を売却する際、その価格は単純な土地の評価だけでは決まりません。建物の状態や土地の広さ、さらには将来的な活用方法によって価格が変動します。
大きく分けると、「取り壊しが前提の場合」「建物に価値がある場合」「開発素地として評価される場合」の3パターンが考えられます。それぞれの価格の考え方を以下で詳しく解説します。
建物の取り壊しを前提とした場合
建物の老朽化が進み、そのままの状態では利用が難しい、つまり取り壊しが前提となるような場合もあります。このような古家付き土地の場合、建物には評価がつかないだけでなく、買主が解体費用を負担しなければならないため、その分土地の価格から控除されることになります。この時の価格の算出方法は以下のとおりです。
古家付き土地の価格=土地価格-解体費用
具体的には、築40年以上経過していて、建物の劣化が著しい場合などが挙げられます。ただし、年数が経っているからといって、必ずしも取り壊し前提になるとは限りません。例えば、定期的に外壁塗装がおこなわれていたり、雨漏りや白アリ被害などの致命的なダメージがなかったりすれば、まだまだ使用可能と判断されることもあります。
そのため、建物の実際の状態をしっかりと確認し、「取り壊し前提」とするのか、「再利用可能」とするのかによって、大きく価格が変わります。
建物に活用価値がある場合
一般的に住宅の資産価値は、築20年〜25年を超えるとほとんど評価されないことが多く、査定上は「建物価格ゼロ」とみなされるケースがほとんどです。しかし、実際には築年数だけで建物の価値が決まるわけではありません。例えば、築30年ほどの住宅であっても、躯体や内装の状態が良好で、リフォームなどの手を加えればそのまま使用できるような場合には、購入希望者から見れば十分に価値のある物件です。
このようなケースでは、売却価格としては「土地価格=販売価格」となることが多いです。建物部分には金銭的な評価がつかない一方で、買主から見れば即入居可能な住宅という魅力も。したがって、表面的には「土地のみの価格」として売り出されていても、実質的には「住める家付きの土地」として、ニーズに合えば高く売れる可能性もあります。
また、リフォームやDIYを楽しむ層には、このような古家付き土地が魅力的に映りやすいため、広告の出し方やターゲティング次第では、存続価値のある建物としての評価も見込めます。
開発素地として評価される場合
古家が建っている土地が一般的な戸建て住宅の敷地よりも広い場合、「開発素地」として評価されることがあります。これは、不動産会社などが複数区画に分譲して販売することを想定して購入するケースです。つまり、将来的に「住宅地」として再整備されることを前提とした土地となります。開発素地として評価される場合の価格は以下のとおり。
古家付き土地の価格=土地価格-取り壊し費用-開発用道路の負担分
ここで注意すべき点は、開発に必要なインフラ整備、特に敷地内に道路を新設する費用です。建築基準法では、建物を建てるには「幅員4m以上の道路に2m以上接道していること」が義務づけられています。そのため、広い敷地を区画分けして住宅を建てるには、道路を設ける必要があり、その道路部分には基本的に評価がつきません。
つまり、広い土地であっても、「道路として使う部分」に関しては金額換算されず、その分だけ土地全体の単価が下がります。そのため、通常の古家付き土地よりもさらに低価格で評価されることがあり、「広い=高値で売れる」とは限りません。
実際には、開発計画の内容やその地域の市街化調整区域・用途地域などによっても価格は大きく異なります。分譲前提の土地は、そのまま売却するよりも時間も手間もかかる可能性があるため、評価もシビアになりやすいのが実情です。
古家付き土地の売却にかかる費用と税金

ここでは、古家付き土地を売却する際に必要となる経費や、注意しておきたい税金を解説します。
売却に必要な諸費用
古家付きの土地を売却する際には、以下のような費用がかかる可能性があります。
- 不動産会社への仲介手数料
- 古家の解体にかかる費用
- 境界確定などの測量にともなう費用
- 所有権移転や抵当権抹消などに関わる登記関連の費用
それぞれの費用の概要を以下にまとめました。
| 費用項目 | 内容 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 不動産仲介手数料 | 売却価格に応じて変動 (消費税課税対象) |
・200万円以下:5%
・200〜400万円:4%+2万円
・400万円超:3%+6万円
|
| 解体費用 | 建物の構造や規模により費用が異なる |
・木造:約3万1,000〜4万4,000円/坪
・鉄骨造:約3万4,000〜4万7,000円/坪
・RC造:約3万5,000〜8万円/坪
|
| 測量費用 | 測量図がない場合、作成に必要な費用 |
・約30〜50万円
(測量会社により変動あり) |
| 登記・抵当権 抹消関連費用 |
登録免許税、抵当権抹消手数料、司法書士報酬 |
・登録免許税:法定額に準ずる
・抵当権抹消:1,000円/件
・司法書士報酬:抵当権抹消で1万円〜2万円前後、所有権移転で4〜9万円程度
|
仲介手数料は、不動産会社に売却を依頼した場合に発生する費用で、金額の上限は国土交通省が定めています。
解体費用は、建物の構造だけでなく、解体現場の立地条件や作業環境によって増減します。例えば木造住宅は比較的安価で取り壊しが可能です。しかし、周囲に住宅が密集している地域では、防音・防塵対策や誘導員の配置が必要となり、追加費用が発生することも。
また、測量費用は不動産売買で必要となる「測量図」がない場合に必要です。測量図は土地の境界を明確に示すもので、法的にも信頼性があります。仮に登記簿の面積のみで売買することも可能ですが、境界杭が見つからない、あるいは登記簿と実測の面積に相違がある場合は、新たに測量が求められます。
登記関係では、売却にともない所有権を移転するために登録免許税が課され、住宅ローンが残っている場合には抵当権の抹消登記も必要に。司法書士に依頼する場合は、別途報酬も発生します。
売却によって発生する税金
古家付き土地を売却することで発生する可能性のある税金は、以下のとおりです。
| 税項目 | 概要 | 税額の例 |
|---|---|---|
| 譲渡所得税 | 売却による利益に 対して課される税金 |
譲渡所得×保有期間 に応じた税率 |
| 印紙税 | 売買契約書に貼る 印紙の費用 |
売却金額に応じて 定額 |
| 固定資産税 | 年初時点の不動産 保有に課される税金 |
売却日までの 日割りで精算 |
譲渡所得税
譲渡所得税は、不動産を売却して利益が出た場合にのみ発生します。逆に、売却によって損失が出た場合には課税されません。譲渡所得にかかる税率は、所有していた年数に応じて異なります。具体的には、売却した年の1月1日時点での所有年数が「5年を超えているか否か」で、長期譲渡所得か短期譲渡所得に分けられ、税率も変わります。
印紙税
不動産売買契約書には、契約金額に応じた印紙を貼る必要があります。これは「印紙税法」に基づき、国税庁が定めた金額にしたがって支払う義務があります。
| 契約金額 | 税額(本則) |
|---|---|
| 10万円を超え50万円以下 | 400円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
固定資産税
固定資産税は毎年1月1日時点で不動産を所有している人に課される税金です。売却が年の途中でおこなわれた場合は、売主と買主でその年の税金を日割りで按分し、清算することが一般的。また、都市部の物件の場合、「都市計画税」も併せて課税されます。古家付き土地の売却を検討している場合には、上記の費用や税金が発生することを事前に把握しておくことで、スムーズな手続きができるでしょう。
古家付き土地を売却する際の注意点

古家が残っている土地を売却する際、事前に確認すべきポイントがあります。ここでは、売却前に知っておくと役立つ注意点をご紹介します。
複数の不動産会社へ査定を依頼する
古家付きの土地を売却する際は、複数の不動産会社に査定を依頼しましょう。同じ物件でも、不動産会社ごとに提示される査定額には差が出る場合が多く、1社だけの査定結果を鵜呑みにするにはリスクがあります。特に古家付きの土地は、「古家を残したまま売るか」「解体して更地にしてから売るか」など、販売戦略の見解が会社によって異なるケースもあります。複数社の意見や提案を比較して総合的に判断することがおすすめです。
しかし、1社1社に個別で連絡して査定を依頼するには、時間も労力もかかるでしょう。そうした手間を軽減したい方は、不動産一括査定サービスなどを利用するといいでしょう。専用フォームに一度入力すれば、複数の不動産会社へ同時に査定依頼ができるため、効率よく比較検討できます。
不動産情報サイト アットホームの「不動産一括査定依頼サービス」では、全国2,415社の不動産会社に一括査定を依頼できます。
契約不適合責任を理解して契約内容を見直す
契約不適合責任に関して正しく理解し、契約内容に反映させることも重要です。売却後に買主から「契約と異なる不備がある」と指摘を受けると、トラブルの原因になります。
契約不適合責任とは、引き渡した物件に「契約内容と一致しない欠陥」があった場合に、買主が売主に対して責任を追及できる制度のことです。例えば、敷地内に埋まっていた産業廃棄物や、建物に雨漏りなどの不具合があった場合、それが事前に説明されていなければ、以下のような請求をされてしまうかもしれません。
- 補修(追完)の要求
- 売買価格の減額請求
- 損害賠償請求
- 契約そのものの解除
ただし、老朽化した古家付きの物件では、建物部分の不適合責任を免責とする契約が一般的です。そのため、不動産会社と相談のうえで、責任範囲や免責の内容を契約書に明記することが大切です。
古家内のゴミや不用品を事前に片付けておく
古家付きの物件では、内部に不用品やゴミが残っているケースもめずらしくありません。売却前に片付けておくことで、スムーズな取引や解体作業につながります。解体作業で生じるゴミは「産業廃棄物」に分類されますが、古家内部に残った生活ゴミや家財道具などは「一般廃棄物」にあたります。産業廃棄物の収集運搬には許可が必要で、解体業者が対応できるものは通常こちらのみです。
一方、一般廃棄物は、自治体の許可を受けた別の業者に依頼しなければ処理できません。そのため、不用品の分別や回収が別途必要になり、解体工程に遅れが出たり、想定外の追加費用が発生したりすることもあります。トラブルを避けるためにも、売却前に建物内部の不用品はあらかじめ整理・処分しておくことをおすすめします。
解体は慎重に判断し、安易に急がない
古家の解体を焦って進めないようにしましょう。建物が古くなっているからといって、必ずしも解体してから売るほうが有利とは限りません。地域や土地の需要によっては、「古家付きでもそのまま購入したい」という買主が現れることもあり、リフォーム前提で探している人にとっては、古家の存在が逆にプラスに働く場合もあります。
解体には費用がかかるうえ、固定資産税の軽減措置が適用されなくなるケースもあるため、事前に不動産会社に相談し、その土地の特性やニーズに合わせて解体すべきか否かを検討することが大切です。
相続した土地は事前に相続登記を済ませる
売却予定の古家付き土地が相続で取得したものである場合、被相続人名義のままでは売却ができません。そのため、相続人へと正式に名義変更をおこなう「相続登記」を先に済ませておく必要があります。
相続登記の手続きでは、他の相続人と話し合って遺産分割の内容を決め(遺産分割協議)、その結果をもとに法務局に登記申請をおこないます。書類の準備や役所での取得なども含めると、通常1〜2カ月程度はかかるため、早めの準備が重要です。
名義変更が未完了のままでは売買契約を進められないため、相続した土地を売却したい場合は、まずは相続登記をおこないましょう。
境界を明確にしておく
土地の売却をおこなう際、売主は「境界を明らかにしておく責任(境界明示義務)」を負っています。この義務を果たさず、境界が不明瞭なまま売却を進めてしまうと、買主が購入後に隣接地の所有者とトラブルを起こす可能性が出てきます。
買主の立場に立てば、購入したあとで隣地との境界を巡って揉め事が起こるような土地の購入に踏み切れないでしょう。そのため、境界が確定していないと売却活動自体が難航することになりかねません。特に、長年放置された土地や、地方にある古い土地では、境界の位置があやふやなケースも多く見受けられます。売却を検討している土地がそのような状況であれば、まずは「境界測量図」などをもとに境界が確定しているかを確認してみましょう。
もし境界が確定していない場合は、近隣の所有者と立ち会って測量をおこない、境界を正式に定める「境界確定測量」の手続きを進める必要があります。
再建築が可能かを事前にチェックする
古家付きの土地を売却する際に確認しておくべき重要な点は、「再建築が可能な土地かどうか」です。建築基準法などの規定により、既存の建物を取り壊したあと、新たに住宅などを建てられない「再建築不可物件」であるケースも考えられます。
もし再建築不可物件であることを把握しないまま古家を解体してしまうと、買主にとっては新しい建物を建てられない土地となってしまい、需要が極端に下がる可能性が高まります。結果的に、売却が困難になる恐れも。
そのため、更地にする前に、その土地が再建築可能かどうかを確認しておくことが重要です。再建築の可否に関しては、土地が接する道路の種類や幅員などが関係しており、建築基準法上の「接道義務」を満たしていない場合には再建築不可となることもあります。
不安な場合は、所在地の市区町村の建築指導課や都市計画課などの担当窓口に問い合わせてみるとよいでしょう。売却を成功させるためにも、事前確認を怠らないようにしましょう。
古家付き土地の売却で使える3,000万円の特別控除
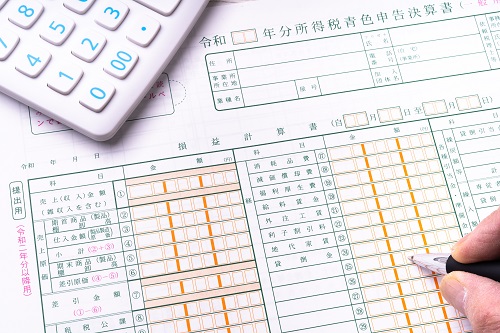
古家付きの土地を売却して利益が出ると、「譲渡所得税」が課税されます。しかし、この譲渡所得に対しては特別控除が用意されており、うまく活用することで大きな節税が可能です。
具体的には、「マイホームを売却した場合の3,000万円特別控除」と「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」の2種類があります。いずれも譲渡所得の計算時に最大3,000万円を差し引ける特例で、場合によっては譲渡所得税そのものが発生しないケースもめずらしくありません。
これらの特別控除は、それぞれ適用できる条件が異なります。「マイホームの控除」は、売却する建物が一定期間本人の居住用として使われていたことが条件です。
一方、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」は、親や祖父母などが住んでいた家を相続し、そのあとに売却する際に利用できる制度です。古家付きの土地を売る際にも、この控除を適用できる可能性も。例えば、古家を解体し、更地にしてから売却した場合でも、条件を満たしていれば控除の対象になることがあります。ただし、上記のケースでは、建物の取り壊し時期や売却時期、所有者の状況などに細かな要件が設定されています。
そのため、古家付きの土地を売却する際には、これらの特例が利用できるかどうかを事前に確認しておくことが重要です。不動産会社だけでなく、税理士など専門家の意見も取り入れながら進めることで、不要な税負担を避けられるでしょう。
まとめ
古家付き土地の売却には、「解体して更地にする」か「古家のまま売る」かの大きな選択がありますが、状況に応じてベストな方法は変わります。大切なのは、感情や先入観だけで判断せず、市場ニーズや専門家の意見を取り入れて判断することです。もし、どう進めていいかわからない場合は、不動産会社や土地活用の専門家に早めに相談することをおすすめします。少しの工夫と正しい知識が、あなたの土地売却を成功へ導いてくれるはずです。
物件を探す
注文住宅を建てる

執筆者
民辻 伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ






