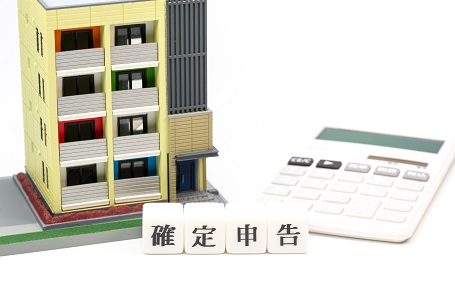マンション売却時の18の失敗事例と対策方法!売却の流れからわかりやすく紹介

この記事では、マンション売却時の18の失敗事例とそれぞれの対策方法を解説します。あわせてマンションを売却する流れから紹介し、順を追って失敗事例を押さえます。記事を読むことで、マンションの売却で失敗しないために必要なことがわかるようになるでしょう。
記事の目次
マンションの売却の流れ

マンションの売却は、相場調査など売却活動を始める前の準備段階から、売買契約を終えたあとの確定申告まで続きます。本章では、売却活動前・売却活動中・売却活動後の3つに分けて売却の流れを解説します。
売却活動前(相場調査・契約の締結)
マンションの売却を成功させるためには、売却活動を始める前の準備が重要です。この段階で適切な準備を済ませておくことで、その後の売却活動がスムーズに進み、結果的に高値での売却や早期成約につながります。
マンションの売却活動を開始するにあたって最初にやるべきことは、マンションの相場調査です。売却するマンションの適切な相場を理解したうえで、不動産会社の査定を受けることが基本になるでしょう。納得のいく価格を提示する信頼できる不動産会社を見つけた場合は媒介契約を締結します。
売却活動中(内覧の開始・買主との交渉)
不動産会社と媒介契約を締結すると、売却活動が開始します。広告を打ち出すなどの集客は不動産会社が代行するため、売主のやるべきことは希望者が現れるまでに内覧の準備を整えることです。内覧が始まる前に部屋を掃除し、落ちない汚れがある場合はハウスクリーニングの利用を検討しましょう。
内覧を通じて購入希望者が現れたら、価格や引き渡し時期の交渉をします。交渉がまとまり、売買契約が締結されれば、売却活動は終了します。
売却活動後(決済と引き渡し・確定申告)
売買契約が締結されたあとは、マンションの売却代金を受け取り、物件を手放す決済と引き渡しの段階に移ります。決済と引き渡しでは、売主・買主だけでなく不動産会社の担当者、必要な登記手続きをおこなう司法書士、住宅ローンを契約している金融機関の担当者も立ち会います。
売主は売却代金を受け取り、住宅ローンが残っている場合は完済したうえで、物件の書類と鍵を引き渡して完了です。マンションの売却益が出た場合は、確定申告で税金を納めなければなりません。税金の支払いが問題なく完了すれば、マンションの売却は終了したと考えられるでしょう。
マンションの売却活動前の失敗事例と対策方法

ここからは、マンションの売却前の失敗事例と、それぞれの対策方法について解説します。
余裕のある売却スケジュールを立てなかった
いつまでに売りたいのかを明確にしないまま売却活動を進めてしまい、スケジュールに間に合わずにトラブルになるケースもあります。具体的には、新居を先に購入して売却が遅れた結果、希望の時期までに売却できずに、前の住宅ローンと新しい住宅ローンの二重ローンの負担に悩まされることも。また、売却を急がざるをえなくなり、不動産会社の買取などを利用して、相場よりも安い価格で売却してしまうケースもあります。
マンションの売却には、通常3〜6カ月程度の時間がかかるのが一般的です。需要のある物件であれば短期間で売れることもありますが、売却に数カ月程度の時間を要することは珍しくありません。余裕のないスケジュールを組み、売却を急いだことで結果的に数百万円単位の損失につながる可能性もあります。
【対策方法】希望時期の半年前には売却活動を開始する
住み替えや転勤などを理由に、希望の売却時期がある場合は、遅くとも希望時期の半年前には売却活動をスタートするのが理想です。マンションの売却であれば余裕を持って1年程度の猶予を見込んでおくと、希望する条件で売却しやすくなります。
また、買い手が見つからなかった場合に備えて、不動産会社と媒介契約を結ぶ際に、買取保証を付けることもおすすめです。万が一、仲介による売却ができなかった場合でも、不動産会社が買取をしてくれるため、希望する時期までに確実に売却できます。スケジュールに余裕を持てば、売却を急ぐことによる失敗を防げます。
相場調査をしなかったため価格相場がわからない
マンションの売却を考える際に、最初におこなうべきことは相場調査です。しかし、十分な相場調査をせずに不動産会社の査定を受けると、査定価格が適切であるかどうかがわかりません。不動産会社の査定価格は、必ずしも相場に沿ったものではないことに注意が必要です。
不動産会社によっては、契約を取るために相場とはかけ離れた価格に設定する場合があります。高額な査定価格を適正価格と信じて契約すれば、時間をかけて売却活動をおこなってもマンションが売れません。査定価格を信じて相場調査を怠ると売却できない場合や、売却活動が長引く危険性があります。
【対策方法】複数の情報を参照して相場を把握する
マンション売却時の相場調査では、一つの不動産会社の査定を信じるのではなく、複数の情報を参照して相場を把握するようにしましょう。不動産会社に査定を依頼する場合は、必ず複数社に依頼します。インターネット上で一括査定を利用すれば、複数の不動産会社の査定価格を取得できるため、相場の把握に役立つでしょう。
不動産情報サイト アットホームの「不動産一括査定依頼サービス」では、マンションをはじめ、土地や一戸建てなどの査定を複数の会社に同時に依頼できます。
また、公的な情報からマンションの相場を調べる場合は、国土交通省が公開する「不動産情報ライブラリ」を利用します。同じエリア・築年数・間取りのマンションの実際の成約価格を確認できるため、相場の把握に便利です。相場調査を入念におこなうことで、価格相場がわからないことを理由に悪質な不動産会社と契約するリスクを抑えられるでしょう。
不動産会社の選び方を間違えてしまった
マンションの売却を成功させるためには、適切な不動産会社を選ぶことが重要です。間違った選び方の典型例は、一社のみに相談して比較検討しないことが挙げられます。他の不動産会社と比較しなければ、広告力の弱さや担当者の経験不足を見抜くことが難しくなります。
【対策方法】最低でも3社以上の不動産会社を比較検討する
比較検討する不動産会社の数は、最低でも3社以上にするとよいでしょう。単純に査定価格を比較するのではなく、不動産会社の販売実績や担当者の対応力にも注目しましょう。大手不動産会社は広告力やブランド力が強みですが、一部の不動産会社は特定の物件・エリアに特化した販売実績を持っている場合もあります。
また、担当者の対応力は、こちらの質問に丁寧に答えてくれるか、売却のリスクやデメリットも正直に説明してくれるかを重視して見極めます。不動産会社の選び方を間違えれば、売却が失敗に終わるリスクが高まるため、比較検討を前提に慎重に選ぶようにしましょう。
媒介契約の違いを知らずに契約した
マンションの売却の仲介を依頼する不動産会社と結ぶ媒介契約には、以下の種類があります。
| 契約形態 | 複数社への依頼 | 自己発見取引 | 活動報告義務 |
|---|---|---|---|
| 一般媒介契約 | 〇 | 〇 | 任意 |
| 専任媒介契約 | × | 〇 | 2週間に 1回以上 |
| 専属専任 媒介契約 |
× | × | 1週間に 1回以上 |
媒介契約は種類によって違いがあり、それぞれの違いを理解せずに契約すると、売却活動が進まなくなることも。例えば、一般媒介契約は複数社と契約できますが、専任媒介契約・専属専任媒介契約は1社のみしかできません。
また、自身でも売却先に心あたりがある場合は、専任媒介契約や一般媒介契約なら不動産会社の仲介を受けずに売主自身が買い手を見つける自己発見取引が可能です。一方で、専属専任媒介契約は自己発見取引が禁止されています。
【対策方法】媒介契約の特徴を理解して契約する
一度結んだ媒介契約は、契約期間の満了まで解消が難しくなります。よって、媒介契約の特徴を理解して契約するようにしましょう。一般媒介契約は複数の不動産会社に依頼できますが、活動報告義務がないため、契約した不動産会社が熱心に売却活動をおこなうとは限りません。需要の少ない物件の場合、積極的に広告をしなければ買い手を見つけることは難しいでしょう。
一方で、専任媒介契約・専属専任媒介契約は活動報告義務があるため、熱心に売却活動をおこなってくれる可能性が高いです。ただし、1社のみしか契約できないため、比較検討して信頼できる不動産会社を選ぶことが重要になります。
売却に必要な書類を用意していなかった
マンションの売却活動を始める前に、必要な書類が揃っていないことで手続きが滞り、スムーズに進まない失敗も考えられます。例えば、登記識別情報(権利証)をなくした場合は再発行ができません。
そのため、事前通知制度の利用や司法書士経由の本人確認など、事前の対処が必要になります。書類の不備や紛失に気付いたタイミングによっては、売却スケジュールに大きな影響を及ぼす可能性があります。
【対策方法】必要書類は早めに準備する
マンションの売却活動に必要な書類は、必ず事前に準備するようにしましょう。以下に必要な書類をまとめました。
- 登記識別情報(権利証)
- 購入時の売買契約書・重要事項説明書
- 住宅ローン残高証明書
- 固定資産税納税通知書
- マンションの管理規約・修繕積立金の明細
万が一、紛失していることが発覚した場合は、再発行ができる書類は再発行し、できない場合は個別に対処方法を考えます。早めに準備すれば、不備があった場合も慌てることなく対応できるため、売却を決断したタイミングから必要書類を集めるようにしましょう。
マンションの売却活動中の失敗事例と対策方法

次に、マンションの売却活動中の失敗事例をまとめました。それぞれ対策方法とあわせて詳しく解説します。
売り出し価格の設定が適切でなかった
マンションの売却で失敗する原因の多くが、売り出し価格の設定が適切でないことです。相場と比較して高過ぎる価格に設定すれば、買い手が見つかりにくいことは理解できるでしょう。しかし、相場に沿った価格であっても、マンションを売りたい金額で売り出すことも適切ではありません。
なぜなら、近年のマンションの売買は、値引き交渉を前提とする場合が多いからです。購入希望者から値引き交渉を求められ応じる場合は、売り出し価格から値引きしなくてはなりません。よって、売却を希望する価格よりも売り出し価格を少し高く設定し、値引きの余地を残さなければ、希望する売却価格で売却できない可能性があります。
【対策方法】専門家のアドバイスを踏まえて設定する
値引き交渉を前提に売却価格を高く設定する場合、相場とかけ離れた価格に設定しては買い手が見つからないため本末転倒です。よって、価格設定はバランスが重要になるため、媒介契約を結んだ不動産会社に相談し、専門家のアドバイスを踏まえることが重要です。自己判断で金額を上乗せするのではなく、プロの意見を取り入れることが適切な売り出し価格の設定につながるでしょう。
売却の時期を選ばなかった
マンションに限らず不動産の売買では、物件が売れやすい時期と売れにくい時期があります。一般的には、入学や就職を理由に環境が変わりやすい2月~3月の時期は需要が高まります。一方で、8月の真夏の時期は不動産の需要が落ちます。首都圏における2024年の中古マンションの月別成約件数を以下にまとめました。
| 2024年 | 成約件数 |
|---|---|
| 1月 | 2,711 |
| 2月 | 3,350 |
| 3月 | 3,810 |
| 4月 | 3,251 |
| 5月 | 2,845 |
| 6月 | 3,259 |
| 7月 | 3,193 |
| 8月 | 2,299 |
| 9月 | 3,047 |
| 10月 | 3,092 |
| 11月 | 3,207 |
| 12月 | 3,158 |
これを見ると、2月~3月に成約件数が増加して、4月~5月に減少していることがわかります。また、8月に成約件数が大きく下がり、9月から回復しています。つまり、2月~3月の需要の高い時期を逃して4月から売却する場合や、もっとも需要の低い8月から売却するケースでは売れるまで時間がかかりやすいでしょう。
【対策方法】需要が高まる時期にあわせて売却を開始する
不動産市場の成約件数の傾向を踏まえて、需要が高まる時期にあわせて売却を開始します。買主を見つけやすくなるため、希望した条件で売却しやすくなるでしょう。
もっとも成約件数が高い時期である2月~3月に合わせて、売却活動を開始するのが理想のタイミング。年度の後半であれば、8月から成約件数が大きく上昇する9月~10月の時期も狙い目です。売却スケジュールに余裕を持って、需要の高いシーズンを狙って売却を開始しましょう。
不動産会社にすべてを任せきりにした
不動産会社の活動報告を確認せず、売却活動を任せきりにして放置したことも、売却が失敗する原因になります。担当者は複数の売却物件を抱えていることから、状況次第では他の物件の売却活動を優先することも。不動産会社の売却活動が消極的になれば、売却期間が長期化する場合があります。
【対策方法】定期的に担当者とやり取りをおこなう
不動産会社に任せきりにせず、定期的に担当者と打ち合わせをおこない、販売活動の進捗を確認しましょう。物件の問い合わせ状況や、具体的な売却活動の内容を確認し、どのように売却するべきか一緒に考えることが重要になります。
不動産会社から囲い込みを受けてしまった
囲い込みとは、不動産会社が自社の利益を優先し、他社の顧客を排除して自社で買主を見つける行為です。囲い込みを受けると売却の機会が減り、成約が遅れる場合や価格が下がるリスクがあります。売主が知らないうちに、囲い込みがおこなわれているケースも少なくありません。
【対策方法】レインズ(不動産流通機構)の登録を確認する
囲い込みを避けるには、レインズ(不動産流通機構)の登録状況を確認し、公開されているかをチェックすることが有効です。信頼できる不動産会社であれば、レインズへの登録を証明する書類を送ってくれます。他社からの問い合わせがないことに疑問を感じた場合は、必ず確認するようにしましょう。
内覧に対する準備が十分でなかった
内覧に対する準備は、売主が積極的におこなう必要があります。掃除が不十分で生活感が残る場合や、汚れている印象を与えれば、購入意欲が下がることも。特に水回りの汚れを放置して購入希望者に不快感を与えるケースや、室内に悪臭が充満しているケースは、売却で致命的になりやすいです。購入希望者が現れても、内覧を理由に購入を見送られることがあれば、売却期間が長引く原因になります。
【対策方法】ハウスクリーニングの依頼を含めて徹底的に清掃する
内覧前には必ず部屋全体を清掃しましょう。玄関・リビング・水回りは購入希望者の目に留まりやすい場所であるため、重点的に整えます。不要な家具や荷物は整理し、室内をできるだけ広く見せる工夫も大切です。自身で掃除をしても落とせない汚れがある場合は、ハウスクリーニングの依頼が効果的。また、売却活動が始まれば、いつ内覧の希望が入るかわからないため、売却活動を始める前に清掃しておくことが重要です。
内覧対応で希望者の印象を悪化させた
内覧時の対応も、売却の成功を左右します。内覧時に物件の魅力を正しく伝えられなければ、購入希望者の興味が他の物件に流れてしまうかもしれません。質問に答えられないことが多いと、希望者の印象を悪化させる可能性があります。基本的に内覧対応は不動産会社の担当者がおこないますが、実際に住んでいる売主の意見を伝えると、購入の後押しになる可能性があります。
【対策方法】ネガティブな部分を含めて相手に伝える
内覧対応は誠実に対応することが重要です。物件の魅力を丁寧に説明するだけでなく、ネガティブな部分を含めて相手に伝えることが重要になります。意図的に不具合を隠そうとすると、契約が成立してからトラブルになることも。実際に住んだ方が話す物件の特徴と周辺環境は、購入希望者にとっても聞きたい話になるため、希望者の立場に立って伝えたい内容をまとめておきましょう。
自己判断でリフォーム・リノベーションをした
マンションを高く売りたいと考えた場合に、物件をキレイにすれば高く売れると考える方も多いです。そのため、リフォーム・リノベーションが売却に効果的と考えて自己判断でおこなってしまうケースがあります。しかし、リフォーム・リノベーションにかけた費用が、売却価格にすべて反映されるとは限りません。結果的にかけた費用を回収できずに赤字になってしまうことがあります。
【対策方法】不動産会社と相談してから判断する
マンションの売却時に大規模なリフォームは、基本的に不要です。ハウスクリーニングなど最低限のメンテナンス、簡単な補修にとどめるのが賢明になります。リフォーム・リノベーションを売却戦略に取り入れたい場合は、不動産会社に相談したうえで、費用対効果を判断するようにしましょう。
値下げ交渉に対する対応を間違えた
マンションの売却では、買主から値下げを要求される可能性が高いです。買主からの値下げ交渉に即座に応じてしまえば、想定以上に安い価格で売却してしまう可能性があります。反対に、一切応じない姿勢を見せると、買い手が離れてしまい売却の機会を逃すことも。値下げ交渉の対応を間違えると、マンション売却の失敗につながります。
【対策方法】最低限受け入れられる価格ラインを決める
マンションの売り出し価格は、希望の売却価格よりもやや高く設定し、希望の売却価格を下回らない範囲内で値下げ交渉に応じます。よって、値下げを最低限受け入れられる価格ラインを決めることが重要です。ただし、交渉の際には即答せず、不動産会社を通して冷静に検討する姿勢が必要になります。また、値下げの代わりに、引き渡し時期の調整や設備の譲渡など、条件面での譲歩で合意する方法も有効です。
買主の住宅ローンの審査が通らずに契約が破棄された
売買契約が成立したあとでも、契約が破棄されるリスクがあります。具体的には、買主の住宅ローンの審査が通らずに契約が解除されるケースです。通常、契約後に買主都合で契約解除される場合、違約金が支払われ、手付金も売主のものになります。
しかし、買主が住宅ローン特約を付けていた場合、住宅ローンの審査が通らないことを理由に契約を解除する時は、無条件で契約を破棄できます。この場合、違約金の支払い義務はなく、手付金も返還しなければなりません。代償のない契約破棄により時間だけが無駄になり、再び売却活動をやり直すことになります。
【対策方法】契約前に仮審査の通過を確認する
契約前に、買主が住宅ローンの仮審査を通過していることを確認しましょう。仮審査の通過を確認すれば、買主が住宅ローンの本審査に通過できないリスクを減らせます。
また、売買契約書を締結する際に、買主は住宅ローンの借入先の金融機関・融資条件を詳しく記載する必要があります。記載内容があまりにもいい加減で信用できない場合や、住宅ローン特約を意識した記載が売主にとって不利になりやすい内容である場合は、本当に契約するべきか再考したほうがいいでしょう。
マンションの売却活動後の失敗事例と対策方法

最後に、マンションの売却活動後の失敗事例と対策方法を紹介します
それぞれ対策方法を含めて詳しく見ていきましょう。
契約不適合責任で買主とトラブルになってしまった
マンションを売却したあとに発生する代表的なトラブルが、契約不適合責任です。売却した物件に隠れた欠陥があった場合に、売主が買主に対して責任を負います。「知らなかった」では済まされず、損害賠償に発展することも。
例えば、引き渡し後に給排水管の不具合、シロアリ被害などが発覚すると、買主から修繕費用の負担や契約解除を求められることも。マンションを高く売るために不具合を意図的に隠す行為は、契約不適合責任を負うリスクが高まります。買主との関係も悪化しやすいため、精神的な負担にもつながるでしょう。
【対策方法】不具合や問題を隠さずに報告する
契約不適合責任を避けるためには、売却前の段階で不具合や問題点を正直に開示することが基本です。小さな不具合であっても隠さず、重要事項説明書に記載するようにしましょう。また、物件の不具合を見逃さないために、インスペクション(建物状況調査)を実施することもおすすめです。
専門家が建物の状態を診断し、事前に欠陥を把握できれば、買主への説明責任を果たせるだけでなく、契約後のトラブル防止につながります。また、万が一、引き渡し後に住宅の不具合が見つかった場合に備えて、契約不適合責任保険への加入も有効です。保険金で修繕費をカバーできるため、売主のリスクを大幅に減らせるでしょう。
売却価格で住宅ローンを完済できなかった
売却するマンションに住宅ローンの残債がある場合、売却代金で住宅ローンを完済できます。しかし、ローン残債が売却価格を上回るオーバーローンである場合は、住宅ローンを完済できず、差額を自己資金で補う必要性が生じます。
例えば、住宅ローンの残債が3,000万円で売却価格が2,500万円の場合、500万円を自己資金で用意しなければなりません。結果的に、オーバーローンでマンションを売却したことで資金繰りが苦しくなります。
【対策方法】売却前に住宅ローンの残債を把握する
オーバーローンを避けるには、売却前に住宅ローンの正確な残債の把握が重要です。金融機関から残高証明書を取り寄せ、想定される売却価格と比較します。売却を急ぐ必要がない場合は、ローン残債が売却価格を下回るアンダーローンになったタイミングで売却するといいでしょう。
ただし、マンションの売却にはさまざまな費用がかかります。売却価格のみを比較する場合は、アンダーローンでも仲介手数料などの諸費用の支払いにより、自己負担が生じることも。住み替えを理由にマンションを売却する場合は、売却で残ったローンを新居のローンに組み込む住み替えローンの利用を金融機関に相談しましょう。
引き渡し後の引越しがうまくいかなかった
売買契約が成立し、引き渡し日が決まったものの、準備が間に合わずに引越しがうまくいかないケースもあります。引越しの際に荷物の搬出が遅れた場合、引き渡し日に買主へ物件を渡せず契約違反となることも。また、繁忙期に引越し会社を予約できず、予定通りのスケジュールで引越しできないこともあります。
【対策方法】引越し会社に早めに見積もりを取る
引き渡し後の引越しトラブルを防ぐには、スケジュールに余裕を持つことです。契約前の交渉段階で引き渡し時期を十分に検討し、引越し準備が間に合うようスケジュール調整が重要になります。引越し会社は3月~4月が繁忙期にあたるため、予約が取りにくい状態になり、料金が高騰します。繁忙期に引き渡し時期が重なった場合は、早めに見積もりを取ることが望ましいでしょう。
確定申告を適切におこなわずペナルティを受けた
マンションを売却して売却益が出た場合は、譲渡所得税・住民税を申告・納税する必要があります。具体的なタイミングは、売買契約が成立した翌年の確定申告時であり、原則2月16日~3月15日の期間内に申告します。しかし、期間内に申告を忘れた場合や、誤って申告すると、延滞税や加算税などのペナルティを課されます。
【対策方法】税理士への相談も検討して適切に申告する
マンション売却の確定申告は、経費計上をもれなくおこない、節税制度の利用をするといった適切な申告が必要です。3,000万円特別控除を利用すれば、マンションの売却益に税金がかからないケースもあります。ただし、3,000万円特別控除によって無税になる場合は、申告しなければなりません。
確定申告に対する知識が少なく、適切に申告する自信がない場合は、専門家である税理士に相談しましょう。税理士に依頼して申告するとミスを防げるだけでなく、自身が把握していない節税制度も適用して適切に申告してくれます。申告を怠ると追徴課税が発生するため、正確な申告を心がけるようにしましょう。
まとめ
マンションの売却は、準備段階から売却活動を開始し、確定申告を終えるまでに多くのステップがあります。その過程では思わぬ失敗につながるリスクが潜んでおり、売却の方法を間違えれば、売れずに時間を無駄にしてしまうケースや、相場よりも著しく安い価格で売却が成立してしまうケースも。
マンションの売却は人生で大きな決断であるからこそ、不安になりやすく、なんとしても失敗は避けたいところです。失敗事例ごとの対策を理解していれば、大きなトラブルを回避しながらスムーズに売却を進められるでしょう。
物件を探す
注文住宅を建てる

執筆者
長谷川 賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ