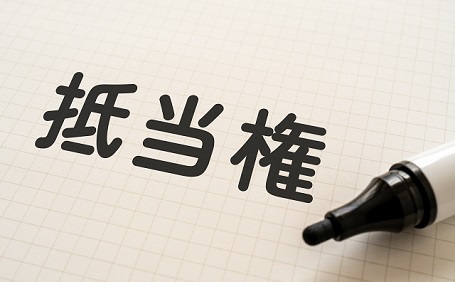測量費用はいくらかかる?相場と測量が必要なケース・依頼方法を解説

土地を売却する時は、諸費用として、不動産会社の仲介手数料や登記費用のほか、測量費用がかかることも。「測量ってどのようなことをするのか、よく知らない」、「そもそも、なぜ測量が必要なのか」、「どれくらいの費用がかかるのか」など測量は一般の方にはあまりなじみのない作業ですので、わからないことが多いのではないでしょうか。
この記事では、測量が必要となるケースから測量にかかる費用や流れ、できるだけ費用を抑える方法まで解説します。
土地を売却する際に測量が必要か、どれくらいの費用や準備期間を考えておけばよいか、紹介していくので、ぜひ最後までご一読ください。
記事の目次
測量の種類

測量には、「現況測量」と「(境界)確定測量」の2種類があります。それぞれ必要となる場面や作業内容が異なり、費用も違います。
現況測量
現況測量とは、現在の土地の状況を調査し、土地の形状や面積を算出する測量方法です。
境界標やブロック塀、道路、電柱などの現況を調査し、大まかに土地の現況を把握したものを図面にします。
一般的には10万~20万円が相場(土地30坪程度)です。建物を新築・増築する時や、土地売買で登記簿上の面積との違いを知りたい場合に活用されます。
(境界)確定測量
確定測量とは、隣接土地の所有者の立ち合いのもと、境界地点の確認、合意したうえで、土地の形状や面積を確定する測量のこと。現況測量と異なり、隣接の土地所有者との合意を含めて土地の状況を把握できるため、信頼性が高い測量方法です。
確定測量にかかる費用は、土地の状況や隣接土地所有者の数などで変わります。一般的には30万~50万円が相場です。
確定測量は、土地を売却する時や土地を分割する時などに必要となります。土地を売却する際に、買い主から隣地と境界線で合意した証明(境界確認書)を求められる場合があります。
他にも、土地を分割する際の分筆登記の申請にも境界確認書が必要です。
測量費用の相場と内訳
一般的には、現況測量の場合、10万~20万円、確定測量の場合30万~50万円の費用が目安ですが、次のような土地の状況によって金額は変わります。
- 隣接する土地所有者が多い
- 隣接所有者が国や市区町村の場合(官民査定が必要)
- 境界標が残っていない、資料が少ない
- 土地形状が複雑(境界点が多い) など
下の表では、確定測量でどのような作業をおこない、それぞれどれくらいの費用がかかるかまとめたので、ご覧ください。
測量費用の内訳
| 費用項目 | 作業内容 | 費用(概算) |
|---|---|---|
| 相談費用 | 土地家屋調査士に測量の相談 | 無料~5千円 |
| 事前調査費用 |
・登記事項証明書や公図、地積測量図などを入手
・隣接地の所有者の調査・測量前の現地調査 |
6万~10万円 |
| 測量業務費用 | ・現地測量 ・境界測量 (境界標の確認、仮境界杭の設置)
・確定測量(仮境界杭から永久杭に打ち換え)
|
10万~15万円 |
| 書類作成費用 | ・確定測量図作成 ・(官民境界等の)申請書類作成
・不動産調査報告書作成 |
3万~5万円 |
| 官民有地境界 確定費用 ※官有地と 接している場合 |
・官民有地境界の立ち合い
・官民有地境界協議・確定申請
・境界確認書の発行 |
7万~10万円 |
| 民有地境界 確定費用 |
・隣地所有者と境界確認の立ち合い
・境界確認書への署名・捺印 |
2万~3万円 |
| 登記費用 | ・登記の申請 ・登記完了証の発行 |
1万5千円 ~3万円 |
| その他 | 交通費等 | 実費 |
同じくらいの面積であっても、隣接する土地の所有者数や土地の広さ、形状などで、測量費用は大きく変わる可能性も。
また、依頼する測量会社によって費用が異なります。相見積もりをとって、作業内容や費用を比較するとよいでしょう。確定測量のみ実施したい場合、法務局に会社を紹介してもらえます。
測量が必要なケースは?
土地を所有している人すべてが、測量しなければならないわけではありません。ここでは、測量が必要となる6つのケースを解説します。
家を建てようとしている

家を新築あるいは増築する場合、測量が必要となる場合があります。
家を建てるとなると、その土地に建てられる広さの基準となる建ぺい率や容積率、道路からのセットバックなどの規制をクリアしなければなりません。そのために土地面積や境界点の情報が求められます。
また、土地の間口や奥行など敷地形状から、どのような建物が建てられるかを知るため、土地の高低差を知るために現況測量がおこなわれます。
抵当権を設定しようとしている
土地に抵当権を設定する場合、測量が必要となります。抵当権とは、住宅ローンなどの融資を受ける際に、その担保として金融機関が設定する権利です。
担保となる土地がどれだけの価値(評価額)であるかを確定させるために、確定測量が必要です。土地の一部に抵当権を設定したい場合も、土地の分筆登記が求められるため確定測量をおこなう必要があります。
相続税を物納しようとしている
土地がどれくらいの価値があるか評価するためには土地面積の情報が求められるため、確定測量が必要です。また、物納の手続き上、相続税の申告・納付期限までに地積測量図や境界線確認書を提出しなければなりません。
※参考:国税庁「延納・物納申請書」
土地が高額である
都心部や駅近の好立地の土地など、土地の評価額が高い場合、土地売買に際して確定測量を求められることも。
土地売買では、登記簿上の面積で取引する公簿取引や確定測量を入れないケースもありますが、土地が高額になると取引対象面積の違いが価格に大きく影響します。
高額な取引は測量費用の負担も吸収しやすいのが特徴です。確定測量をおこなって正確な土地面積が求められるでしょう。
分筆登記する時
相続した一筆の土地を相続人間で遺産分割する場合は分筆登記が必要です。また、土地の一部を売却したい、土地全体ではなく一部に抵当権を設定したい場合にも、分筆登記が必要となります。
※参考:不動産登記法│e-Gov法令検索
境界がわからない・測量後年月が経っている
隣接地との境界が不明、もしくは過去の測量からかなりの年月が経過している場合、確定測量をしておいたほうがよいでしょう。境界標やフェンス、ブロックなどの状況から境界がわからないと、土地の売却や相続税の納付が難しくなることも。また、隣接地との境界紛争のもととなる可能性もあります。
最後の測量から年月が経っていると、当時の測量の精度が高くないこともあり、「実際の土地面積と異なる」と土地売買時にトラブルへと発展するかもしれません。このようなトラブルを防ぐためにも確定測量が必要になります。
測量を依頼してから登記するまでの流れ

測量の作業内容や費用相場を解説しましたが、ここでは、測量の依頼から登記が完了するまでの流れを解説します。
土地家屋調査士に依頼
土地家屋調査士に測量の相談、見積もりを依頼します。
測量の目的をしっかりと伝えるとともに、土地の状況がわかるように、土地購入時の図面や登記関係資料などがあれば持参しましょう。かかる日数の目安は1~3日です。
土地家屋調査士と測量士の違い
土地家屋調査士と同様に、測量士も土地の測量を業務としておこないます。
測量士は公共工事も含めて測量するのに対し、土地家屋調査士は一般の土地所有者が主な依頼主です。
また、測量士は測量法に基づいて、土地の計測が主な業務であるのに対し、土地家屋調査士は、測量だけでなく、不動産登記法や民法も含めた、登記に関わる業務も対応できる点で異なります。
事前調査
依頼者との面談内容をもとに、土地家屋調査士は、法務局で最新の登記事項証明書や公図、地積測量図、隣接土地所有者の情報を入手したり、役所や道路管理者で必要書類を事前に調査したりします。また、測量前に現地調査をおこない、現地の状況を確認し、測量にどのような作業が必要となるか計画を立てます。
同時に、隣接所有者や行政の担当者に連絡をし、立ち合いの段取りを進めましょう。事前調査にかかる目安は1週間程度です。
現況測量
現地で測量をおこないます。事前に入手した資料と現地の状況を照らし合わせ、境界点を推定し、仮境界杭を設置します。調査した境界点と同じ場所に境界標が残っていれば、そこが境界とみなされます。
要する期間は1日~3日程度です。
境界立ち合い・確認
依頼主と隣接土地所有者、土地家屋調査士が現地で立ち合い、境界を確認します。
隣接地の所有者が少なければ1日で終わることもありますが、複数の所有者がいる場合、予定が合わなければ何日かにまたがることも。
官民境界の場合、役所に持ち帰ったあと、結果が出るまでに時間を要することに注意しましょう。
確定測量

すべての隣接地の所有者から合意を得られれば、仮境界杭を永久杭に打ちかえ、すべての境界点、境界線をもとに確定測量図を作成します。
合意事項として境界確認書(筆界確認書)に署名・捺印をもらい、依頼主、隣接土地所有者がそれぞれ1通保管します。期間の目安は、境界の立ち合い・確認を含め1程度、隣地所有者の数等によって、それ以上かかる場合があります。
登記を申請
最後に登記の申請をします。
登記上の面積と確定測量図の面積が異なる場合、土地家屋調査士に土地の地積更正登記を申請してもらい、登記上の面積と確定測量図の面積が一致することで完了となります。
測定費用を抑えるポイント
測量には一定の費用が必要ですが、この費用を抑えられるのでしょうか。5つのポイントを解説していきましょう。
不動産会社に直接買い取ってもらう
不動産会社に土地を買い取ってもらう場合、測量費用は必要ありません。土地を売る方法には「仲介」と「買取」があります。買取の場合、不動産会社が土地を買い取るため、仲介より売却金額は下がりますが、測量費用やリフォーム費用などをかけず、現状のままで売却します。
買主と交渉する
測量費用を買主と交渉する方法も費用を抑えるポイントの一つです。一般的には、売主には境界を明示する義務があり、測量費用を負担します。しかし、費用負担者は法律上決まっているわけではありません。
取引価格や他の取引条件などと合わせて、測量費用の一部もしくは全部を負担してもらえるよう買主と交渉できることもあります。
確定申告で費用計上する

確定申告で測量費用をしっかりと計上することで税金の負担を減らせることがあります。土地を売却し、譲渡利益が出た場合、発生するのが「譲渡所得税」と「住民税」です。
譲渡利益を算出するうえで、売却する際の測量費用は、売却のために支出した経費として控除対象となることがありますので、税金の負担を軽くすることができるでしょう。
隣地の所有者に売却する
隣接地の所有者に土地を購入してもらうことで、測量費用を抑えることができることも。
隣地所有者が、土地を買い増しして「2世帯住宅を建てたい」「駐車場や庭を広くしたい」と考えているようなケースが該当するでしょう。また、買い増しすることで土地全体の価値が大きく上がることもあります。
隣地所有者に売却する場合、確認する境界地点が減り、測量費用を削減することが可能です。また、敷地の状況や条件交渉によっては、測量費用の一部または全部を負担してもらえることもあります。
過去に測量を依頼したところに再度依頼する
法務局に備え付けられている測量図には、過去測量した土地家屋調査士が記載されています。同じ土地家屋調査士に依頼することで、過去のデータを活用すると、測量費用を抑えられる場合があります。
測量費用についてよくある質問

最後に、測量費用のよくある質問を紹介します。
測量費用はどのくらいかかる?
現況測量と確定測量で費用は異なります。
測量する土地や隣接地の状況によって変わりますが、現況測量で10万~20万円、確定測量で35万~50万円程度が目安です。
ただし、確定測量は、個々の状況によって費用が変わる可能性があります。
測量費用は売主・買主どちらが負担する?
土地売買の測量費用は一般的に売主の負担となります。ただし、どちらが負担するかが法律上決まっているわけではありませんので、買主との交渉も可能。
また、土地価格が安い、測量に要する期間が長いなど、状況によっては測量せず取引することもあるでしょう。
測量費用を安く抑えることはできる?
不動産会社に買い取ってもらったり、買主と交渉したりすることで、測量費用を抑えられる場合があります。
ただし、測量費を抑えるために、売却価格がそれ以上に下がることは本末転倒です。土地の売却価格や売れやすさ(需要)を踏まえて売却の仕方を考えましょう。
測量を測量士に依頼してもいい?
測量する目的は、土地の広さを正確に把握するためだけでなく、隣接地との境界を明確にし、隣地との境界紛争を防止することにあります。
そのため、測量は土地の境界を明示する業務の専門家である土地家屋調査士に依頼しましょう。
まとめ
測量は、土地を売却したり、新たに建物を新築したりする際に必要となります。その費用は、一般的な相場として、現況測量では10万~20万円、確定測量は35万円~50万円です。ただし、土地や隣地の状況によって、費用は大きく変わる可能性もあります。
下記のような事情があると、時間がかかりやすく、土地家屋調査士の業務も増えるため、測量費も高くなる点には注意をしましょう。
- 隣接する土地が多い(同意をえる相手が多い)
- 土地の形状が複雑・広い
- 公有地と隣接している
- 境界があいまい、隣地所有者と合意が難しい など
土地の売却で測量が必要となる場合、測量費を抑える方法も含め、ぜひ参考にしてください。
物件を探す