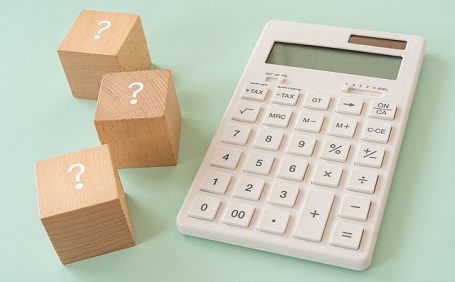実家じまいとは?費用から手順、補助制度・税金控除まで徹底解説

この記事では、実家じまいを始めるタイミングや費用、手順の他、実家じまいで活用できる自治体の補助制度や税金の控除をわかりやすく解説します。
記事の目次
実家じまいとは?

実家じまいとは、親や祖父母が住んでいた自分の実家を整理して処分する一連の手続きのことです。
昨今、仕事や結婚などの関係で親と離れて暮らす子どもが多く、日常的には実家に戻らないケースも珍しくありません。そのため、親が亡くなったり、施設に入居したりして実家に誰も住まなくなると、実家を処分するかどうかを決断する必要が出てきます。
実家じまいが増えている理由

最近は、実家じまいを考える人が増えているようです。なぜ実家を処分しようと考える人が増えているのでしょうか。その理由を見ていきましょう。
高齢者社会の進展
日本は高齢化社会が進んでいます。人口のなかで高齢者が占める割合は、29.1%と過去最高を記録しました。一方で子世代の少子化・核家族化も進んでおり、実家を維持管理できる人が少なくなっています。団塊の世代も後期高齢者に入った昨今、介護サービスを受けるために施設へ入居する人が増えたり、残念ながら、亡くなる人もいらっしゃいます。その結果、実家が空き家になり、実家じまいせざるをえない状況となっています。
出典:統計局「統計からみた我が国の高齢者」
相続登記の義務化
実家じまいが増えているもう一つの理由は、相続登記の義務化です。
誰も住まない実家が増えることで、空き家問題にもつながります。空き家が放置されることで、周辺環境の悪化や防犯上のリスクが高まることが問題視されてきました。また、これまでは相続時の名義変更が任意となっていたことから、所有者不明の土地が増加の一途をたどっていました。
そこで2024年4月1日から、相続により土地や家屋を取得した場合、3年以内に相続登記をおこなうことが義務化されるようになりました。
また、相続登記の義務化が始まる前に相続した不動産も対象となり、期間内に相続登記の申請をおこなわなければペナルティとして10万円以下の過料が課される可能性があります。
実家を引き継ぐことで維持管理の負担が生じ、なおかつ税金面の負担も発生することから、実家じまいを考える人が増えています。
出典:東京法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地 !~」
実家じまいのタイミング

実家じまいは、どのようなタイミングでおこなうのがよいのでしょうか。ここでは、実家じまいをするのに最適なタイミングを解説します。
相続が発生した時
親が亡くなり、実家を相続した時は、実家じまいをするタイミングです。相続人は、実家に住んでいなくても固定資産税を支払っていかなければなりません。また、実家を適切に維持管理する負担も発生します。実家に住む予定がない場合、あらゆる負担をなくすため、相続の発生は実家じまいに着手するよい機会になります。
親が施設入居・長期入院をする時
介護が必要になった親が施設に入居したり、長期入院したりする時も、実家じまいをするタイミングです。親の介護の度合いや健康状態にもよりますが、実家に戻る可能性が低い場合は、実家じまいを考えてもよいでしょう。
実家の維持管理を負担に感じた時
家の維持管理を負担に感じるようになった時は、実家じまいに着手するよいタイミングになります。自宅を維持しながら、離れた実家も維持管理していくのは、精神的にも経済的にも重荷になりがちです。維持管理に必要な経費や固定資産税の負担、ときどき実家に足を運ぶための交通費の負担を考えると、実家じまいにより負担をなくすことを考えてもよいでしょう。
実家じまいにかかる費用

実家じまいをする際、あらゆる面で費用の負担が発生します。おもにどのような費用がかかるのか解説します。
不用品処分費用
実家じまいをするには、実家にある不用な荷物を処分する必要があります。家一軒分の荷物を個人で処分するのは負担が大きすぎるので、不用品回収の専門会社に依頼するとよいでしょう。
総務省が2020年3月に公表した「遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査結果報告書」によると、遺品整理サービスに支払った費用の平均は約30万円との結果が出ています。実際にはサービスの内容や不用品の量、立地条件、部屋数によっても費用は異なり、場合によってはさらに高額になるかもしれません。
不動産売却費用
実家を売却する際には、売却の手続きに必要な費用がかかります。おもな費用は、仲介手数料、印紙代、抵当権抹消費用、譲渡所得税(譲渡益が発生した場合)などです。
仲介手数料の上限額は、法律で下記のように定められています。
仲介手数料(※売買価格が400万円超の場合)=売買価格×3%+6万円+消費税
ただし、2024年7月より空き家等に係る媒介報酬規制の見直しにより、売買価格が800万円以下の場合、仲介手数料の上限は30万円(税抜)になりました。
印紙代は売買契約書に記載されている金額により異なりますが、1万~3万円程度。抵当権抹消費用は不動産1件あたり1,000円ですが、司法書士に依頼する場合は、目安として1.5万~2万円程度かかります。
実家の解体費用
次は実家の解体費用です。立地条件によっては実家を解体して更地にしたほうが売却しやすいケースがあります。また、実家の老朽化が進んでいる場合も解体を検討するタイミングです。
実家を解体する際の費用相場は、立地条件や規模、構造などにより異なり、1坪あたりの目安は以下のようになります。
- 木造:4万~5万円
- 鉄骨造:6万~7万円
- 鉄筋コンクリート造:7万~8万円
引越し費用
親が実家に住んでいるタイミングで、実家を手放す場合、引越し費用が発生します。かかる費用は荷物の量や転居先までの距離、引越し会社により異なります。引越しの会社を決める時は、複数の会社から見積りを取り、よく検討して決めましょう。
税理士や司法書士など専門家への依頼費用
実家じまいでは税務面や法律面で複雑な手続きが多いので、税理士や司法書士などの専門家に依頼してサポートを受けるのもよいでしょう。税金に関しては税理士、登記関連は司法書士が専門になります。費用は依頼する事務所により異なるので、信頼できる専門家を探し、相談してみましょう。
実家じまいの手順

実家じまいは家族の思い出が詰まった家を処分するので、家族がそれぞれに抱える感情も絡みやすくなります。家族間のトラブルを避け、効率よく進めるためにも、適切な手順に沿って実家じまいをおこないましょう。
実家じまいにかかる期間は、3カ月~6カ月が目安ですが、売却する時は、場合により1年程度かかるかもしれません。
ここでは、実家じまいの具体的な手順をご紹介します。
家族・親族間で話し合いをする
家族や親族間のトラブルを避けるには、早いうちから実家の処分方法を話し合うことが重要です。実家の選択肢としては、売却、賃貸、解体、家族が住むなどの方法が考えられます。親の意見だけでなく、兄弟姉妹の意見もすり合わせて、最適な方法を検討しましょう。
親の住み替え先を決める
親が健在なうちに実家じまいをおこなう場合、親の住み替え先を決めます、住み替え先は選択肢があります。
- 子どもと同居する
- 有料老人ホームや介護施設に入居する
- サービス付き高齢者向け住宅に入居する
- 賃貸住宅に住む
住み替え先に有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を選ぶ際は、いくつかの施設を見学して担当者に話を聞くことをおすすめします。介護施設への入居を希望するなら、地域包括支援センターに相談しましょう。
親の経済状況や健康状態、介護の有無などを考慮して、最適な住み替え先を決めましょう。
家財道具を整理する
実家じまいをする際は、実家にある家財道具を整理する必要があります。残しておきたいもの、リサイクルするもの、人に譲るもの、処分するものに分けて整理しておきましょう。
片付け・不用品処分をする
次は片付け・不用品処分です。実家にある荷物のなかで、残しておきたいものを取り分けましょう。リサイクルの手続きをしたり、欲しい人に譲ったりして、不要なものを減らしていきます。最後に残ったものは不用品として処分します。
実家の不用品を個人で処分するのは労力と時間が必要です。特に思い入れがあるものなどは処分が心苦しく思えたり、時間がかかってしまうことも。効率よく処分するには、専門会社へ依頼するのがよいでしょう。あくまでも目安になりますが、一戸建て住宅の場合、専門会社に作業を依頼すると1日~3日で片付けをしてもらえます。
売却・解体など手放す方法を選ぶ
実家を手放し、賃貸にも出さない時は売却することになります。その際、土地と家を一緒に売却するか、更地にして土地だけを売却するか、どちらの方法にするか決めましょう。更地にして売却する時は、家の解体を依頼する必要があります。
処分の手続きを進める
実家の処分方法を決めたら、必要な手続きを進めましょう。
実家を売却する場合は不動産会社に依頼します。また、荷物の処分を専門会社へ依頼するなら、複数の会社へ見積りを依頼して決めましょう。
実家を処分する際には法的な手続きや書類が必要になるため、税理士や司法書士などの専門家のサポートを受けながら進めるとスムーズです。

- 不動産売却はどこがいい?会社選びのポイントや大手と中小の違いを解説
- みなさんは所有している不動産を売却したいと考えた時に、誰に相談しますか?名の通った大手の不動産会社か、それとも街の小さな
続きを読む

実家じまいで活用できる補助制度・税金控除
自治体のなかには、実家じまいの時に活用できる補助制度を実施しているところがあります。実家の所在地で補助制度をおこなっていないか自治体のホームページなどで事前に確認しましょう。また、実家を売却して譲渡所得税がかかる時に利用できる特別控除もあります。
補助制度や税金控除を活用して負担を抑えながら実家じまいを進めましょう。
自治体ごとにおこなわれている空き家の解体に関する補助金
実家が空き家になり解体する場合、活用できる自治体がおこなっている補助金制度をご紹介します。
東京都空き家家財整理・解体促進事業|東京都
東京都では、空き家状態の早期解決や空き家の利活用を推進するため、都内にある空き家の家財整理や解体費用の一部を補助する制度を実施しています。
○補助金額
【都内にある空き家の家財整理の場合】
「東京都空き家ワンストップ相談窓口」で相談すると、空き家の家財整理費用の2分の1(限度額5万円)補助
【都内にある空き家を解体する場合】
解体費用の2分の1(限度額10万円)を補助
出典:東京都「東京都空き家家財整理・解体促進事業」
老朽危険家屋除却費等助成制度|東京都墨田区
東京都墨田区では、区内にある老朽危険家屋の倒壊事故や火事を防ぐため、法律で規定された「不良住宅」に該当する家屋の除去費用の一部を助成しています。
○助成金額
除去工事費の2分の1(上限50万円)
※無接道敷地にある不良住宅の場合は上限100万円
出典:墨田区「老朽危険家屋除却費等助成制度」
空家等解体費補助金|栃木県矢板市
栃木県矢板市では、老朽化・経年化した空き家の倒壊や崩落により周辺住民に重大な被害が及ぶのを避けるため、危険性の高い空き家を解体すると解体工事費の一部を補助しています。
○補助金額
解体費用の2分の1
※矢板駅西地区の用途地域内の場合:上限60万円
※その他の地域:上限50万円
出典:矢板市「空家等解体費補助金」
浜松市空き家解体補助金|静岡県浜松市
静岡県浜松市では、老朽化した危険な空き家の増加を抑制するため、要件を満たした物件の除去費用の一部を補助しています。
○補助金額
解体費用の3分の1(最大50万円)
出典:浜松市「浜松市空き家解体補助金(浜松市空家等除却促進事業費補助金)」
老朽危険空家解体事業補助金|長野県上田市
長野県上田市では、空き家を解消し、安全で安心な暮らしを確保し、居住環境の改善を図るため、1年以上使用されていない木造の一戸建て住宅の解体工事費の一部を補助しています。
○補助金額
解体工事費の2分の1(限度額50万円)
出典:上田市「老朽危険空家解体 利活用事業補助金について」
大洲市危険空き家除却事業補助金|愛媛県大洲市
愛媛県大洲市では、老朽化した危険な空き家の倒壊による被害を防止し、災害発生時に避難経路を塞ぐことがないよう、要件を満たした危険空き家の除去工事の一部を補助しています。
○補助金額
下記(1)(2)のうち、いずれか少ない金額(補助上限額:80万円)
(1)補助対象経費の10分の8以内
(2)国土交通省が定める標準建設費の除却工事費の10分の8以内
出典:大洲市「危険空き家の除却費用の一部を補助します」
要件や申請の流れなど詳細については、各自治体のホームページや窓口にてご確認くださ
空き家バンクの補助制度
空き家バンクとは空き家情報を提供するしくみで、自治体が運営し、家を買いたい人と売りたい人をつなぐ制度です。自治体のなかには、空き家バンクに登録された空き家に対する補助制度を実施しているところがあります。
今回は、2つの自治体で実施している空き家バンクの補助制度をご紹介します。
千葉県富津市「空家バンク登録支援・利用者支援補助金」
「空家バンク登録支援・利用者支援補助金」は、空家バンクに登録する予定の人や登録された空家に引越しをする人を対象にした補助金制度です。家財整理や登記手続き、仲介手数料、引越し作業にかかった経費の一部を補助しています。
〇補助金額
補助対象経費の2分の1以内(上限10万円)
出典:富津市「空家バンクへの登録・利用にかかる費用の補助」
栃木県栃木市 空き家バンクリフォーム補助
空き家バンクリフォーム補助は、空き家バンクに登録された空き家の所有者と購入者が利用できる制度で、リフォーム工事と家財処分費用の一部を補助するものです。
〇補助金額
リフォーム工事費の2分の1(限度額50万円)
住居内の家財処分費用(限度額10万円)
出典:栃木市空き家バンク あったか住まいるバンク「補助金について」
要件や申請の流れなど詳細については、各自治体のホームページや窓口にてご確認ください。
相続空き家の3,000万円特別控除
相続や遺贈で取得した被相続人が所有していた居住用家屋と敷地(空き家)を2027(令和9)年12月31日までに売却し、一定の要件に当てはまる場合、譲渡所得金額から最高3,000万円までの控除ができます。
被相続人が所有していた居住用家屋は、以下のものが対象となります。
- 1981(昭和56)年5月31日以前に建築された家屋であること
- 区分所有建物登記がされていない建物であること
- 相続開始直前に、被相続人以外に居住していた人がいないこと
また、売却代金が1億円を超える時は、この特例は利用できないので注意が必要です。
特例のくわしい内容や手続きは国税庁のWebサイトにてご確認ください。
出典:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
実家じまいをする時のポイント

実家じまいをスムーズに進めるには、どのような点に留意する必要があるのでしょうか。実家じまいをする時の5つのポイントをご紹介します。
家族で実家の処分について方向性を決めておく
家族間のトラブルを避けるためにも、実家の処分方法は早い段階から家族と十分に話し合い、方向性を決めておくことが重要です。親の希望を聞き、兄弟姉妹それぞれの希望をすり合わせて、最適な方法を検討しましょう。
相続法や不動産登記法の法律を理解する
実家じまいでは、相続や登記など法律に関する手続きが発生します。一連の手続きは、法律でどのように定められているのかあらかじめ理解しておきましょう。
かかる税金を把握する
実家を引き継ぐと、固定資産税の支払いが発生します。また、実家を売却して譲渡益が出た時は譲渡所得税が発生します。
さらに、親が亡くなった時は相続税が発生する場合があります。実家じまいをするうえで、どのような税金が発生するのかを把握しておくことはとても重要です。
住宅購入時の契約書・領収書がないと譲渡所得税が高額になる可能性がある
実家を売却して譲渡益が出た場合、譲渡所得税が発生します。ただ、譲渡所得税を計算する時は、売買価格から実家の購入価格や登記費用や印紙代など売却するのに直接かかった費用を差し引くことが可能です。
購入価格を確認するには、購入時の契約書や領収書があればよいのですが、紛失して確認できない時は、売買価格の5%相当額を実家の取得費として計算することになります。そのため、場合によっては譲渡所得税が高額になる可能性がある点は留意しておきましょう。
売却できない時の対処法を検討しておく
実家を売却したいと考えていても、立地条件が悪かったり、築年数が古かったりする時は、売却できないことがあるかもしれません。売却が難しくなりそうな時は対処法も考えておきましょう。
例えば、リフォームをする、更地にして売却する、賃貸物件として貸し出すなどの対処法があります。
遺品整理の計画をする
親が亡くなった場合、遺品整理は計画的におこないましょう。相続税は、亡くなったことを知った翌日から10カ月以内に申告手続きをしなければなりません。
遺品のなかには相続税の対象となる財産が含まれている場合もあります。相続財産や形見分けをするもの、不用品などをピックアップし、申告期限までに余裕を持って計画的に整理しましょう。
まとめ
実家じまいについて押さえておきたいポイントを3つピックアップしました。内容を確認しておきましょう。
実家じまいとは?
親が住んでいた自分の実家を整理して処分する一連の手続きのことです。
実家じまいのタイミングは?
親が亡くなり相続が発生した時や親が介護施設に入居する時、実家の維持管理を負担に感じるようになった時が、実家じまいをするタイミングになるでしょう。
実家じまいにかかる費用はどれくらい?
実家じまいをする際にかかる費用のなかで、高額になりやすいものといえば、実家の不用品を処分する費用です。不用品回収の専門会社に依頼した場合の平均額は約30万円といわれていますが、不用品の量や部屋数、立地条件によって、かかる費用も異なるため、事前に見積もりを取って具体的な金額を確認しましょう。
実家を解体して更地にする場合、解体費用として木造では1坪あたり4万~5万円程度かかります。
また、売却する際には、不動産会社に支払う仲介手数料もかかるでしょう。仲介手数料の上限は、売買価格が400万円超の場合、「売買価格×3%+6万円+消費税」。他にも印紙代や抵当権抹消費用も必要です。
さまざまな費用が実家じまいには必要なため、税金の特別控除や解体費用に活用できる自治体の補助制度などを活用しましょう。
思い出の残る実家の処分は、精神的な負担がともなうことがあるかもしれません。しかし、その後の維持管理や経済的負担を考えると、人生で大事なプロセスになるでしょう。
今回ご紹介した実家じまいのタイミングや費用、手順などを参考に、親や兄弟姉妹と十分に話し合い、実家じまいを計画的に進めていきましょう。
物件を探す
注文住宅を建てる