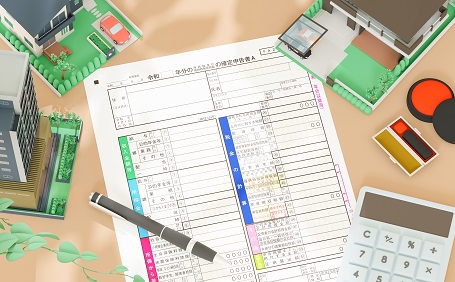譲渡所得の内訳書とは?書類の入手方法や書き方を紹介

この記事では、譲渡所得の内訳書の概要と、書類の入手方法・書き方・書類提出前に知っておきたい注意点を解説します。記事を読めば、譲渡所得の内訳書の書き方から提出方法までがわかるため、ぜひご一読ください。
記事の目次
譲渡所得の内訳書とは

譲渡所得の内訳書とは、所有する土地や建物を売却し、確定申告をおこなう際に提出する書類です。不動産を売却して利益を得た時は、売却益にかかる譲渡所得税を支払わなければなりません。売却益から経費を差し引き、課税価格をチェックできるのが譲渡所得の内訳書です。
譲渡所得の内訳書は、給与所得や事業所得とは別に作成する必要があります。会社勤めの方は給与所得の調整を年末調整でおこなうため、確定申告の時に譲渡所得の内訳書を作成して提出しましょう。個人事業主の方は、事業所得の確定申告書とは別に、譲渡所得の内訳書を作成して提出します。
譲渡所得の内訳書の入手方法と書き方

譲渡所得の内訳書をはじめて作成する方は、記載する書類やフォーマットをどこで入手できるのか、どのように記入すればいいのかがわからないかと思います。事前に確認しておけば、書類作成時期に慌てることもないため、確定申告が始まる前にチェックしておきましょう。ここでは、書類の入手方法と書き方を解説します。
譲渡所得の内訳書の入手方法
譲渡所得の内訳書の様式やフォーマットの入手方法には、国税庁と税務署の2種類があります。それぞれでメリットが異なるため、自分に合う方法を選ぶことが大切です。
| 入手先 | 入手方法 | メリット |
|---|---|---|
| 国税庁 | 国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」から必要書類をダウンロード | 自宅で手軽に書類を作成できる |
| 税務署 | 税務署窓口で書類を受け取る | 不明点を職員に相談しながら作成できる |
書き方をある程度把握している、またはインターネットで書き方を調べながら作成できる方には国税庁からの入手がおすすめです。必要書類をダウンロードし、印刷して記入すれば必要書類を用意できます。
調べても不明点がいくつもあり、自分で作成できる自信がない方は税務署窓口から入手しましょう。窓口で受け取れば、不明点を職員に相談できます。書類作成に必要な情報を持参すれば、その場で書類を作成できるため、不備のない譲渡所得の内訳書を手に入れられるでしょう。
譲渡所得の内訳書は総合譲渡用と分離課税用がある
譲渡所得の内訳書には総合譲渡用と分離課税用があり、売却したものに応じてどちらかを把握しなければなりません。売却したもの別の分類先をまとめました。
| 種類 | 分離課税 |
|---|---|
| 総合譲渡 | ゴルフ会員権 下記の分離課税に該当されない資産 |
| 分離課税 | 土地や建物 短期所有地の譲渡 株式 |
不動産を売却した場合は、分離課税に該当します。もし分離課税に該当しない場合は総合譲渡に分類されますが、不安な方は税務署に相談することがおすすめです。総合譲渡と分離課税はそれぞれで書類が用意されているため、売却する資産に応じて書類を用意しましょう。
確定申告書等作成コーナーでも作成可能
譲渡所得の内訳書は国税庁のWebサイト「確定申告書等作成コーナー」で作成できるため、確定申告書と一緒に作っておきましょう。譲渡所得の内訳書の作成の流れは以下のとおりです。
- STEP 1「作成する申告書等の選択」で所得税を選択
- STEP 2生年月日と申告書の提出方法を選択
- STEP 3「収入金額・所得金額の入力」で「土地建物等の譲渡所得」を選択
- STEP 4「土地建物等の譲渡所得」で内訳書作成を選択
- STEP 5表示される譲渡内容に該当する項目をチェック
- STEP 6売却した不動産の住所や売却金額などを入力
- STEP 7売却するために支払った費用を入力
- STEP 8取得費の計算に必要な項目を入力
- STEP 9適用する特例を選択
- STEP 10入力内容の確認
書類の作成にはさまざまな情報が必要なため、事前に確認しておきましょう。必要な情報を集めておけば、作成もスムーズに進みます。確定申告期間中であれば、国税庁のWebサイト「確定申告書等作成コーナー」は24時間利用できるため、空いた時間を活用して作るとよいでしょう。
内訳書の書き方
譲渡所得の内訳書は1~5面まであり、4・5面は特別控除を受ける際に記入する必要があります。1~3面までは誰もが記載しなければならないため、書くべき内容をよく確認してください。
| 書類 | 記入項目 |
|---|---|
| 1面 | 氏名・現住所・電話番号・職業を記載 (不動産を売却した年の1月1日以降に引越した場合は、前住んでいた住所も記載) |
| 2面 | 売却した不動産の下記の情報を記載
・所在地(所在地番、住居表示)
・どのような物件であるか
・利用状況
・売却日(不動産売買契約書の締結年月日)と引き渡し日
・買主の情報(住所、氏名、職業)
・売却価格(売却した際の総額)
・参考事項など
|
| 3面 |
・売却した不動産の購入金額
・減価償却費
(減価償却費=建物の取得価額×0.9×償却率×経過年数で算出)
・取得費
(取得価額から減価償却相当額を控除した金額)
・譲渡費用
(契約書印紙税・仲介手数料・測量費など売却に要した費用の総額)
・譲渡所得金額
(譲渡所得金額=譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除で算出)
などを記載 |
| 4面 | 買換え特例を希望する場合に記載 |
| 5面 | 相続や遺贈によって受け取った不動産を売却する場合に記載 |
細かな記載例は「国税庁の資料(PDF)」を確認しましょう。
2・3面は記載項目が多いため、漏れのないよう注意しましょう。特に3面は、税額を決定するために重要な項目が多く含まれています。情報に誤りがあると、納税額が足りなかったり、多く支払いすぎたりするかもしれません。不備がないように記載しましょう。
4・5面は、売却にあたって特例を受ける方が記載します。4面は不動産売却後に居住用不動産を購入する方を対象とした「特定のマイホームを買い換えた時の特例」、5面は相続や遺贈によって受け取った不動産を売却した方を対象とした「被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例」です。
いずれかに該当する方は、1~3面に加え、希望する特例の書類も記載して提出しましょう。
確定申告に必要な書類と申請方法

確定申告に必要なのは、譲渡所得の内訳書のみではありません。その他にも用意すべき書類があるため、不備のないよう注意しましょう。ここでは、はじめて確定申告をおこなう方に知っておいてほしい、確定申告に必要な書類と手続きの流れを解説します。
確定申告に必要な書類
確定申告に必要な書類は以下のとおりです。
- 確定申告書
- 譲渡所得の内訳書
- 申告書第三表(分離課税用)
- 不動産を購入した時と売却した時の売買契約書のコピー
- 譲渡費用と取得費用を証明する領収書のコピー
- 登記事項証明書
- 本人確認書類
- 源泉徴収票
「確定申告書」・「譲渡所得の内訳書」・「申告書第三表」のフォーマットは、国税庁のWebサイトから入手できます。申告書第三表は「総合譲渡用」と「分離課税用」にわかれているため、不動産売却での確定申告の場合は「分離課税用」を使用するように注意しましょう。
「売買契約書」、「譲渡費用と取得費用を証明する領収書」は、手元に保管しているかと思います。原本を提出する必要はないため、それぞれをコピーしておきましょう。
本人確認書類は、運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きのものが望ましいとされています。顔写真が付きの書類を用意できない場合は、身元を証明する書類を2つ以上提出しなければなりません。保険証や源泉徴収票、公共料金の領収書、印鑑登録証明書などのコピーを用意しましょう。
給与所得者の方は、源泉徴収票を用意する必要があります。書類を提出する必要はありませんが、収入金額や源泉徴収金額を記載しなければならないため、手元に用意しておきましょう。
確定申告の手続きの流れ
確定申告は、以下の流れでおこないます。
- STEP 1必要書類の用意
- STEP 2譲渡所得と所得税額の算出
- STEP 3確定申告書の作成
- STEP 4書類の提出
まずは申告に必要な書類をすべて用意しましょう。確定申告書・譲渡所得の内訳書・申告書第三表(分離課税用)はのちほど作成するため、先にほかの書類を用意するとスムーズです。
続いて、譲渡所得と所得税額の算出をおこないます。譲渡所得は売却価格-(取得費+譲渡費用)で算出できるため、それぞれの金額を確認したうえで計算しましょう。売却する不動産の所有期間が5年以上の場合は譲渡所得額×15%、5年以下の場合は譲渡所得額×30%で所得税額を算出できます。
続いて、国税庁のWebサイト「確定申告書等作成コーナー」から確定申告書・譲渡所得の内訳書・申告書第三表(分離課税用)を作成しましょう。毎年1月ごろから確定申告書作成コーナーが利用できるため、活用することがおすすめです。
書類をすべて作成し終えたら、2月16日~3月15日までに申告手続きをおこないます。書類すべてを電子化できるのであればe-Taxで、難しい場合は税務署窓口に行き、書類を提出しましょう。
譲渡所得の内訳書に関する注意点

譲渡所得の内訳書を作成するにあたって、気を付けておきたいことを解説します。
売却によって損をしても内訳書は提出した方がいい
不動産の売却によって損が出ても、確定申告の手続きは済ませておくことがおすすめです。不動産を売却した際の金額よりも、購入費のほうが多ければ「譲渡損失」になります。利益を全く得られなかった場合は確定申告の必要がないものの、税務署からお尋ねがくる可能性があります。
税務署は、不動産売買がおこなわれたことを把握していても、内容の詳細までは知りません。そのため、確定申告をしていないことがわかれば、不動産売買で本当に譲渡損失が発生したのかを確認します。本当に損失が発生しても、税務署に尋ねられれば不安を覚えるでしょう。確定申告を済ませておけば税務署から調査が入ることもないため、念のため手続きを済ませておくと安心でしょう。
売却益がある場合は無申告に注意する
売却によって利益を得た場合は、必ず確定申告をおこないましょう。売却によって発生した利益には、所得税がかかります。確定申告をしなければ納税額がわからず、支払いもできないため、納税せずにそのままになってしまいます。納税義務があるにも関わらず放置すると、無申告加算税と延滞税が課せられてしまいます。
無申告加算税と延滞税がそれぞれどのくらいの金額になるのかについては、以下の通りです。
| ペナルティの 種類 |
加算割合 |
|---|---|
| 無申告加算税 |
・申告期限から1カ月以内に自主的に納付した場合:ペナルティなし
・税務署の調査を受ける前に自主的に申告をした場合:5%
・納付税額が50万円までの場合:15%
・納付税額が50万円以上の場合:20%
|
| 延滞税 |
・納期限の翌日から2カ月以内:7.3%
・納期限の翌日から2カ月を過ぎた場合:14.6%
|
無申告加算税と延滞税は、納税額に加算割合をかけて算出します。納税額に上乗せして支払う必要があるため、場合によっては高額の支払いになると考えておきましょう。
延滞税は原則7.3%または14.6%ですが、原則の数字と延滞税特例基準割合+1%、または7.3%の低いほうが適用されます。延滞税特例基準割合は、令和4年1月1日~令和6年12月31日までは3.4%と16.%となっています。納付期限の翌日から2カ月以内に納付した場合は低いほうの割合が適用されるため、もし延滞してしまってもできるだけ早めに納税を済ませましょう。
申告前に利用できる控除がないかを確認する
確定申告をおこなう前に、利用できる控除や特例がないかを確認しておきましょう。
居住用の建物や土地を売った場合は「マイホームを売った時の特例」、相続や遺贈によって取得した不動産を売却する場合は「被相続人の居住用財産を売った時の特例」を利用できます。
売却金額よりも購入金額のほうが大きく、譲渡損失が発生した場合も控除を受けられます。マイホームを買い換えた時や、住宅ローンの残っているマイホームを売却した際に発生する譲渡損失に対する控除があるため、利益の有無に関わらず特例や控除を利用できると考えておきましょう。
利用できる控除や特例は税務署から教えてもらえません。自身で確認するしかないため、申告前に利用可能な控除や特例をチェックしましょう。不安な方は、税理士に相談することがおすすめです。
書類に不備や漏れがないように気を付ける
確定申告の手続きを進める前に、書類の不備や漏れがないかを入念にチェックしましょう。通常の確定申告に比べ、不動産売却に関する確定申告にはさまざまな書類が必要です。ひとつでも抜けがあると修正申告をしなければならないため、手続きを終えるまでに時間がかかります。
万が一申告した金額が少なかった場合は、早めに修正申告をおこないましょう。税務署から指摘される前に修正し、不足分を納税すればペナルティはありません。しかし、税務署からの調査を受けたり、指摘をされたりしたあとに修正すると、「過少申告加算税」が課されます。
過少申告加算税は、新たに払うことになった税金の10~15%相当額を追加で支払う必要があるため、不要な支払いを増やさないよう、早めに修正をすることが大切です。
まとめ
譲渡所得の内訳書は、建物や土地などを売却し、確定申告をおこなう際に作成・提出する必要がある書類です。売却した年の翌年の確定申告に遅れないよう、ほかの書類とあわせて準備しましょう。
無申告だと無申告加算税や延滞税が加算されるため、確定申告の手続きは忘れずにおこないましょう。
物件を探す

執筆者
長谷川賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ