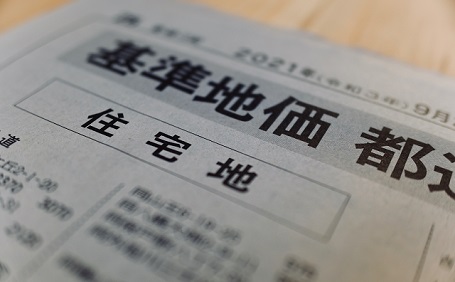土地を売却する際の注意点は?事前準備から税金まで総合的に解説

本記事では、土地を売却する際の注意点を、事前準備から税金の支払いまで解説します。記事を読むことで、土地の売却全体における注意点を把握できるでしょう。
記事の目次
土地の売却時の事前準備に関する注意点

はじめに、土地の売却に対して具体的に動いていない、事前準備の時点での注意点を5つまとめました。それぞれ詳しく見ていきましょう。
所有する土地の現状を把握してから手続きを進める
売却を検討する前に、まず土地の形状や周辺環境を確認して、現状を把握しましょう。土地の権利関係と抵当権の有無、隣地や道路との境界の確認など、売却をおこなうために必要な情報を調べます。
現状の把握をおろそかにすると、買主との契約のタイミングや、引き渡し後にトラブルが発生することも。相続などで土地を取得しており、土地の状況を理解していない場合は、現状の把握から始めてください。
隣地との境界を明確にする
現状を把握した結果、隣地・道路との境界が明確でない場合は、トラブルを防ぐために土地家屋調査士に測量を依頼して境界を明確にしましょう。境界確定測量では、土地家屋調査士が隣地所有者と立ち会いのもとで境界を確認し、合意のもとで測量をおこないます。
隣地との境界が明確でない場合は、土地の引き渡し後にトラブルになることも。土地を購入する買主もトラブルを避けるために、境界が明確な土地を求める傾向にあります。境界標設置、境界確認書類の取得をおこない、隣地との境界を確定させてから売却の手続きに移るようにしましょう。
相続した土地の場合は相続登記をおこなう
土地を相続した場合は、相続登記をおこなわなければ、土地の名義が被相続人のままになります。この状態で土地の売却を進めると、所有権移転登記をおこなえません。相続登記をしなければ買主に所有権を移せないため、売買契約が成立しなくなる恐れがあります。
また、相続によって取得した土地は相続登記が義務化されており、相続発生から3年以内に登記しなければ罰則があります。登記をあと回しにして売却手続きを進めてしまうと、トラブルの原因になるかもしれません。
契約に必要な書類を用意する
売却手続きを進める前に、契約に必要な書類を用意するようにしましょう。土地の売買契約に必要な代表的な書類を、以下にまとめました。
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 登記識別情報通知書または登記済証 | 所有者を確認するための書類 |
| 固定資産税評価証明書 | 土地の面積と評価額がわかる書類 |
| 境界確認書類 | 隣地・道路との境界が明確であることを示す書類 |
| 土地を購入した時の売買契約書 | 確定申告に必要な書類 |
| 印鑑証明書(3カ月以内に発行) | 土地の引き渡しに必要な書類 |
土地の売却では、その他にも必要に応じて複数の書類が必要になります。また、印鑑証明書のように有効期限がある書類もあるため、書類を用意するタイミングに気を付けましょう。
ローンが残っている場合は抵当権抹消手続きが必要になる
土地にローンが残っている場合は、引き渡し前に抵当権を抹消する必要があります。ローンが残っている土地でも、売却代金を利用して返済ができるため売却が可能です。
ただし、ローンの残債が売却価格を上回るオーバーローンの状態にある場合は、土地を手放すために、自己資金でローンを返済する必要があります。
土地の売却相場の調べ方に関する注意点

土地の売却を検討するにあたって、自身の所有する土地がいくらで売れるのか気になる方も多いことでしょう。正確な売却価格は、実際に売却してみなければわかりませんが、相場を調べることで目安を調べられます。相場の調べ方に関する注意点を以下にまとめました。
最初に実勢価格や公示価格などの公的な指標を調べる
土地の査定は、最初から不動産会社に任せればいいと考えるかもしれません。しかし、自身でも相場の目安となる情報を調べたうえで査定に望むほうが、不動産会社の出した査定価格が適切なものであるかを判断しやすくなります。
国土交通省などの公的機関が発表する指標である実勢価格・公示価格を調べることで、根拠のある相場の目安を知ることができます。具体的な公的指標と内容を以下にまとめました。
| 項目 | 内容 | 公開している 機関 |
|---|---|---|
| 実勢価格 | 実際に売買が成立した 取引事例に基づく価格 |
国土交通省 |
| 公示価格 | 地価公示法に基づき 国土交通省が発表する価格 |
国土交通省 |
| 基準地価 | 国土利用計画法に基づき 都道府県が発表する価格 |
各都道府県 |
| 路線価 | 国税庁が道路ごとに評価した 相続税の評価額 |
国税庁 |
| 固定資産税 評価額 |
市町村が3年ごとに評価替えする 土地の評価額 |
各市町村 |
基準地価は各都道府県の公式サイトだけでなく、国土交通省の不動産情報ライブラリで公開されています。公的な指標を調べることで、根拠のある数値で相場を把握することが可能です。
優先して調べる指標は実勢価格と公示価格であり、より詳しく相場を知りたい場合は、基準地価・路線価・固定資産税評価額も参考にしましょう。万が一、相場から明らかにかけ離れた査定をする不動産会社があっても、先に公的機関の指標を調べておけば気付くことができます。
一つの不動産会社の価格査定のみを参考にしない
不動産会社にはそれぞれ得意エリアや査定方法に違いがあり、過去の取引事例の蓄積状況も異なるため、一社だけの査定では偏りのある結果になってしまうことがあります。複数の不動産会社に査定を依頼して比較すれば、適切な売り出し価格を設定しやすくなるでしょう。
おすすめの査定方法は一括査定。オンラインでおこなえる簡易査定を利用して複数の不動産会社の査定結果を受け取れるサービスです。複数の査定結果から、土地の相場を把握しやすくなります。複数の不動産会社で査定を受ければ、それぞれの査定結果から相場を把握しながら、不動産会社を絞り込むことができるでしょう。
不動産情報サイト アットホーム「不動産一括査定依頼サービス」では、土地をはじめ、マンションや一戸建てなど、複数の不動産会社に査定を一括で依頼できます。
最新情報を確認する
公的機関が発表する指標は、定期的に情報が更新されます。そのため、最新情報を確認することが重要です。また、不動産会社で価格査定を受けた場合、基本的に3カ月程度の売却を想定した価格を提示します。
土地の売却相場は常に変動しているため、古い情報を頼ると精度が落ちることは避けられません。より正確な相場を知りたいなら、最新情報を確認するようにしましょう。
土地売却時の不動産会社選びに関する注意点

土地の売却相場を理解して、目安となる売却価格に納得した場合は、売却を仲介する不動産会社を選び、実際に売却を進めていくことになります。土地の売却において不動産会社選びは、売却の成果に直結するため、慎重に選ぶようにしましょう。注意点を3つまとめました。それぞれ詳しく見ていきましょう。
不動産会社の信頼性と実績を確認する
不動産会社と契約をする前に、信頼性と実績を必ず確認するようにしましょう。国土交通省・各都道府県公式サイトでは、宅地建物取引業者を検索できます。免許番号がなく、不動産会社が登録されていない場合は取引を避けましょう。登録があっても、行政処分歴を確認して過去に問題がないか、チェックすることをおすすめします。
実績は、売却する土地が属するエリアの取引実績や成約件数を、公式サイトやパンフレットなどから調べておきましょう。また、口コミサイトもチェックし、評判が悪い状況にないかを確認します。
不動産会社の担当者と話した際には、売却価格について根拠があり、納得のいく説明ができるかどうかを見極めます。インターネットで得られる情報から問題ないと判断し、担当者と実際に話したうえで、信頼できる不動産会社を選びましょう。
自分にあった媒介契約を選ぶ
自分にあった媒介契約を選ぶようにしましょう。大きく分けて3つの媒介契約があります。それぞれの媒介契約の内容を以下にまとめました。
| 契約形態 | 複数社への 依頼 |
自己発見取引 | 活動報告義務 |
|---|---|---|---|
| 一般媒介契約 | 〇 | 〇 | 任意 |
| 専任媒介契約 | × | 〇 | 2週間に 1回以上 |
| 専属専任 媒介契約 |
× | × | 1週間に 1回以上 |
一般媒介契約は複数社に依頼できますが、すべての不動産会社が積極的に土地の売却に動かないことも。そのため、複数社に依頼できない代わりに、販売活動を積極的におこなう専任媒介契約・専属専任媒介契約も有力な選択肢です。
一般的に選ばれている媒介契約は、専属専任媒介契約とは異なり、売主が直接買主を見つけて契約が可能な自己発見取引ができる自由度の高い専任媒介契約です。ただし、専属専任媒介契約では1週間に1回以上の活動報告を受けられるため、不動産会社の販売活動の実施状況をこまめに確認できます。
媒介契約にはそれぞれ特徴があるため、自分にあった媒介契約を選ぶことが重要です。媒介契約の選び方も売却の成果や成約時期に影響を与える可能性があるため、理解しておきましょう。
複数の不動産会社に相談する
信頼できる不動産会社を選ぶには、複数の不動産会社に相談する必要があります。相場に沿った価格査定であり、信頼できる不動産会社であるかどうかを見極めるためには、比較する必要があるからです。適切な売却価格を把握するために、1社に相談して契約を決めてしまうことがないようにしましょう。
また、信頼できる不動産会社は顧客に寄り添い、売主本人の意思を無視して契約を急かすことはありません。担当者から契約を急がせることを言われた場合は、信頼しにくい不動産会社である可能性があります。
最低でも3社以上に相談したうえで、実際に担当者と話すことをおすすめします。媒介契約で専任媒介契約・専属専任媒介契約を選ぶ場合は、1社以外に土地の売却活動を依頼できないため、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。
土地の売却時の契約に関する注意点

選んだ不動産会社が買主との売買を仲介し、契約までたどり着いた場合は、のちのトラブルを避けるために契約に関する注意点を守りましょう。契約に不備があった場合、法的な争いに発展するケースもあります。注意するべきポイントを3つまとめました。
重要事項は売買契約書に必ず記載する
土地の売却では、必ず売買契約書に重要事項を記載するようにしましょう。具体的には、土地のインフラ状況や土壌汚染など、将来的に買主に不利益をもたらす可能性がある事項を漏れなく記載します。売買契約書に記載する義務がある内容に記載漏れがあると、説明不足を理由にトラブルに発展する危険性も。
悪質な不動産会社は、早期売却を優先してマイナス事項を買主に説明しないケースがあります。売主も責任を問われる可能性があるため、重要事項が記載されているかどうか自身で確認することが重要です。
契約不適合責任に問われると法的なトラブルに発展する
記載するべき重要事項が記載されておらず、買主が受けるべき説明を受けられなかった場合は、売主が契約不適合責任に問われる可能性があります。買主は契約不適合責任を理由に契約解除、損害賠償請求をおこなうことが可能です。
買主は不適合事実を知ってから1年以内であれば請求できるため、あとから問題が発覚すればトラブルになります。場合によっては法的な論争に発展することも。土地の事前調査と契約書による告知義務を徹底して、契約不適合責任に問われることがないようにしましょう。
売買契約後に必要な登記手続きをおこなう
売買契約後は、必要な登記手続きを速やかにおこないましょう。土地の売却で必要になる登記手続きは、売主から買主に所有権を移す所有権移転登記と、ローンを組んでいる場合に必要な抵当権抹消登記が挙げられます。
登記を怠ると、買主が第三者に対して土地の所有権を主張できないため、トラブルに発展します。相続した土地の売却で相続登記をおこなっていない場合、買主に所有権を移せない問題が発生するのもこのタイミングです。登記は司法書士などの専門家に相談したうえで、売却スケジュールに支障をきたすことがないように済ませるようにしましょう。
土地の売却時の税金に関する注意点

土地の売却は、買主に無事に土地を引き渡し、売却代金を受け取って終わりではありません。売却によって利益を得た場合は、税金を支払う必要があります。最後に、土地売却時の税金に関する注意点を紹介します。
譲渡所得税・住民税は確定申告によって納付する
土地の売却によって得た利益は、譲渡所得に分類されます。譲渡所得がある場合は、申告分離課税として翌年の確定申告期間(2月16日~3月15日)に所得税・住民税を申告しましょう。確定申告の義務があり、申告しなかった場合は無申告加算税などのペナルティが科されることも。
譲渡所得は次の計算式で求められます。
譲渡所得 = 土地の売却代金 -(取得費 + 譲渡費用)
取得費は土地の購入代金、譲渡費用は仲介手数料・測量費用などの土地の売却にかかった費用のこと。これらを売却代金から差し引けます。
所得税の納付は確定申告期間におこない、住民税の納付は確定申告をおこなった年の6月から納める仕組みです。土地を売却した場合は、確定申告を怠らないようにしましょう。
土地の所有期間の計算に気を付ける
譲渡所得にかかる税率は所有期間に応じて決まっており、短期譲渡所得・長期譲渡所得の2種類があります。以下に税率をまとめました。
| 短期譲渡所得 | 長期譲渡所得 | |
|---|---|---|
| 所有期間 | 5年以下 | 5年超 |
| 所得税率 | 30% | 15% |
| 住民税率 | 9% | 5% |
| 復興特別所得税率(※) | 0.63% | 0.315% |
| 合計 | 39.63% | 20.315% |
※復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興財源にあてるため、2037年12月31日まで通常の所得税に上乗せして徴収される特別税です。
重要になる点は土地の所有期間であり、5年以下の場合は短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得になり税率が安くなります。
例えば、2020年3月に土地を取得して、2025年6月に売却したと仮定しましょう。所有期間の起算日は、売却した年の1月1日時点で判定される仕組みです。よって、2025年1月時点では所有期間が5年を超えないため、こちらのケースでは短期譲渡所得になります。
短期譲渡所得と長期譲渡所得では税率に差があるため、場合によっては土地の売却タイミングをずらすことも検討しましょう。
節税制度の条件を把握してから利用する
土地の売却では、複数の節税制度を利用できます。しかし、利用には条件があるため、把握してから利用するようにしましょう。例えば、売却対象が居住用財産であれば、譲渡所得から3,000万円を差し引ける「3,000万円特別控除」を利用できるかもしれません。他の節税制度と併用できない場合があるため、誤りのないように申告しましょう。
土地の売却で得た利益を確定申告するにあたって、節税制度の利用を含めて最適化したい場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
土地の売却に関する全体的な注意点を紹介しました。事前準備から税金の申告までの工程で複数の注意点があるため、今の段階でやるべきことをこなしつつ、慎重に売却手続きを進めましょう。
土地の売却は、すべて一人で完結させられるわけではありません。わからないことがあれば不動産会社をはじめ、必要に応じて司法書士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。自身ではわからなくても専門知識を持った人に相談することで、一つひとつ問題を解決していけるでしょう。
物件を探す
注文住宅を建てる

執筆者
長谷川 賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ