マンション売却時の減価償却とは?計算方法をシミュレーション付きで紹介

本記事では、マンション売却時の減価償却の計算方法をシミュレーション付きで紹介。税金の計算に必要であることは知っていても、そもそも減価償却が何かわからない方に向けた解説もおこないます。記事を読むことで、マンション売却時の税金計算で必要な減価償却を順序立てて理解できるようになるでしょう。
記事の目次
減価償却とは?
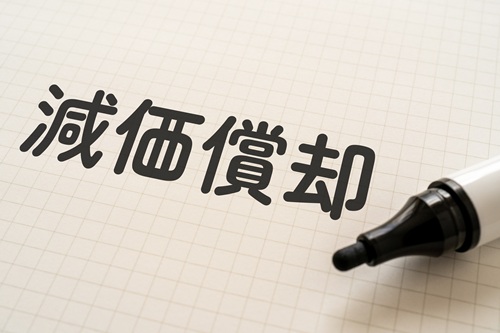
減価償却とは、マンションを含む耐用年数が決められた資産を、使える年数に分けて少しずつ経費にする仕組みです。減価償却の対象となる資産は買った年だけでなく、数年〜数十年にわたって使い続けます。購入した時の支出を一度に経費として計上するのではなく、使える期間に応じて分割して費用にする経費申告の考え方になります。
例えば、40万円のパソコンを買ったと仮定しましょう。一般的なパソコンの法定耐用年数が4年であるため、年間あたりの経費は次の計算式で求められます。
40万円 ÷ 4年 = 10万円
不動産投資用にマンションを購入した場合、購入価格が高いため、一度にすべての支出を経費として計上すれば、大きな赤字になることは避けられません。購入価格が高いほど、費用を少しずつ計上できることにメリットが生まれやすくなります。
以下の項目では、さらに減価償却に関する内容を深掘りしていきます。
減価償却の対象になる資産
減価償却の対象になる資産は、長期間にわたって利用できるものと決まっています。例えば、マンション、事務所などの建物は、長期間にわたって利用する性質から対象になります。一方で、短期間で使い切る消耗品は減価償却の対象になりません。減価償却の対象となる代表的な資産は、以下のとおりです。
| 項目 | 具体例 |
|---|---|
| 建物 | マンション、事務所、店舗、倉庫など |
| 建物附属設備 | 照明設備、空調設備、エレベーターなど |
| 事業用の機械・装置 | クレーン、旋盤、発電設備など |
| 自動車 | 営業用車両、トラック、バスなど |
| 工具・器具・備品 | パソコン、事務机・椅子、コピー機など |
上記に該当する資産であっても、以下の条件を満たす場合は減価償却できません。
- 使用可能期間が1年未満
- 取得価額が10万円未満
例えば、10万円未満のパソコンであれば、原則として全額を消耗品費または事務用品費として計上します。分割して経費計上するには安過ぎるものは、長期間にわたって利用するものであっても対象外になります。
減価償却が必要な理由
減価償却は利益を正しく求め、税金を適正にするためにおこないます。高額な資産を買った年にすべて経費にすると、その年の利益だけが小さくなり、翌年以降使用しても経費が発生しません。耐用年数にあわせて購入費を少しずつ配分すれば、その期間に使った分だけ経費にすることが可能です。特定の年の利益が実態から離れることがないため、正確な利益を申告できるようになるでしょう。
確定申告によって、利益に税金がかかるため、正確な利益を申告できなければ課税も偏ります。購入した年にまとめて計上すれば、その年は税金が極端に少なく、翌年以降は多く支払うことになるでしょう。減価償却をすれば税負担が均等になり、適正に税金を支払えるようになります。
また、減価償却の考え方では、資産は使うほど価値が少しずつ減ることに。減価償却をしなければ帳簿上では、過大評価された資産価値が載ったままになり、年数が経過するほど実際の価値から大きく離れることも。減価償却によって帳簿上の価値を適切に減らすことで、資産価値の透明性を高める狙いもあります。
特に、マンション売却時の減価償却では、購入した時よりもマンションの価値が減少している点が重要です。減価償却は利益を正しく計り、税金を適正にするために必要な調整であると理解しておきましょう。
マンション売却時の減価償却に対する考え方

減価償却の基礎知識を理解したうえで、マンション売却時に減価償却が必要な理由と減価償却をおこなう範囲を解説します。不動産売却時の減価償却に対する考え方を理解しておきましょう。
正確な取得費を求める
マンション売却にかかる税金では、まず売却価格からマンションの購入費用と仲介手数料などの購入時にかかった諸費用を差し引いて、課税対象となる譲渡所得を計算します。計算方法は以下のとおりです。
- 譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
譲渡所得を求めたあと、マンションの所有期間に応じた税率をかけて税額を算出します。しかし、取得費の計算では、マンションの購入費用をそのまま取得費にできません。なぜなら、建物部分は年数が経過するごとに価値が減少するからです。
よって、取得費の計算は、減価償却を考慮する必要があります。減価償却を含めた取得費の計算方法は以下のとおりです。
- 取得費 = 購入価格(建物 + 土地)+ 諸費用 - 減価償却費(建物)
取得したマンションの価値を減価償却で調整すれば、正確な取得費を売却価格から差し引けるようになります。減価償却を差し引かずに取得費を計算すると、実態よりも取得費が大きくなり、課税対象となる譲渡所得が少なく計算されます。つまり、税金の過少申告と認識されるため、そのまま申告すれば税務署から修正申告を求められるでしょう。
減価償却は、マンション売却時に正しい税金を申告するための考え方です。税務署から修正を求められないためにも、正確な取得費を求める必要があります。
減価償却の対象に土地は含まれない
上述した計算方法は、減価償却の対象は建物のみであり、土地が含まれていません。減価償却は、資産価値が時間の経過とともに減少するものに適用されますが、土地は価値が減る資産とはみなされないため、減価償却の対象外です。
土地は建物のように時間の経過で劣化するわけではなく、利用価値が永続すると考えられています。不動産市場の取引実態からも、土地価格は需給や景気に左右されるものであると分析できるでしょう。よって、土地部分は購入費をそのまま取得費として計上できます。
減価償却の対象は、長期間にわたって利用できる資産です。しかし、土地だけでなく、美術品・骨董品なども原則として価値が減らない資産であるため、減価償却に適さないことから例外もあります。取得費の計算では、マンションの購入費用のなかで建物部分と土地部分の価格を分けて考える必要があるでしょう。
マンション売却時の減価償却の計算方法

居住用のマンションを売却した場合の減価償却の計算方法は、以下のとおりです。
- 減価償却費 = 建物の購入価格 × 0.9 × 償却率 × 経過年数
上記の計算をするために、必要な手順を以下にまとめました。
- STEP 1居住用と事業用を区別する
- STEP 2建物の購入にかかった費用を求める
- STEP 3償却率を調べる
- STEP 4経過年数を確認する
それぞれ詳しく解説します。
ステップ1.居住用と事業用を区別する
最初にするべきことは、マンションの居住用・事業用の区別です。居住用と事業用では減価償却の計算が異なるため、勘違いがあれば取得費・税金の計算に誤りが発生します。
居住用のマンションは、事業に使用しているわけではないため、できる限り税金を発生させないように独自の計算方法が採用されています。よって、事業用のマンションと比較すると減価償却費が少なくなりやすいため、差し引ける取得費が増え、譲渡所得が減少すれば課税金額が減る仕組みです。
定額法による減価償却費の計算方法は、マンションの取得日が2007年3月31日以前であるか、4月1日以降であるかによって異なります。
2007年3月31日以前
- 減価償却費 =(建物の購入価格 - 残存価額)× 償却率 × 事業用として使用した月数 ÷ 12
2007年4月1日以降
- 減価償却費 = 建物の購入価格 × 償却率 × 事業用として使用した月数 ÷ 12
2007年4月1日以降の計算では、残存価額が廃止されました。残存価額は、法定耐用年数が経過したあとの資産価値を示す金額です。事業用のマンションの減価償却費を求める場合は、取得日によって計算方法も異なるため、気を付けましょう。
ステップ2.建物の購入にかかった費用を求める
建物の購入費用は、売買契約書に記載されている建物価格を使用します。建物価格がわからない場合も、複数の方法で購入費用を割り出すことは可能です。例えば、物件全体の購入価格と消費税がわかっていれば、購入時の消費税率から計算できます。消費税は土地にはかからず、建物のみにかかるため、以下の計算式が成り立ちます。
- 建物の購入価格 = 消費税 ÷ 購入時の消費税率
消費税が300万円、購入時の消費税率が10%と仮定すると、計算結果は以下のとおりです。
- 300万円(消費税)÷ 10%(購入時の消費税率)= 3,000万円(建物の購入価格)
売買契約書から正確な建物の購入価格がわからない場合は、ケースごとに適切な方法を知るためにも、不動産会社や税理士に相談したほうがいいでしょう。
ステップ3.償却率を調べる
次に、マンションに適用される償却率を調べます。償却率は居住用・事業用で異なるため、対応した償却率を調べる必要があります。居住用のマンションの償却率を以下にまとめました。
| 建物の構造 | 償却率 |
|---|---|
| 鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造 | 0.015 |
| れんが造、石造またはブロック造 | 0.018 |
| 木造または合成樹脂造 | 0.031 |
| 木骨モルタル造 | 0.034 |
| 金属造(肉厚4mm超) | 0.020 |
| 金属造(肉厚3mm超4mm以下) | 0.025 |
| 金属造(肉厚3mm以下) | 0.036 |
国税庁 「減価償却費」の計算についてより筆者作成
一方で、事業用のマンションは、取得日が2007年3月31日以前である場合は旧定額法、4月1日以降であれば現行の定額法の償却率を適用します。償却率を調べるにあたって、物件の耐用年数が重要であり、耐用年数47年の鉄筋コンクリート造のマンションの償却率は0.022です。
ステップ4.経過年数を確認する
最後に、居住用のマンションの購入から売却に至るまでの経過年数を確認しましょう。新築マンションを購入した場合は、実際の築年数をそのまま使用できます。しかし、中古マンションを購入した場合は、実際に所有している期間を計算する必要があります。
例えば、築10年の中古マンションを購入して築25年で売却した場合は、減価償却の計算上の経過年数は15年です。経過年数は年単位であるため、6カ月以上の端数は切り上げ、6カ月未満の端数は切り捨てます。
例えば、経過年数が15年7カ月の場合は16年にして計算しましょう。事業用マンションの場合は、事業用として使用した月数が基準になるため、月単位で計算結果に影響を及ぼすことに注意が必要です。
以上で減価償却の計算に必要な手順をすべて紹介したため、減価償却費を計算できるようになりました。次の項目で実際に計算してみましょう。
マンション売却時の減価償却の計算シミュレーション

マンション売却時の減価償却の計算を居住用・事業用に分けてシミュレーションしました。それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。
居住用のマンションを売却したケース
居住用のマンションの売却条件と実際の計算を以下にまとめました。
- 建物の購入価格:3,000万円
- 償却率:0.015
- 経過年数:20年
- 3,000万円(建物の購入価格)× 0.9 × 0.015(償却率)× 20年(経過年数)= 810万円(減価償却費)
減価償却費は810万円となり、仮に取得費の合計が3,090万円であるなら「3,090万円 - 810万円 = 2,280万円」が減価償却費を差し引いた正確な取得費になります。
事業用のマンションを売却したケース
事業用のマンションの売却条件と実際の計算を以下にまとめました。
- 建物の購入価格:5,000万円
- 取得日:2007年4月1日以降
- 償却率:0.022
- 事業用として使用した月数:120カ月
- 5,000万円(建物の購入価格)× 0.022(償却率)× 120カ月(事業用として使用した月数)÷ 12 = 1,100万円(減価償却費)
事業用マンションは取得日が2007年4月1日以降であるため、定額法で計算しました。取得費の合計が9,000万円の場合、「9,000万円 - 1,100万円 = 7,900万円」が取得費です。
上記を参考に減価償却費を計算して取得費を求めれば、「譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)」に取得費を含めた数値を当てはめて、譲渡所得を計算できるようになります。
マンション売却時の減価償却に関するポイント

最後に、マンション売却時の減価償却に関するポイントを3つまとめました。それぞれ詳しく見ていきましょう。
最新の情報を確認する
減価償却の計算方法、耐用年数と償却率は、税法の改正により変更される可能性があります。実際に事業用のマンションでは、減価償却の計算方法が2007年に変更されました。そのため、最新の情報を調べてから計算するようにしましょう。減価償却に限らず、マンション売却時の税金を計算する場合は、国税庁などの公的な情報元から最新情報の確認をおこなうことが基本です。
税負担が上がった分は特例や控除で補える
減価償却費を取得費から差し引くと、全体の取得費が小さくなり、譲渡所得が増加して税金が高くなります。税負担を少しでも下げたい場合は、特例や控除を活用しましょう。減価償却そのものは避けられませんが、他の方法で税負担を抑える余地はあります。
例えば、居住用のマンションに使用できる3,000万円特別控除は、譲渡所得から3,000万円を差し引けるため、譲渡所得が3,000万円以下だった場合は非課税です。10年超所有軽減税率の特例を利用すれば、居住用マンションの所有期間が10年を超えている場合に、譲渡所得にかける税率が軽減されます。
減価償却費を計算して取得費を差し引いた結果、税負担が重くなっても利用できる特例や控除を適用すれば、十分に補える可能性があります。
計算が難しい場合は専門家に相談する
減価償却を含めたマンション売却の税金に関してわからないことがある場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。税理士に確定申告を依頼すれば、売買契約書などの必要な書類を提出すると、正確な減価償却費を求めて正しく税金を申告してくれます。また、特例や控除の適用可否も確認してもらえるため、最適な節税ができるでしょう。
税金の計算を間違えると、過大申告になれば本来納める必要がない税金を余分に支払うことになります。一方で、過少申告をすると、あとから税務署から指摘を受けて修正申告をしなければなりません。計算が難しく自信がない場合は、専門家に相談して依頼料を負担したうえで、確定申告を代行してもらうことも選択肢の一つです。
まとめ
マンション売却時の減価償却費は、正確な取得費を求めるために計算が欠かせません。不動産の建物部分は、年数の経過によって価値が下がります。その分を減価償却費として差し引かなければ、正確な譲渡所得を算出できません。
居住用のマンションの場合、建物の購入価格、償却率、経過年数がわかれば計算可能です。計算のために調べることは多くないため、やり方がわかればご自身で調べて実際に減価償却費を算出できます。ただし、必ず間違いのないように計算する必要があるため、よく確認をしてミスのないようにしましょう。
物件を探す
注文住宅を建てる

執筆者
長谷川 賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ



