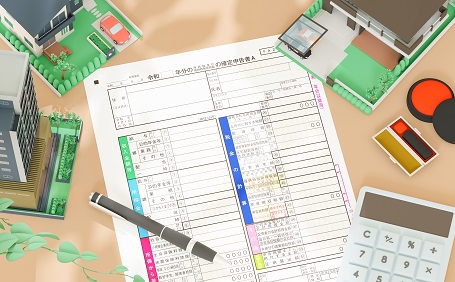相続した不動産を売却する時の手順は?必要書類や注意点を解説!

本記事では相続した不動産をどうするか、売却するまでの手順や必要な書類などについて解説します。スムーズに進めるためにも、基礎知識を押さえておきましょう。
記事の目次
相続した不動産を売却するまでの手順

相続した不動産はそのままでは売却することができません。不動産の名義変更(相続登記)が必要となります。財産を相続した際にかかる相続税は相続開始の翌日から10カ月以内に納めなければなりません。また、相続した不動産を売却して利益が出た場合には、譲渡所得として申告する必要があります。手順は下記のとおりです。
- STEP 1遺言状の有無を確認する
- STEP 2相続人と相続する財産を確認する
- STEP 3遺産分割協議をおこなう
- STEP 4相続登記をする
- STEP 5相続税を申告・納税する
- STEP 6相続した不動産を売却する
- STEP 7確定申告をする
それぞれ詳しく見ていきましょう。
遺言状の有無を確認する
まずは不動産を残して亡くなった被相続人の遺言状の有無を確認しましょう。遺言状には次の3種類があります。
| 自筆証書遺言 | 遺言者が自筆で書いたもの |
|---|---|
| 公正証書遺言 | 遺言者が口述し、公証人が筆記したもの 原本が公証役場に保管されている |
| 秘密証書遺言 | 遺言者が作成し、遺言の内容を秘密にして公証人が存在だけを証明するもの |
「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は、家庭裁判所が遺言書を確認し、偽造などを防止するための「検認」が必要となります。検認は、遺言の存在と内容を知らせるためのもので、有効・無効を判断するためのものではないことを覚えておきましょう。
遺言書があった場合は、基本的にそれにしたがって遺産を分割します。ない場合は法定相続人で集まり、遺産分割協議をおこないます。遺産分割協議については後述します。
相続人と相続する財産を確認する
遺言状の有無を確認したら、相続人と相続する財産を確認しましょう。財産はプラスのものだけでなく、マイナスのものも相続します。それぞれの財産の具体例は下記のとおりです。
| プラスの財産 | マイナスの財産 |
|---|---|
| 不動産 預貯金 有価証券 保険金 |
借金 ローンの残債 被相続人の葬儀費用 |
被相続人が所有していた不動産がわからない場合は、市区町村で「名寄帳」(なよせちょう)を取得しましょう。「名寄帳」とは、所有者別に土地や家屋に関する情報がまとめられたものです。所有者の名前や住所、地番などが確認できます。
遺産分割協議をおこなう
遺言状があった場合は、内容にしたがって相続を進めますが、なかった場合は遺産分割協議をおこないます。遺産分割協議とは、相続人全員の話し合いによって、遺産をどのように分割するかを決めるためのものです。
不動産を売却したい場合には、必ず「遺産分割協議書」を作成しましょう。不動産の所有権を移転する際に必要となります。遺産分割協議書を作成する際には、次のポイントを押さえておきましょう。
- 不動産の適正な査定価格を算定する
- 不動産の売却で発生する必要経費を適切に算定する
- 相続登記から不動産売却、その後の売却代金の分け方までを明確にする
「なんとなく……」で決めてしまうとトラブルのもととなります。円満に進めるためにも、できれば行政書士や司法書士などの専門家に依頼して作成しましょう。
相続登記をする
相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人へと変更する手続きです。相続した不動産を売却する場合でも、名義を変更しなければなりません。もし、相続登記をしない場合、他の相続人が自分の持分まで勝手に売却してしまったりする恐れがあります。トラブルを起こさないようにするためにも、確実におこないましょう。また、相続登記には必要な書類が多く、複雑なため、司法書士へ依頼するのが一般的です。必要な書類は後述します。
相続税を申告・納税する
相続税とは、相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる税金です。相続税がかかるかは次の式で計算できます。
相続税の課税遺産総額=プラスの財産-マイナスの財産-基礎控除額
なお、基礎控除額は次の計算式で求めます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、プラスの財産が6,000万円、マイナスの財産が1,000万円、法定相続人が2人だった場合を見てみましょう。
基礎控除額は4,200万円(3,000万円+600万円×2)となります。
相続税の課税遺産総額は800万円(6,000万円-1,000万円-4,200万円)となり、相続税が発生します。相続税は相続開始(被相続人が死亡したことを知った日)の翌日から10カ月以内に、申告と納税をしなければなりません。
相続した不動産を売却する
相続した不動産を売却しましょう。個人的に売却先が決まっている場合を除いて、不動産会社へ仲介または買取を依頼するのが一般的です。不動産会社によって査定額が異なるため、複数社に査定を依頼しましょう。
査定は名義変更の完了前でも受けられるため、売却することが決まっている場合は早めに依頼をしておきましょう。スムーズに売却を進められます。
確定申告をする
相続した不動産を売却して利益が発生した場合には、確定申告が必要です。不動産や株式などを譲渡して得た所得を譲渡所得といい、所得税と住民税の課税対象となります。「相続税も払ったのに、譲渡所得税も払わないとならないの?」と思われる方もいるでしょう。
しかし、譲渡所得の申告をする際に「相続税の取得費加算の特例」が適用されるため、税金負担が軽くなります。「相続税の取得費加算の特例」とは、不動産の相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過するまでに譲渡した時、相続税額のうち、一定の金額を譲渡資産の取得費に加えられるというものです。もし譲渡所得税が0円となる場合でも、確定申告は必要です。忘れずに申告しましょう。
相続した不動産の分け方

相続した不動産を相続人で分ける場合、4つの方法があります。どういった方法があり、売却する際に選択しやすいかを確認しておきましょう。
現物分割
現物分割とは、相続した財産をそのまま、各相続人に分配する方法です。例えば、家と土地はAさん、車はBさんといったように、財産をそれぞれに分けます。遺産を単独で所有できるというメリットがありますが、公平に分けづらいというデメリットもあります。
換価分割
換価分割とは、遺産の全部または一部をお金に換えて、そのお金を分割する方法です。不動産を売却して得られた代金を、相続人の間で均等に分けられます。例えば、不動産を売却して得た利益3,000万円を相続人3人で1,000万円ずつ分けるといった場合です。もし相続人の間で話がまとまらない場合でも、公平に分割ができます。
代償分割
代償分割とは、ある相続人が遺産を現物で取得し、他の相続人に自分の財産を支払う方法です。例えば、Aさんが不動産を取得し、不動産を取得した代償として、AさんがBさんとCさんに現金を払うといったケースです。特定の相続人が不動産の所有を希望している場合が当てはまります。ただし、他の相続人に代償金を支払う必要があるため、経済的な負担は大きくなります。
共有分割
共有分割とは、相続人の持分を定めて共有する方法です。相続した不動産を共有する場合、法定相続割合に応じた「共有持分」を取得して、全員で共有します。しかし、相続人が亡くなった際、新たに所有者が増えて、将来売却しにくくなるというデメリットがあります。
これまでに4つの分割方法を見てきました。相続した不動産を売却する場合には「現物分割」または「換価分割」を選択するのが一般的です。相続のトラブルはのちのち響くものです。相続人全員が納得できる方法を選ぶようにしましょう。
相続した不動産の名義変更に必要な書類と方法

手順の章で説明したように、相続した不動産を売却するためには、相続登記(不動産の名義変更)をする必要があります。相続登記をすると、土地や建物を所有していることを主張できるようになります。しかし、どういった形で相続をおこなったかによって、手続きの際に必要となる書類が異なります。
相続登記に必要な書類
どのケースにも必要な書類は下記のとおりです。
| 書類名 | 入手先 |
|---|---|
| 相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村 |
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 被相続人の本籍地の戸籍謄本 |
| 被相続人の住民票の除票 | |
| 不動産取得者の住民票 | 本籍地または住所地の市区町村 |
| 相続する不動産の固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村 |
| 収入印紙 | 法務局・郵便局 |
| 登記申請書 | 法務局ホームページ |
| 返信用封筒 | 郵便局・コンビニエンスストア |
揃える書類は複数ありますが、「法定相続情報証明制度」を利用すると、一部の書類を省略できます。法定相続情報証明制度とは、法務局に戸籍謄本などの書類と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を写した写しを無料で交付するという制度です。これを利用すると、その写しだけで済むため、何度も書類を提出する必要がなくなります。司法書士に作成を依頼するにあたって、書類を集める必要がありますが、各種の手続きに利用できるため、申請するのも一つでしょう。
法定相続分どおりに相続した場合
法定相続分とは、民法で定められた法定相続人の相続分のことです。法定相続人は、被相続人の配偶者と一定の血族(子ども、親、兄弟姉妹)に限られています。法定相続分どおりに相続した場合、相続登記に必要な書類は先述したものに加え、相続関係説明図が必要です。ただし、法務局に申請して「法定相続情報一覧図」を作成した場合は不要となります。
遺言に基づいて相続した場合
遺言書に基づいて法定相続人が不動産を取得した場合には、「遺言書」が必要となります。先述したように、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は、家庭裁判所による検認が必要です。もし法定相続人以外が相続した場合には、次の書類が必要となります。
- 遺言執行者が遺言によって選ばれた場合:遺言執行者に選ばれた人の印鑑証明書
- 遺言執行者が家庭裁判所の審判で選ばれた場合:遺言執行者に選ばれた人の印鑑証明書、遺言執行者選任審判謄本
- 遺言執行者がいない場合:相続人全員の印鑑証明書
遺言執行者とは、遺言者の意思を実現するために、手続きなどをおこなう人のことです。
遺産分割協議に基づいて相続した場合
民法では、遺言書がない場合は法定相続割合で相続権を有するとされています。しかし、相続人全員の同意があれば、自由に相続財産を分割でき、法定相続割合よりも優先されます。相続登記をする際には「遺産分割協議書」が必要です。相続人全員の署名、実名による押印が必要となるため、忘れないようにしましょう。また、相続人の印鑑証明書も必要です。なかには被相続人の本籍地が遠方の場合もあるでしょう。郵送で請求することも可能なため、自治体に問い合わせましょう。
相続した不動産を売却するための必要書類

相続登記を終え、相続した不動産の所有権を持ったら、ようやく売却手続きに入ります。売却するための必要書類は下記のとおりです。
| マンション | 一戸建て | 土地 | |
|---|---|---|---|
| 本人確認書類 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 印鑑証明書 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 登記簿謄本または登記事項証明書 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 売買契約書 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 購入時の重要事項説明書 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 登記済権利書または登記識別情報 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 土地測量図・境界確認書 | ― | ◯ | ◯ |
| 固定資産税納税通知書または固定資産税評価証明書 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 物件の図面 | ◯ | ◯ | ― |
| 建築確認済証または検査済証 | ― | ◯ | ― |
| マンションの管理規約または使用細則 | ◯ | ― | ― |
| マンションの維持費がわかる書類 | ◯ | ― | ― |
| 耐震診断報告書 | ◯ | ― | ― |
| アスベスト使用調査報告書 | △ | △ | ― |
もし、共有名義で相続して売却する場合には、共有者全員分の実印と印鑑証明書、本人確認書類が必要となります。スムーズに売却を進めるためにも、早めに準備しておきましょう。
相続した不動産の売却時における注意点

相続した不動産を売却する際には、注意点がいくつかあるため、事前に確認しておきましょう。
共有名義の売却は名義人全員の同意が必要
共有名義の不動産を売却する時には、共有名義人全員の同意が必要です。不動産の売却は、所有権を移転する行為です。共有名義の不動産は、所有権を共有しているため、名義人全員の同意を得なければなりません。「自分の持ち分だけでも売却したい」といったことはできないため、遺産分割協議の際によく話し合いましょう。
また、売却自体の同意だけでなく、価格への同意も必要となります。例えば、Aさんが「売却価格2,000万円なら許容できる」としていても、Bさんが「3,000万円はないと納得できない」といった場合、同意が得られないため話を進められません。そのため、共有者全員で事前に最低の売却価格を決めておきましょう。査定を依頼した際に、一番低かった価格を参考にすると決めやすいでしょう。
1人で所有権を取得している時は贈与にならないよう気を付ける
相続した不動産を、相続人の1人が単独で所有権を取得し、売却したあとで他の相続人に分ける場合、贈与とみなされないように気をつけましょう。贈与とみなされてしまうと、贈与税が発生してしまいます。贈与税の発生を防ぐためにも、遺産分割協議書に、換価分割することが目的で1人が相続したことを明記しておきましょう。
実績があって信頼できる不動産会社に依頼する
相続した不動産を売却する際には、実績があって信頼できる不動産会社に依頼しましょう。相続税の納付や売却した際の特例を使える時期に期限があるため、スムーズに進める必要があります。不動産会社によって、何が強みなのかが異なります。査定価格や実績などを参考にしながら、信頼できる会社に依頼しましょう。
相続してから一定期間を過ぎて売却すると譲渡所得税が高くなる
相続した不動産を売却する際、一定期間を過ぎてから売却すると、譲渡所得税が高くなってしまいます。相続した不動産を売却した時に使える特例として2つあります。
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
先述しましたが、相続で取得した財産を一定期間に譲渡した際に、相続税額のうち一定額を、譲渡資産の取得費に加算できるというものです。相続税の申告期限(10カ月)の翌日以後3年以内に売却した時に適用されます。
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」
相続した不動産を売却した際、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できるものです。この適用を受けるためには、相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに売却する必要があります。
どちらも3年が目安となるため、相続した不動産を売却するなら3年以内といわれています。特に空き家を放置すると、崩落したり、草木がのびたりなど、近隣トラブルを引き起こしかねません。不要であれば早めに売却するのも一つでしょう。
まとめ
本記事では相続した不動産を売却するまでの手順や必要書類、注意点などを解説しました。何に基づいて不動産を分けるかによっても、必要となる書類は異なります。親族関係のトラブルとならないようにするためにも、よく話し合い、相続人全員が納得する形で進めるようにしましょう。初めてのことで慣れないことも多く、専門知識も必要となるため、遺産分割協議書の作成は行政書士や司法書士などの専門家に依頼すると安心でしょう。また、相続した不動産を売却する際には、実績があり、信頼できる不動産会社に依頼しましょう。
物件を探す

執筆者
民辻伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ