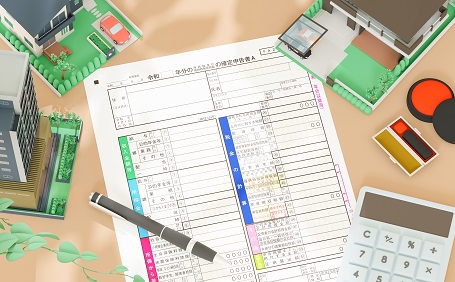マンション売却に確定申告は必要?必要書類と計算方法を解説

本記事では、マンションの売却で確定申告が必要なケースと不要なケースを紹介したうえで、確定申告をするにあたって必要なことを解説します。
記事の目次
マンション売却で確定申告が必要なケースと不要なケース

マンションの売却において確定申告が必要なケースと不要なケースを紹介します。
- 必要なケース:譲渡所得が発生している
- 不要なケース:損失が発生している
それぞれ詳しく見ていきましょう。
必要なケース:譲渡所得が発生している
譲渡所得とは、マンションなどの特定の資産を譲渡によって生ずる所得のことです。譲渡所得には日本の税法によって定められた税率がかかり、所得税・住民税を納める義務があります。
確定申告とは個人が年間で得た収入に対して、正しい手順で書類をまとめて税務署に提出し、計算した税額を納める国民の義務です。
つまり、マンションの売却に限らず譲渡所得があり、所得税・住民税の納める義務が発生したのであれば、確定申告が必要ということになります。確定申告を怠ったことがあとから発覚した場合は、「延滞税」などのペナルティ対象になるため注意が必要です。
不要なケース:損失が発生している
譲渡所得は、マンションの売却金額からマンションを購入するためにかかった取得費と売却にかかった譲渡費用を差し引くことから、譲渡所得がマイナスになることもあります。
譲渡所得を計算した結果、マイナスとなり損失が発生している場合は、所得税・住民税を課されないことになっており、原則として確定申告の義務はありません。確定申告しなかったことでペナルティなどの不都合が発生することもありません。
しかし、確定申告が不要のケースでも税法で定められた特例を適用できる場合があります。特例を適用すると、年間で支払う税金の減少などの恩恵が受けられます。特例を適用するためには確定申告が必要であるため、確定申告が不要であっても節税を考えるならしたほうがいいケースも存在します。
マンション売却の確定申告はいつまでに申告する?

マンションを売却した際の確定申告は原則として、今年の1月1日~12月31日に得た譲渡所得を、翌年の2月16日~3月15日までに申告する必要があります。最終の日付が土曜・日曜・国民の祝日・休日にあたる場合は、翌日の月曜日が期限日です。
年度によっては情勢を加味して、申告期限が引き延ばされるケースもあったことから、最新の情報は国税庁の公式サイトを確認するようにしてください。原則として、毎年決まった時期に申告する必要があるため、翌年の2月に余裕をもっておこなえるように準備を進めましょう。
マンション売却の確定申告に必要な書類

マンション売却後の確定申告に必要な書類は以下のとおりです。
- 1.確定申告書
- 2.分離課税用の確定申告書
- 3.譲渡所得の内訳書
- 4.マンションの購入・売却時の売買契約書
- 5.諸経費の明細がわかる領収書
1~3までの書類は、お近くの税務署でもらうか、国税庁の公式サイトからダウンロードできるため、確定申告の直前であっても入手に困ることはありません。
4の、マンションの購入・売却時の売買契約書の写しはご自身で用意する必要があり、5の仲介手数料・印紙税などの諸経費がわかる領収書は不動産会社に発行してもらう必要があります。
4と5の書類に関しては用意に時間がかかる場合もあるため、確定申告の時期よりも余裕をもった準備をおすすめします。
マンション売却の確定申告に必要な計算方法
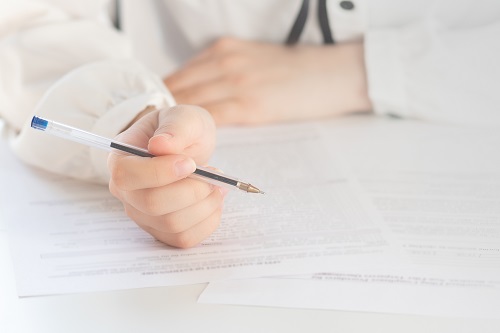
マンション売却後の確定申告では、譲渡所得で発生した実際の売却益から納めるべき税額を計算する必要があります。ご自身で計算するにあたって基本的な計算の手順と、具体的なシミュレーションをまじえて解説します。
基本的な計算の手順
マンション売却後の確定申告をするにあたって必要な譲渡所得の計算式は以下のとおりです。
・ 譲渡所得=譲渡価格-取得費-譲渡費用
譲渡価格から取得費を計算し、仲介手数料・印紙税など物件の売却にかかった経費となる費用を差し引くことで、譲渡所得が求められます。そのなかでも、取得費は減価償却費を考慮しなければならないことから計算が複雑になります。計算式は以下のとおりです。
・ 取得費=マンションの購入金額-減価償却費
マンションは経年とともに劣化するため、減価償却の考え方に基づき、経年劣化による価値の低下を算出し、マンションの購入金額から差し引くことで公平な取得費を求めます。この計算で必要なマンションの購入金額は建物部分に限ります。減価償却費を求める計算式は以下のとおりです。
このなかでもご自身で国税庁の公式サイトから調べる必要がある情報が「償却率」であり、建物の構造によって償却率が異なる仕組みです。減価償却費が求められれば取得費がわかるため、譲渡所得の計算が可能になります。
上記の計算をおこなって譲渡所得がプラスになった場合は、確定申告の義務があります。マイナスになった場合、確定申告は不要です。ただし、前述したように節税のメリットが得られるケースもあるので、その場合は確定申告をしたほうがよいでしょう。
譲渡所得に対する税額は以下の計算式で求められます。
・ 譲渡所得の税額=譲渡所得×所定の税率
譲渡所得は保有期間によって税率が変化する仕組みであり、税率は以下のとおりです。
| 所得税 | 住民税 | 復興所得税 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 (5年以内) |
30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 (5年以上) |
15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
所得税と住民税のほかに、復興所得税が2013年から2037年まで施行されていることから、復興所得税を含めて計算すると短期譲渡所得が39.63%、長期譲渡所得が20.315%になります。最後にここまで紹介した計算式を一本化して以下にまとめます。
具体的なシミュレーション
基本的な計算の手順を踏まえたうえで、具体的なシミュレーションをおこなっていきましょう。計算に必要な条件を以下にまとめました。
・譲渡価格:6,006万円・譲渡費用:200万円
・マンションの購入金額:6,000万円
・マンションの購入金額(建物部分):3,000万円
まずは、減価償却費から求めていきます。上記の条件をもとに計算式に代入すると以下のとおりです。
減価償却費が求められたことから取得費が求められます。
・取得費=6,000万円-405万円=5,595万円
取得費が求められれば、「譲渡所得=譲渡価格-取得費-譲渡費用」から譲渡所得が求められるため、代入していきます。
211万円に対して課税する金額を求めるため、所有期間が10年となっていることから、長期譲渡所得の税率を適用して計算します。
以上で、マンションを売却した際の確定申告に必要な譲渡所得の税額を実際に計算できました。確定申告の必要書類を用意したうえで、ご自身の譲渡所得の税額を計算してみましょう。
マンション売却の確定申告で知っておきたいポイント

マンションを売却した際の確定申告で知っておきたいポイントを3つ紹介します。
- 利用できる特例を把握する
- 期限内におこなわない場合は延滞税が発生する可能性がある
- 自信がない場合は税理士に依頼する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
利用できる特例を把握する
上記で紹介した譲渡所得の計算式がマイナスになった場合は、確定申告は不要です。しかし、マンションの売却において利用できる特例は多いため、ご自身に適用できる特例があるなら、節税の恩恵を目的に利用すべきです。
マンションの売却において利用できる可能性がある特例は以下のとおりとなっています。
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
- 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率適用の特例
- 特定の居住用財産を買い換えた時の特例
- 居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
- 住宅ローンが残る居住用財産を売却した場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
上記の特例はご自身で申告することで受けられるため、条件を満たしている場合でも申告しなければ恩恵は受けられません。譲渡所得に損失が出た場合でも、一定の要件を満たせば適用できる特例となっているため、確定申告が不要であっても申告するべきか迷う方は特例を確認してみましょう。
期限内に確定申告をしない場合は延滞税が発生する可能性がある
確定申告を期限内におこなわなかった場合は、延滞税が発生する可能性があります。また、税務署から通知があるまで申告しなかった場合は、延滞税に加えて無申告加算税が課され、悪質と判断された場合は重加算税が課せられます。
確定申告の期間である2月16日~3月15日までに正しく申告しているのであれば、課されることがない税金であるため、義務がある場合は必ず申告するようにしましょう。
自信がない場合は税理士に依頼する
ここまでマンションを売却した際の確定申告について紹介しましたが、ご自身でできる自信がない場合は税理士に依頼することも選択肢のひとつです。税理士に依頼する場合は依頼料を支払う必要があります。
しかし、税法に対する深い知識を持つ税理士に依頼すれば、ご自身では気付かなかった特例や節税制度を適用して申告できる場合もあるため、節税効果が依頼料を上回ることも期待できます。
初めて確定申告する場合は慣れないことも多く、費用をかけてでも税理士への依頼はおすすめです。確定申告に自信がない場合は、税理士への依頼も検討したうえで、正しい申告を心がけましょう。
まとめ
マンション売却後の確定申告は、譲渡所得を計算すれば確定申告が必要であるかがわかります。譲渡所得で利益が発生した場合は、定められた時期に必ず申告するようにしましょう。一方で、損失が出ており不要であった場合も、特例の適用により節税のメリットが得られる可能性があるため、申告を検討しましょう。必ずしもご自身で申告する必要はなく、税理士に依頼する選択肢もあるため、総合的に判断しましょう。
物件を探す

執筆者
長谷川賢努
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ