不動産の売却時にふるさと納税するとお得?計算方法と手続きの流れや注意点を徹底解説

本記事では、不動産売却後の税負担を減らし、実質的な利益を得るためのふるさと納税の活用法を解説します。さらに、控除額の算出方法や活用するタイミングにも触れるため、税金対策に役立ててください。
記事の目次
不動産売却時にふるさと納税するとお得になる仕組みは?
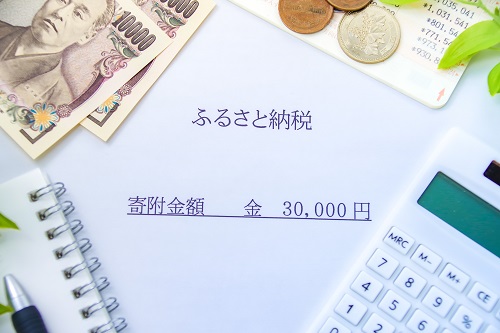
不動産を売却すると、その取引により利益(譲渡所得)が発生する場合があります。利益が出ると所得とみなされ課税対象になり、通常の年よりも多くの税金を支払わなければなりません。そのような時に有効に活用できる制度がふるさと納税です。本章では、不動産の売却とふるさと納税がどのように関係し、どのようにお得になるのかを解説します。
不動産を売却すると譲渡所得が発生する場合がある
まずは、不動産の売却時に発生する譲渡所得について解説します。譲渡所得とは、売却価格から取得費(購入時の価格や諸経費)や譲渡費用(仲介手数料、登記費用など)を差し引いた金額です。また、「3,000万円特別控除」などの特例制度もあり、マイホームを売却した場合にはその分を差し引けるため、譲渡所得を抑えられる可能性があるでしょう。
ただし、それらを差し引いてもなお利益が出る場合には、譲渡所得となり、所得税・住民税の課税対象になります。特に地価の高いエリアや、長期間保有して値上がりした物件を売却した場合、想定以上に大きな譲渡所得が発生する場合もあるため、事前の試算が重要です。不動産の売却は一時的に多額の収入となるため、税金対策を講じる必要が出てくるでしょう。
譲渡所得が発生した時にかかる税金
譲渡所得が発生した場合、分離課税の対象となり、通常の給与所得などとは別に所得税と住民税がかかります。税率は不動産の保有期間によって異なり、具体的には下表のとおりです。
また、マイホーム(居住用財産)を10年超所有して売却した場合には、「居住用財産の軽減税率の特例」が適用される点も確認しておきましょう。この特例で、長期間保有してきた自宅を売却した際の税の負担軽減が可能です。
| 所有期間 | 所得税 (復興特別所得税を含む) |
住民税 | |
|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% |
| 所有期間10年超の 軽減税率 *適用条件あり |
10年超 | 6,000万円以下の部分:10.21% 6,000万円超の部分:15.315% |
4% 5% |
このように、不動産を売却し、短期譲渡所得だった場合、売却益の約40%もの税金が課される可能性があるため、多くの方にとって負担となるでしょう。この税負担をうまく軽減できる有効な手段のひとつがふるさと納税です。
ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、地域への寄附を通じて実質的に税金を控除できる制度です。具体的には、自分が選んだ自治体に対して寄附をおこない、翌年の所得税や住民税から一定額の控除が受けられます。寄附をおこなうと、寄附金のうち2,000円を除いた金額が控除対象となり、実質2,000円の負担で返礼品(特産品や宿泊券など)が受け取れます。
なお、ふるさと納税で寄附する金額には上限がありませんが、控除できる金額には上限があります。その年の所得や家族構成、扶養状況などによって異なり、上限額を超えて寄附した分は自己負担となるため、事前にシミュレーションしておくようにしましょう。
ふるさと納税は、税金を自分の意志で振り分けられる制度で、特に所得が高くなった年ほど効果が大きくなります。
また、控除を受けるには確定申告が必要です。不動産売却において利益が発生した場合、確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる「ワンストップ特例制度」は利用できないため注意が必要です。
譲渡所得発生時にふるさと納税をおこなうとどのようになるか
不動産を売却して利益が生じた年に、ふるさと納税を活用すると、税負担の軽減と実質的なメリットの両方が得られます。ふるさと納税をしない場合は、単純に税金を国や自治体に納めるだけで、何も手元には残りません。しかし、ふるさと納税をすれば、支払う税額は基本的に変わりませんが、追加で2,000円を負担するだけで、その寄附先の自治体から返礼品を受け取れます。
つまり、同じ税金を支払うなら、少しの負担で実質的な見返りを受けられる点が、譲渡所得が出た年にふるさと納税をおこなうメリットです。高額な譲渡益が出た年ほどふるさと納税の控除上限額も大きくなるため、多くの寄附が可能となり、より多くの返礼品を受け取れるチャンスになるでしょう。
例えば、通常の年収に数百万円の譲渡所得が加算されると、ふるさと納税で控除される金額も大きくなります。その結果、通常なら数万円の寄附しかできなかった方でも、10万円以上の寄附が実質2,000円の負担で可能になる場合もあります。このような場合、翌年の所得税と住民税が軽減されるだけでなく、寄附をおこなった自治体から魅力的な返礼品を受け取れるため、経済的なメリットも享受できるでしょう。
また、寄附する金額が大きくなるほど、受け取れる返礼品の価値も上がります。基本的に、返戻品の金額は寄附金の3割以下です。例えば、1万円の寄附では、3,000円相当の返礼品が送られてくるのに対し、10万円の寄附では3万円程度の品物が受け取れるでしょう。不動産の売却益を活かすと、普段よりも高価な特産品やサービスを受け取れることになります。
不動産売却時にふるさと納税を利用するとよいケース

不動産を売却する際、ふるさと納税を活用するとよいのは、特にどのようなケースでしょうか。以下で詳しく説明します。
取得費がわからない不動産の売却時
不動産を売却した際の税金は、譲渡所得に対して課税されます。この譲渡所得は次の計算式で求められます。
売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
しかし、古い不動産や相続した不動産などでは、購入当時の契約書や領収書が残っておらず、取得費が不明な場合も少なくありません。取得費がわからない場合、税法上では概算取得費の扱いになり、売却価格の5%にしかなりません。つまり、売却価格の95%が課税対象になるため、課税所得が大きくなり、多額の税金が発生するでしょう。
このように取得費がわからないケースでは、ふるさと納税の活用が効果的です。その年の課税所得が大きくなる分、ふるさと納税の控除上限額も比例して上がります。結果、数万円〜十数万円の寄附を実質負担2,000円でおこなえるようになり、住民税や所得税の一部が控除されるでしょう。寄附する金額の目安を早めに把握し、計画的に実施しましょう。
特別控除を使えない場合
マイホームを売却した場合、一定の要件を満たせば3,000万円の特別控除が適用され、譲渡所得から3,000万円までを非課税にできます。しかし、この特別控除はすべてのケースで適用できるわけではありません。例えば、居住用ではない投資用不動産の売却や、引越し後に空き家となってから長期間経過した物件、さらには親名義の家を相続してすぐに売却した場合などは、控除の対象外になる可能性があります。こうした場合は譲渡所得の全額に課税されるため、所得税・住民税を合わせて20%超の税負担が発生するかもしれません。
このように特別控除が使えず税額が大きくなる年には、ふるさと納税の控除上限額も増えるため、より多くの寄附が可能となります。
ふるさと納税上限額のシミュレーション

ふるさと納税を上手に活用するには、自分がどれだけ寄附できるか、つまり控除上限額の正確な把握が欠かせません。この上限を超えて寄附しても、超過分は自己負担となるため、効果を最大化するには控除上限額を把握しておきましょう。なお、控除上限額は年収や家族構成、所得控除の内容などで異なるため、人により金額は大きく変わります。
本章では、具体的な数字をもとに、ご自身で上限額を計算するためのステップを見ていきましょう。なお、本章で解説する計算式では、わかりやすく考えるため、復興特別所得税を抜いて計算しています。
ステップ1.住民税所得割額(総合課税分)を調べる
まずは、住民税所得割額(総合課税分)を計算します。給与所得控除後の所得金額を確認しましょう。これは、会社員など給与所得者にとって基本的な収入の情報で、源泉徴収票でかんたんに確認できます。源泉徴収票の支払金額が年収に該当し、そこから一定の控除(給与所得控除)を差し引いた金額が給与所得です。この控除額は年収に応じて定められており、例えば年収500万円の方なら、おおよそ170万円が給与所得控除となり、給与所得は約330万円になるでしょう。
源泉徴収票で確認する項目は「給与所得控除後の金額」です。この金額がふるさと納税の控除限度額を算出する際のベースとなるため、まずはこの数値を正確に把握しておきましょう。また、医療費控除や社会保険料控除など、所得控除を受ける予定がある場合は、それらも加味する必要があります。これらの控除が多いほど課税所得は減り、結果、ふるさと納税の上限額も小さくなるため、控除を正確に把握しておきましょう。
住民税所得割額(総合課税分)の計算式は全国一律で10%となっています。
住民税所得割額(総合課税分)= 所得控除後の金額 × 10%
ステップ2.不動産譲渡所得から住民税所得割額(分離課税分)を計算する
1章で紹介したとおり、分離課税分の住民税の税率は、売却した不動産の所有期間で異なっていました。
| 所有期間 | 税率 |
|---|---|
| 5年以下(短期譲渡所得) | 9% |
| 5年超(長期譲渡所得) | 5% |
| 10年超(軽減税率の特例) | 6,000万円以下の部分:4% 6,000万円超の部分:5% |
住民税所得割額(分離課税分)の計算式は以下のとおりです。
住民税所得割額(分離課税分)= 課税所得 × 税率
ステップ3.ふるさと納税控除額上限額の目安を計算する
ここで具体的な数値を入れて、ふるさと納税の控除上限額を求めてみましょう。まず、控除上限額の計算式は以下になります。
控除上限額 = 個人住民税所得割額 × 0.2 ÷(0.9 - 所得税の税率)+ 2,000円
復興特別税率を考慮した場合は、下記のとおり。
控除上限額 = 個人住民税所得割額 × 0.2 ÷(0.9 - 所得税の税率 × 1.021)+ 2,000円
計算時の条件は以下とします。
| 課税譲渡所得 (控除などもすべて計算後) |
200万円 |
|---|---|
| 売却物件の所有期間 | 9年 |
| 年収 (所得控除などしたあとの課税所得) |
500万円 |
| 所得税率 | 20% |
まずは、総合課税分の住民税所得割額から求めます。
住民税所得割額(総合課税分)= 500万円 × 10% = 50万円
次に、分離課税分の住民税所得割額は次のとおりです。
住民税所得割額(分離課税分)= 200万円 × 5%(長期譲渡税率)=10万円
最後に、控除上限額を計算してみましょう。
(10万円 + 50万円)× 0.2 ÷(0.9 - 0.2)+ 2,000円 = 17万3,428円
今回の前提条件の場合、ふるさと納税の控除額上限額は約17万3,400円となります。不動産を売却して利益が出た年は、譲渡所得が大きくなるため所得税や住民税の負担も増加しますが、それにともないふるさと納税の控除上限額も大幅に増えるでしょう。
特に年収が高い方や、不動産の売却によって一時的に所得が跳ね上がった方には、ふるさと納税の上限額が通常よりも高く設定され、返礼品の種類や量も充実したものとなります。自分の上限額がどの程度になるかを把握するには、ふるさと納税のシミュレーションサイトの活用がおすすめです。年収や家族構成などを入力するだけで、目安の上限額を簡単に知ることができるため、利用してみましょう。
不動産の売却でふるさと納税を利用する時の注意点

不動産の売却にともない譲渡所得が発生した年は、ふるさと納税の控除上限額が増えるため、大きな節税効果を狙えるタイミングです。しかし、その反面、通常の年とは異なる注意点がいくつか存在します。制度の仕組みや期限、確定申告との関係を正しく理解しておかなければ、本来受けられるはずの控除が無効になったり、損をしたりするかもしれません。
特に確定申告が必須になるケースや、ワンストップ特例制度が使えない点など、不動産売却特有の条件に気をつける必要があります。本章では、不動産の売却でふるさと納税を利用する時の注意点を見ていきましょう。
確定申告が必須になる
不動産を売却して譲渡所得が発生した場合、ほとんどの方は確定申告をおこなわなければなりません。そして、ふるさと納税で控除を受けるには、この確定申告の際に寄附金控除を正しく申告する必要があります。寄附金控除を受けるためには、各自治体から発行される寄附金受領証明書が必要です。これをもとに、確定申告書の該当欄に寄附金額を記入し、証明書を添付、またはe-Taxでデータ送信をすると、翌年の住民税から控除されるでしょう。
確定申告を忘れてしまったり、寄附金控除を申告しなかった場合、ふるさと納税の効果は一切反映されません。特に年が明けてからは不動産の売却による譲渡所得の申告に意識が集中し、ふるさと納税の申請をうっかり忘れてしまうケースも見られます。節税効果をしっかり得るためにも、寄附証明書の管理と確定申告の準備を計画的におこなうようにしましょう。
ワンストップ特例は利用できない
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税に設けられた便利な仕組みです。確定申告が不要な給与所得者などが、寄附先の自治体に申請書を送るだけで、ふるさと納税の控除を自動的に反映してもらえる制度になります。通常、5自治体以内の寄附ならこの制度を利用できますが、不動産の売却で譲渡所得が発生し、確定申告が必要な場合は、この制度を使用できません。確定申告とワンストップ特例制度は併用できないため、ふるさと納税の寄附も確定申告で申請する必要があります。
もしワンストップ特例制度の申請をしていても、確定申告をおこなえばそれは自動的に無効となり、寄附分の控除が適用されなくなるでしょう。そのため、不動産の売却をおこなった年にふるさと納税を利用する場合は、最初から確定申告で控除を受ける前提で準備しておく必要があります。
控除額の上限をよく確かめる
ふるさと納税のメリットを最大限に活かすには、自己の控除上限額の正しい把握が不可欠です。控除上限額は、年間の所得額と家族構成、社会保険料や生命保険料控除などの状況によって決まります。特に不動産の売却で譲渡所得が増えた年は、通常よりも上限額が大きくなる傾向がありますが、これは必ずしも単純計算できるわけではありません。
譲渡所得は分離課税のため、また特別控除や他の控除制度との兼ね合いで実際の控除可能額が変動するためです。インターネット上のシミュレーターでは概算しか出せないため、金額が大きい場合は税理士やファイナンシャルプランナーなどに相談して、より正確な上限額を見積もるようにしましょう。上限を超えて寄附してしまった場合、その超過分は単なる寄附になり、税金の控除は受けられません。単なる寄付目的ではなくふるさと納税をおこなうなら、上限額を把握しておく点がポイントです。
ふるさと納税の決済日に注意する
ふるさと納税の控除対象になる期間は、その年の1月1日から12月31日までに寄附(決済)した金額です。したがって、不動産を売却して譲渡所得が出た場合でも、その年の12月31日までにふるさと納税の決済を完了していなければ控除の対象になりません。注意すべきことは、申込日ではなく決済日が基準になる点です。クレジットカード決済やオンライン決済では即時に処理されますが、銀行振込やコンビニ支払いなどの場合、支払いが年をまたぐと翌年分の寄附になり、控除の対象外となるかもしれません。
また、決済が年末間近になると、自治体側の処理が混雑する可能性があり、書類の発送や確認に遅れが生じるリスクもあります。そのため、売却のタイミングを見て、年内の早い段階で寄附を済ませるようにしましょう。特に12月中旬以降の申し込みには慎重さが求められます。
特別控除を受けられる場合にはふるさと納税はおすすめでない
不動産の売却に際して「3,000万円特別控除」などの譲渡所得に対する控除制度が適用される場合、譲渡所得が0円またはマイナスになる可能性があります。この場合、課税される譲渡所得がないため、実際には所得全体が増えておらず、ふるさと納税の控除上限額も増えていないでしょう。控除上限は所得全体に基づいて計算されるため、給与所得など他の収入がない方にとっては、ふるさと納税をおこなっても控除が受けられず、自己負担が増えるだけになる可能性もあります。
つまり、課税されない譲渡所得に対して、ふるさと納税をしてもメリットがありません。加えて、3,000万円特別控除の適用を受ける場合は、その適用条件(居住用の住宅、住まなくなってから3年以内の売却など)にも注意が必要です。ふるさと納税をおこなう前に、自分の売却がどのように課税対象となるか、税理士などの専門家に確認したほうがよいでしょう。
不動産売却時のふるさと納税活用に関するよくある質問
不動産の売却時のふるさと納税活用に関するよくある質問をまとめました。
不動産の売却時にふるさと納税するとどうお得?
不動産の売却で多額の譲渡所得が発生した年にふるさと納税を活用すると、税金の負担を軽減しながら実質的な見返りが期待できてお得です。
ふるさと納税は、地域に寄附をして所得税と住民税の控除を受けられる制度で、寄附金額のうち2,000円を除いた金額が控除の対象です。通常は年収に応じて控除額の上限が決まっていますが、不動産の売却によって一時的に所得が増加すれば、その上限も上がるため、普段より多くの寄附ができ、返礼品もより充実したものを受け取ることができます。
不動産の売却時にふるさと納税をするとよいのはどのようなケース?
次のような場合でふるさと納税をすると有効でしょう。
- 取得費が不明な古い不動産や相続物件を売却する場合
- マイホームの3,000万円特別控除が適用されない場合
例えば、取得費が不明の物件を売却する場合、取得費が概算(売却額の5%)となり、課税所得が大幅に増えるかもしれません。しかしふるさと納税で、2,000円の自己負担で、地域の返礼品を受け取りつつ、税金の還付も受けられるため、負担増の年こそ計画的に活用しましょう。
不動産を売却してふるさと納税をする時の控除額上限はどう計算する?
まず、住民税所得割額(総合課税分)と譲渡所得から住民税所得割額(分離課税分)を計算し、次の計算式に当てはめて計算します。
控除上限額 = 個人住民税所得割額 × 0.2 ÷(0.9 - 所得税の税率)+ 2,000円
なお計算が難しい場合は、シミュレーション機能を活用すると、自分の目安を簡単に確認できます。控除上限額は年収や家族構成、所得控除の内容により大きく異なるため、より正確な計算は専門家に依頼したほうがよいでしょう。
不動産売却の年にふるさと納税を活用する時の注意点は何?
不動産売却の年にふるさと納税を活用する際は、確定申告や控除条件に注意し、制度を正しく理解したうえで行動することが重要です。
不動産の売却で譲渡所得が発生した場合、確定申告が必須となり、ふるさと納税による控除を受けるためには寄附金受領証明書を添えて正しく申告しなければなりません。ワンストップ特例制度は確定申告と併用できず、自動的に無効になるため、はじめから確定申告を手続きする前提で準備を進める必要があります。
また、譲渡所得がある年は一時的に所得が増え、控除上限額も上がる可能性がありますが、これは他の控除制度や課税区分の影響で一概にいえません。正確な上限額を知るには専門家に相談しましょう。
さらに、ふるさと納税の控除対象となるには、その年内に決済を完了させる必要があり、特に年末のタイミングには余裕を持って行動しましょう。ただし、3,000万円特別控除などが適用されるケースでは課税所得が発生しないため、ふるさと納税をおこなっても控除を受けられず、単なる寄附となるリスクがあります。こうした点を踏まえ、メリットを求めてふるさと納税を検討するなら、不動産売却による所得や税負担の状況を正確に把握して、適切に手続きを進めましょう。
まとめ
本記事では、不動産の売却後にふるさと納税を活用する方法を紹介しました。不動産の売却による譲渡所得の増加は、税負担を重くしがちですが、ふるさと納税をおこなうと実質的な負担を軽減し、加えて地域特産品などの返礼品を得られます。特に、取得費が不明な物件や特別控除が適用されない場合、ふるさと納税は大変有用でしょう。
ただし、控除額の上限は所得や税率によって異なるため、計算方法やシミュレーションを使った事前の確認が欠かせません。適切に専門家の助言を受け、税制や手続きに関する注意点をしっかり把握し、計画的に活用しましょう。
物件を探す
注文住宅を建てる

執筆者
民辻 伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ





