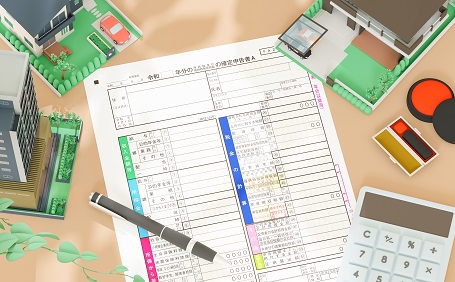相続した不動産の売却は確定申告が必要?不要?税金を抑える特別控除も解説!

今回は、売却した際にかかる税金や、確定申告が必要なのか、税金負担を減らす特例について解説します。ここで取り上げるケースはあくまで例ですが、基本的な考えを押さえておきましょう。
記事の目次
相続した不動産の売却は確定申告が必要?不要?

相続した不動産を売却した際に、売却益が出た場合には確定申告が必要です。土地や建物の売却による所得を「譲渡所得」といい、利益に対して所得税がかかります。
譲渡所得の計算式
譲渡所得は次の式で求められます。
譲渡所得=収入金額―(取得費+譲渡費用)
収入金額とは相続した不動産の売却価格です。売買契約書に記載されているため、確認しましょう。
取得費とは、被相続人(不動産を残して亡くなった人)が不動産を取得した際にかかった費用のことです。具体的には、不動産の購入費や不動産会社に支払った仲介手数料などが該当します。また、売却した不動産に建物が含まれる場合は、減価償却分を差し引きましょう。
土地の価値は変わりませんが、建物の場合、時間が経つとともに価値が下がっていきます。そのため、下がった価値の分を引く必要があります。
譲渡費用とは、相続した人が不動産を売却した際にかかった費用のことです。例えば、建物の解体費用や印紙税などがあたります。
上記の式でマイナスだった場合は、譲渡所得がないため、確定申告の必要はありません。
確定申告する際の注意点
相続した不動産を売却した場合、通常の売却と違い、気をつけなければならない点があります。
取得費は被相続人が取得した費用で計算する
前項でも説明しましたが、取得費は被相続人が不動産を取得した際にかかった費用で計算します。例えば、両親が亡くなり、実家を相続した場合には、両親が実家を購入した際の費用で計算します。購入した時から時間が経っており、書類が残っていない場合もあるでしょう。その際は、収入金額の5%相当額を取得費として計算できます。
減価償却費は被相続人が取得した時から計算する
売却した不動産に建物が含まれていた場合、減価償却分を引く必要があります。この減価償却分は、自分が相続した時ではなく、被相続人が購入した時から計算します。相続した不動産の場合、時間が経っていることから、減価償却費が高額になることも珍しくありません。そのため、結果として取得費が少なくなり、譲渡所得も高額になる場合もあります。
減価償却費の計算式は次のとおりです。
減価償却費 = 取得価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数
経過年数が1年未満の場合の端数は、6カ月以上は1年、6カ月未満は切り捨てて計算します。また、償却率は、鉄骨や木造など建物の構造によって異なります。詳細は国税庁のホームページを確認しましょう。
申告不要の場合の注意点
先ほどの譲渡所得を求める式でマイナスだった場合、確定申告は不要です。しかし、税務署から「お尋ね」という文書が届くことがあります。税務署は、不動産の売買があったことを登記簿の記録から把握しているため、譲渡所得の有無を確認します。
文書が届いた場合には、書類に記入し、譲渡所得がなかったことを伝えましょう。
相続した不動産を売却した時にかかる税金

相続した不動産を売却した際にかかる税金は何があるのでしょうか。なかには確定申告で譲渡費用に含められるものもあります。今一度、どういう税金があるのか、確認しておきましょう。
登録免許税
登録免許税とは、不動産の登記や登録について課税されるものです。不動産をはじめ売却した際、所有権が新しい所有者に移転するため課税されます。一般的に買主が負担しますが、不動産の売却金額で住宅ローンを完済した場合には、抵当権抹消の登記手続きをしなければなりません。この場合は1つの不動産につき、登録免許税として1,000円がかかります。
印紙税
印紙税とは、契約書や領収書などの課税文書に対してかかる税金です。不動産を売却する際に取り交わした売買契約書に課税されます。契約金額によって印紙税の金額は異なり、以下のようになっています。
| 不動産譲渡契約書 | 本来の 印紙税 |
軽減後の印紙税 (2024年3月31日に作成されるもの) |
|---|---|---|
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円超10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円超50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円超 | 60万円 | 48万円 |
また、印紙税は軽減措置が適用されており、2024年3月31日までに作成されるものが適用されます。これはもともと2022年3月31日まで適用だったものが延長されました。法律の改正によって納める金額が変わるため、最新の情報をチェックするようにしましょう。
譲渡所得税
不動産を売却した際に得た利益に対してかかる税金です。先述した譲渡所得に、所有期間で異なる税率をかけます。
| 所有期間 | 税率 |
|---|---|
| 5年以下 | 30% |
| 5年超 | 15% |
この所有期間は、被相続人が取得した時から計算します。自分が相続した時からではない点に注意しましょう。
住民税
相続した不動産を売却した場合、住民税も課税されます。譲渡所得税と同様、所有期間によって税率が異なり、下記のとおりです。
| 所有期間 | 税率 |
|---|---|
| 5年以下 | 9% |
| 5年超 | 5% |
所有期間は、売却した年の1月1日時点の所有期間で判断するため、売却日ではないことに気をつけましょう。
譲渡所得税の計算例
実際どれくらいの税金がかかるのか、気になるところでしょう。例として、亡くなった両親が4,000万円で購入した不動産を、5,000万円で売却した時の譲渡所得、譲渡所得税を計算してみましょう。
まずは譲渡所得から求めていきます。
収入金額:5,000万円
取得費(両親が購入した金額):4,000万円
登録免許税:16万円
譲渡費用(仲介手数料など) 156万円
印紙税:2万円
5,000万円 -(4,016万円+158万円)= 826万円
例の場合、826万円が譲渡所得となりました。控除がある場合は控除額を引いたあと、所定の税率をかけて、譲渡所得税を計算します。
所有期間が30年だったとして、譲渡所得税を計算してみましょう。所有期間が5年超のため、税率は15%です。
826万円 × 15% = 123.9万円
なかなか大きな金額になるのがわかります。しかし、控除が利用できる場合には、差し引くことができるため、譲渡所得が発生しない可能性もあります。利用できる控除がないか、確認するようにしましょう。
相続した不動産の売却後の確定申告で利用できる特別控除

一定の要件に当てはまる場合、確定申告で利用できる特別控除があります。控除を適用すると、譲渡所得から差し引くことができるため、その分、税負担を軽減でます。本章では、相続した不動産を売却した場合に適用できる控除を解説します。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除
居住用財産を売却して譲渡所得が発生した場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できます。ただし、この適用を受けるには、相続した人が住んでいなければなりません。つまり、親子で住んでいて、親が亡くなって子が相続した場合には適用されます。
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除
相続した空き家や土地を売却し、譲渡所得が発生した場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円までを控除できます。この適用を受けるための主な要件は、次の3つです。
- 昭和56年5月31日以前に建てられたこと
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと
- 相続の開始直前において、被相続人以外に住んでいた人がいなかったこと
なお、2024年1月1日以後に売却し、被相続人の居住用財産を相続した相続人数が3人以上である場合は、2,000万円までの控除となります。他にも細かな要件があるため、税理士などの専門家に確認しながら進めましょう。
取得費加算の特例
相続した不動産を一定期間内に売却した場合、相続税額のうち一定の金額を取得費に加算できます。一定期間とは、相続開始の翌日から3年10カ月以内です。適用する場合には、確定申告の際、相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書を提出する必要があります。この書類を利用すると、取得費に加算できる相続税額を求められるため、一度計算してみるといいでしょう。
相続した不動産の売却後の確定申告で必要な書類

確定申告をすると、譲渡所得税の金額が確定し、その金額を納めます。もし、譲渡所得があるにも関わらず確定申告をしなかった場合、ペナルティとして無申告加算税を払わなければなりません。本章では、確定申告に必要な書類を解説します。
| 書類の種類 | 入手先 |
|---|---|
| 確定申告書 | 税務署 国税庁のホームページ |
| 譲渡所得の内訳書 (確定申告書付表兼計算明細書) 【土地・建物用】 |
|
| 登記事項証明書 | 売却した不動産を管轄する法務局 |
| 不動産購入時の資料 | 自分で用意する |
| 不動産売却時の資料 | |
| 本人確認書類 |
確定申告書
譲渡所得の申告は確定申告書の第一〜第三表まで使用します。第一表には給与所得や所得控除など、第二表には社会保険料控除などの詳細を記入します。第三表には、分離課税用の申告書で売却した不動産の場所や必要経費などを記入する必要があります。
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】
譲渡所得がいくらになるのかを計算し、証明するための書類です。売却した日や売却金額などを記入します。適用できる特例があれば、それも記入する必要があるため、自分が何を適用できるのか事前に確認しておきましょう。
登記事項証明書
相続時から売却時までの登記の流れを確認するためのものです。売却した不動産を管轄している法務局で入手しましょう。オンラインでの申請も可能なため、仕事で忙しい場合などには利用してみましょう。
不動産購入時の資料
被相続人が不動産を購入した際の売買契約書や仲介手数料などの領収書です。取得時期が古い場合、資料が残っていない可能性もあります。その場合は、取得費を収入金額の5%として計算しましょう。
不動産売却時の資料
相続した不動産を売却した際の売買契約書や印紙税、仲介手数料などの領収書が該当します。金額が多いほど、税負担を軽くすることができます。確定申告書に売却金額など記入する際にも必要なため、探しておきましょう。
相続した不動産の売却後の確定申告の流れ

初めて確定申告をおこなう方もいるでしょう。確定申告の時期は不動産を売却した翌年の2月16日〜3月15日までとなっています。終盤になるほど、税務署は大変混雑するため、早めに申告するためにも事前に準備を済ませておきましょう。
1.必要書類を準備する
先述した必要書類を準備しましょう。被相続人が取得した時の書類は時間が経っていたりと、探すのに手間がかかることも。ゆとりをもって確定申告をおこなうためにもなるべく早めに探しておきたいですね。
2.書類に記入する
確定申告書や譲渡所得の内訳書に記入しましょう。記入漏れやミスがあると、受理されず、再度提出しなければなりません。一つずつ正確に記入しましょう。
3.税務署に提出する
記入した書類を住所地の税務署へ持ち込むか郵送しましょう。もしマイナンバーカードがあるなら、電子申告であるe-Taxを利用すると、自宅にいながら申告が可能です。不明点や疑問点があれば、税務署や税理士に問い合わせてみましょう。税理士会が主催する無料相談会などを利用すると、的確なアドバイスが受けられます。
4.納税する
確定申告を通して確定した税金を、期限までに納めましょう。クレジットカードやコンビニエンスストアでも支払うことができます。ただし、クレジットカード決済の場合は手数料が発生します。また、コンビニエンスストアでの納付は、事前にQRコード付きの納付書が必要で、30万円以下までとなります。
納付額が高額の場合は、金融機関の窓口でおこなうのが安全でしょう。気をつけなければならないのは、納税の期限も確定申告書の提出期限と同じ3月15日であることです。提出だけを済ませて、満足しないようにしましょう。
まとめ
今回は、相続した不動産を売却したあとの確定申告について解説しました。譲渡所得が発生していない場合は、申告が不要です。しかし、税務署は売却したことを把握しているため、「お尋ね」文書が届くことがあります。届いた際には書類に記入し、譲渡所得が発生しなかったことを伝えましょう。
確定申告をする際は、利用できる特別控除がないか必ず確認をおこないます。一人ひとり適用できる特別控除は違うため、税務職員や税理士などの専門家に相談すると、より的確なアドバイスがもらえるでしょう。
物件を探す

執筆者
民辻伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ