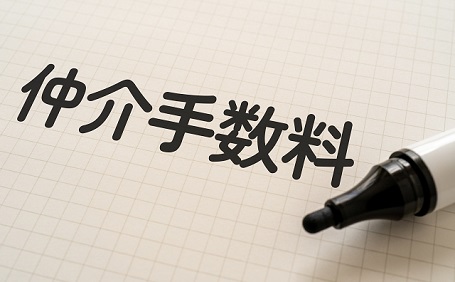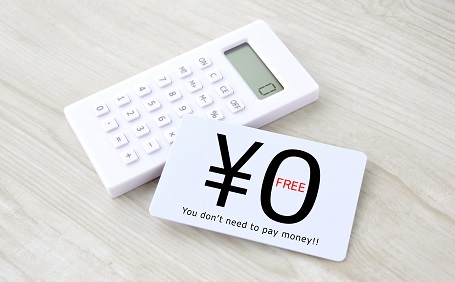社会人が一人暮らしを始めるのに必要なことは?初期費用や物件の選び方について解説

記事の目次
社会人が一人暮らしを始めるタイミングは?

社会人が一人暮らしを始めるタイミングには、年齢的な節目や金銭的な余裕、自立心、恋人の有無などが関係していると考えられます。実際のきっかけや時期を、具体的に見てみましょう。
新卒入社直後のタイミング
短大や大学を卒業し、就職するタイミングで一人暮らしをするケースは少なくありません。精神的・金銭的に独立したいと考えたり、入社した会社までの利便性を考慮したりして一人暮らしを始める方が多いようです。
就職して数年後のタイミング
就職して数年間は実家で暮らしながら貯蓄額を増やし、金銭的に余裕が生まれた時期に一人暮らしを始めるケースです。年齢や精神的な変化に伴い、自立したいと考える場合も絶好のタイミングといえます。
転職のタイミング
遠方の配属先に転職が決まるなど、住む場所を変えざるを得ないタイミングがあります。その際は、一人暮らしをするチャンスと前向きに捉え、自分自身の成長へとつなげましょう。
結婚や同棲をするタイミング
結婚や同棲を考える恋人ができた際も、一人暮らしを始めるのによいタイミングです。ただし、同棲する場合は二人暮らしが可能な物件を探す必要があるため、相手ときちんと検討することが大切です。
社会人が一人暮らしを始める際にかかる費用は?

一人暮らしをするには、それなりに費用がかかります。新居への引越しにかかる初期費用から、家具・家電の購入費、家賃や光熱費といった固定費用までを細かく見ていきます。
初期費用
引越しには以下のような初期費用が発生します。賃貸物件の契約に必要な初期費用の目安は、家賃の5~6か月分といわれています。もちろん、それを踏まえて資金面を検討することも大切ですが、初期費用を抑える術も知っておいて損はありません。
例えば敷金・礼金0円の物件を探したり、賃貸物件の契約において一定期間の家賃が無料になるフリーレントの物件を検討したり、複数の引越し業者を比較したり。さまざまな方法が存在するので、それも含めて費用別に説明します。
前家賃
前家賃とは、賃貸物件の契約時に翌月分の家賃を前もって支払うことです。家賃と管理費、共益費などをまとめて指します。これは、家賃の滞納リスク防止と退去時のトラブルを減らすためという理由からです。
日割り家賃
日割り家賃とは、賃貸借契約を月の途中で結んだ場合に発生する費用です。一般的には、家賃の月額を日数で割って計算します。
家賃 ÷ 月の日数 × 入居日数
家賃が発生する時期は、契約前に借り主と貸し主の話し合いで決めることが多いようです。
敷金
敷金とは、賃貸物件を借りる際に貸し主や管理会社に預ける費用のことです。これは、家賃の未払いや原状回復費用に備える担保としての役割があります。金額は家賃の1~2か月分が相場です。基本的には退去時に全額返金されますが、家賃の滞納や借り主に責任がある損傷の修繕費は差し引かれます。
礼金
礼金とは借り主から貸し主に支払われる一時金で、大家に対するお礼の意味合いで渡されます。金額は家賃の1~2か月分が相場です。最近は、敷金とともに礼金0円の物件も増えています。初期費用を抑えたい場合は、敷金・礼金が必要か必ず確認してください。
仲介手数料
仲介手数料とは、賃貸の契約が成立した際に不動産会社に支払う報酬です。入居審査や契約などの手続きをサポートしてくれた対価として支払います。金額は「家賃の0.5~1ヶ月分+消費税」とされるケースが多いようです。
火災保険料
火災保険料とは、火災や落雷、風災、盗難などの事故によって建物や家財に損害が生じた場合に支払われる費用です。金額は保険会社が定める保険金額や建物の構造、築年数、補償内容などによって異なりますが、1年あたり約7,000円~1万5,000円が目安です。
保証会社手数料
近年、連帯保証人の代わりに保証会社を必須としている物件も増えています。
保証会社手数料とは、賃貸物件を借りる際に保証会社に支払う費用です。初回保証料の相場は、家賃の50~100%とされています。
鍵交換費用
鍵交換費用とは、物件の鍵とシリンダーを交換する際に発生する費用です。前の入居者が合鍵を作っている可能性があるため、防犯上の理由で鍵を交換する必要があります。金額は1万~3万円程度が相場です。
引越し会社費用
引越し費用は荷物の量や移動距離、時期、業者によって大幅に変わってきます。単身者の場合、繁忙期(2~4月)と通常期では平均1万〜2万5,000円の差があるようです。費用をできるだけ抑えたい方は、繁忙期や土日祝日、月末・月初を避けたり、午後便を利用したりして工夫しましょう。また、複数の引越し会社から相見積もりを取って、比較検討することをおすすめします。
家具家電の購入にかかる費用
一人暮らしを始めるにあたっては、家具家電や日用品を揃える必要があります。そのための費用は、20~29万円が相場です。この費用を節約したい方は、家具家電の付いた物件を検討してみるとよいでしょう。ただし、デザインが自分好みでない場合もあるので、注意が必要です。
毎月かかる固定費用
家賃
家賃は貸し主に支払う賃貸料金です。毎月支払うかたちが一般的で、無理なく継続して支払える範囲で予算を決めておきましょう。また、初期費用を抑えたい場合は、フリーレント物件も検討してみてください。
光熱費
光熱費や水道料は、電気・ガス・水道などのライフラインにかかる費用です。金額は生活スタイルや住む地域によって異なりますが、総務省統計局が公表している「家計調査報告〔家計収支編〕2024年(令和6年)平均結果の概要」によると一人暮らしの平均的な支出額は電気代が6,750円、ガス代が3,056円、上下水道代が2,282円程度です。
通信費
通信費は電話代やインターネット料金、郵便代、テレビに関する費用などを指します。スマートフォンは、契約中のオプションやプランを変更したり、家族割や学生割引などをうまく利用したりすれば節約できます。
インターネット料金においては、インターネット無料の物件も存在します。毎月の固定費をなるべく抑えたい方におすすめです。
食費
食費は食事にかかる費用です。「家計調査報告〔家計収支編〕2024年(令和6年)平均結果の概要」によると、1カ月あたりの食費は43,941円。
食材の購入費や外食代、飲料や菓子類の購入費などを含みます。実際の費用については、自炊か外食かで食費は大きく変わってきます。自炊をしたほうが節約はできますが、無理せず自分の状況に合った食生活を心掛けましょう。
交通費
交通費は鉄道やバス、飛行機、船などの交通機関、または自動車を利用する際に発生する費用です。利用するのが、公共交通機関か自動車かによって変動します。自転車や自動車を所有する場合、駐輪場・駐車場完備の物件を探すとよいでしょう。
また、バスや電車で通勤している方であれば、週末のおでかけは定期券の区間内で済ませると節約につながります。
社会人におすすめの物件の選び方は?

給与に対する家賃の目安や間取り、立地、セキュリティなど、社会人の一人暮らしにおすすめする物件の選び方を見ていきます。自分に合った理想の物件に住めるよう、参考にしてください。
家賃と予算
| 年代 | 平均年収 | 家賃等の目安 |
|---|---|---|
| 20代前半 | 302万円 | 6.2万円 |
| 20代後半 | 389万円 | 8.5万円 |
| 30代前半 | 439万円 | 9.6万円 |
| 30代後半 | 475万円 | 10.2万円 |
| 40代前半 | 510万円 | 10.8万円 |
出典:「doda平均年収ランキング(年齢別・年代別の年収情報)【最新版】」より年代別に年収・家賃の平均を計算
家賃は月収(手取り)の1/4~1/3に抑えることが理想です。賃料の他に月々にかかる費用も考慮し、無理なく支払える金額を設定しましょう。
間取りと設備
一人暮らしの社会人に人気の間取りはワンルーム、1K、1LDKです。まずは、ワンルームや1Kから一人暮らしを始めて、ある程度の社会的基盤ができてきたら、1DKや1LDKに引越すことをおすすめします。ただし、1LDKは他の間取りに比べて、家賃が高い傾向にあります。その際は、築年数や条件を気にせずに選ぶと家賃が抑えられるでしょう。
また、お風呂の時間を楽しみたい方は、バスとトイレが別になっている物件や、追い炊き機能が付いている物件がおすすめです。
また、ファッション好きの方は、大きめのクローゼットがあるかも重視してください。ファミリータイプの物件に比べるとどうしても狭いので、自分が何を優先するかで間取りを検討しましょう。
立地
立地は通勤のしやすさや治安のよさ、周辺環境などを考慮して選ぶのがポイントです。物件を内見する際に、自分にとって生活しやすい環境が揃っているかも確かめる必要があります。
また、物件を内見する際は、昼と夜それぞれ訪れるとよいでしょう。交通・街の騒音や、物件周辺の人通り、街灯の有無など日中気づきにくいこともチェックすることができます。
セキュリティ
一人暮らしの社会人、とくに女性が安全に暮らすためには、セキュリティがしっかりとした物件を選ぶことが大切です。防犯性能の高い鍵か、オートロックや共用部に防犯カメラが備わっているか、室内にモニター付きインターホンが付いているかなどを確認しましょう。
一人暮らしを始める際に必要な手続きは?

一人暮らしを始める際には、さまざまな手続きが必要です。賃貸契約時と引越し前後に分けて、以下で詳しく説明します。
賃貸契約で必要になる書類
まずは、賃貸契約の際に必要な書類を見ていきましょう。
住民票
住民票(住民票の写し)は市区町村の役所、あるいはコンビニエンスストアで取得可能です。ただし、コンビニエンスストアの場合はマイナンバーカードが必要となります。
収入を証明するもの
収入を証明する書類には、給与明細書や源泉徴収票、確定申告書、住民税課税証明書などがあります。収入証明書は家賃の支払い能力を判断する資料となるもので、入居審査のタイミングで求められることが多いでしょう。
連帯保証人に関する書類
前途で紹介した「賃貸保証会社」を利用する場合は必要ありませんが、連帯保証人をたてて物件を借りる場合は、連帯保証人に関する資料が必要となります。
連帯保証人に関する書類には、一般的に署名・捺印をもらった「連帯保証人引受承諾書」と、連帯保証人の「住民票」「印鑑証明書」「収入証明書」などがあります。これらは連携保証人に用意してもらう必要があるため、事前に伝えることが重要です。
引越し前後でやっておくべき手続き
次に、引越しの前後におこなう手続きを見ていきましょう。
転入・転出届
転出届は、引越し前の市区町村の役所に提出します。引越しの2週間前から手続きできるので、早めに済ませておくと安心です。転入届は引越し後2週間以内に、引越し先の役所に届出をします。なお、同じ市区町村内での引越しの場合は、転居届を提出してください。
電気・ガス・水道
実家を出て一人暮らしをする場合は、電気、ガス、水道を新たに契約します。すでに一人暮らしをしていた場合も、移転の手続きをおこなわなければなりません。手続きは、電力会社、ガス供給会社、地域の水道局に電話をするか、公式ホームページからできます。
ガスは引越し後、開栓作業の立ち会いが必要です。そのため、立ち会えるスケジュールを設定し、その時間には新居にいるようにしましょう。
郵便物転送
前の住所に届いた郵便物を、1年間、新居に転送してもらえる無料のサービスがあります。手続きは郵便局でおこないます。転送開始までに数日かかることもあるので、早めに済ませておくことが重要です。また、インターネットショッピングや通販サービスを利用している場合も、発送先を新しい住所に変更しておきましょう。
ネット回線
インターネット回線を契約する場合は、希望するプロバイダの公式ホームページから手続きをします。回線工事が必要となるケースもあるので、すぐに使いたい場合は早めの手続きがおすすめです。
社会人が一人暮らしを始める際に必要なものは?

家具や家電、日用品といった社会人が一人暮らしを始める際に必要なものを、表を参考にしながらチェックしていきましょう。
家具
| 家具 | |
|---|---|
| カーテン | ソファ |
| デスク・チェア | ゴミ箱 |
| 収納 | 寝具 |
一人暮らしに必要な家具には、カーテンやソファ、デスク・チェア、ゴミ箱、収納、寝具などがあります。カーテンは、防犯対策やプライバシーを守るための必須アイテムです。部屋のなかでも面積が大きい部分になるので、機能性も考慮することが大切になります。
家でリラックスする時間が多い方は、くつろぐためのソファがあると便利です。一方、リモートワークをするという方には、作業用のデスクにゲーミングチェアも人気があります。部屋に十分なスペースがない場合は、スツールタイプや折りたたみ式、収納付きといったものがよいでしょう。
ゴミ箱は、部屋用とキッチン用に分けるのがおすすめです。収納家具は衣類や靴、生活用品などを整理し、部屋をすっきりとさせるために必要です。ただし、物件によってはクローゼットやシューズボックス、キッチン収納が備え付けられている場合があります。
寝具は布団、枕、毛布、シーツ、寝巻き、ベッド、マットレスなど就寝時に使うものの総称です。まずは部屋の広さを考慮し、布団にするかベッドにするかを決めましょう。布団は、畳んだとき空いたスペースを有効活用できるのがメリットです。ベッドはベッド下に収納機能が付いたチェストベッドや天井の高さに余裕があればロフトベッド、ソファとベッドが一体化したソファベッドを選ぶことで、デッドスペースを減らし部屋を広く使えます。
家電
| 家電 | |
|---|---|
| 照明 | テレビ |
| 電子レンジ | 炊飯器 |
| 冷蔵庫 | ケトル |
| 掃除機 | 洗濯機 |
| エアコン | ドライヤー |
| 充電器類 | アイロン |
一人暮らしに必要な家電には、表に示したものが挙げられます。
物件によっては照明器具が取り付けられてないケースもあるため、内見時にチェックしておきましょう。照明器具でメインとなるのが、天井に取り付けるタイプのシーリングライトです。部屋全体を均一に照らしてくれるのが特徴で、デザインのバリエーションもたくさんあります。また、勉強やリモートワークといったデスクでの作業用に卓上スタンドがあると便利です。
テレビは、部屋の大きさに合った画面サイズを選ぶことが重要です。6帖までは24~32インチ、8~10帖が40~50インチ、12帖以上で52インチ以上のものが目安となります。また、録画機能の種類や、インターネット通信機能が備わっているかも確認しておきましょう。部屋をより広く使いたいなら、壁掛けタイプがおすすめです。ただし、賃貸では壁に穴を開けず設置できるものを選んでください。
電子レンジを使えば、手軽に食材を加熱できます。温めだけでなく、電子レンジだけでできる料理もあります。電子レンジには17L程度の小さいものから30L以上の大きい容量のものまであるので、料理の頻度や使い道に合わせて選んでください。なお、一人暮らしなら20L程度の容量で十分でしょう。
炊飯器はご飯を炊くのに欠かせない家電ですが、最近は一人用のコンパクトなモデルでも、機能の充実したものがあります。例えばおかずやパンも作れるタイプがあるので、日々の生活に重宝するでしょう。どのような機能が必要か、予算と共に検討してください。
冷蔵庫は、自炊しない方でも必要な家電です。さまざまな大きさがあるので、自分のライフスタイルやキッチンの広さに合った容量を選びましょう。自炊をメインにしたり、週末などに食材をまとめ買いしたりするなら、150~300L程度の容量が必要です。
電気ケトルは温かい飲み物を飲んだり、カップラーメン等を食べたりする際に、必要な分だけお湯を沸かせます。標準サイズは0.8Lですが、一人暮らしであれば0.6Lでも十分でしょう。使用頻度が高いなら、少し大きめの容量を選んでください。
掃除機は置くスペースが必要ですが、きれいな部屋を保つのに役立ちます。どうしても掃除機が置けないなら、粘着カーペットクリーナーやクイックルワイパーでも代用は可能です。
洗濯機には、大きく分けて縦型とドラム式があります。縦型洗濯機は狭いスペースでも設置しやすく、比較的安いのがメリットです。価格重視なら、縦型を検討するとよいでしょう。一方、ドラム式洗濯機は乾燥機能が備わっているのが特徴です。部屋干しを避けたい、あるいは洗濯する時間がバラバラという方に合っています。いずれの場合でも、一人暮らしには洗濯容量5~6kgのものがおすすめです。この容量なら、衣類などを2~3日分まとめて洗えます。
部屋にエアコンが設置されていなければ、自分で購入する必要があります。エアコンの有無は、物件探しの段階で確認しましょう。部屋の広さによって適したエアコンが異なり、費用も違ってきます。6~8帖で4~7万円、10~12帖で5~12万円、14~16帖で7~16万円が目安です。自動で掃除してくれる機能や、空気清浄機能が付いたタイプになるとさらに高くなります。
ヘアドライヤーは髪を乾かしたり、セットしたりするのに欠かせないアイテムです。大風量や静音性、マイナスイオンなど機能はさまざまなので、自分に合ったものを選びましょう。
充電器類は、スマートフォンやパソコンを使ううえでの必須アイテムです。引越し当日も必要となる場合があるので、あらかじめ準備しておいてください。
また、アイロンは一人暮らしでも持っていると便利です。収納場所にも困らないコンパクトなハンディタイプもあるので、とくに制服やスーツを清潔に保ちたいなら用意しておきましょう。
キッチン用品
| キッチン用品 | |
|---|---|
| まな板 | 包丁 |
| フライパン | お鍋 |
| 食器類 | 調味料類 |
| キッチンペーパー | 食器洗い用洗剤/スポンジ |
一人暮らしに必要なキッチン用品には、表に示したようなものがあります。最初は、まな板、包丁、フライパン、鍋、ざる、ボウル、調理スプーンといった最低限の調理器具で十分でしょう。食器も茶碗や皿、コップ、箸、スプーン、フォークなど、普段の食事で使うものから準備していくのが無難です。収納スペースも限られるので、料理の頻度に合わせて少しずつ足していきましょう。
バス用品
| バス用品 | |
|---|---|
| シャンプー・トリートメント | ボディーソープ |
| バス用洗剤 | 掃除用具 |
| バスタオル | バスマット |
一人暮らしに必要なバス用品には、シャンプーやリンス、トリートメント、ボディーソープの他に、バス用洗剤、掃除用具、バスタオル、バスマット、バスチェア、洗面器などがあります。バスタオルは洗濯の回数によって揃えたい枚数は異なりますが、3枚は持っておくと役立ちます。バスマットはタオル生地のほか、速乾性のある珪藻土マットも人気です。
日用品
| 日用品 | |
|---|---|
| トイレットペーパー | ティッシュペーパー |
| 洗濯用洗剤 | 柔軟剤 |
| 歯ブラシ/歯磨き粉 | ハンドソープ |
| ハンガー | 掃除用具 |
| ラップ・アルミホイル | タオル類 |
| ゴミ袋 | 消臭剤・芳香剤 |
一人暮らしに必要な日用品には、表に示したようなものがあります。ティッシュペーパーとトイレットペーパーは生活の必需品です。これらは突然なくなると困るので、ストックを常備しておくのがよいでしょう。洗濯用洗剤には洗濯洗剤、漂白剤、柔軟剤などがあります。洗剤は、洗濯機の用途に沿って使い分けてください。
洗面用品には歯ブラシ、歯磨き粉、歯磨き用コップなどがあります。また、女性であればメイク用品、男性であればシェーバーなど、普段から使っているものも忘れずに揃えておくと安心です。
また、衣類を掛けるハンガーも必要になるでしょう。とくにスーツやコートはたたむとシワになりやすいので、ハンガーを使って収納することをおすすめします。
タオル類はお風呂や洗面、キッチン、トイレで使用します。バスタオル3枚以外に、フェイスタオルも9枚程度は用意しておきましょう。ゴミ袋は種類やゴミの出し方が自治体によって変わるので、規定を確認することが大切です。
薬類
| 薬類 | |
|---|---|
| 常備薬(頭痛薬・風邪薬など) | 絆創膏 |
| 体温計 | 冷えピタ・湿布 |
救急箱を用意しておくと、万が一の事態に役立ちます。頭痛薬や風邪薬などの常備薬や絆創膏、体温計、冷えピタ・湿布、消毒薬、ガーゼ、包帯、マスクなどは揃えておくと安心です。
社会人が一人暮らしをするメリット

社会人が一人暮らしをすることで得られるメリットをお伝えします。
自由な生活ができる
一人暮らしをすると、自由な生活ができます。複数人で暮らしている場合、食事や入浴の時間がある程度決まっていることもありますが、そういった時間を自由に使うことが可能です。家族の生活音も気になりませんし、趣味などのプライベートな時間を有意義と過ごせるのもメリットといえます。
生活能力が高まる
仕事と家事を両立していくうちに、生活能力が高まるでしょう。また、自尊心や責任感が芽生え、対処する力も養えます。
自分好みの空間が作れる
自分の好みに合わせて部屋をコーディネートできるため、欲しかった家具や家電を揃えられます。
金銭管理能力が向上する
収入や支出の管理なども、自分でおこなう必要があります。計画的に貯金や節約に目を向けられるようになると、金銭管理能力が身につくでしょう。
通勤がしやすくなる
路線やエリアを考慮して新居を選べば、通勤しやすくなります。会社までの乗り換え回数や、交通費をしっかりと把握しましょう。
社会人が一人暮らしをするデメリット

メリットがある一方で、デメリットも発生します。それらをなるべく避けられるように、以下の項目を参考にしてみてください。
支出が増える
お金の管理に慣れないと散財してしまい、生活費が足りなくなることがあります。一人暮らしを楽しむのもよいですが、安定するまでは余裕のある生活を心掛けましょう。
家事全般を自分でやる必要がある
家事全般を自分でしなければ、すぐに部屋が汚れてしまいます。衛生面においても、頻繁に家事をする時間を設けることが重要です。
生活リズムが乱れやすくなる
夜ふかしばかりしてしまったり、つい暴飲暴食をしてしまったりと、生活が不規則になりやすいため注意が必要です。生活リズムが乱れると、心身の不調につながる可能性もあります。普段から、規則正しい生活を送れるように意識しましょう。
病気やけがをしたときが大変
病気やけがをした際に、自分一人で対応することになります。柔軟な対処法と知識を身につけておきましょう。
防犯対策が必要となる
防犯対策も、一人暮らしをするうえでは重要です。できれば、オートロックや防犯カメラといった防犯対策のある物件を探しましょう。また、窓からの侵入窃盗を防ぐために補助錠や防犯フィルム、防犯センサーなどを活用し、窓まわりの防犯も徹底してください。
孤独や寂しさを感じる
生活空間内に自分しかいないと、孤独感や寂しさを感じることが多いかもしれません。近所に友人を作ったり、いつでも電話できる相手を探したりと、対策することが望ましいでしょう。
社会人が一人暮らしを始める際の注意点とポイント

最後に、社会人が一人暮らしを始める際の注意点とポイントを解説します。
家賃を手取りの4分の1〜3分の1に抑える
家賃の金額を手取りの4/1〜3/1に抑え、余裕のある生活につなげられるよう努めましょう。
物件の譲れない条件や優先順位を明確にする
すべて自分の理想を求めてしまうと、その分だけ費用が高くなってしまいます。オートロック付きやバス・トイレ別など物件の譲れない条件を絞り、優先順位を明確にしておくことが大切です。
部屋が決まったら広さをしっかりと測る
部屋が決まったら、広さをしっかりと測っておきます。そうすることで、家具や家電選びに失敗しません。ベッドや冷蔵庫、洗濯機といった大きなものはサイズが合わなければ置けないため、とくに注意が必要です。
繁忙期を避けて引越しする
3月から4月までは、引越し会社の繁忙期です。引越し費用を抑えるために、なるべくこの時期は避けましょう。また、複数の引越し会社から見積もりを取って価格を比較し、早めに予約することも大切です。
福利厚生を活用する
福利厚生とは、給与や賞与以外で会社から提供される制度・サービスのことです。会社によって条件などはさまざまですが、具体的には各種手当(住宅手当、ランチ費用の補助など)や休暇制度(有給休暇、特別休暇など)、設備(社員食堂、レジャー施設の割引制度など)、医療保険(健康保険、厚生年金保険など)、退職金制度、子育て支援などが福利厚生の一部として挙げられます。これらを知っておくことで、生活面だけでなく、仕事上のパフォーマンス向上も期待できます。
生活の質を落としすぎないよう気をつける
生活の質を落としすぎないように気をつけましょう。例えば、節約するために食費を大幅に削ったり、冷暖房の使用を我慢したりすると、体調を崩して仕事に支障をきたしてしまうかもしれません。最悪なケースとして食中毒や熱中症で入院が必要となることも。一人暮らしを楽しむためにも、無理のない範囲で節約することが望ましいでしょう。
まとめ
本記事では、社会人が一人暮らしを始める際に役立つ費用の目安や物件選びのポイント、さらには必要な家具や家電のリストまで細かく説明しました。しっかりと計画を立てて、充実した一人暮らしをスタートさせましょう。