年収750万円でいくらの住宅ローンを組める?借入額の決め方や無理なく返済するポイントを解説

それぞれ家庭の状況は違うため、年収で一括りに考えるのではなく、個々にあったローンを組むことが大切です。どういったポイントを押さえるべきか、参考にしてください。
記事の目次
年収750万円の生活レベルはどれくらい?

国税庁の「令和4年分民間給与実態統計調査-調査結果報告-」によると、平均年収は458万円となっており、年収750万円は平均の約1.6倍にあたります。多いように思えますが、これから税金を引くとどうなるのでしょうか。本章では、まず年収750万円の生活レベルについて解説します。
年収750万円の手取り
配偶者の有無や収入状況、扶養者の年齢などによって、所得から差し引くことができる控除が変わります。例えば、配偶者の合計所得が48万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。次の3パターンの場合、年収750万円の時の手取りは下記のとおりです。
独身の場合:約562万円
配偶者のみを扶養している場合:約573万円
配偶者と16歳以上の子どもを1人扶養している場合:約583万円
月収にすると、約46〜約48万円となります。
年収750万円の生活費
年収750万円の方が、実際にどのような生活を送っているのか気になるところでしょう。ここではデータを見ながら解説していきます。
年収750万円に絞ったデータはありませんが、年収700〜750万円の家計と、年間収入が約700万円で住宅ローンを返済している家計をまとめてみました。
| 年間収入700〜 750万円の家計 |
年間収入約700万円で住宅ローンを返済している家計 | |
|---|---|---|
| 世帯人員 | 3.37人 | 3.6人 |
| 消費支出 | 33万1,024円 | 31万4,450円 |
| 住居費 | 1万9,326円 | 8万2,809円 |
| 食費 | 8万6,160円 | 8万7,755円 |
| 水道・光熱費 | 2万561円 | 1万9,586円 |
| 家具・家事用品 | 1万3,866円 | 1万499円 |
| 衣類 | 7,857円 | 8,143円 |
| 保健医療 | 1万3,188円 | 1万1,047円 |
| 交通費 | 8,935円 | 7,087円 |
| 通信費 | 1万3,120円 | 1万3,107円 |
| 教育費 | 7,217円 | 1万5,113円 |
| 教養・娯楽費 | 3万2,906円 | 3万7,136円 |
| その他 | 6万3,713円 | 5万4,077円 |
| 交際費 | 1万8,475円 | 1万2,062円 |
| 貯蓄 | 10万9,296円 | 6万1,113円 |
年収700〜750万円の家計の住居費は、持ち家の人も含んでいるため低くなっています。しかし、それ以外の支出の項目を見ると、あまり大差がないことがわかります。
年収750万円でいくらの住宅ローンを組める?

年収が750万円の場合、住宅ローンはいくら借りられるのでしょうか。まずは平均的な借入額から見ていきましょう。
平均的な借入額
国土交通省の「令和4年度 住宅市場動向調査報告書」によると、物件タイプごとの借入額、年間返済額、返済負担率は下表のとおりです。返済負担率とは、収入に対して住宅ローンの返済額がいくらなのかという割合を示したものです。一般的に20%以下が無理のない返済負担率とされています。
| 借入金 | 年間返済額 | 返済負担率 | |
|---|---|---|---|
| 注文住宅 | 3,772万円 | 174万円 | 16.4% |
| 分譲戸建住宅 | 3,205万円 | 126.6万円 | 18.8% |
| 分譲集合住宅 | 3,610万円 | 148.1万円 | 17.4% |
| 中古戸建住宅 | 2,070万円 | 106.7万円 | 16.6% |
| 中古集合住宅 | 1,641万円 | 101.3万円 | 16.6% |
新築と中古だけでなく、物件タイプによっても、借入額に差があることがわかります。特に注文住宅は借入金、年間返済額ともに高くなっています。しかし、返済負担率を見ると、どの物件タイプも20%以下に収められており、なるべく家計に負担をかけないようにしているのが伺えます。
年収倍率からみた借入額
年収倍率とは、購入する予定の物件価格が、年収の何倍であるかを表すものです。一般的に5〜6倍が適正とされています。
例えば、年収750万円の場合、3,750万円〜4,500万円が適正となります。しかし、この数字はあくまで目安であることを理解しておきましょう。他にも借り入れがあったり、働き手が1人だったりなど、家計状況によってはもっと下げる必要もあります。個々の事情に合った借入額を決めることが大切です。
返済負担率からみた返済額
先述したように、無理のない返済負担率は20%とされています。
例えば、年収750万円で独身の場合(手取り約562万円)で考えると、無理のない返済額は年間で約112万円、月々の返済額は約9万3,000円となります。
先ほどの年収倍率で借入額を計算すると、金額が大きくイメージしづらい部分がありますが、返済負担率から月々の返済額を計算してみると、購入後の家計状況をイメージしやすくなるでしょう。
ですが、こちらもあくまで目安のため、それぞれに合った無理のない借入額を決めることが大切です。ファイナンシャルプランナーなどの専門家と相談しながら、決めるようにしましょう。
借入額別返済シミュレーション
借入額で月々の返済額は大きく変わります。ここでは借入額別に返済シミュレーションをしてみました。あくまでシミュレーションのため、参考程度にしておきましょう。
<条件>
返済期間:35年
返済方式:元利均等方式
金利:1.96%(全期間固定)
| 3,000万円 | 4,000万円 | 5,000万円 | |
|---|---|---|---|
| 月々の返済額 | 9万8,764円 | 13万1,685円 | 16万4,606円 |
| 年間返済額 | 118万5,168円 | 158万220円 | 197万5,272円 |
| 総返済額 | 4,148万652円 | 5,530万7,676円 | 6,913万4,725円 |
借入額が変われば、月々の返済額をはじめ、年間や総返済額も変わります。もちろん、借入額だけでなく、返済期間や金利によっても返済額は変わります。しかし、返済期間や金利は途中で変更できますが、借入額だけは変更できません。そのため、慎重に決める必要があります。
適正な借入額を決めるためのポイント
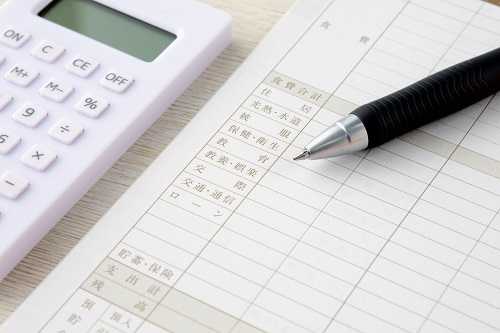
繰り返しになりますが、年収倍率や返済負担率から求めた数値は、あくまで目安でしかありません。それぞれの家計に合った住宅ローンを組むことが重要です。本章では、適正な借入額を決めるためのポイントを解説します。
毎月の家計に余裕が出るようにする
大切なのは住宅を購入することではなく、住宅を購入したあとの生活です。住宅ローンの返済が始まった途端に家計が苦しくなるようではいけません。毎月の家計に余裕が出るよう、自由に使えるお金が手取りの5〜10%確保できるようにしましょう。
また、金融機関が提示するのは「借入可能額」であって、無理なく返済できる金額ではないことを理解しておきましょう。
ライフイベントを想定した返済計画を立てる
住宅ローンの返済は長期間に渡るため、ライフイベントを想定した返済計画を立てましょう。例えば、夫婦で収入合算したり、ペアローンを組む場合、妻が妊娠・出産で働けなくなり、収入が減少する可能性も考えなければなりません。
他にも、病気やケガで働けなくなってしまったり、定年で収入が減ることも考えられます。今のことだけを考えるのではなく、先々予想されるできごとを想定する必要があります。
住宅ローンを無理なく返済するためのポイント

住宅は大きな買いもののため、住宅ローンを契約する前、もしくは返済が始まったあとも、「本当に完済できるだろうか……」と不安になることもあるでしょう。本章では、無理なく返済するためのポイントをお伝えします。
頭金を多めに用意する
頭金を多めに用意すると、借入額が減るため、毎月の返済額を抑えることができます。また、金融機関に返済能力があると判断され、金利が優遇されたり、審査に通る可能性も高くなります。頭金の有無で返済額がどう変化するのかを見てみましょう。
<条件>
物件価格:3,500万円
返済期間:35年
返済方式:元利均等方式
金利:1.96%(全期間固定)
| 3,500万円 (頭金なし) |
3,200万円 (頭金300万円) |
|
|---|---|---|
| 月々の返済額 | 11万5,224円 | 10万5,348円 |
| 利息額 | 1,339万4,256円 | 1,224万6,077円 |
| 総返済額 | 4,839万4,256円 | 4,424万6,077円 |
頭金として300万円を入れた場合、月々の返済額は約1万円下がりました。また、総返済額は約400万円減り、頭金の金額以上に下がっているのがわかります。
しかし、返済が楽になるからといって、必要以上に頭金を用意してはいけません。収入が減ってしまったり、病気で今までどおり働けなくなったり、といった万一の場合に耐えられるよう、ある程度の資金を残しておきましょう。
ペアローンや収入合算を検討する
ペアローンや収入合算を検討することも、無理のない返済計画を立てる方法の一つです。ペアローンとは、夫婦や親子がそれぞれ住宅ローンを契約する方法で、住宅ローン控除も別々に受けられます。一方、収入合算とは、契約者と配偶者の収入を合算して、1つの住宅ローンを契約する方法です。
金融機関は返済能力を重視するため、収入のある人が2人いれば、審査に通りやすくなります。また、借入額を増やすことができ、希望する物件を購入できる可能性もより高まります。しかし、借入額が増えたからといって、上限まで借りるのはおすすめしません。どちらの方法であっても、一方の収入で返済できるように借り入れれば、無理のない返済計画が立てられるでしょう。
住宅ローン以外の借り入れを返済する
住宅ローン以外の借り入れがある場合は、できるだけ早めに返済しましょう。もし奨学金やマイカーローンなどの借り入れがある場合、これらの返済額に加えて、住宅ローンの返済額も増えることになります。
毎月の返済額が増えるため、返済が滞ってしまう可能性も……あります。資金に余裕がある場合には、繰上げ返済や完済するなどして、他の借り入れを返済しましょう。住宅ローン借り入れ後の家計が安定し、無理なく返済できるでしょう。
返済期間を長めに設定する
返済期間を長めに設定すると、毎月の返済額を抑えられます。実際にシミュレーションしてみましょう。
<条件>
借入額:3,000万円
返済方式:元利均等方式
金利:1.96%(全期間固定)
| 返済期間 | 25年 | 35年 |
|---|---|---|
| 月々の返済額 | 12万6,572円 | 9万8,764円 |
| 利息額 | 797万1,756円 | 1,148万652円 |
| 総返済額 | 3,797万1,756円 | 4,148万652円 |
返済期間が25年と35年の場合で比較してみました。返済期間を長くすると、月々の返済額が約3万円減っているのがわかります。しかし、元本の減りが遅いため、利息が多くなってしまい、総返済額が増える点を理解しておきましょう。
繰上げ返済を活用する
住宅ローンの返済が始まってから、繰上げ返済を活用することもできます。繰上げ返済とは、毎月の返済額に加えて、住宅ローン残高の一部を返済することです。元金を減らすことができるため、利息も減り、総返済額を減らす効果があります。
また同時に、返済期間も短縮できます。ボーナスなど、まとまった収入が入った時におこなうと、家計に負担をかけることなく無理なくできるでしょう。ただし、手数料がかかる場合もあるため、事前に確認しましょう。
住宅ローン控除を活用する
住宅ローン控除を活用することで、所得税や住民税の負担を減らせます。住宅ローン控除とは、年末時点の住宅ローン残高に一定の率をかけた金額を、所得税や住民税から差し引くことができる制度です。住宅の環境性能によって控除額は変わりますが、長期優良住宅もしくは低炭素住宅であれば最大35万円控除されます。申請しなければ控除を受けることができないため、忘れず申請するようにしましょう。

- 住宅ローン減税制度では住民税も控除される?制度利用の手続き方法を紹介
- 住宅ローンを組んで住宅を購入した場合には、住宅ローン減税制度を利用することができます。住宅ローン減税制度が適用されると
続きを読む

まとめ
今回は、年収が750万円の場合に組める住宅ローンについて解説しました。年収倍率や返済負担率で目安を知ることはできますが、個々の家計に合った住宅ローンを組むことが大切です。ファイナンシャルプランナーなどの専門家の力を借りながら、適正な借入額を決め、無理のない返済計画を立てましょう。
物件を探す

執筆者
民辻伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ









