退去の時にかかる原状回復費の相場はいくら?
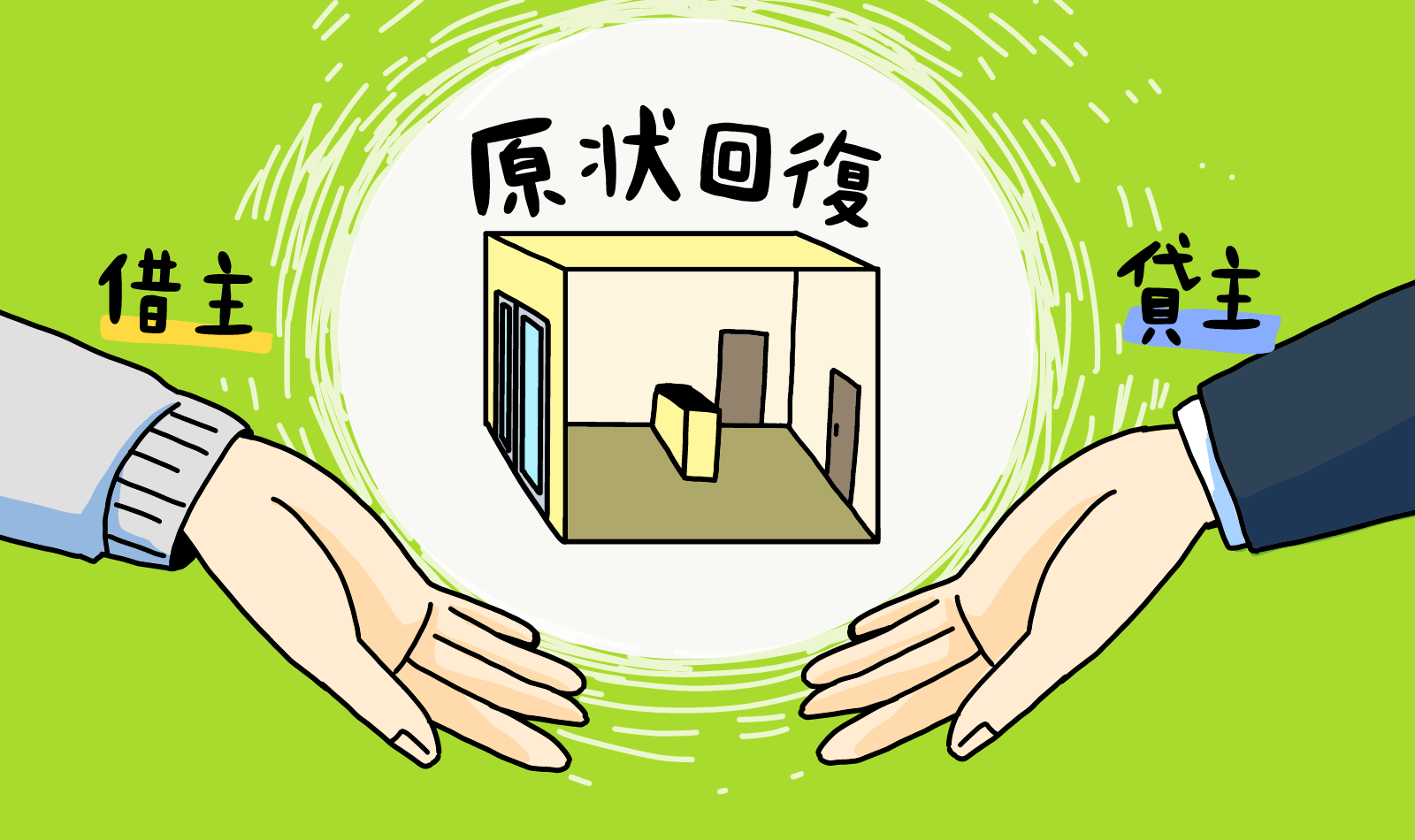
賃貸住宅を退去する際、トラブルになりがちなのが「入居時からあったキズの修繕代を請求された」などの原状回復に関する内容です。
「部屋を出る際は入居時の状態に戻して退去する」ということはなんとなくご存知かもしれませんが、退去時にトラブルを回避するには、原状回復の定義やルールまで理解しておくことが非常に重要です。
記事の目次
まず原状回復とは、「借主の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、退去時に借主の故意・過失や善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような利用方法など借主の責任によって生じた損耗やキズなどを復旧すること」です。
善管注意義務とは民法400条に定められた「善良なる管理者としての注意義務」の略で、「通常期待される注意をもって使用・管理しなければならない」といった規定です。これに違反して通常の損耗などを放置したり、手入れを怠ったことが原因で損耗が拡大した場合、その復旧費用は借主負担となります。
つまり、通常の使用による住宅の損耗や経年劣化に関しては、借主の責任ではないので回復に要する費用を負担する必要はありません。
原状回復に関しては、一般的な建物賃貸借契約書ならば「借主は契約終了時には本物件を原状に復して明け渡さなければならない」といった文言で定められています。
ここで注意したいのは、「退去時は、借りていた物件を入居時とまったく同じ状態に回復しなければならない」という意味ではないということです。繰り返しますが原状回復とは、「借主の責任によって生じた損耗やキズなどを復旧すること」なので忘れないようにしましょう。
ただでさえ出費が多い転居時に多額の原状回復費を請求されたら、困る方が多いでしょう。しかし、契約時に敷金(保証金)を預けていれば、そこから原状回復費を差し引いて返金されるので、経済的な負担を軽減できます。敷金は家賃の滞納だけでなく、このような借主の故意・過失による損耗を復旧するためにも預けているのです。
PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク)に寄せられた賃貸住宅の原状回復にかかわる相談件数は、以下のように推移しています。
2016年:1万3905件
2017年:1万3210件
2018年:1万2489件
若干減少傾向ではあるものの、毎年1万3000件前後のトラブル相談があるという高止まり状態です。
最近の相談事例には以下のようなものがあります。
このようなトラブルに対処するため、東京都では「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」、国土交通省では「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を作成しています。
今回は、こちらのガイドラインの内容を元に様々なケースについて解説していきます。
原状回復とは、「借主の責任によって生じた損耗やキズなどを復旧すること」であるとご説明しました。
では、借主の責任とはならないキズや汚れとはどのようなものなのでしょうか。具体例をあげて借主、貸主のどちらが回復費を負担するべきか説明します。

冷蔵庫、テレビなど熱を発生する家電製品を設置した際の後部壁面の黒ずみ、いわゆる電気焼けは通常損耗として貸主負担になります。なお、借主所有のエアコン設置による壁のビス穴や汚れも、一般的な生活をしていくうえで仕方がないとして貸主負担となります。
日照や建物の欠陥による雨漏りなどによる色落ちは、借主に責任がないとして貸主負担になります。一方で引越しの際にできたひっかきキズやキャスター付きのイスによる凹み、窓の開けっぱなしによる雨の吹込みで生じた変色などは、善管注意義務違反として借主負担となります。
家具の設置だけでできた凹みや跡は通常の使用による損耗として貸主負担となります。
流し台やガスコンロなどの住宅設備が耐用年数を過ぎてから故障した場合は、経年劣化による自然損耗として貸主負担となります。なお、主な住宅設備の耐用年数は次のようになっています。
耐用年数5年:流し台
耐用年数6年:エアコン、ガスコンロ、冷蔵庫、インターホン、畳床、カーペット
耐用年数8年:戸棚などおもに金蔵製以外の家具
耐用年数15年:便器、洗面台
居室の壁紙や床がヤニで変色したり、臭いが付いていた場合は、通常の使用を超える汚れとして借主負担になります。これは借主が清掃などの管理を怠ったため発生したと判断されるからです。
たとえば冷蔵庫下のサビ跡は、拭き掃除によって除去できる場合もあります。また、エアコンの水漏れによる壁の汚れは、放置しなければ免れることができたかもしれません。そのため、これらが設備の手入れ不足による汚れと判断された場合は、善管注意義務違反として借主負担になります。
猫が柱で爪とぎをする、クロスに爪の跡をつける、カーペットに糞や尿の臭いが付くなど、ペットによる傷や臭いは借主の負担となります。これは、借主によるしつけや糞尿の処理に問題があると考えられるためです。
直射日光によるふすまや障子の日焼けや畳の変色、家具の重みによる畳の変形や劣化は貸主による修繕負担となり、原状回復費には含まれません。
一方、物をぶつけるなどしてふすまや障子に空けてしまったり、窓を開けっ放しにしてしまったために雨が吹き込み、畳が濡れて痛んだ場合は借主の負担となります。
地震は貸主、借主のどちらにも責任があるものでありませんが、被害により修理が必要な状況が生じた場合は貸主の負担で修理をしなければならないことが民法で定められています。
仮に借主が家具の転倒防止の対策を取っていなかったために床に傷が付くなどした場合も、家具の転倒の原因が地震である以上、修繕は貸主の負担になると考えられます。
室内の温度と外気温の差が原因でガラスが割れる「熱割れ」や、ガラスの中に網目状の金属線が入ったガラスで経年劣化により起きる「さび割れ」などによるガラスの破損は原状回復に含まれず、貸主の負担となります。
また地震、台風などの突風で飛んできた物が当たった場合など、災害による破損も原状回復費には含まれません。借主の責任となるのは、あくまで借主が故意に、または過失により破損してしまった場合に限られます。
上記のように原状回復費を借主と貸主のどちらが負担するかは、一つひとつのキズや汚れを細かく確認していく必要があります。その際の原則をまとめると次のようになります。
借主負担になるケース
例
貸主負担になるケース
例
ただし、これには例外があります。それは賃貸借契約時に付けられる特約です。
借主と貸主で合意すれば、原則と異なることでも定めることが可能になります。一般的には「電球」「蛍光灯」「給排水栓のパッキン」といった比較的安価なものが特約によって借主負担になることがあります。
しかし、それ以上に借主に不利な特約もないとは言い切れません。そこで東京都では特約が成立する要件として次の3点をあげています。
契約書に特約が付けられていたら、これら3点を参考に合意するか否かを判断しましょう。
原状回復のトラブルを回避するには、入居時と退去時に物件を細かくチェックすることが大切です。
入居時にやるべきこと
入居時は借主と貸主(管理会社)の立会いのもと、現状のキズや汚れを確認します。その結果は書面に記録し、写真も撮って双方で保存しておきましょう。
退去時にやるべきこと
退去時も貸主(管理会社)の立ち会いのもと、物件状況を確認することになります。その際は、入居時に作成した書類・写真と比較しながら損耗や汚れの程度をチェックします。この際に借主の責任によるものがあれば、あらためて書面に記録し、写真も撮っておきます。
その後、借主宛に原状回復費の見積書が送られてくるので、退去時の記録と相違ないか確認します。そこで疑問に思うことがあれば、納得できるまで貸主(管理会社)に説明を求めましょう。
賃貸物件の原状回復においてトラブルを回避するには、上記のように分からないことや納得できないことをとことん聞くというのが重要になります。
それでもよく分からなかったり困ったことがあれば、入居前であれば契約を保留にする、また契約の前後に関わらず下記消費者ホットラインなどに相談するといった方法で、解決の道を探ることをお勧めします。
国民生活センター「消費者ホットライン」
http://www.kokusen.go.jp/map/