同性パートナーには相続権がない?今できる4つの相続対策と注意点

この記事では同性パートナーが直面する可能性がある、相続のトラブルやその対応方法を詳しく解説していきます。
記事の目次
LGBTQの同性パートナーは相続できない?

LGBTQの同性カップルはパートナーに相続できないのでしょうか。結論からいえば、相続できないのが現状です。なぜ相続できないのか詳しく解説します。
パートナーシップ制度
同性婚が民法上認められていない日本では、いくつかの自治体がパートナーシップ制度を導入しています。パートナーシップ制度とは、同性カップルが互いに支え合い、生活をともにすることを公に認める制度で、住民票や戸籍抄本などで証明されます。
しかし、このパートナーシップ制度は、婚姻制度とは異なり、法的な効力が限定的です。具体的には、民法上の法定相続人である配偶者として認められない、相続や所得税や住民税の配偶者控除の対象にできないことが挙げられます。
渋谷区や世田谷区など一部の自治体では、パートナーシップ証明書を独自に発行する動きがおこなわれていますが、現状では二人の関係を公に示すものとしての活用は期待されつつも、民法や税法などの制度上では、いまだ同性パートナーは配偶者として認められていません。
さらに、パートナーシップ制度は自治体ごとに異なるため、全国的な統一性がありません。ある自治体で認められても、他の自治体に移動した場合、その効力が失われることもあります。
同性パートナーの相続権
現行の日本の民法では、相続権は配偶者や子や孫、両親などの直系血族、兄弟姉妹などに限定されており、同性パートナーはこれに含まれません。そのため、長年連れ添ったパートナーが亡くなった場合でも、残されたパートナーはその財産を法的に相続する権利はないでしょう。
同性パートナーに相続権がないことで起こる3つのリスク
同性パートナーに相続権がないことで起こる3つのリスクを見てみましょう。
- 預貯金が引き出せなくなる
- 自宅を退去しなければならなくなる
- 親族とのトラブルに発展する
それぞれ具体的に説明します。
預貯金が引き出せなくなる
人が亡くなったことが金融機関に通知されると、その預貯金は凍結され、原則として自由に引き出せなくなります。婚姻関係のないパートナーが亡くなった場合、相続権がない同性パートナーは凍結解除の手続きがおこなえないため、法定相続人以外の人が預貯金を引き出すことは難しくなることが、一つ目のリスクです。
銀行は葬儀費用のような限られた用途で一定の金額までであれば、相続預金を引き出す手続きに応じてくれる場合があります。しかし、それ以外の生活費などは遺産分割協議や遺言の内容に従って引き出すことになります。特に、遺言書がない場合、同性パートナーは遺産分割協議に参加できないため、何も対策がなければ残された預貯金を受け取る権利もないことになりかねません。
自宅を退去しなければならなくなる

同性パートナーが所有する自宅に住んでいた場合、そのパートナーが亡くなったあと、その自宅の所有権が法定相続人に移転すると、退去を求められる可能性があります。特に長年一緒に住んでいた場合、その自宅は生活基盤となっています。住まいを失うことは、心理的・経済的にも大きな負担となるでしょう。
親族とのトラブルに発展する
同性パートナーの死後、その法定相続人が相続人となり、財産分配を巡ってトラブルが発生することがあります。後述する遺言や死因贈与契約がないと法定相続人ではない同性パートナーは遺産を受け取る権利がなく、どれだけ生前の関係を主張しても、法的に財産を受け取る権利がありません。そのため、法定相続人が理解を示して相続分を譲渡してくれるという事情がない限り、同性パートナーは不利な状況になります。
同性カップルの相続対策4つ
同性カップルの相続対策4つを解説します。
- 公正証書遺言
- 死因贈与
- 養子縁組
- 生命保険
各相続の対策を詳しく見ていきましょう。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書です。同性パートナーに財産を遺贈する場合、遺言を作成する方法がもっとも確実です。なかでも公正証書遺言は法律のプロである公証人が作成するため、遺言者の意志が明確に反映されます。
また、公証役場で遺言の内容が保存されるため、自筆で作成する遺言(自筆証書遺言)に比べて遺言書の偽造や無効化のリスクが低くなるでしょう。例えば、遺言書に具体的な財産分配の内容を記載してもらうことで、パートナーへの財産遺贈を確実に実現できます。
死因贈与
死因贈与は、贈与者が死亡した時点で効力を発生する贈与契約です。これは、遺言書と似た役割を果たしますが、契約としての性質を持ちます。死因贈与契約は、契約書により明確にされるため、遺言書と同様に効力が強いのが特徴です。
例えば、財産を受け取る条件として「贈与者が死亡した場合」と明記することで、同性パートナーへの財産遺贈を確実におこなえます。
死因贈与も確実に内容を実現させるためには、公証役場での公正証書の形式での死因贈与契約をおすすめします。
養子縁組

同性パートナーを養子にすることで、法的な家族関係を築き、相続権を確保する方法も相続対策の一つです。ただし、この方法は養親の年齢が上でないとならない制約があります。
養子縁組により、法定相続人となるため、遺産分割協議への参加が可能になります。
生命保険
生命保険を活用することで、パートナーに一定の財産を確実に残すことが可能です。同性パートナーを保険金受取人に指定することで、税制上の優遇も受けられる場合も。生命保険は、死亡時に受取人に直接支払われるため、相続手続きが不要です。生命保険の受取人に同性パートナーを指定することで、確実に財産を残せるでしょう。
同性カップルの相続対策の注意点
同性カップルが相続対策をする際に気を付けるべき点もあります。
特に遺言書の作成や死因贈与契約は、確実に内容を実現するために法的な要件をしっかりと確認して文書に反映しておく必要があるでしょう。
遺言書を作成する際には、民法で形式が厳密に規定されるため、法的に有効な形式を守ることが重要です。
また、同性パートナー同士で養子縁組を利用して相続対策をおこなう際には、養子縁組をした者は婚姻できないということも注意しましょう。将来的に日本で同性婚の制度ができた際に、養子縁組をしていると結婚が難しくなる可能性があります。
生命保険を活用してパートナーに財産を残す場合は、生命保険契約時に法律上親族でないものを保険金受取人に指定するために、保険会社の審査が必要になるケースもあります。
同性カップルの相続対策では、法的な手続きをしっかりとおこない、可能な限り専門家のアドバイスを受けることが大切です。
同性パートナーのマイナス遺産は相続されるのか?

同性パートナーのマイナス遺産は相続されるのかどうかあらかじめ把握しておきましょう。
債務は相続の対象外
一般的に、同性パートナーは法定相続人ではないため、債務の相続義務はありません。ただし、包括遺贈を受けた場合や債務引受契約などがある場合は別です。
包括遺贈は相続の対象
遺贈とは遺言で財産を特定の者に譲ることです。包括遺贈とは、不動産など特定の財産を遺贈(特定遺贈)するのではなく、全財産の一定割合を遺贈するものです。この場合、財産の一定割合を相続する法定相続人と変わりありません。
したがって、受遺者が債務も引き受けることになるでしょう。例えば、遺言書に「全財産を包括的に遺贈する」と記載されている場合、受遺者は財産とともに債務も引き受ける義務があります。
同性カップル向けの住宅ローンを組んでいる場合
同性カップル向けの住宅ローンを利用している場合、契約内容によっては死亡時に残りのローンの返済をしなければならないケースもあります。詳しくは以下の記事をご覧ください。
同性パートナーの相続で公正証書遺言を作成する際のポイント
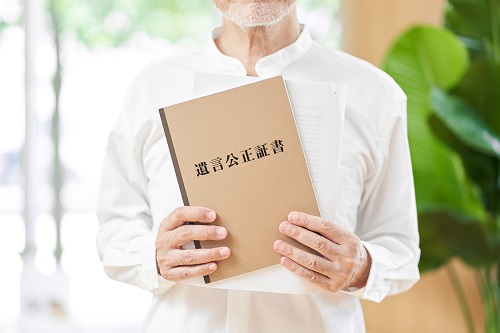
同性パートナーで公正証書遺言を作成するポイントを解説します。
遺留分に配慮する
遺留分は、法定相続人に保障された最低限の相続分です。同性パートナーに多くの財産を遺贈する場合でも、遺留分を考慮することが重要です。遺留分侵害額の請求は法定相続人の権利であり、請求される可能性を考慮して生前に財産形成をしておくことが重要です。
遺言執行者を手配する
遺言執行者は、遺言の内容を実現させるために遺産分配などの手続きを進める者であり遺言で指定します。信頼できる人物を選任することで、遺言の確実な執行が期待できます。例えば、弁護士や司法書士、信頼できる友人を遺言執行者として指定すると、遺言の内容が確実に実行されるでしょう。
祭祀主宰者(承継者)を指定する
祭祀主宰者は、葬儀や法要を取り仕切る役割を担います。同性パートナーを指定することで、パートナーの意向に沿った形での供養が可能です。
特定遺贈か包括遺贈を指定する
遺贈の方法として、特定の財産を遺贈する特定遺贈と、特定の財産を指定せずに財産の一定割合を遺贈する包括遺贈があります。
それぞれの違いを理解し、適切に選択することが重要です。特定遺贈は具体的な財産を明示するため相続されるものがわかりやすいですが、包括遺贈をした場合は相続人として扱われるので遺産分割協議への参加が必要なことがあります。
付言(ふげん)事項を記載する
付言(ふげん)事項は、遺言者の希望やメッセージを伝えるための部分です。ここに、同性パートナーへの感謝や今後の生活への配慮を書き添えることや、遺言によって法定相続分よりも少なくなる相続人への事情の理解を求めることが可能です。
同性パートナーへの相続対策まとめ

同性パートナーへの相続対策を解説しましたが、主要な内容を振り返っておきましょう。
同性パートナーは相続できない
現在の民法では、同性パートナーは法定相続人ではありません。そのため、遺言書の作成などの特別な対策が必要です。この対策を怠ると、遺産を巡るトラブルや経済的困難に直面する可能性があります。
同性パートナーの相続権がないことで起こるリスク
法的な相続権がないため、同性パートナーは法定相続人とのトラブルや相続預金の引き出しなど多くのリスクに直面します。これを回避するための準備が不可欠です。
同性パートナーの相続対策
公正証書遺言、死因贈与、養子縁組、生命保険など、さまざまな方法を組み合わせることで、同性パートナーの相続に備えられます。弁護士や司法書士などの専門家の助言を受けながら、最適な対策を講じましょう。
現在の日本では、同性パートナーには法的な相続権が認められていません。そのため、公正証書遺言や死因贈与、養子縁組、生命保険などを活用しつつ、残された同性パートナーにとって望ましい形での財産の移転を準備することが重要です。
物件を探す

執筆者
渋田貴正
司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。相続に特化した司法書士事務所として幅広くサービスを提供している。
https://www.pright-si.com/



