不動産の相続はどうする?流れや分け方、税金などの基礎知識をわかりやすく解説!

今回の記事では不動産の相続について、流れや分け方、相続税に関する基本的なことを解説します。よりよい選択ができるよう、基礎知識を押さえておきましょう。
記事の目次
不動産相続の基本的な流れ

まずは、不動産を相続するまでの基本的な流れを見ていきましょう。簡単な流れとしては下記のとおりです。
- STEP 1遺言書の有無を確認する
- STEP 2相続人と相続財産を確定する
- STEP 3遺産分割協議をおこなう
- STEP 4相続する財産の名義を変更する
- STEP 5相続税の申告・納付をする
それぞれ詳しく見ていきましょう。
遺言書の有無を確認する
まずは遺言書の有無を確認しましょう。遺言書がある場合には、遺言書の内容にしたがって手続きを進めます。遺言書は大きく3つに分けられます。
| 自筆証書遺言 | 遺言者が自筆で書いたもの |
|---|---|
| 公正証書遺言 | 遺言者が口述し、公証人が筆記したもの 原本が公証役場に保管されている |
| 秘密証書遺言 | 遺言者が作成し、遺言の内容を秘密にして公証人が存在だけを証明するもの |
3つのうち、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」の場合は、家庭裁判所で検認手続きをおこなう必要があります。検認とは、遺言書を確認し、偽造などを防止するための手続きです。あくまで偽造などを防止するためのものであり、有効かを判断するものではないことを覚えておきましょう。
相続人と相続財産を確定する
次に相続人と相続財産を確定させましょう。相続人とは相続する人のことで、被相続人(相続財産を遺して亡くなった人)の配偶者と一定の血族がこれにあたります。また、「財産」と聞くともらえるものといったプラスのイメージがありますが、そうとは限りません。借金やローンの残債など、マイナスの財産も相続する可能性があることを覚えておきましょう。
遺産分割協議をおこなう
遺言書がない場合は、相続人全員で協議をおこない、遺産を分割します。この時におこなう協議が遺産分割協議です。不動産を売却する際には、所有権を移転させなければなりません。その際には「遺産分割協議書」が必要となります。もし、相続した不動産を売却する場合には、次のポイントを押さえて作成しましょう。
- 不動産の適正な査定価格を算定する
- 不動産の売却で発生する必要経費を適切に算定する
- 相続登記から不動産売却、その後の売却代金の分け方までを明確にする
書類の形式には決まりがありませんが、スムーズに進めるためにも、司法書士などの専門家に依頼しましょう。
相続する財産の名義を変更する
例えば、相続した不動産を売却したい時、被相続人の名義では売却できません。被相続人の名義から相続人の名義に変更する「相続登記」をおこなう必要があります。また、相続登記をしなかった場合、所有権を公的に証明できないため、他の相続人が勝手に売却してしまっても、手の打ちようがありません。相続登記は必要書類が多いため、司法書士などの専門家に依頼するのが安心でしょう。
相続税の申告・納付をする
不動産を相続し、財産の評価額が一定額を超える場合は、相続税の申告と納付が必要です。相続開始(被相続人の死亡を知った日)の翌日から10カ月以内に納めなければなりません。もし、この時までに遺産分割協議が終わらなかった場合でも、法定相続分で相続があったものとみなして申告します。相続税に関しては、3章で詳しく解説します。
相続する不動産の分け方
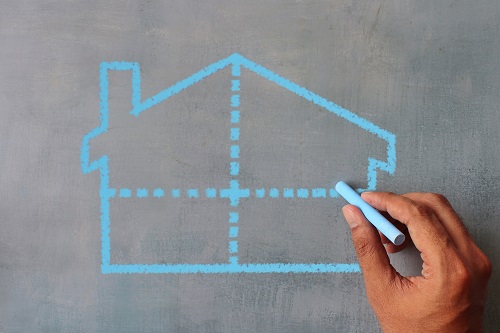
預貯金であれば分けやすく、難しく考える必要もありません。しかし、不動産の場合はどのように分ければよいのでしょうか。本章では相続時の不動産の分け方を解説します。
不動産をそのまま相続する現物分割
現物分割とは、相続財産である不動産をそのまま引き継ぐ方法です。例えば、Aさんには不動産、Bさんには現金など、それぞれの相続人が単独で所有することができます。また、土地を分けてそれぞれ相続する場合も該当します。
しかし、土地を分けた場合、価値が下がってしまう可能性もあります。さらに、形によっては建物を建てるために必要な要件を満たせなくなるかもしれません。不動産を現物分割したい場合は、不動産会社や弁護士など、専門家に相談してみましょう。
不動産を売却したあとのお金を分ける換価分割
換価分割とは、不動産を売却したあとのお金を相続人で分ける方法です。例えば、相続人が3人いて、相続した不動産を4,500万円で売却した場合は、一人ずつ1,500万円をもらうことができます。相続人全員で均等に分割できる点がメリットです。
しかし、売却する際の費用がかかったり、売却後に税金が発生する可能性もあるため、事前にシミュレーションをしておきましょう。
1人が不動産を相続して他の相続人に代償金を払う代償分割
代償分割とは、ある相続人が相続した不動産を現物で取得し、他の相続人に自分の財産を支払うことで、財産を分ける方法です。例えば、Aさんが土地と住宅を相続し、他の人に現金を払うケースです。他の相続人に対して代償金を払わなければならないため、経済的な負担が大きくなります。
相続人で不動産を共有する共有分割
共有分割とは、相続人それぞれの持分を定めて共有する方法です。相続した不動産を売却する予定がない場合などが該当します。もし売却することになった場合は、相続人全員の同意が必要となります。
また、相続人が亡くなった場合、相続人の子どもが相続することになるなど、所有者が増え、権利関係が複雑になることも理解しておきましょう。
相続する不動産の評価方法

相続や遺贈によって財産を取得した際には相続税がかかります。先述したように、遺産分割協議で話がうまくまとまらなかった場合でも、法定相続分で相続があったものとみなし、相続開始の翌日から10カ月以内に納めなければなりません。
相続税を計算するには、まず相続した財産を集計し、非課税の財産や控除額を引いて課税額を算出。そのあと、相続人それぞれの納付税額を計算します。
また、相続した財産の評価によって、相続税も変わります。本章では不動産がどのように評価されるのかを見ていきましょう。
土地の場合
土地の相続税評価額は、路線価方式と倍率方式の2つの求め方があります。
・路線価方式
路線価とは、道路に面する宅地の1平方メートルあたりの価額のことです。路線価に、土地の形に応じた奥行価格補正率と土地の面積をかけて求めます。
土地の相続税評価額=路線価×奥行価格補正率×土地の面積
例えば、次のような条件の場合を計算してみましょう。
路線価:20万円
奥行価格補正率:0.95
土地の面積:500平方メートル
20万円×0.95×500平方メートル=9,500万円
もし土地が二つの道路に面している場合は、正面と側方の奥行補正価格補正率、側方路線影響加算率をかけて計算します。
・倍率方式
倍率方式とは、路線価が定められていない宅地の評価方法です。固定資産税評価額に一定の倍率をかけて求めます。倍率は国税庁のホームページで見ることができます。固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書で確認できます。もし見当たらない場合は、市区町村で確認できるため、問い合わせてみましょう。
家屋の場合
家屋の相続税評価額は、固定資産税評価額に1.0をかけて計算します。
例えば、固定資産税評価額が4,000万円だった場合、家屋の相続税評価額は4,000万円×1.0で4,000万円となります。なお、固定資産税評価額は3年に一度見直しされるため、確認しておきましょう。
マンションの場合
マンションの場合は建物と土地に分けて、それぞれ計算します。建物の相続税評価額は、固定資産税評価額と同じです。マンションの場合は専有部分だけでなく、共用部分も含めて計算しなければなりません。しかし、固定資産税の課税明細書に記載されている固定資産税評価額には、共用部分も含めて計算されているため、この価格がそのまま相続税評価額となります。
土地の相続税評価額は、マンション敷地全体の評価額を持分割合で按分した金額となります。計算式は次のとおりです。
土地の相続税評価額=敷地全体の評価額×持分割合
持分割合は、登記事項証明書に記載されているため、確認してみましょう。
相続した不動産の評価額を減らせるケース

相続した不動産の評価額が高い場合、相続税も高くなり、負担が大きくなってしまいます。本章では、負担を軽くするために評価額を減らせるケースを解説します。
小規模宅地等の課税価格の計算の特例
先述したように居住用や事業用の宅地の相続税が高い場合、相続したあとに住んだり、事業を引き継いだりできず、手放すことを考えるでしょう。そこで、負担を減らすために設けられたのが「小規模宅地等の課税価格の計算の特例」です。通常の評価額から、利用区分に応じて一定の割合で減額することができます。例えば、亡くなった方が住んでいて特定居住用宅地等の要件を満たしていた場合は330平方メートルまで80%減額されます。ただし、誰が取得したかによっても、要件が異なります。詳しい要件は国税庁のホームページで確認しましょう。
貸家の場合
相続した不動産が貸家だった場合、相続税評価額を減らすことができます。貸家は他人に貸しているため、所有者が自由に使えるわけではありません。権利の制約が大きいため、相続税評価額では自用地(自分のための不動産)よりも価値が下がります。具体的な計算式は次のとおりです。
相続税評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
借家権割合とは、相続税の計算時に利用される割合のことで、30%と決められています。賃貸割合とは、全部屋のうち、実際に貸し出されている部屋の割合を指します。もし全室貸し出されている場合は100%となり、節税効果も高くなります。
例えば、固定資産税評価額が5,000万円で、賃貸割合が100%だった場合を計算してみましょう。
5,000万円×(1-30%×100%)=3,500万円
自用だった場合の相続税評価額は5,000万円となるため、1,500万円下げられたことになります。
不動産の相続時にかかる費用

不動産を相続する際には、相続税だけではなく、さまざまな費用がかかります。本章ではどういった費用がかかるのか、詳しくみていきましょう。
登録免許税
不動産の所有権を移転する際にかかる税金で、相続登記で不動産の所有権を公示するためにも必要となります。不動産を取得した理由によって税率が異なります。計算式は次のとおりです。
登録免許税=固定資産税評価額×0.4%
次のケースに当てはまる場合は、免税となり、登録免許税がかかりません。
- 相続登記をする前に相続人が亡くなった場合
- 相続する土地の固定資産税評価額が100万円以下の場合
この免税措置は、2025年(令和7年)3月31日までと期間限定のため、注意しましょう。
相続税
相続税は、亡くなった人の財産を相続した人が、一定額を超える場合に課税されます。相続税を計算する際には、遺産にかかる基礎控除額を差し引くことができます。基礎控除額は次の計算式で求めます。
遺産にかかる基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が4人だった場合は次の額を控除できます。
3,000万円+600万円×4=5,400万円
もし誰かが「相続を放棄する」としていた場合でも、放棄がなかったものとして法定相続人の数に含められます。また、被相続人に養子がいる場合には、実子がいる場合は1人まで、いない場合には2人まで含められることを理解しておきましょう。
その他の費用
不動産を相続する際には、登録免許税や相続税のほかにも、下記の費用がかかる場合があります。
- 必要書類の取得費用
- 相続登記の報酬
- 財産の管理・維持費用
相続登記の際には、戸籍謄本をはじめとした書類が必要となります。必要な書類は1通だけではありません。例えば、戸籍謄本の場合、亡くなった人の出生から死亡するまでのすべてが必要となります。戸籍謄本は本籍地でしか取得できないため、遠方の場合は郵送費や交通費も必要となるでしょう。1通あたりの手数料は少額でも、まとめると大きな金額となります。
また、相続登記を司法書士に依頼する場合には、報酬の支払いが必要です。報酬の目安としては5〜15万円となります。相続登記をする際には、あらかじめ資金を用意しておきましょう。また、誰がいくら負担するかも決めておくと、スムーズです。
さらに、相続した不動産をそのまま維持する場合には、管理・維持費用がかかります。誰も住まなくなった家は、劣化が早く進むため、定期的にメンテナンスが必要です。先々のことを見越したうえで、相続した不動産をどうするかを検討しましょう。
相続したあとの不動産をどうする?

相続したあとの不動産をどうするかが悩ましいところでしょう。「残しておきたい」「売って活用したい」など、人それぞれ考えがあります。まずどういった方法があるのかを把握し、納得のいく選択をできるようにしましょう。
売却する
相続したあとの不動産を売却するのも一つの方法です。売却すると現金化できるため、相続税の納付や相続人の生活費に充てることができます。相続人が多い時や公平に分けづらい時などに検討するといいでしょう。ただし、売却する際には相続人全員の合意が必要です。また、売却することだけでなく、売却価格に対する合意も必要となります。そのため、売却する際には、いくらなら売却するのか、最低価格を決めておくといいでしょう。
保有する
相続した不動産をそのまま残すことも可能です。相続した時点でローンは完済されているため、家賃を気にすることなく住むことができます。ただし、築年数が経っているほど、修繕費がかかることを理解しておきましょう。誰も使う予定がない場合でも、庭木の手入れなどの維持・管理が必要です。
有効活用する
相続した不動産を有効活用する方法もあります。例えば、賃貸に出して家賃収入を得たり、コインランドリーや駐車場などで収入を得ることもできます。いくらぐらい収益を見込めるのかは、不動産会社などの専門家に相談してみましょう。
まとめ
今回は、不動産を相続する際の流れや不動産の分け方、相続税について解説しました。相続によって財産を取得した際には、相続税がかかります。相続した不動産の評価額によって、相続税も変わります。しかし、要件を満たしている場合には、特例を使え、評価額を下げられます。特例を使えるかわからない場合は、専門家に相談をしてみましょう。また、相続したあとの不動産をどうするかもよく考えておきましょう。
相続人全員が納得できるよう、不動産会社などの専門家に相談しながら、円満に話し合いを進めましょう。
物件を探す

執筆者
民辻伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ




