1,000万円の土地の売却にかかる税金をシミュレーション!確定申告・納税方法も紹介

本記事では、1,000万円の土地の売却にかかる税金の種類を紹介したうえで、税金の計算方法をシミュレーション形式で解説。また、利用できる節税制度・確定申告と納税方法もあわせて紹介します。
記事の目次
1,000万円の土地の売却にかかる税金
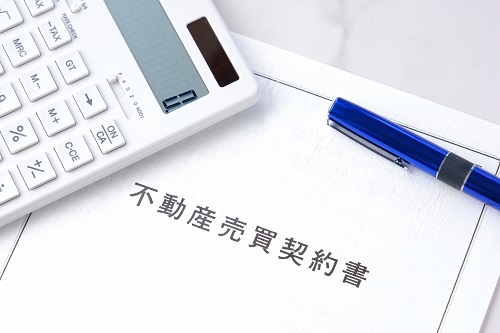
1,000万円の土地の売却にかかる税金は下記のとおりです。
- 譲渡所得税・住民税
- 印紙税
- 登録免許税
譲渡所得税・住民税
土地の売却で得られた利益は、譲渡所得として扱われます。譲渡所得は土地や建物、株式・ゴルフ会員権の譲渡を対象にした所得です。課税対象となる譲渡所得に対して、所有期間に応じた一定の税率が課されます。譲渡所得に対して所得税と住民税、2037年までは復興特別所得税が徴収される仕組みです。
譲渡所得と具体的にかかる税金の求め方は以下のとおりです。
-
・譲渡所得 = 売却価格 -(譲渡費用 + 取得費)
・譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率
譲渡所得がゼロの場合は非課税となり、納税は不要です。一方、譲渡費用がプラスの場合、金額に決まった税率をかけて、納税額が決まります。
また、税率は売却する土地の所有期間によって異なります。売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合、所得税と住民税合わせて39%(復興特別所得税を含めると39.63%)、一方、所有期間が5年を超えている場合は、20%(復興特別所得税を含めると20.315%)となります。
印紙税
土地売買契約書を作成する際には、契約書の記載金額に応じて印紙税の納付が必要です。印紙税は契約書・証書の作成に対して課される税金になります。
印紙税は契約金額に応じて税額が決まります。1,000万円を契約金額と仮定すれば税額は1万円です。2027年3月31日までは軽減税率が適用されるため、税額が5,000円になります。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超 | 2万円 | 1万円 |
土地の売買契約書は、売主・買主がそれぞれ作成し、それぞれが印紙税を負担することが一般的です。しかし、売主・買主のどちらかが両方の印紙税を負担する場合は、負担が2倍になります。
登録免許税
登録免許税は、登記手続きにかかる税金です。土地の売却にかかる可能性がある登記手続きは、抵当権抹消登記と所有権移転登記があります。
売主が一般的に負担するものは、抵当権抹消登記の登録免許税です。ローンを返済中で抵当権が設定されている土地の数だけ税金がかかります。登録免許税は土地1件あたり1,000円かかります。抵当権抹消はローンを組んでいる場合におこなう手続きであるため、ローンを組んでいない場合は発生しません。
また、相続した土地を売却する場合、名義が被相続人のままだと売却することができないため、所有権移転登記をおこなって名義変更が必要になります。
例えば、固定資産税評価額から課税標準額が時価の7割にあたる700万円であったと仮定します。
この場合、所有権移転登記にかかる登録免許税は、次の計算式で求められます。
700万円 ×2% = 14万円
なお、2026年3月31日まで適用される軽減税率は1.5%です。ただし、売主から買主へ所有権移転登記する際の登録免許税は、契約内容によって異なるものの、一般的には買主が負担する税金です。
よって、登録免許税は土地のローンの返済状況や誰が所有していることになっているか、契約内容に応じて発生する税金といえるでしょう。登録免許税が発生する場合は、自身で登記する場合を除いて、司法書士に依頼する報酬がかかるため、税金以外の費用が発生する点に注意が必要です。
1,000万円の土地の売却にかかる税金計算シミュレーション

1,000万円の土地の売却にかかる譲渡所得税・住民税は、実際に計算して求める必要があります。以下のステップで税金計算をシミュレーションします。
- STEP 1譲渡所得を計算する
- STEP 2利用できる控除を適用する
- STEP 3所有期間に応じた税率を適用する
- STEP 4税額の合計を求める場合はほかの税金と合算する
STEP 1:譲渡所得を計算する
まずは、課税対象金額である譲渡所得を計算しましょう。譲渡所得の計算式は以下のとおりです。
譲渡所得 = 売却価格 - (譲渡費用+取得費)
取得費は、土地の購入代金を含めた取得にかかった費用。譲渡費用は、不動産会社の仲介手数料などの土地の売却にかかった経費を指します。1,000万円の土地を売却するにあたって、以下の条件をもとに計算しました。
- 土地の売却価格:1000万円
- 取得費:600万円
- 譲渡費用:50万円
1,000万円 -(50万円 + 600万円)= 350万円
計算結果から1,000万円の土地の売却時の譲渡所得が350万円であると求められました。
取得費がわからない場合の譲渡所得の計算
土地の購入に関する領収書を保管しておらず、客観的に物件の取得費を証明できない場合は、売却額の5%を取得費として計上できます。土地の売却価格が1,000万円の場合は、50万円が取得費になります。
1,000万円 -(50万円 + 50万円)= 900万円
物件の取得費がわからない場合の税負担は、物件の取得費を正しく計上する場合と比較して重くなります。土地の購入当時の書類を集めて、正しく取得費を計算するようにしましょう。
STEP 2:利用できる控除を適用する
利用できる控除がある場合は、譲渡所得を求めた段階で差し引くようにしましょう。例えば、「居住用財産の3,000万円特別控除」を利用できる場合は次のとおり。
350万円 - 3,000万円 = - 2,650万円
この場合、計算結果がマイナスになることから税金がかかりません。控除を差し引いた結果、計算結果がマイナスまたはゼロになる場合は、ステップ3以降の計算手順は不要です。
出典:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」
STEP 3:所有期間に応じた税率を適用する
譲渡所得に対しては、土地の所有期間に応じた税率を適用します。売却した年の1月1日現在で土地の所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、土地の所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得となります。
| 短期譲渡所得 | 長期譲渡所得 | |
|---|---|---|
| 所得税率 | 30% | 15% |
| 住民税率 | 9% | 5% |
| 復興特別所得税率 | 0.63% | 0.315% |
| 合計 | 39.63% | 20.315% |
譲渡所得が350万円である場合、短期譲渡所得と長期譲渡所得でかかる譲渡所得税・住民税の税額をまとめました。
| 短期譲渡所得 | 長期譲渡所得 | |
|---|---|---|
| 所得税 | 105万円 | 52万5,000円 |
| 住民税 | 31万5,000円 | 17万5,000円 |
| 復興特別所得税 | 2万2050円 | 1万1,025円 |
| 合計 | 138万7,050円 | 71万1,025円 |
短期譲渡所得と長期譲渡所得では、税額に約2倍の差が発生します。同じ1,000万円の土地の売却でも、取得費・譲渡費用の額により譲渡所得が異なり、所有期間に応じて税率が異なることから、実際に計算しなければ、土地の売却時の税金を判断することは難しいといえるでしょう。
STEP 4:税額の合計を求める場合はほかの税金と合算する
1,000万円の土地の売却における譲渡所得税・住民税・印紙税・登録免許税を合算した最終的な税額を、以下の条件で計算しました。
- 譲渡所得:350万円
- 譲渡所得税・住民税:71万1,025円(長期譲渡所得適用時)
- 印紙税:5,000円(軽減措置適用時)
- 登録免許税:1,000円(抵当権抹消登記)
71万1,025円(譲渡所得税・住民税) + 5,000円(印紙税)+ 1,000円 (登録免許税)= 71万7,025円
以上のシミュレーションより、1,000万円の土地の売却にかかる税額の合計は71万7,025円となりました。
上記の計算方法を参考に、1,000万円の土地の売却にかかる税額を確認しておきましょう。
1,000万円の土地の売却で利用できる可能性がある節税制度

1,000万円の土地を売却する際、利用できる可能性がある節税制度があります。事前に確認して節税につなげましょう。
居住用財産の3,000万円特別控除
居住用財産の3,000万円特別控除は、マイホームの建物とその敷地を譲渡した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。特例を受けるための条件は以下のとおりです。
- 自分が居住していた土地である
- 家屋の取り壊しから1年以内に譲渡契約を締結する
- 家屋の取り壊し前に居住していた日から3年目の12月31日までに売却をする
- 売却をするまでに事業用として使用していない
- 売却の前年と前々年にその他の特例を利用していない
- 売主と買主の関係が、親子や夫婦など「特別の関係がある人」でない
出典:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」
この特例を受けるためには、仮に控除後にかかる所得税・住民税がゼロになる場合でも、確定申告が必要となります。
居住用財産を売った時の軽減税率の特例
居住用財産を売った時の軽減税率の特例は、土地の所有期間が10年を超える場合に適用される、譲渡所得に対する税率を軽減できる制度。税率は以下のとおりです。
| 税目 | 軽減税率 |
|---|---|
| 所得税 | 10% |
| 住民税 | 4% |
| 復興特別所得税 | 0.21% |
| 合計 | 14.21% |
軽減税率の特例は、先ほど紹介した居住用財産の3,000万円特別控除と併用できる節税制度でもあります。
被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例
被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例は、相続により取得した被相続人が居住していた建物およびその敷地を2027年12月31日までに譲渡する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。特例を受けるための条件を見てみましょう。
- 被相続人が居住していた家屋・土地である
- 家屋は1981年5月31日以前に建築されたものである
- 家屋を取り壊した場合、相続から取り壊しまでの間に事業用として使用していない
- 相続開始から3年目の12月31日までに売却する
- 売却価格が1億円以下である
- 売却の前年と前々年にその他の特例を利用していない
出典:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
また、制度を利用するには、土地に対して相続税が課税されていることが前提です。課税されていない場合は特例の適用対象外となるため、注意しましょう。
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例は、相続や寄贈で取得した建物・土地を売却する際に取得費の計算で、相続税額の一部または全部を取得費に加算できる制度です。相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年を経過する日までに譲渡が必要になります。相続税申告期限は相続開始から10カ月以内であるため、相続開始日の翌日から3年10カ月以内が期限です。
出典:国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
1,000万円の土地の売却で納付する税金の確定申告・納税方法
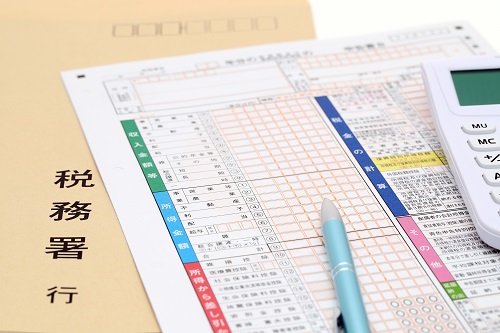
1,000万円の土地の売却では、印紙税は契約書を作成したタイミング、登録免許税は登記申請をおこなったタイミングで納税します。しかし、譲渡所得税・住民税は売却した時点では納めません。指定された期間に確定申告をおこない、譲渡所得税・住民税ともに別々の期間に納める必要があります。
1,000万円の土地の売却で納付する税金の確定申告・納税方法を見ていきましょう。
土地を売った翌年に確定申告をおこなう
土地の売却で納付する税金の確定申告は、基本的には土地を売った翌年の2月16日から3月15日に納めることになっています。計算した譲渡所得税・住民税を記載して、確定申告書を作成しましょう。申告方法は、所轄の税務署の窓口に持参する、または郵送で提出するか、インターネットを利用した電子申告であるe-Taxを利用する方法があります。
確定申告期間中に譲渡所得税を納付する
確定申告で記載した譲渡所得税は、申告期間中に納付する必要があります。納付方法は、銀行口座から税額を引き落とす振替納税、クレジットカード納付やコンビニ納付も受け付けています。さまざまな方法で納税できるため、自身が納税しやすい方法を選びましょう。
6月以降に住民税を納付する
確定申告を終えた年の6月以降に住民税が請求されます。住民税の支払い方法は主に普通徴収と特別徴収があり、普通徴収では6月・8月・10月・12月の4回に分けて住民税を納付します。
特別徴収は、会社員などの給与所得者が利用できる徴収方法であり、毎月の住民税から差し引かれる仕組み。譲渡所得税・住民税は確定申告をおこなって、それぞれ別のタイミングで納税します。
1,000万円の土地売却時の税金に関するポイント

1,000万円の土地の売却時の税金について注意すべきポイントがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
税金がかからない場合がある
1,000万円の土地を売却して、譲渡所得の計算結果がマイナス、またはゼロになった場合は税金がかかりません。例えば、取得費・譲渡費用が売却価格を上回る場合、税務上では譲渡損失として扱われるため、税金がかかりません。また、3,000万円特別控除などの特例制度を利用して、譲渡所得がマイナスになる場合も同様です。
ただし、控除を適用した結果、税金がかからない場合も適用条件を満たしていることを示すために確定申告は必須です。譲渡損失が発生している場合も、損益通算・繰越控除を利用できる場合があります。土地を売却した際には、税金がかからなくても確定申告をしましょう。
土地の所有期間で適用される税率が異なる
1,000万円の土地を売却する場合、短期譲渡所得・長期譲渡所得・軽減税率の特例で適用される税率が異なります。節税を考えるなら、できる限り低い税率が適用される所有期間を意識することが重要です。ただし、所有期間の計算方法を間違えていると、想定していた税率が適用されないことも。
税率が低い長期譲渡所得の適用を受けるためには、土地の所有期間が5年を超える必要があります。所有期間を判定するタイミングは売却した年の1月1日時点であり、売却時点では所有期間が5年を超える場合でも長期譲渡所得が適用されないケースがあるため注意が必要です。
例えば、2020年2月に購入した土地を2025年4月に売却した場合、所有期間は5年を超えますが、1月1日時点では5年を超えないことから、短期譲渡所得が適用されます。短期譲渡所得と長期譲渡所得の合計税率の差は19.315%、長期譲渡所得と軽減税率の特例の税率の差は6.105%。税率の差はけっして小さくないため、所有期間の計算を間違えると、土地の売却にかかる税金が大幅に増額するかもしれません。
土地に消費税は課税されない
建物を売却する場合は、3つの税金に加えて消費税が課税される場合があります。ただし、日本の税法では土地の売却に対しては消費税が課されません。土地は消費税法上では非課税資産に該当するからです。不動産の売却で消費税が課される対象は法人・事業主で、駐車場などの施設が付随しない土地のみの売却では消費税は課税されないでしょう。
税金以外にも費用がかかる
土地の売却では税金以外にも費用がかかります。具体的な費用を確認しましょう。
- 仲介手数料
- 解体費用(土地に家が建っていた場合)
- 司法書士報酬
- 測量費用
不動産会社に支払う仲介手数料は、土地の売却時にかかる費用として代表的です。仲介手数料とは、依頼した不動産会社に対して仲介業務の報酬として支払います。
仲介手数料の上限は、成約価格 ×3% +6万円 + 消費税で求めることができます。
その他にも、売却が困難な古い家を解体するための解体費用、司法書士に登記を依頼する場合の司法書士報酬、売却前におこなう確定測量を土地家屋調査士に依頼する測量費用が必要に応じてかかります。
税金以外にかかる負担も確認しておきましょう。また、譲渡所得の計算ではこれらの費用を譲渡費用に計上できるため、経費が発生した場合の領収書は必ず保管するようにしてください。
まとめ
1,000万円の土地の売却で発生する税金は複数ありますが、基本的には譲渡所得税・住民税が高額になりやすいです。ただし、計算結果によっては税金がかからない場合や、制度の利用で節税できる場合があります。
また、土地の売却では基本的に確定申告が必要になります。所定の申告期間を守って正しい税額を納税するようにしましょう。最適な形で節税制度を利用して申告するなら、税理士などの専門家に相談することも選択肢の一つです。
物件を探す
注文住宅を建てる

執筆者
長谷川 賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ







